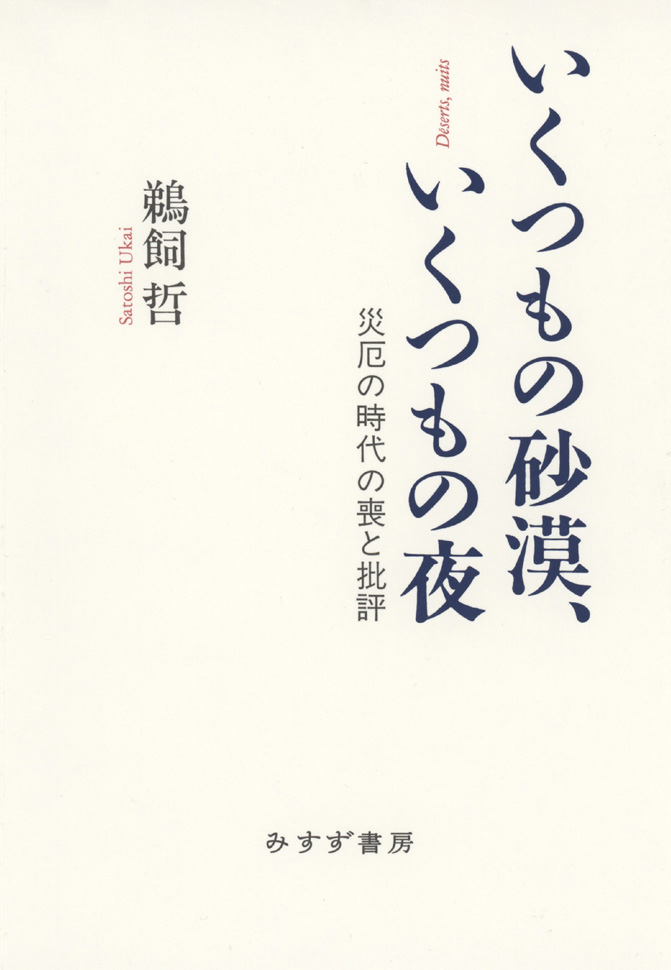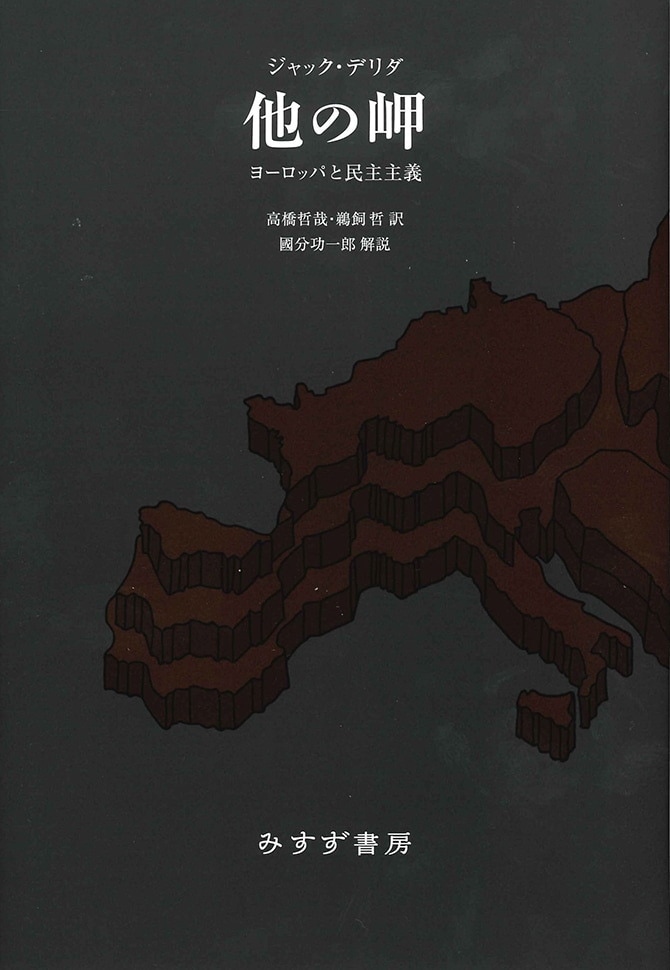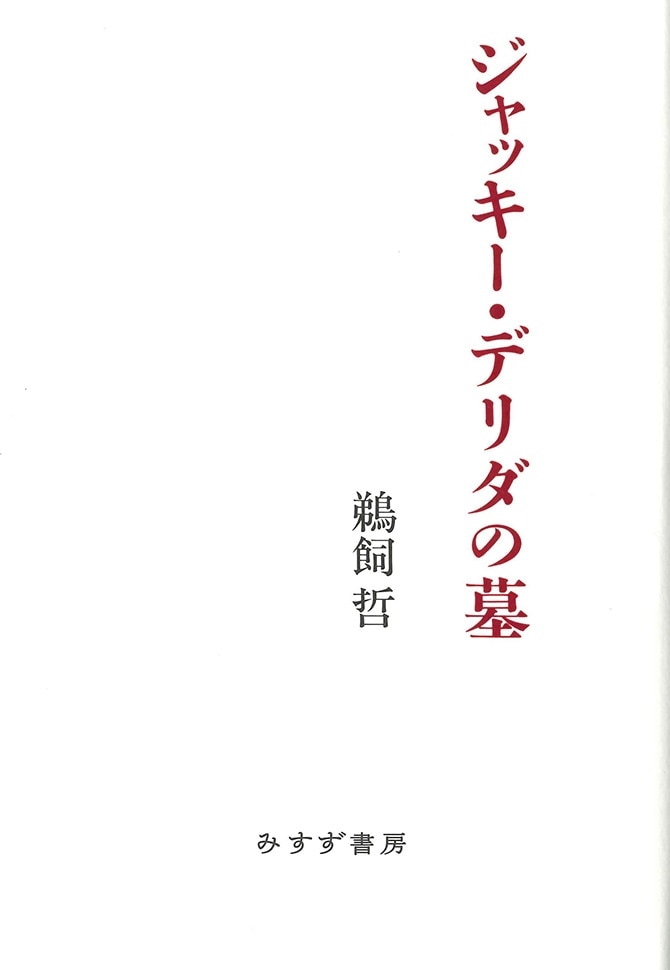すぐれた批評とは哲学と詩の融合であることを、鵜飼哲ほど示してくれる著者は稀である。世紀が変わってから20年あまりの間に、国内国外で招かれた機会に執筆・発表された(フランス語、英語のものを含む)論考から、文学・思想・芸術に関する32篇を選んで編まれた本書『いくつもの砂漠、いくつもの夜』は、副題にある「喪」と「批評」というテーマを底流に、さまざまな問いを続けてきた仕事の集成である。「問い」の眼力と魅力は、ほんの短い抜粋を読むだけでも伝わるのではなかろうか。
「それにしても、追悼とは、誰を、何を、どのように、そしていつ、「追う」ことなのだろう。これらの問いに答えがないことが、哀悼の言説を解体し、毎回、一回限り、言葉の発明を強いてくる。」(解体と発明)
「災厄の責めを詩が引き取ること、それは「月日」を「百代の過客」として再認することとは相容れない。時間がもはや流れなくなったとき、「過ぎ去り行く者」となることに、「私達」ははじめて責任を負う。死者が「残る」ために。死者と「生きる」ために。」(旅のさとり)
「私たちの身体のなかにはひとつの砂漠があり、そこで声が響く、つねにすでに多数の声が、音と言葉のあいだで。ジャン=リュック・ナンシーは彼の声で、声というものの永遠の若さを証言する。声は自らを保つ、絶対的な、しかも惜しみなく分/有された孤独のなかで。」(終わりなき響き)
「赦し、和解、救済、殉教。これらの問いを映画の問い、イメージの問いに転換すること。後期のゴダールはたえずこの課題に取り組んでいた。」(真理の二つの顔、あるいは敗者たちの詩人)
「砂漠と夜は、ヨーロッパのニヒリズムの特権的な形象になりました。かならずしもニーチェとともに始まったわけではないこの過程は、ヨーロッパばかりでなく、近代特有の荒廃を経験したヨーロッパ外の多くの場所でも、様々な表現と思想の変異体を生み出してきました。」(いくつもの砂漠、いくつもの夜)
「朝鮮半島の分断が克服され、韓国・朝鮮と日本の関係が根本的に変化し、東アジアにおける米国のプレゼンスが軍事的性格を喪失したとき、『火山島』はどのように読まれることになるのでしょうか?」(夢と自由と)
「一つの言葉のゆくえにいやおうなく結ばれる像が、そのまま現れてくることがなにか恐ろしく、「読みが当たる」ことがあってもそれはつねに不安の的中であり、理解の節約にはいささかもつながらず、かえって取り返しのつかない、退路を断たれた意味の外への旅に連れ出されてしまうのである。」(「道おしへ」のポエティック)
「そもそも「李禹煥」とは誰なのか、あるいは何なのか? 名前なのか? 作品なのか? 人物なのか? 思うに、誰にとっても、同時にこの三つの次元で李禹煥に出会うことは稀だろう。例えば私の場合、彼との出会いは実際に三段階で生じたのである。」(〈出会う〉とはどのようなことか、とりわけまず、李禹煥に?)
最近刊の論集『はじまりのバタイユ』(法政大学出版局)に収められた鵜飼哲の論考「笑いの感染」の結語もここで引用したい。「(デリダとバタイユとの関係の)どの切断面からも聞こえてくる笑い、その挑発に応答する思考の発明を試み続けたい。」こうした「思考の発明」に満ち、簡便な要約を拒むような書物だからこそ、『いくつもの砂漠、いくつもの夜』は、ゆっくりと、そして何度でも読み返すに足る一冊となっている。