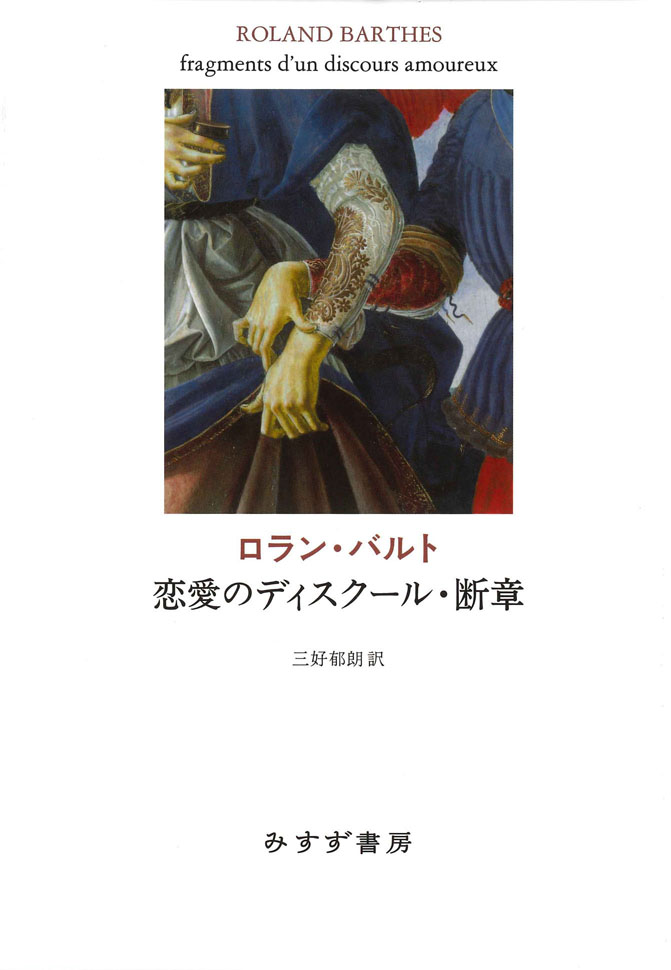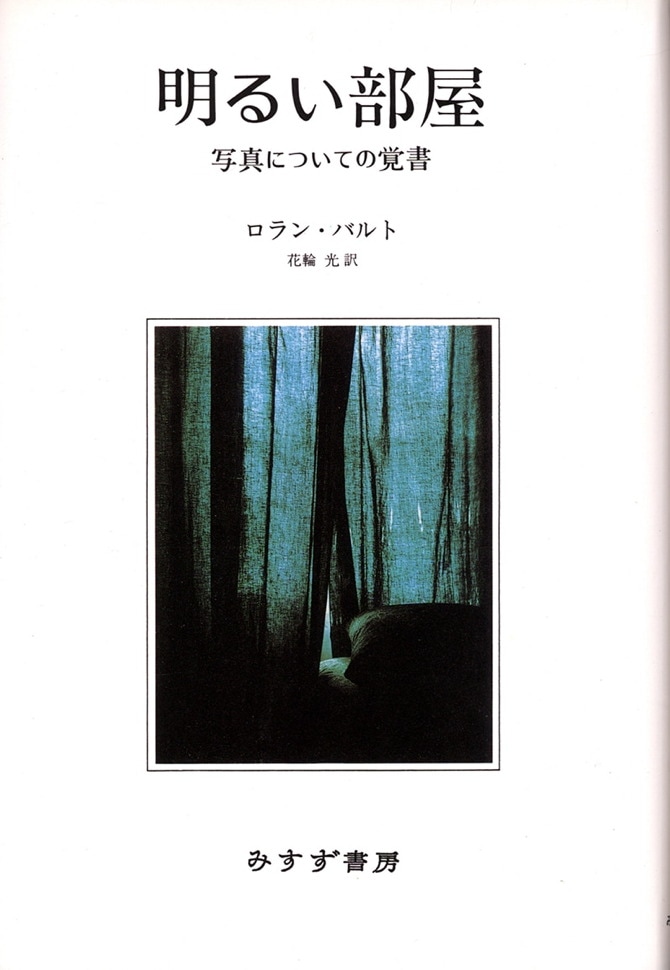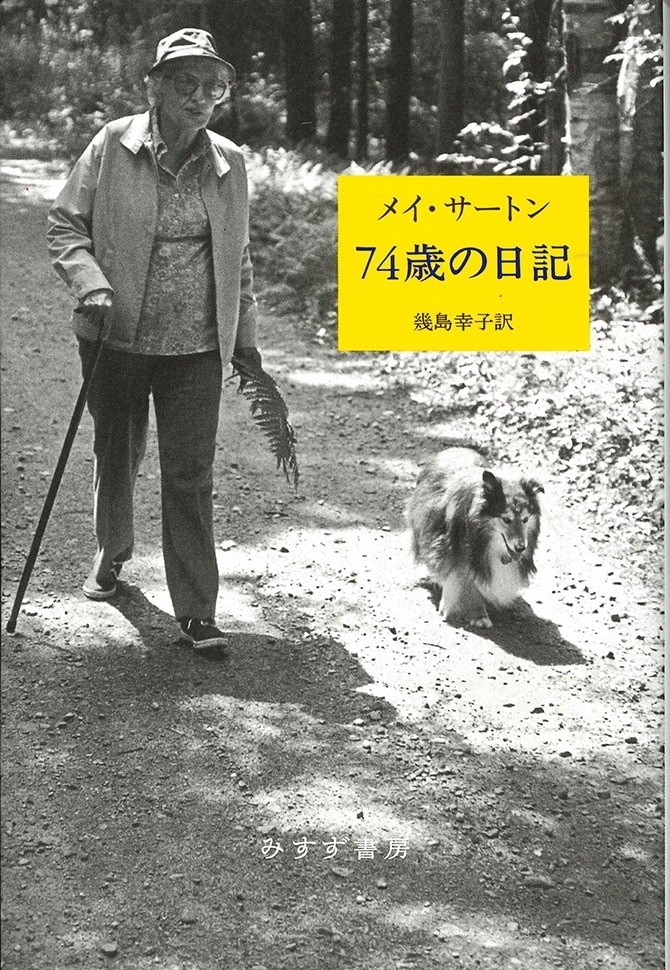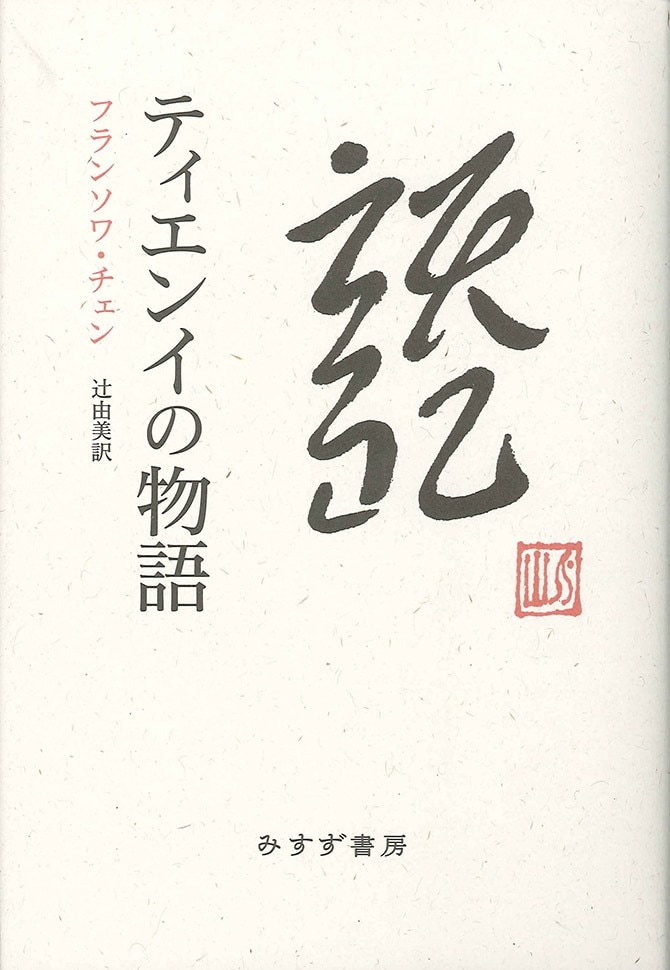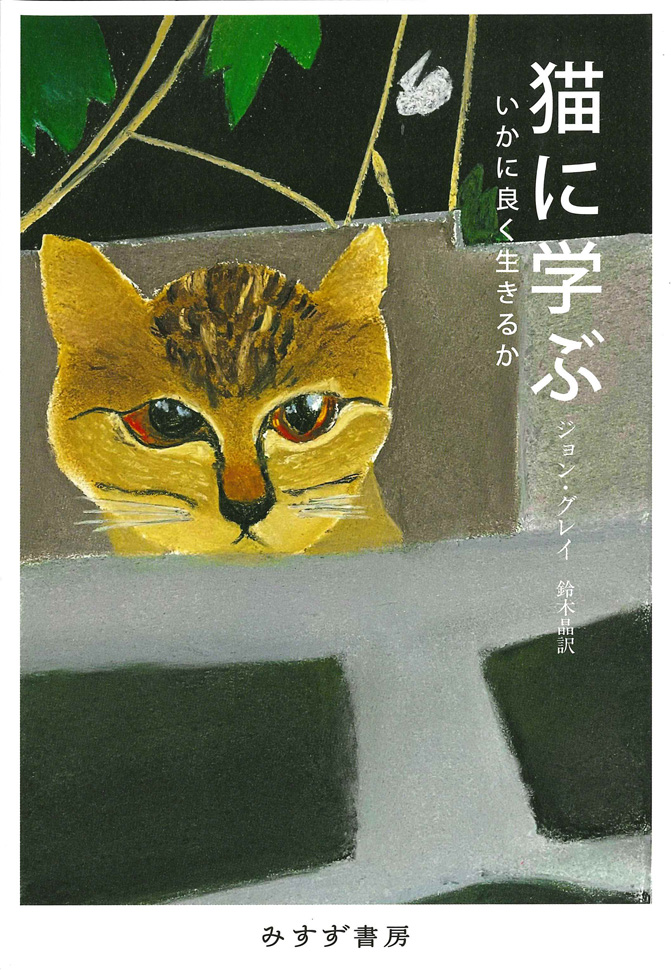日本でジャン・フランソワ・ビレテールの名を知る人はそう多くないだろう。それでも、この哲学者の仕事のなかでも特別なこの本は出したかった。
コレージュ・ド・フランスで行われたビレテールの連続講義を小社から『荘子に学ぶ』という題で刊行した2011年、毎日新聞に養老孟司氏の書評が載った。そこでは「この本の価値は少なくとも三点ある」と説きおこして、第一に「現代人に古典の読み方を教えていること」、第二に「『荘子』の解釈そのもの」、そして第三に「スイス人が読んだというところ」だという。また、鶴ヶ谷真一氏による別の書評では「ウィトゲンシュタインからプルースト、セザンヌに言及するのは、それが荘子の新しい読み方を可能にするからにほかならない」とある。二人の読み巧者は、ビレテールの学問の本質を見抜いていた。また、東洋哲学を西洋哲学と比較しながら読み直している中島隆博氏は著書の『荘子の哲学』(講談社学術文庫)でビレテールの学術的意義を大きく取り上げている。
スイス人の際立った中国思想研究者。そんな印象が変わったのは、ビレテールがリヒテンベルクの『雑記帳』をフランス語に訳して出版した2014年のことだった。池内紀氏が『リヒテンベルク先生の控え帖』として編訳している18世紀ドイツの作家を、ここまで読み込んでいるのは、いったいどんな人物なのか。そして数年後、パリの書店で見かけた『北京での出会い』という小さな本(ほぼ新書サイズ)の表紙で、微笑みながらこちらを見ている若い女性の上にビレテールの名前を発見して、ますますその人となりに興味を持った。
「出会ったのは半世紀前だった。今日まで語らずにきたのは、どう取りかかればいいかわからなかったからだ」と書き起こされる本書の読者は、数ページ後には1963年の北京に身を置くことになる。24歳のビレテールはスイス人留学生の第一号としてこの町に入った。着いたばかりの青年には、毛沢東下の政治状況についての知識も、プロレタリア文化大革命の予感もなかった。ところがある夜、北京在住のスイス人宅でのダンスパーティーで、彼は恋に落ちる。「二曲目か三曲目のとき、背中まで垂れている見事な黒い三つ編みをわたしはきゅっと引っ張った。彼女はびっくりして、ぴたりと動きを止め、そのあと一緒に笑ってから、ダンスを再開した。」
彼女の名は文(ウェン)。運命的に出会い半世紀をともに過ごしてきた彼女が2012年11月に突然、脳出血で亡くなる。それからのことを記したのが『もうひとりのオーレリア』である。「打撃は凄まじかった。殴り倒されたかのようだった。何日ものあいだ、わたしは自動人形のようにふるまった。」「孤独に耐えられる? と聞いてくる者がいる。この質問にわたしは唖然とした、というのも文(ウェン)は驚くほどたしかに、そこにいたから。」妻を失った夫は、研究者の習慣として、日付入りのメモを書き続ける。「十一月十五日 午睡。情動を受け入れよう。四月の雨を受け入れるように。人びとはわたしを慰めようとするらしいーーそれだけはやめてくれ。」
同じ日にいくつもの言葉が書き付けられることがある。例えば11月19日。「午睡。横になるやいなや、涙の大雨。喜びか、苦しみか? 情動に自分がどのような考えを結びつけるかによる。」「死は存在しない。終わる生があるだけだ。ほかのあらゆる言説がもたらす悪。」「彼女がしばしここにいたなら、話したいことの数々。時間が足りるかどうか。」けれども翌日には、こう嘆く。「わたしがもはや持たないもの、それは、なにもかも話せる一人の人間。」あるいはこんな記述もある。倒れた妻が病院に着いたとき、イヤリングを片方しかつけていなかったと聞かされていた。「今日ベッドを整えていたら、失った宝石が出てきた! 彼女は片方をつけて去り、片方をわたしに残した。彼女の茶目っ気はつづいている。」
妻が死んで一か月後、転機が訪れる。ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの絵《鏡の前のマグダラのマリア》を思い浮かべることで苦痛が和らげられ、聴けなくなっていた音楽を聴く気になるのだ。「マレイ・ペライアの弾く《ゴールドベルク変奏曲》をかけてみた。またも奇跡が起きた。」もはや限界に達していた麻痺状態を脱して、少しずつ動きを取り戻すための長い道のりを、ビレテールは歩み始める。もちろん激しい動揺の揺り戻しはあるが、そこからの覚え書きには、徐々に文学や思想の言葉、美術や音楽について記されるようになってくる。
ところで、先ごろスイスで公開されたジャン・フランソワ・ビレテールへのインタビューがある。
https://www.plansfixes.ch/films/jean-francois-billeter/
最後のところで、『もうひとりのオーレリア』はあなた自身のためにおこなった「死についての考察」なのですかと尋ねられたビレテールは、「まったく違う」と答えている。それらは自分と妻とは独立しているというのだ。刊行時のまえがきにもそうあった。「この波乱の時期に考察したいくつかのことをまとめておけば、わたしもまた有用な仕事を残せるかもしれない。」これは、著者個人の経験を昇華した自著への率直な思いのように思える。
ロラン・バルトの『恋愛のディスクール』を恋する人が読んでいる。やはりバルトの『喪の日記』は近親者を失った人が読んでいる。大切に記された言葉が、言葉を大切にする人たちに伝わっている。これは本というものの重要なあり方だろう。ビレテールの本書もそうした特別な一冊になってくれるように望んでいる。