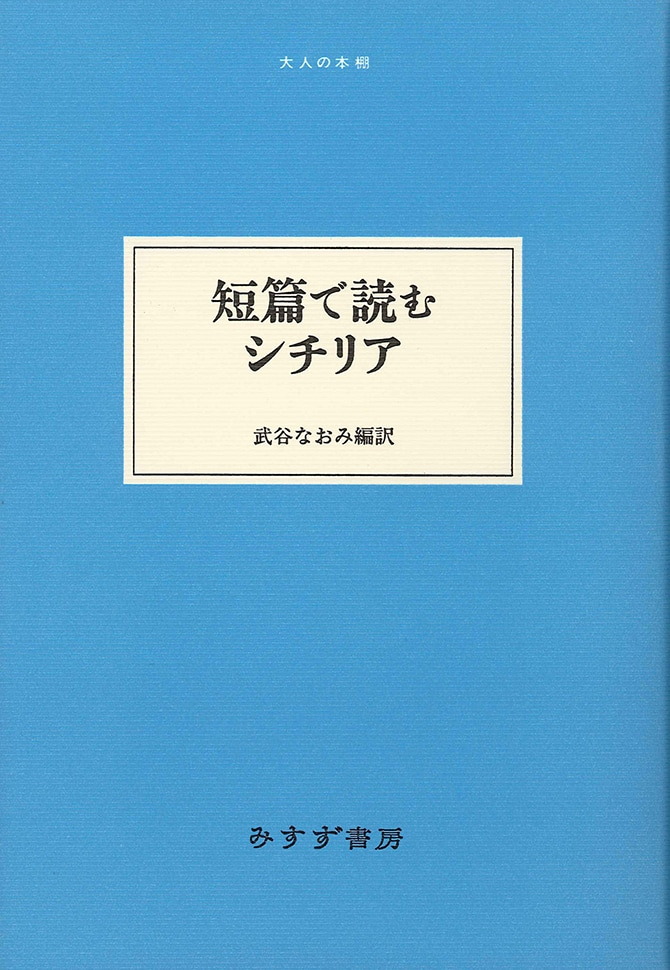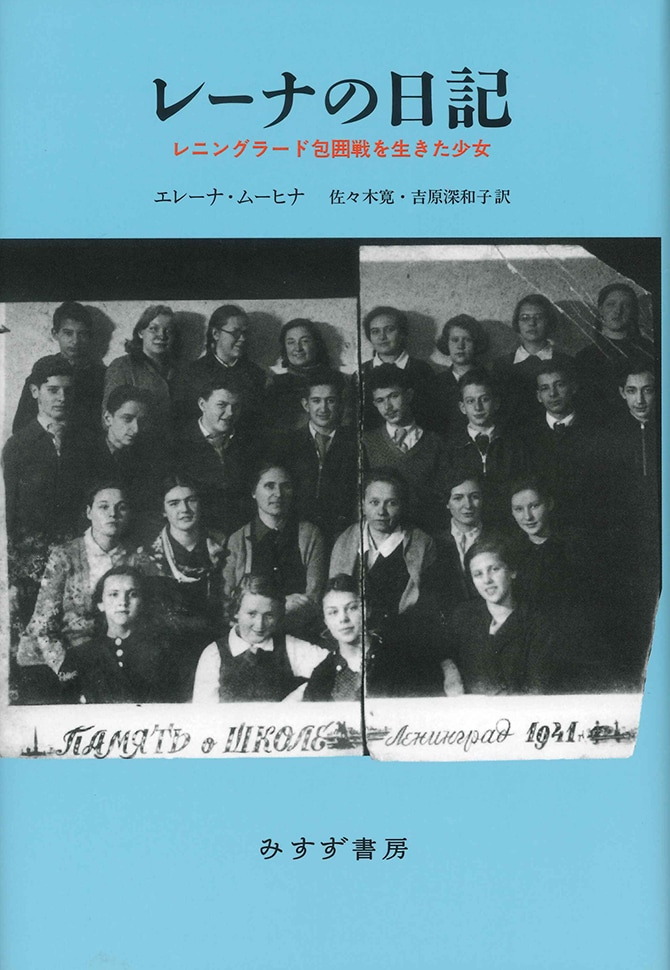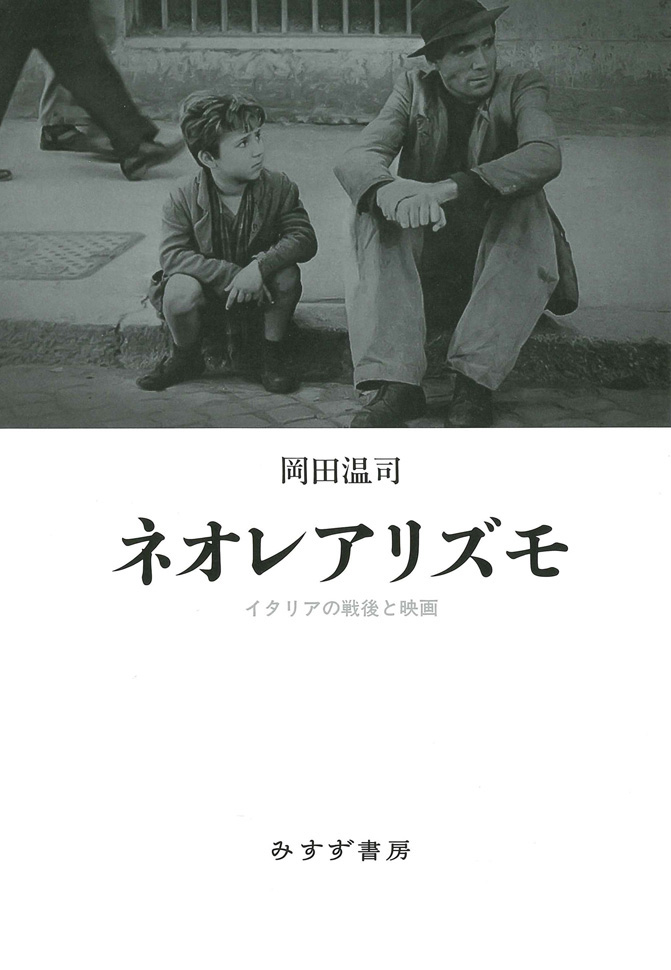- 当ウェブサイトのためにご寄稿いただきました
古賀弘人
(北海道大学名誉教授・イタリア文学)
一向に溶けあうことがない「不在」の感受性
それにしても、いきなり、「不在」である、ドキッ、穏やかでない。誰が、何が、不在なのか?
短篇を読み進めていくと明らかになってくる、──「私」主人公が不在であり、私にとって家庭と家族が不在であって、要するにこの私という少女は、家族のなかで、社会のなかで居どころがなく、員数にならず、身の置きどころがないという感受性が露わになっている。末っ子の私は、家族のみなから(とりわけ父親から)一人前と認められず、半分だけしか家族に属していない。この孤絶した感情を埋めるかのように少女は、日ごとノートに感情をつづってゆく、誰にも心の奥底を打ち明けずに。不在である私は、この秘密のノートのページの内にのみ存在していた。
全体を読破して明らかになることは、家族と学校と友人と世相すべてに対して一向に溶けあうことがない「不在」の感受性が、享年75までイタリア社会を横断しつつ書きつづけたナタリーア・レーヴィ(のちギンズブルグ)という人の核心に、居坐っていたことだろう。少女の未明の刻限に掌に握りしめた、魔法めいたこの負の感性を、ナタリーアは最期まで失わなかった。とりあえず言葉という魔法にすがって生きるほかはなかった。ちなみに、物語の随所に作家はメイドという仕事の人物を覗かせているが、なぜならこの脇役は、少女に似て“半分だけ”家族の一員であったからだろう。
「色に染まる」のが苦手
ナタリーアは父がユダヤ人の生理学者である、トリーノという都市の家庭に生まれ落ちた、そしてロシアから移住したユダヤ人の文学者、レオーネ・ギンズブルグと知りあって結婚し、二児の母となり、ようやく「不在」の感情と縁が切れたかと見えたが、夫は自由を求める戦いに立ち、獄中で殺された。言い換えればナタリーアは、ファシズムの暴風に吹き飛ばされそうになっていた。生まれ落ちたイタリアという土地でユダヤ人という二律背反を負っていながら、二児を抱えて、しかし複雑きわまる窮乏を耐え忍ばざるをえなかった、とまとめて良いであろう。
そもそも周囲に対して異和を感じていた少女―母親は、ただただノートに書きつづけ、時にその書きものを発表し、糊口をしのいだ。少女―母親はそのまま、いつしか「作家」になっていた。書いたものを読んでもユダヤ人ゆえの懊悩や、ファシズム独裁の激しい風圧ゆえの艱難を、ナタリーアは、それらをとくに強調して書いていない。もっと奥底を見つめていた。それは何ゆえであったのか?
ナタリーアはある「色に染まる」ことが苦手で、自ずと避けていたのだろう。英雄たる夫レオーネの妻であるという色や、エイナウディ出版社に働く左翼であるという色や、フェミニストであるという色や、こうした「身分証明書」に似たものを彼女は放棄していたからである、ある主義主張から自由に書くために。
「女性について」という原著編者のスカルパ氏が秀逸であると推奨する評論を読むと、つまり、女性とは、〈母になった少女〉に他ならない、子供の有無にかかわらず。ナタリーアにとって、女性であることは「常態」であり、なおかつ「出来事」でもあった。ここにしか作家が足を踏まえる「井戸」はなかった、時にその井戸に落ちてしまうのだが。なるほど、男の物書きは「男性について」という文章は書かない。
白黒のデッサン
スカルパ氏が作品中の「ふたつの梁」のもう1つと推奨する夫の死を悼む「思い出」という22行の詩篇がある(本書所収)。
思い出
人びとが都会の道を行き交っている。
食べ物や新聞を買い、それぞれの仕事で動いている。
バラ色の顔、唇は生き生きとふくらんで。
あなたは布をもち上げてあの人の顔をみつめた、
いつもの仕種でかがんで口づけをした。
だがそれは最後だった、いつもの顔だった、
いつもより少し疲れていたけれど。いつもの服を着ていた。
いつもの靴をはいていた。そしてあの、
パンをちぎり、葡萄酒をそそいついでいた手。
きょうもまた、過ぎゆく時のなかで、あなたは布をもち上げて
あの人の顔を、これを最後と、見つめる。
道を歩いても、あなたのそばには誰もいない。
こわくなっても、誰も手を握ってくれない。
そして道はあなたのものではない、都会はあなたのものではない。
まばゆい都会はあなたのものではない、まばゆい都会は他の人びとのもの、
行き交い、食べものや新聞を買う人びとのもの。
あなたは静かな窓から少し顔を出して
闇にしずむ庭をだまって見つめることはできる。
あのころは、泣いていると、あの人の晴れやかな声がとどいた。
あのころは、笑っていると、あの人の沈んだ笑い声がとどいた。
けれども暗くなっても開いていたあの門は永遠に閉ざされるだろう、
そしてあなたの青春は見捨てられ、火は消えて、家は空っぽ。
(1944年11月8日)
この短い詩作が行われた特別な事情については、訳者の望月紀子さんが温かく丁寧な解読を書いている。作家は、時が逝ってのちに、これを詩作によってしか表現するほかなかったことだけを、指摘しておく。
ナタリーアは喪失した英雄である夫にいつまでも恋々としていなかった。レオーネの妻であったという色は避けた。英文学者のバルディーニと再婚し、遠い異邦のロンドンに居を定めた一時期もあった。馴染んだイタリアという色から逃れ離れる好機であった。ここまで評者は、作家が「色」に染まらないという論旨を引っさげてきたが、「色」という語から連想が動くナタリーア作品の成立について、その特長をさらに追求したい。
つまりナタリーアの描く文章は、「物語、記憶、クロニクル」の三部立てのいずれをとっても、もしも美術の言い方を借りるならば、評者の僻目の見るところ、「白黒のデッサン(素描)」ではないかと想わせるのである。世の中の鑑賞者はふんだんに色が塗りたくられた画布を好むものらしい。ナタリーアの作品は男性の批評家たちから芳しくない評価を被ってきた、一例がG・コンティーニの場合であるが、名著の誉れ高い彼の『統一イタリアの文学 1861-1968』の大冊(1968)に、ナタリーア・ギンズブルグの名前は載っていない。それは何ゆえであろうか? ナタリーアが描く人物、事物、社会、世界がいわば無彩色の様相をとっているからであろう。
言い方を換えるならば、彼女は自らが踏破しつつイタリアの20世紀を、もっぱらその「骨格」を描いてきた。レントゲン写真に映る「骨」は灰色で、色を持たない。
レオナルドのデッサンをしかと視た人ならば、彼の芸術の真髄がデッサンの描写にあって、ほかではないことを見抜くであろう。ナタリーアの表した作品から受ける心象は、レオナルドから受ける心象とさして遠くはない。もしやモノクロームのデッサンによる「骨格」ではもの足らなければ、それに十分に彩色している精鋭のスカルパ氏と篤実な望月紀子氏の記した、委細を尽くした解読を読めば、肯けるであろう。
今、この時点で、評者はナタリーアを、イタリアの戦中―戦後における「偉大な」作家であるとは言わない、そう言っても余計であろう、「偉大な」というありきたりな評言を避け、「切実な」模範であると言いおくとしよう。
ナタリーアの読者はこれまで女性に傾いていると解説のお二人が言っているが、いかなる時機にあっても〈異和〉を表明しつづけた「少女―母親―作家」は、ようやく、ここに、男性の読者をも多く獲得するであろう。
イギリスには誰しも、ヴァージニア・ウルフがいると想う、同じように、イタリアにはナタリーア・ギンズブルグがいると想うようになる日は近い。