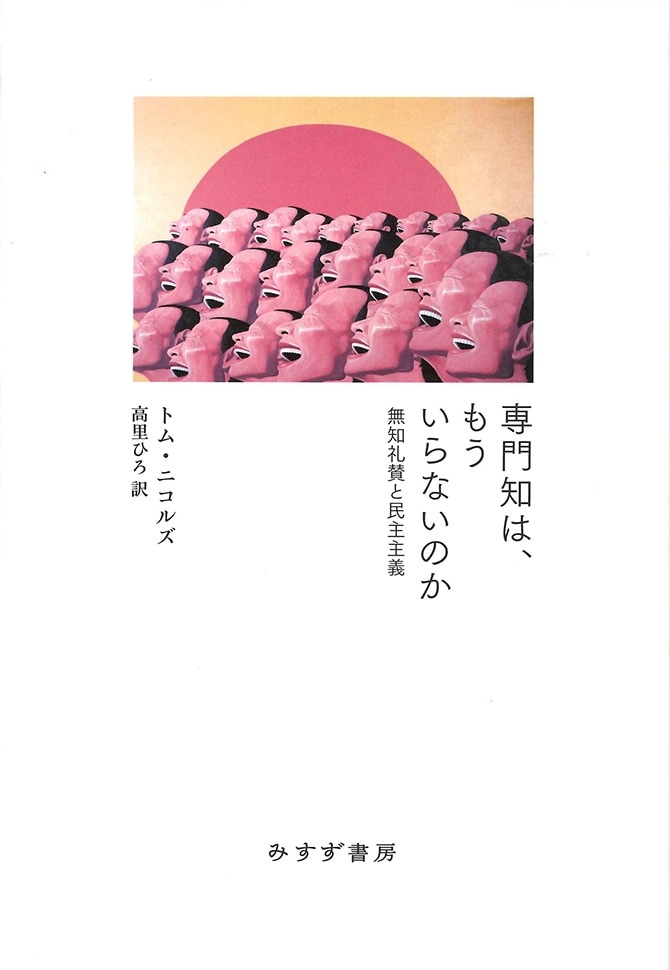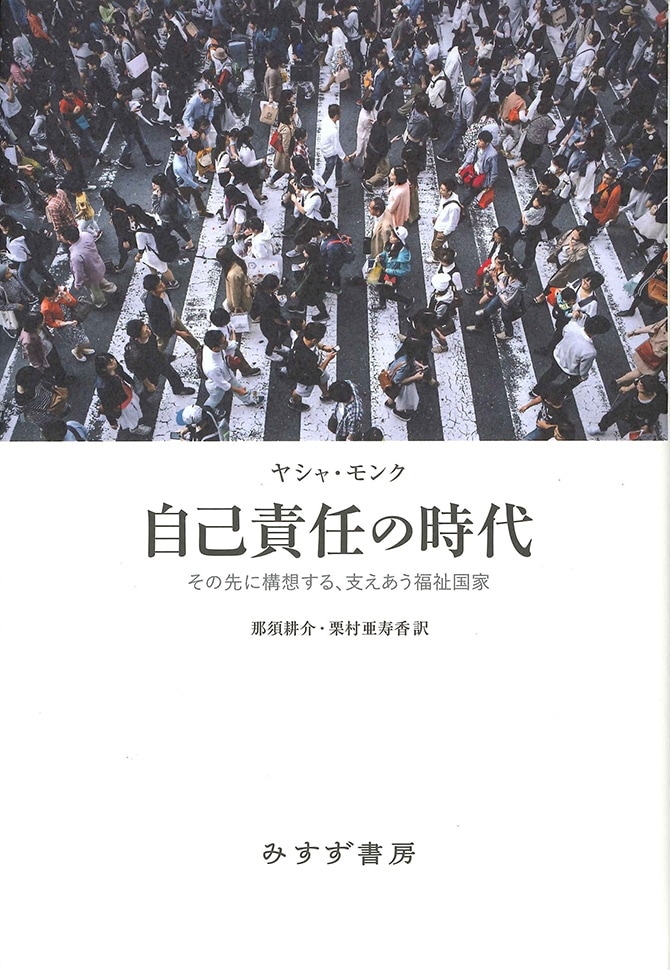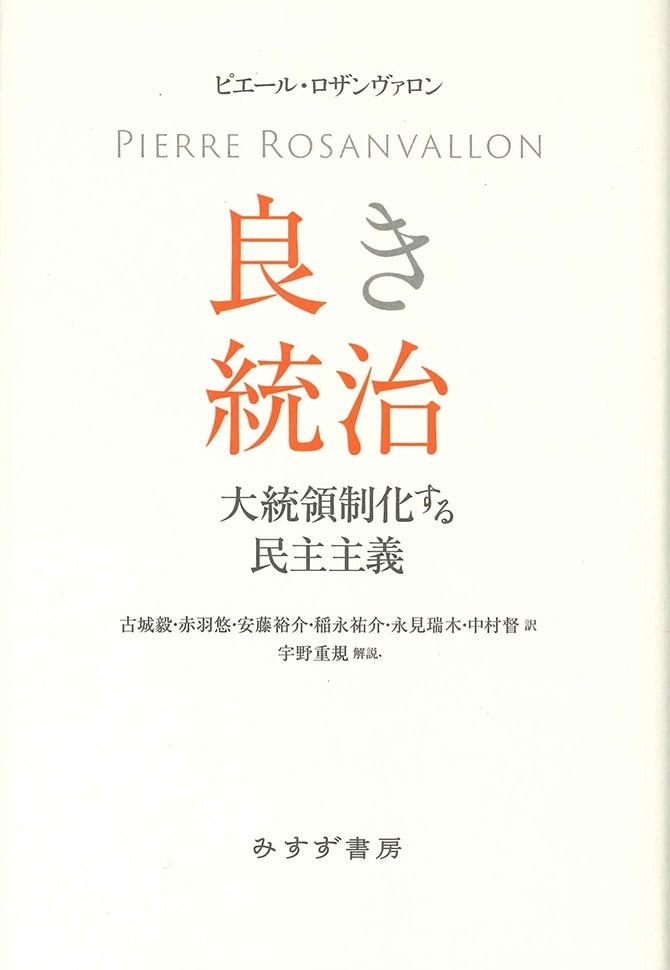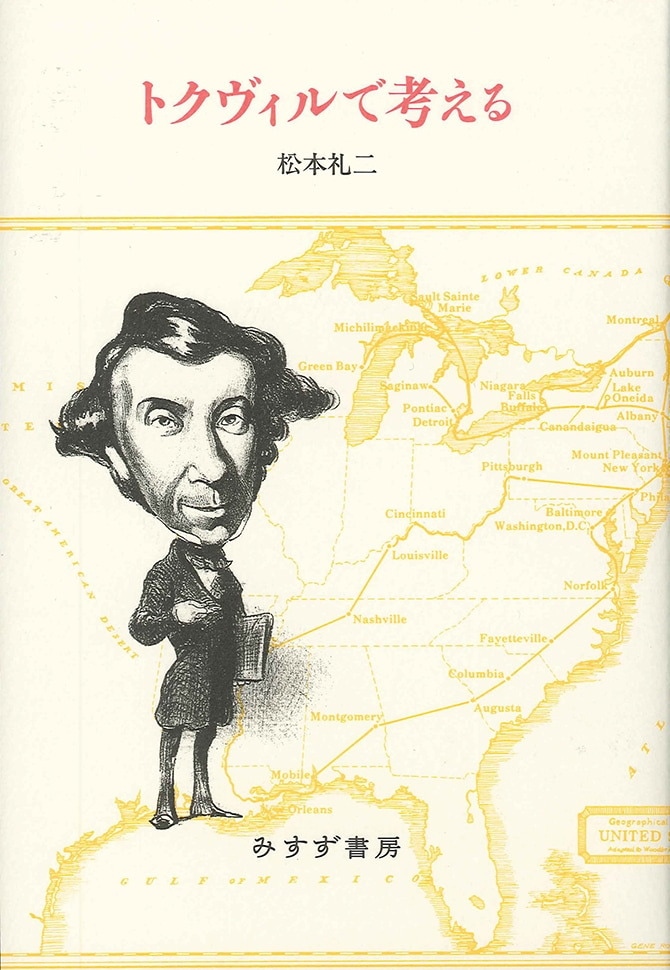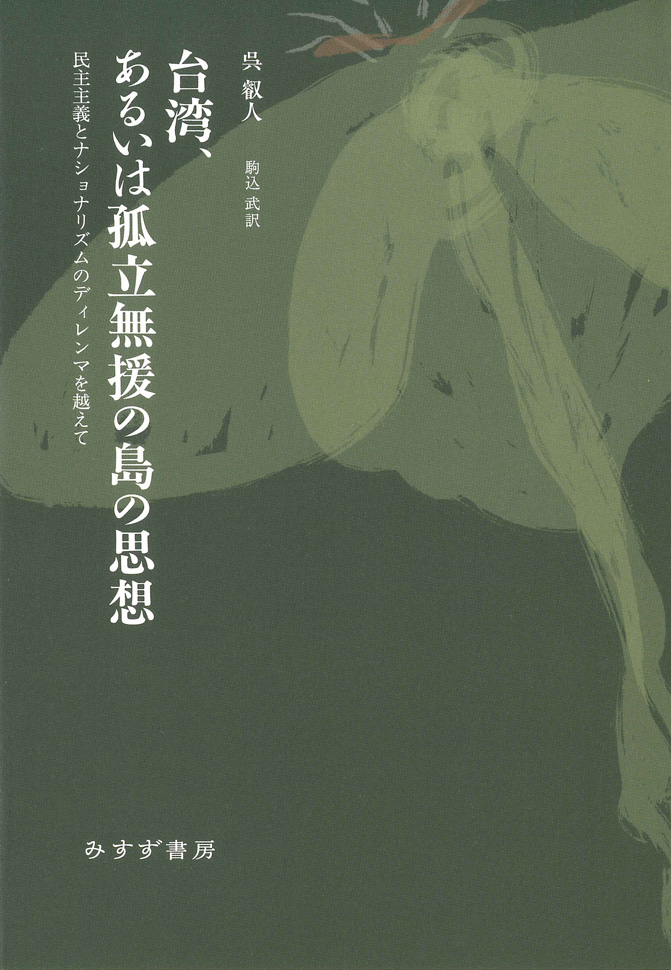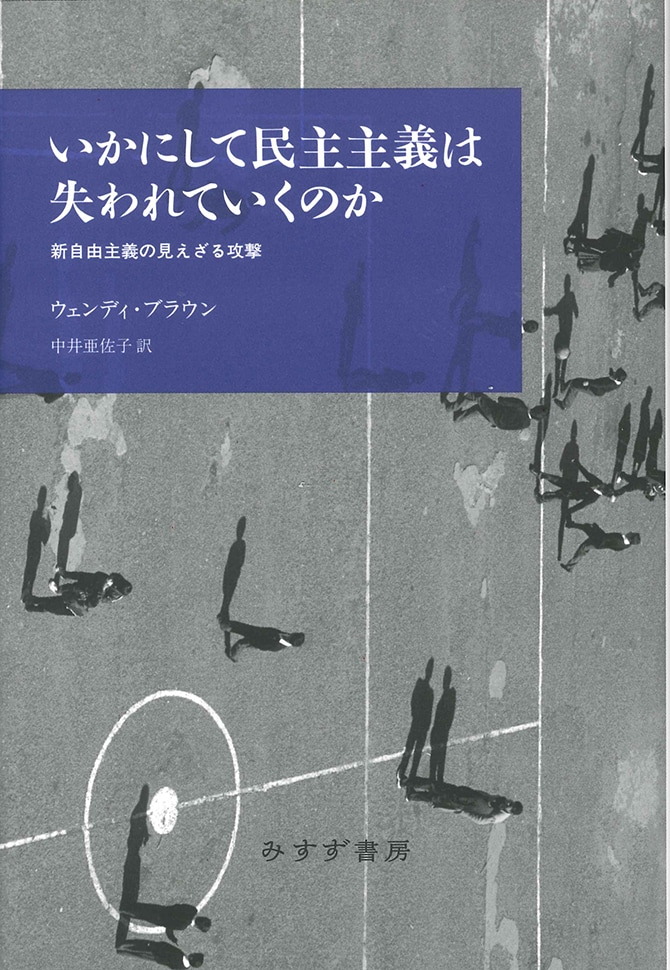著者のヤン=ヴェルナー・ミュラーは『ポピュリズムとは何か』が各国で読まれ、広く知られるようになった政治学者である。その後に刊行された『試される民主主義』を読まれた方も多いことだろう(どちらも岩波書店刊)。そうした既刊書を読まれていたら、本書のところどころで遭遇する著者のユーモアに面食らうことがあるかもしれない。民主主義の危機についての本だというのに、このトーンはどうなのか――と。
トランプ大統領を生んだアメリカの例に顕著なように、ポピュリズムの原動力のひとつに知識人やリベラルへの嫌悪がある。ヤン=ヴェルナー・ミュラーもそうした嫌悪の対象になるのだろうか。そうはいっても、国民の分断や民主主義の機能不全を語るときに煙たがられることを意識して議論を妥協するわけにはいかないし、上からひたすら正論を述べても、場合によっては分断がさらに広がるかもしれない。民主主義は、億単位の人びとができるだけ穏やかに共存してゆくために必要なベースなのに、数百、数千、数万の人ですら民主主義を議論するためにおなじ地平に立てないとなると、民主主義は本当に終わってしまう。
本書のユーモアは、冴えているものもあれば反応に困るものもあるかもしれない。原書の編集者にあれこれ言われることなく、ノビノビと筆をふるったのだろうと想像している。一流の政治学者がくりだすジョークに初めは戸惑うだろうが、読者にはそれを「おもしろい」とか「…」とジャッジする自由がある。しかも、そうするのに政治学の博士号は不要で、同じ人間としてすなおに評価するだろう。本書の読後感になにか個性的なものを感じて、それがなんなのか考えていたのだが、もしかするとこの洗練されすぎないユーモアが一因だろうか。これが、書き手と読み手がおなじ地平にいるような空気を醸成している。
ただの気のせいかもしれない。そう考えていてふと思い出したのが、深刻なピンチの局面で登場人物がジョークを飛ばすという、ハリウッド映画でよくある場面である。あれは初めて観たときには感心したものだが、しだいにお約束のようにあの映画にもこの映画にも出てくるようになると、興ざめを通り越してそのわざとらしさが痛々しく、ピンチのジョークというものに悪いイメージしか持てなくなっていた。しかし危機時に冷静さを保つ効果がユーモアにあるのは、おそらく真実だろう。本書における民主主義の危機と政治学者のユーモアは、著者が意識してかしないでか、そういう意味でもうまく噛み合っているように思う。――しかし、これも気のせいなのだろうか。いずれにしても、そんなことをつらつらと考えさせる、味わい深いユーモアセンスだと思う。さて、本書を読まれたみなさんは、賛成してくれるだろうか?