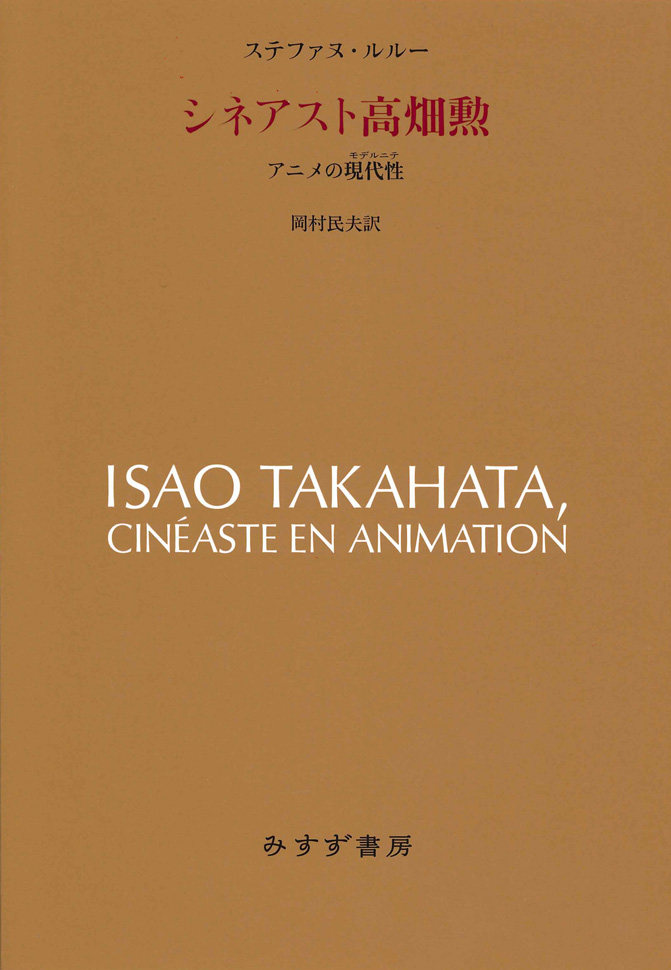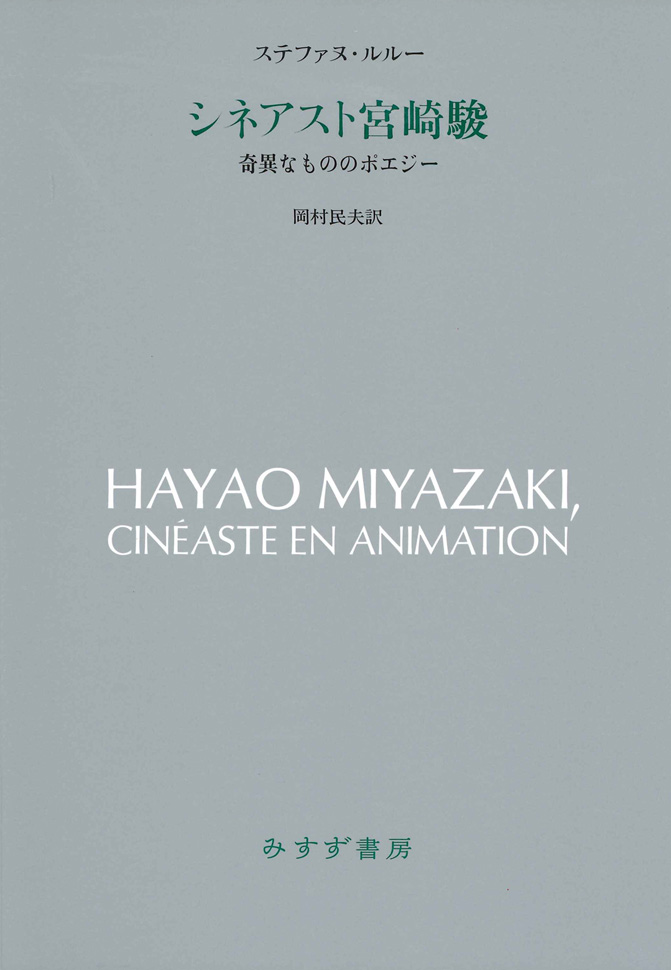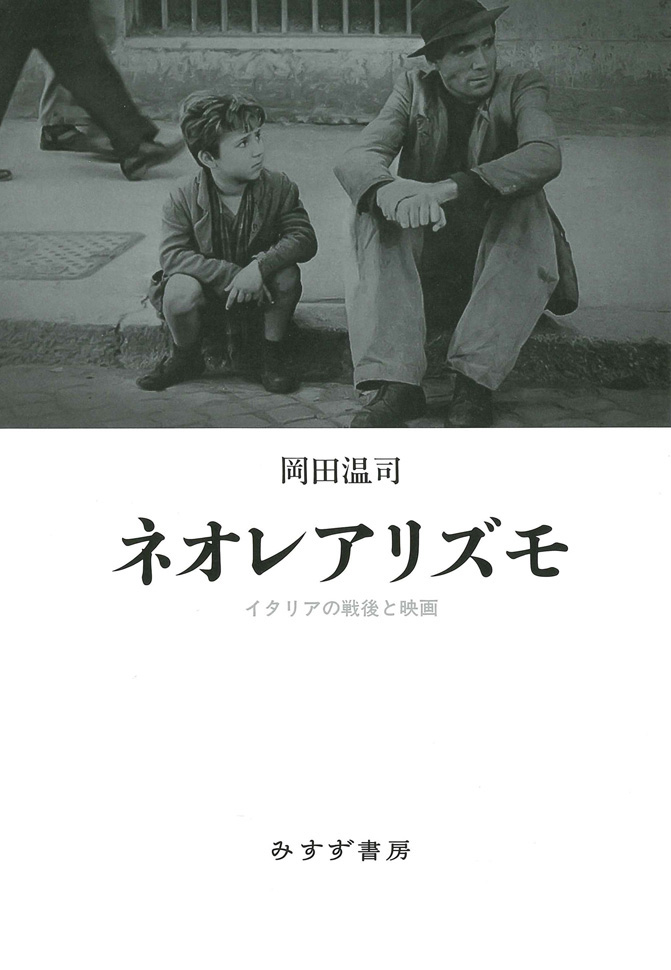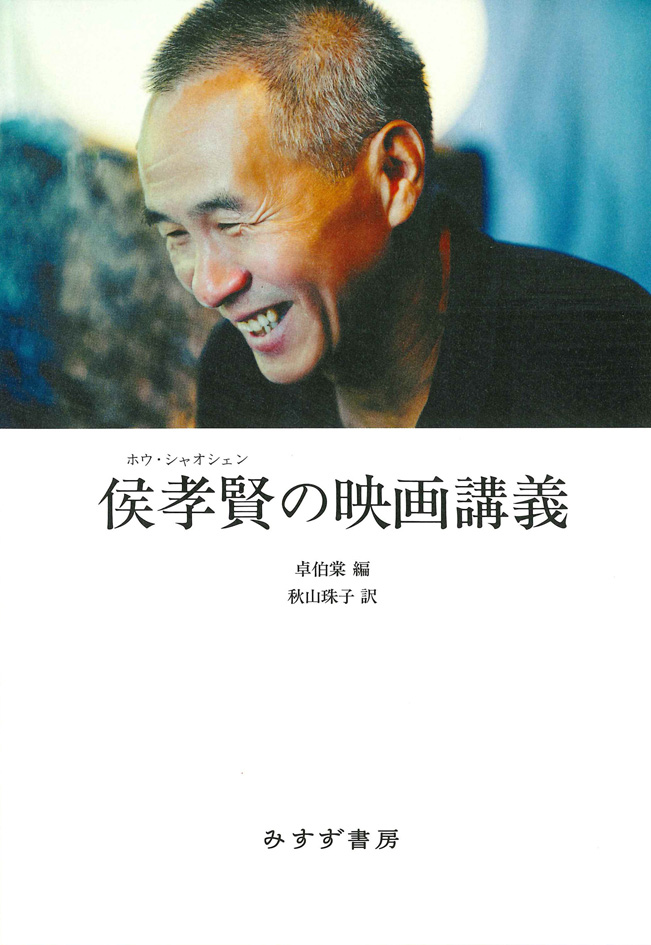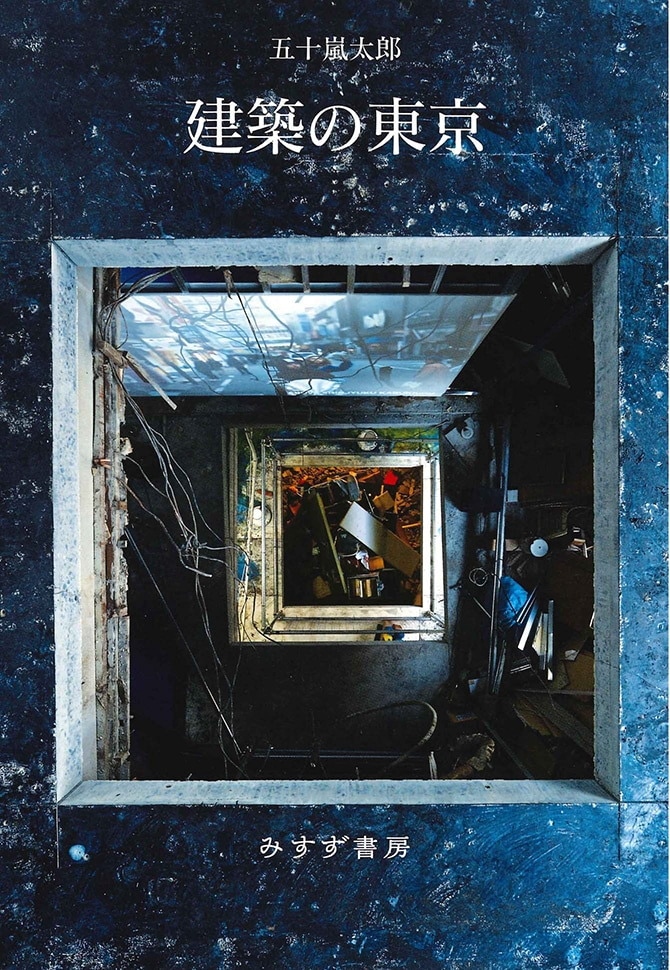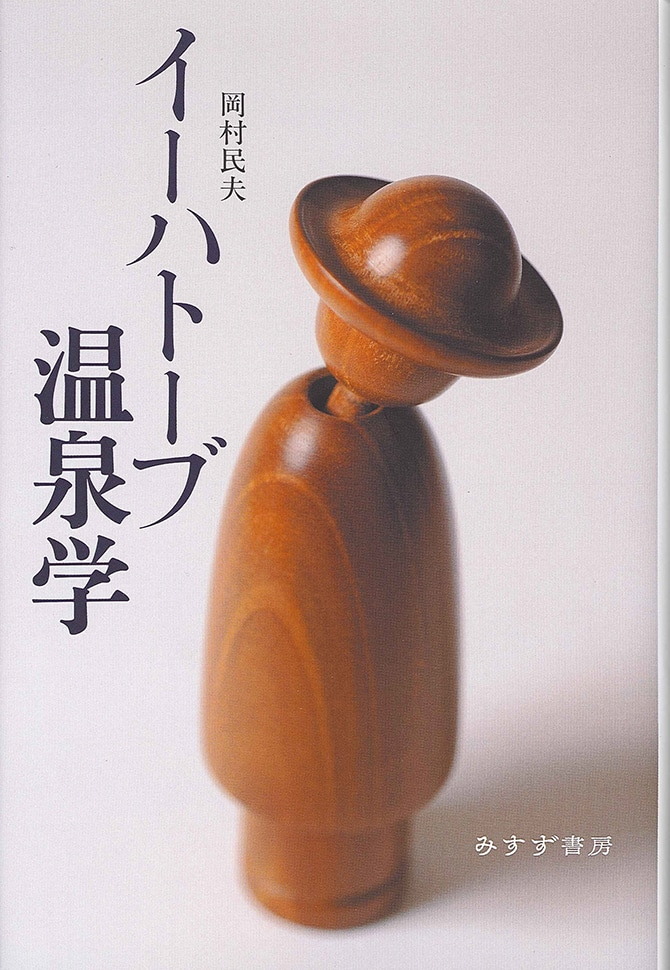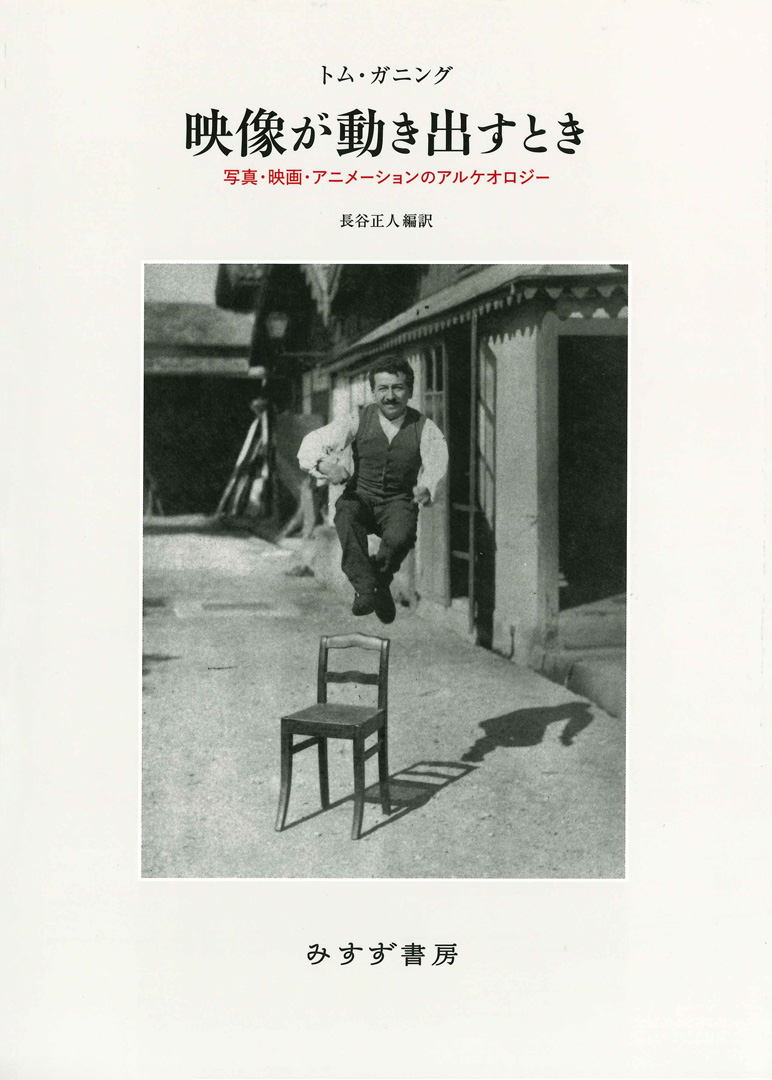ステファヌ・ルルーが博士論文『アニメの空間演出術(セノグラフィ)と映画術(シネマトグラフィ)──東映動画からジブリまで(1968-1988年) 高畑勲と宮崎駿によるリアリズム派』をもとにラルマタン社から『シネアスト高畑勲──アニメの現代性(モデルニテ)』(Isao Takahata, cinéaste en animation: modernité du dessin animé)を刊行したのは2010年、『シネアスト宮崎駿──奇異なもののポエジー』(Hayao Miyazaki, cinéaste en animation: poésie de l’insolite)を刊行したのは翌年である。諸般の事情から第1巻の本書の翻訳があとまわしとなってしまったことをお詫びしたい。2010年にはルーマニア出身のマリア・グラジディアンによるドイツ語の『高畑勲』(Takahata Isao, Peter Lang)が6月に刊行されているが、ルルーの本は一月に出ている。小谷野敦の『高畑勲の世界』(青土社)が出たのは2013年であり、それ以降日本でも単独の著者による本は出ていない。つまり単著の単行本としては『シネアスト高畑勲』はたぶん世界初の高畑勲論であり、いかに先駆的で貴重な仕事かがわかろう。
『シネアスト宮崎駿』では、宮崎が高畑のかたわらで学んだリアリズムと自分自身の「驚異的なもの」(冒険活劇、神話的ファンタジー、奇妙な機械や乗り物)への志向をかけあわせながら作品のスタイルを練りあげるプロセスが論じられていた。本書ではその前提となっていた高畑的リアリズムが焦点となっている。その意味で本書は『シネアスト宮崎駿』の理解を深めるのに役立つ潜在的な宮崎論でもある。高畑やスタッフの発言、絵コンテや資料集などはずいぶん参照されているが、日本人研究者の論考はほとんど参照されておらず、制作事情、伝記的情報、日本社会などの理解には不十分なところもあろう。けれども、そうした方面の充実は外国の青年の先駆的研究にかならずしも求められる事柄ではあるまい。そのような不足があろうともルルーの高畑論には日本のアニメ界に閉じがちな日本国内の議論に対して生産的刺激となりうる緻密さとスケールがそなわっている。そこでは西洋の長編アニメ映画との比較を伴った緻密な映像分析がなされ、高畑の仕事が世界アニメーション史における「現代性」の創出として位置づけられる。それだけでなく実写映画──ルルーはもっぱら「伝統的映画」と呼んでいる──の性質や歴史がたえず参照枠とされ、「アニメの現代性」が世界映画史の地平に位置づけられる。これは海外のアニメや実写映画に精通し、「アニメーション映画を通して映画作品をつくる」(p. 57)という志をもって日本のアニメを革新したシネアストに対してたいへんふさわしいアプローチではないか。
「現代性」と呼ばれているのはたんなる新しさ、現在への近さではなく、1930年代後期から50年代のディズニーアニメを範とした長編アニメの「古典主義」に対するアンチテーゼであり、批判的な新しさである。そして「現代性」と不可分な「リアリズム」とは、たんなる現実の自然主義的再現ではなく、ストーリーの円滑な進行に抵抗するざらつきをあえてアニメに導入する美学である。
「古典主義」においては映画世界が主人公を中心に求心的に組織されており、それ以外の人物も事物もひたすら主人公の物語を盛りあげるための従属的役割にとどまる。そしてその映画世界は容易に把握できる「驚異的」見世物、閉じた自己完結的世界として呈示され、その制約のなかで観客はみずからを全知の遍在的超越者であるかのように錯覚する。こうした根本的性格を形式の次元で支えているのは正対的人物の横方向のアクション、中心的なものを定めるフォーカス、求心的フレーミング、入れ子型イントロダクション、なめらかなつなぎなどである。
ルルーは、高畑の映画第1作『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968年)において画面の奥行きを活かした場面演出術、パンフォーカス、撮影カメラの存在感やそのエフェクトの模倣、はずれたフレーミング、遅れたフレームイン、視野以前からのインとアウト、そっけないイントロダクション、無造作なカットつなぎなどの駆使を通し古典的時空が解体され、別種の時空が立ちあがっていることを詳細に検証している。主人公の体験にも観客の知覚にも還元されえないそれ自体としての厚みをもった時空として映画世界が「実在感」を獲得し、観客は物語の流れに抵抗する唐突な出来事や、解釈に開かれた欠落や謎がある出来事を前に「臨場感」を感じる。その物語内容上の画期性、すなわちヒルダの二面性やアイデンティティのゆらぎと多元的で動的な集団劇は、映画世界の「実在感」「臨場感」と不可分な仕方で表現される。
外的・内的制約のせいで高畑やスタッフの野心が不十分にしか実現されなかったとはいえ、『太陽の王子 ホルスの大冒険』は間違いなく世界アニメーション史上革命的作品だ。ただし突然変異のように出現したわけではない。ルルーは、ディズニー的規範からはみだした先駆的作品、高畑自身がはっきりと意識した1950年代の傑作、ポール・グリモーの『やぶにらみの暴君』(1952年)、ハラス&バチュラーの『動物農場』(1954年)、レフ・アタマーノフの『雪の女王』(1957年)との比較考察をしっかりおこなっており、それは継承と飛躍の複雑な関係を浮かびあがらせた繊細でていねいな考察となっている。『安寿と厨子王丸』(1961年)や『わんぱく王子の大蛇(おろち)退治』(1963年)との比較考察についても同じことがいえる。これら二作品のなかに奥行きのある構図‐逆構図、複雑なカメラワーク、唐突な画面通過といった『太陽の王子 ホルスの大冒険』を予感させる手法が散見することが指摘され、演出補として参加していた高畑による可能性が示唆される。
興行的惨敗のせいで東映動画を退社したあと、高畑の「アニメの現代性」はどうなったのか。第5章「『ホルス』後、人間的リアリズムへ」でルルーが説いているのは、一言でいえば以前より簡素なスタイルによってそれがいっそう推し進められたということである。
第一に、高畑は70年代のテレビシリーズ制作の厳しい条件下(リミテッドアニメーション、低予算、1週間ごとの納期)で『太陽の王子 ホルスの大冒険』に見られた派手で複雑なアクション、カメラワーク、カメラ効果、モンタージュを控えたが、全50回以上の大河ドラマ的シリーズのなかでフィックス、長まわし、ズーム、同じ場所の反復的登場などのシンプルな手法をたくみに運用することを通し、従来アニメには不向きとみなされていた日常的時間や年代記的時間を表現した。
第二に、こうしたテレビシリーズの過程でだんだん登場人物の記憶、想像、夢、幻想などを慣習的なフラッシュバックを介さずに導入するようになり、カットつなぎやワンショットで「日常的リアリティ」と「精神的リアリティ」を共存させ、隠れた心理を表現した。つまり「現実」の概念を拡張し重層化した。
第三に、原作を発想源としてのみ受容する宮崎駿と異なり、高畑は原作の批評的読解にもとづいた翻案を通して人間心理の繊細な「演出」に傾注した。
第四に、第二、第三と関連し、高畑は感情移入を優先する演出から遠ざかり、「異化されたリアリズム」へ向かった。それはスタジオジブリにおいて『火垂るの墓』(1988年)から明確に企てられ、『おもひでぽろぽろ』(1991年)で高度な達成をみた。この映画は「観客を単一で連続した筋のなかに引きこまず、思い出という次元によってある種の媒介を設け」ている。
『太陽の王子 ホルスの大冒険』が革命的だったとはいえ、それに4つの章が割かれ、その後の諸作品の分析が最後の第5章に押しこめられているのは高畑勲論としてはたしかに均衡を逸している。とくに「異化されたリアリズム」の論述は他の部分と比べ足早な感が否めない。もっともルルー自身そう感じていたのだろう。あるいはこの構成は一種の話術だったのかもしれない。彼は『シネアスト宮崎駿』でも『ルパン三世』第1シリーズ(1971年)から『ホーホケキョ となりの山田くん』(1999年)までの作品についてしばしば考察を述べ、とくに『風の谷のナウシカ』(1984年)以降の宮崎作品の叙法が主人公の視点に寄り添って観客の感情移入やファンタジックな冒険への没入を誘う傾向を強めたことに対する高畑の批判に言及しながら、「異化されたリアリズム」を補説し、字幕、ナレーション、絵柄なども異化=距離化に関与することを示す。これは、宮崎の変化に対するアンチテーゼの提出という反語的なかたちで、高畑が宮崎の影響を受けたということを含意する。本書が潜在的な宮崎論であるのに劣らず、第2巻は潜在的な高畑論なのである。本書から読みはじめた読者にはやはり第2巻の併読をお薦めしたい。
ルルーは高畑に影響を与えた可能性の高い実写映画を、映像の具体的表情にもとづきながらそこかしこで挙げている。たとえばホルスとブランコに乗ったヒルダが見つめあうシーンに関して、ジャン・ルノワールの『ピクニック』(1946年)の影響をみているのは慧眼といえる。ルルーは知らなかったようだが、高畑は『一枚の絵から──海外編』(岩波書店、2009年)の「申潤福〈蕙園傳神帖〉から〈端午風情〉」のなかでこのシーンの魅力と撮影方法に言及していた。さらにルルーが高畑の「日本ヌーヴェル・イマージュ」フェスティバルでの講演からヒルダのブランコ・シーンをめぐってフランソワ・トリュフォーの『大人は判ってくれない』(1959年)に言及した部分を引用し、その影響可能性を示唆しているのも興味深い。
『アルプスの少女ハイジ』(1974-75年)の山小屋における牧師とアルムおんじの対話シーンが、オーソン・ウェルズの『市民ケーン』(1941年、日本公開1966年)の小屋における銀行家とケーン少年の両親との対話シーンを参照に演出されているとする指摘は、双方のシチュエーションだけでなくカメラワークも酷似しているので間違いあるまい。
『市民ケーン』はすでに死んだ主人公の人生を複数の人物の証言=フラッシュバックを介して表象した叙法でも画期的なので、高畑の「異化されたリアリズム」にも影響した可能性があるだろう。ただし記憶や幻を現在の客観的場面にシームレスに導入する演出を重視するルルーが挙げるのは『8 1/2』(1963年)や『フェリーニのアマルコルド』(1973年)である。私の知るかぎり高畑の書いたものやインタビューにフェリーニは登場しないが、『かぐや姫の物語』(2013年)のプロデューサー西村義明は、高畑が同作の脚本執筆時に書き込みの多い「フェデリコ・フェリーニの『道』〔1954年〕の脚本だったと思う」古びた冊子を彼に見せ、「こうやって、勉強した時期もあったんですよ」と言ったと記していた。高畑のネオレアリズモへの愛好(…)を考えれば、初期に『道』のようなネオレアリズモ系の映画を撮っていたフェリーニ(およびアントニオーニ)のその後の仕事をフォローしていた可能性は十分ある。なお溝口健二を観ていたことは確実なのだから、客観的場面にワンショットで幽霊が平然と出現する演出で名高い『雨月物語』(1953年)の影響も想定できよう。実際、第二巻でルルーは現在と過去をワンショットで撮る監督として「溝口やフェリーニ」をあげている。
重要なのは、こうした指摘が元ネタ探しの羅列ではなく、以下のような映画史的展望──「序」に凝縮されている──にもとづいていることである。
古典的ディズニーアニメには30-40年代のハリウッド映画の「フレーミングの階梯に相当するものや、カメラの動き、つなぎ」が見られ、「上出来のハリウッド映画に準じ(…)ハリウッド映画の極相にあた」る。「長編アニメはスタジオの強力なロジックを必要とする。このロジックはアメリカで30年代にウォルト・ディズニーによって定められ、40年代から50年代を通して(…)他の者たちによって継承された」。
欧米における撮影所システムは50年代以降しだいに衰退し、実写映画は「50年代から60年代に深い変動を経験した」。にもかかわらず長編アニメ映画のほうは「他のジャンルよりスタジオの美学、共同の創造の仕方と内的に結ばれているので、果敢さや新しすぎることを受け容れる余地がたいしてな」く、ほとんど変わらないままだった。ルルーによれば、だからこそグリモーやハラス&バチュラーは「古典主義」に抗する長編をつくる際、大きな困難に遭遇し、その後短編やリメイクしかつくれなかった。
監督となる自己形成期に高畑に本質的影響を与えたと思われるルノワール、ウェルズ、溝口、デ・シーカなどは撮影所システムが堅固な時代に標準的スタイルから逸脱し、画面の奥行き、長まわし、複雑なカメラワークを通して出来事の「実在感」や「臨場感」ないし両義性を表現したユニークな監督たちにほかならない。そしてイタリアのフェリーニやアントニオーニ、フランスのトリュフォーやゴダールは、こうしたマイナーな先行監督の仕事を継承しながら50年代末から60年代に映画の「深い変動」を引き起こした「作家」である。つまり高畑は、30年代から60年代の反主流的実写と50年代の反主流的アニメーションの流れを束ねて革新的作品を創造したということになる。
感心するのはルルーが高畑の微細なポジションをしっかり捉えていることである。「『太陽の王子 ホルスの大冒険』は革命をジャンルの内部、大手スタジオの伝統的枠組みのなかで企てている」。そのため、この創作における高畑は従来のようなさまざまなスタッフの仕事の「調整者」よりは「〈作家〉の概念に近いポジションに立っ」ており、日本のアニメ史上初の「本物のシネアスト」である。けれども、スタッフの諸提案を取捨選択し統一するというやり方を積極的に選んだという点で、はじめから大手スタジオの撮影所システムの外でインディペンデントとして映画を撮ったヌーヴェルヴァーグの監督たちとは大きく異なる。高畑は70年代半ばからもっと集権的に監督した作品を発表するが、それもヌーヴェルヴァーグ的作家性に収まらない。彼らが大がかりなセット撮影ができず、主としてロケ撮影を選んだのに対し、高畑は実写のセットに相当する「美術背景」を積極的に活用しつづけたのだから──「アニメをそれ以外の映画制作と区別しているのは舞台装置の極度の厳密さと存続であって、これは現代性の勃興による変動以後もずっと存続するだろう」。ルルーの映画史的展望を延長していえば、撮影所システムの崩壊とともに崩壊したセットの美学の「現代的」な継承・展開が高畑以後の日本のアニメのなかにみられるということでもある。
最後に日本映画史の観点から若干補説しておこう。ルルーは東映動画の長編映画制作が始まった時代、すでにヨーロッパやソヴィエトのアニメーションスタジオは長編映画を断念していたことを指摘している。アメリカでも60年代前半には大手撮影所のアニメーション部門の廃止や縮小があいつぎ、ディズニーも美学的には停滞した。このタイムラグは、本質的には映画の撮影体制の推移のタイムラグに帰すことができよう。欧米では撮影所システムが衰退していった50年代、日本の撮影所システムは発展していった。1958年に年間観客数が頂点(のべ11億人強)を記録し、1960年に年間制作本数が頂点(547本)を記録した。産業としての日本映画が衰退していくのは普及するテレビに観客を奪われた60-70年代である。東映動画が発足した1956年、『白蛇伝』が完成した1958年は日本の撮影所全体の全盛期のさなかだったわけだ。日本のこうした「遅れ」がかえって高畑らに欧米の先行作品を反省的・批評的にみる距離をもたらしたという側面があろう。そして60年代後期に「スタジオのロジック」と闘いながら『太陽の王子 ホルスの大冒険』を制作できたのも、衰弱していたとはいえ東映動画の撮影所システムがまだ機能していたからに違いない。
高畑・宮崎の小プロダクション遍歴とスタジオジブリ結成は、いずれ撮影所システム崩壊後の組織づくりの模索のユニークなケースとして記述されるべきだろう。(…)
Copyright © OKAMURA Tamio 2022
(筆者のご同意を得てウェブ転載しています。
なお転載に際し行のあきなどを加えています)