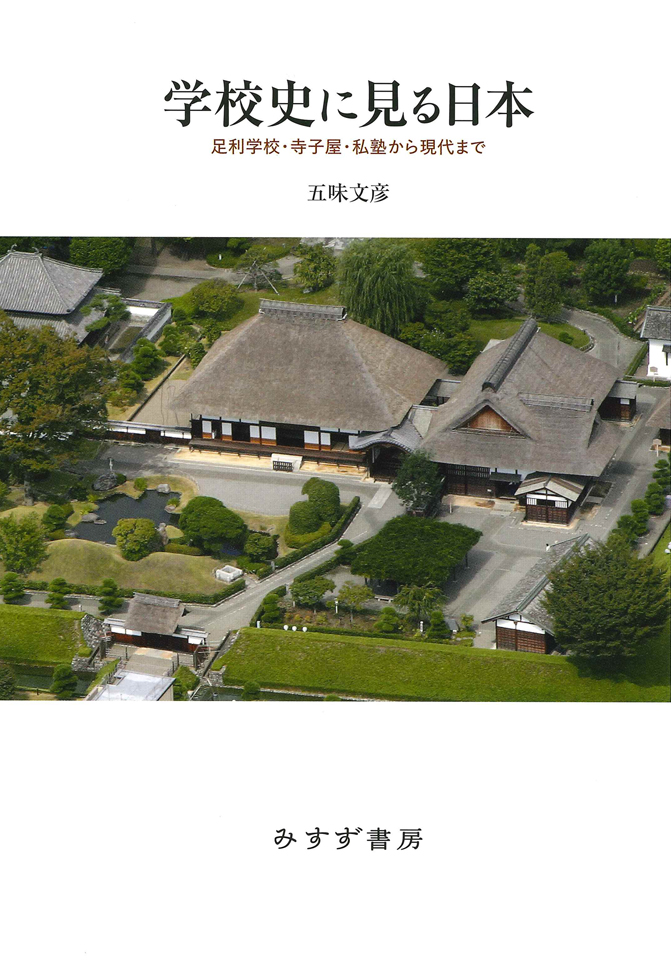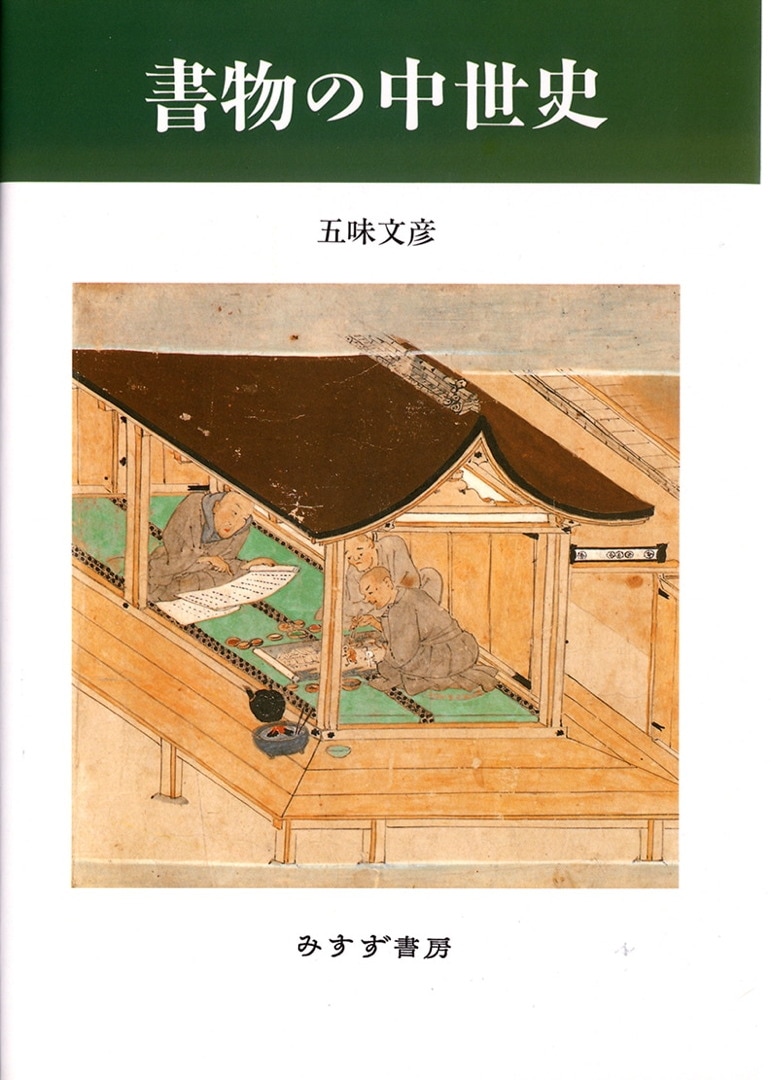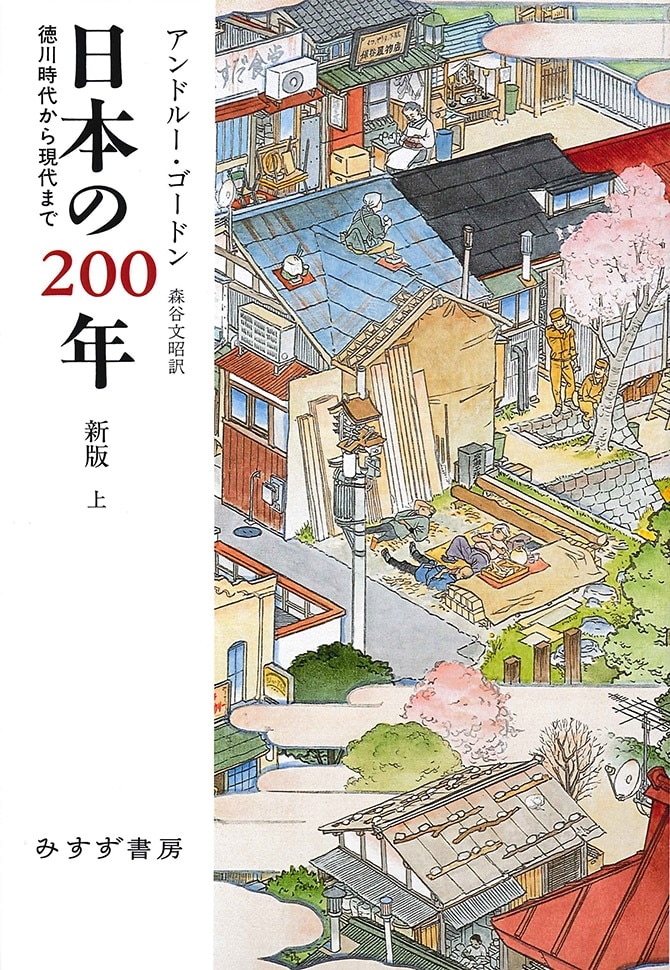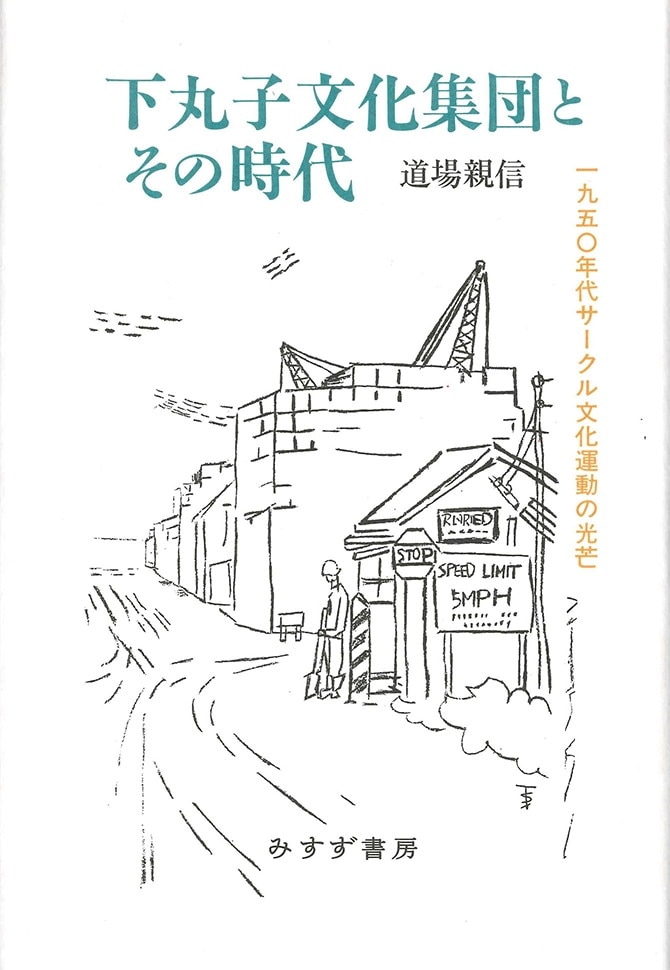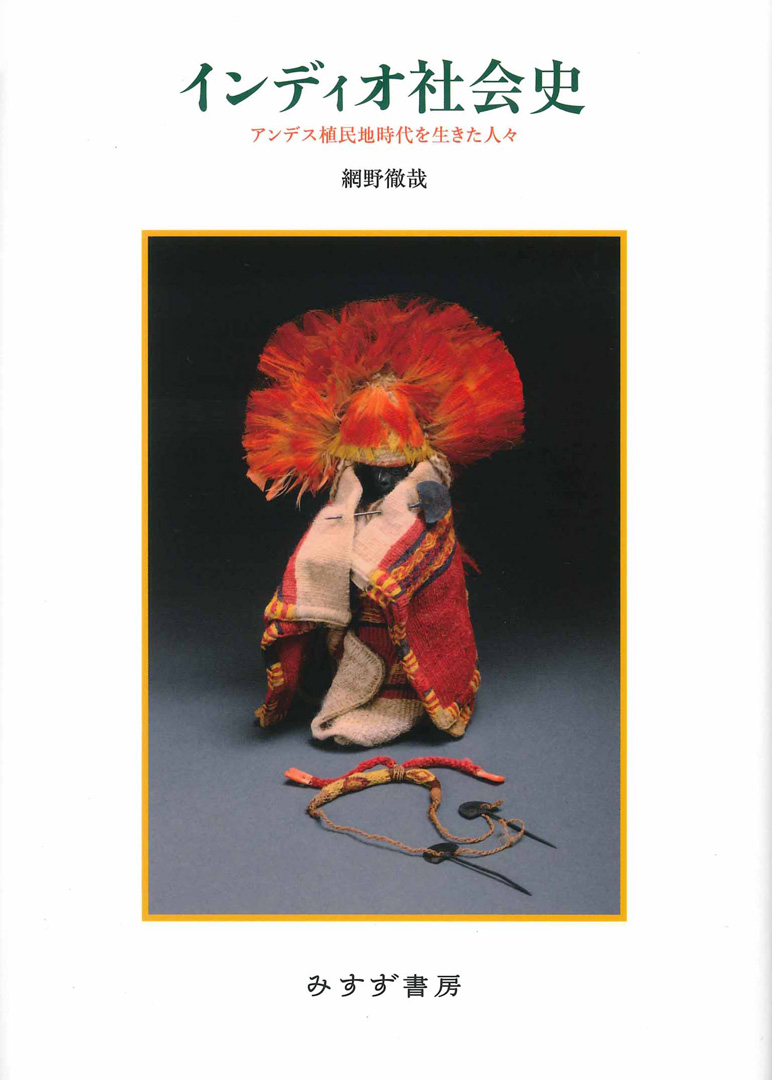古代から現代に至る学校の歴史を、時代の動きに沿って見てゆくことにしよう。興味深い事項や現代に直接につながる問題を取り上げるのは当然としても、それだけでなく学問や教育との関わりに注意し、しっかり丁寧に、わかり易く記してゆきたい。それによって現在のコロナ「社会」における学校の在り方や、学校の存在意義が見えてくるであろう。
本書で扱う藩校や塾、寺子屋などの語については、『礼記(らいき) 』に「家に塾有り、党に庠(しょう)あり、術(すい)に序有り、国に学有り」とあって、その家は二十五戸、党は五百家、術は一万二千五百家からなるもので、それぞれの大きさの単位に基づいて、塾・庠・序・学などの学校が周代に存在し、これに基づいている。
(はじめに)
足利には学徒が多い時で四千人を数え、それに荘住人をも含め五千人ほどにもなろうか。そうであれば足利は学園町であったといえよう。日本で初めての学園町であったわけである。
フロイスの『日本史』は、「全日本でただ一つの大学、公開の学校が、坂東地方の足利と呼ばれるところにある」と記し、足利学校が公開の学校であり、多くの人々に開かれた学校、唯一の大学であるという。
そうであれば、学校のある足利の地を戦乱から守らねばならない。天正八年(一五八〇)十月に甲州の武田勝頼は「学校」に「軍勢甲乙人等が寺中に於いて濫妨狼藉するのを停止」しており、同十一年十月に相模の北条氏康も同様の禁制を出し、「鑁阿寺・学校」の両所を「加敗」(保護)することを伝えている。鑁阿寺・学校がある足利は平和領域として機能していたのである。
(第二章「学徒の町・足利」「学校の講義と学徒」)
閑谷学校はその呼称といい、藩主の墓所(和意谷墓所)の近くに設けられたことといい、足利学校と同じく、特別な保護が加えられ、単なる郷学とは異なる学問所、学校に発展していった。地方の指導者を育成するために、武士のみならず庶民の子弟をも教育し、広く門戸を開き、他藩の子弟も受け入れた。就学年齢は八歳頃から二十歳頃まで、一と六の日に講堂で講義があった。在学者は三十〜五十名、藩校と同様に朱子学が講じられ、課外には教授役などの自宅で会読・研究がすすめられた。
閑谷学校は「郷校」として新たな発展を遂げた。君立が文化十一年に丹後田辺藩の牧野豊後から依頼され記した『閑谷学校課業規則』には、民間の入学希望者は、家主名を記し、村役人が認めた願書を提出、岡山学校惣奉行がこれを聞き届け学房に渡すことで入学できた。家中の子弟も同様で、近村から通学する者は、習字所・講堂に出席、他領から入学を願う者は一年を限り、民間に逗留して引受主が入学願を出し、習字所で習机、木硯、玉盤、習筆、刷毛、水入れ、手本の紙も渡された。
(第三章「閑谷学校」、第四章「閑谷学校の世界」)
当初は経営が不安定だったが、文化七年に淡窓は詩「桂林荘雑詠諸生に示す」を掲げ、塾生の教育に邁進した。
文化十四年(一八一七)、堀田村に塾を移すと、塾名を「咸宜園」とした。入塾希望者は、入学金を納入して入門簿に姓名・郷里・紹介者など必要事項さえ記入すれば、誰でもいつでも入塾できた。入塾にあたっては身分・学識・年齢の差が奪われ(「三奪」)、平等に学ぶことができ、優劣の差がつくのは学問のみであった。
様々な人材を育てたのが、日田の咸宜園である。来学者が増大し、塾舎外に寄宿人もでたので、北隣の長兵衛の家を借りて甲舎、他にも家を借り乙舎と称し、丙舎には「居家生」を住まわせた。天保十年(一八三九)の塾生は、月旦評の百五十五人、在塾生三十九人、外塾生十一人、居家生十五人、帰省中の帰省生が五十五人で、月旦評の等級も九級に上下の別を加え、無級もあわせて十九級となった。
(第四章「咸宜園の教育」、第七章「三計塾・山梔窩・咸宜園」)
この改革の時代にあって、水戸藩主徳川斉昭は藩改革を行ない、幕府に改革を求めるなか、天保九年(一八三八)に神儒一致、忠孝一致、文武一致、学問事業一致、治教一致に基づく藩校設立の「弘道館記」を作成、同十二年(一八四一)七月に水戸城三の丸内に弘道館が落成して、安政四年(一八五七)五月に本開館となった。
その弘道館と一対の施設となる偕楽園を、「一張一弛(いっちょういっし)」の考えから、修業の間の休息も教育の一つであるとし、天保十三年に弘道館の西約二キロの景勝の地に修養の場として設けた。今につながる偕楽園である。
財政窮乏にもかかわらず規模は大きく、文武両道を教育方針として広く諸科学、諸学問を教育・研究、医学や天文学など自然科学教育研究をも行ない、総合大学的性格が認められる。学校創設の意見『学問所建設意見書』を著した会沢正志斎と青山延光とが教授頭取となり、藩士とその子弟の十五歳から四十歳までの者に規定の日割に基づき修業を義務づけた。
(第六章「水戸の弘道館」)
やがて改革の時代、文明の時代、経済の時代、文明と戦争そして敗戦後、環境の時代から今日へ。これから学校は社会の時代へ向かうのか。将来をも本書は洞察する。
〈学校史〉から歴史の流れを語りおろす。類のない日本通史。