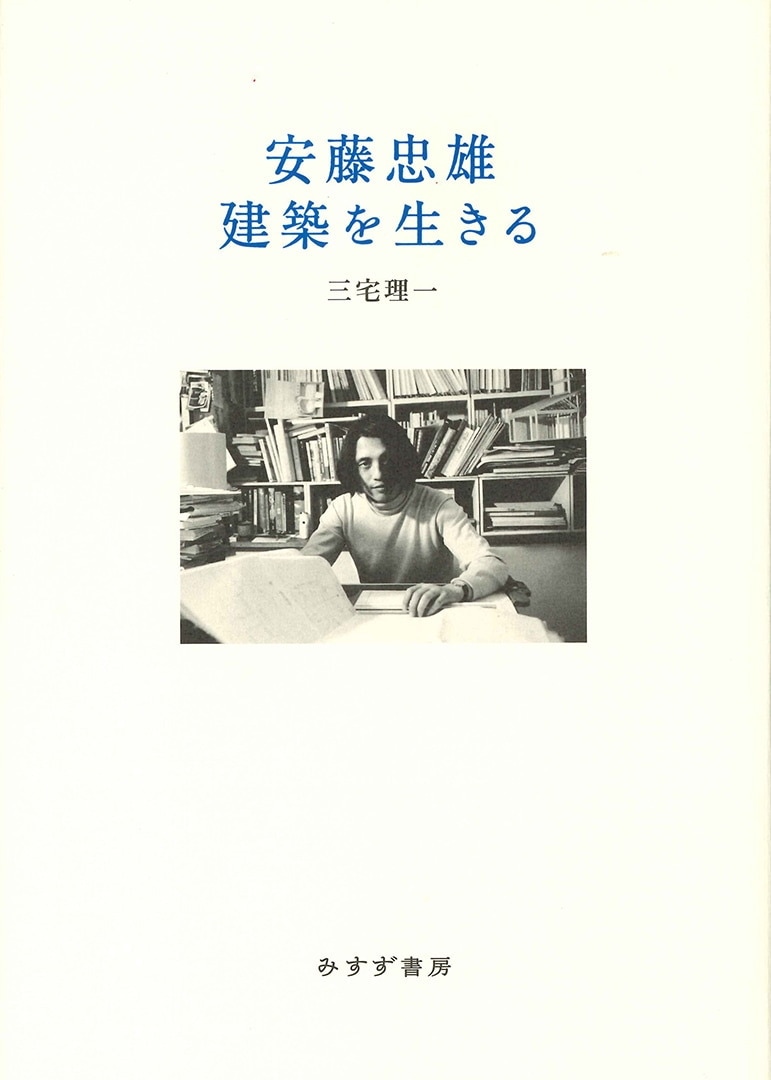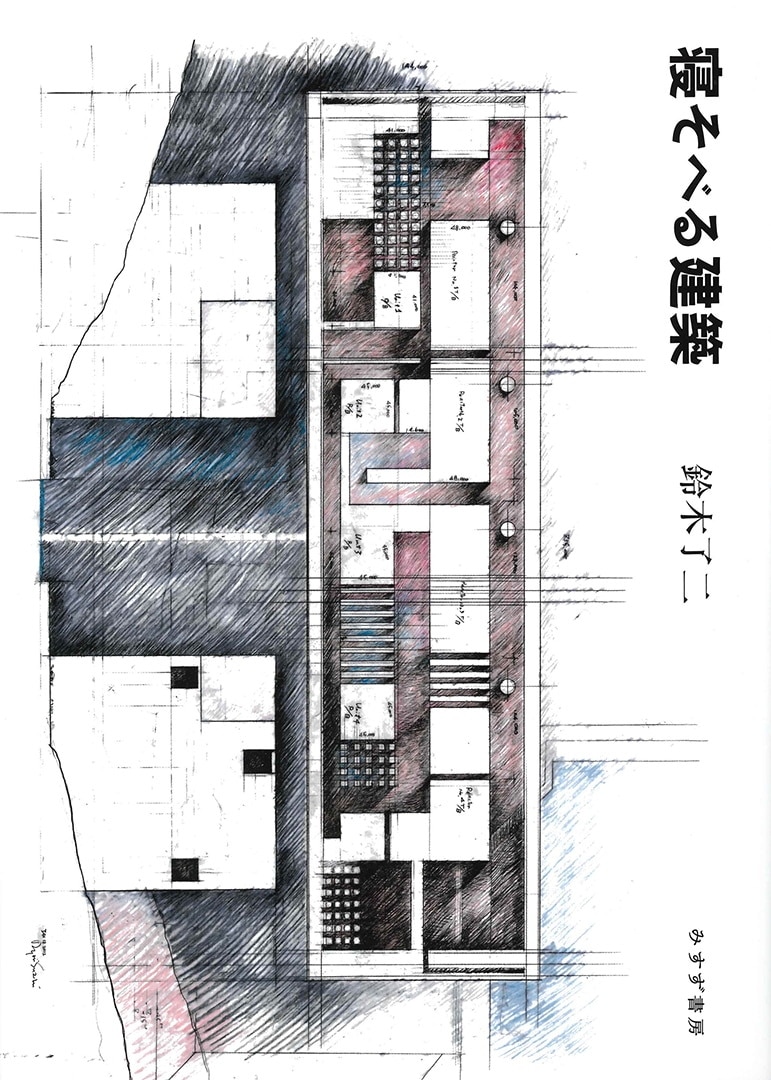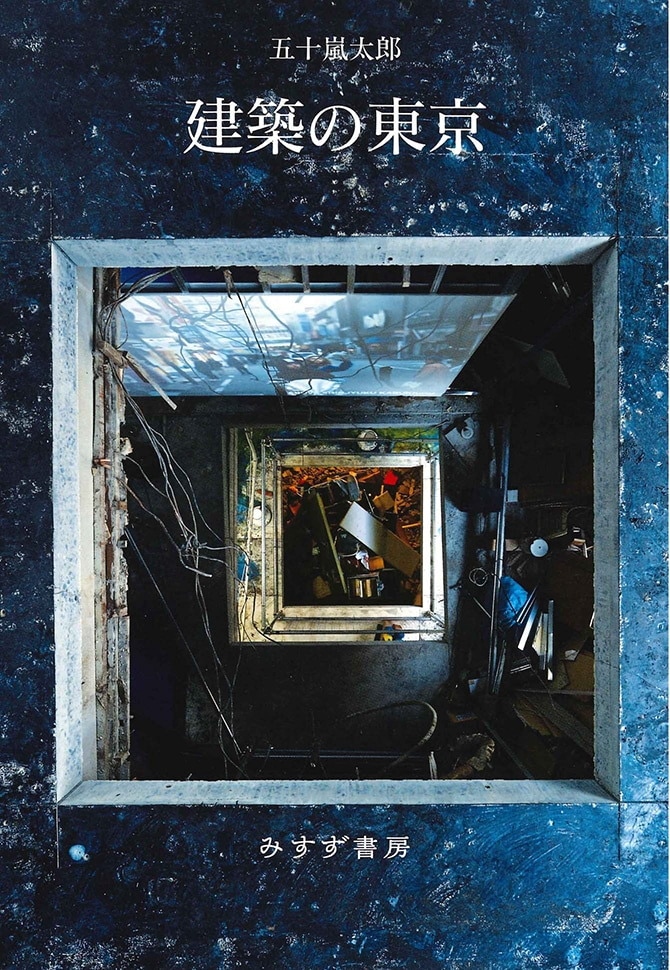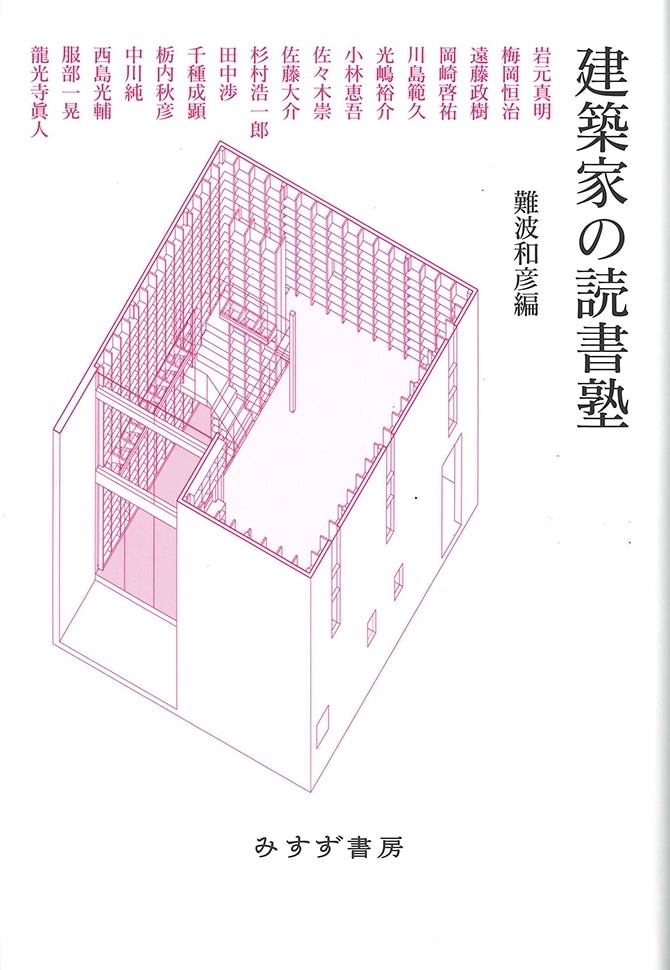内藤廣
コロナ禍は建築の何を変えるのでしょう。無責任な予想をいえば、急には何も変わらないと思います。歴史的にみれば、建築はいつも時代を先取りするどころか半歩遅れて時代の空気をまといます。その例にならえばしばらくは何も変わらないはずです。
しかし、その先となると話は少し違ってきます。社会が不安定になったり不透明になってくれば、人々の心は必然的にみずからの暮らしを守り固める方向に傾いていくでしょう。すでにこの流れは始まっています。これを機にテレワークが進めば住まいで過ごす時間が増え、その環境を充実したものにしたいという希望が増え、そうした空気が住宅を染めていくはずです。コロナ禍以前、住宅をめぐる昨今の傾向は、「仮の住まい系」と「終の住まい系」に分かれつつあると言及したことがありますが、ここからは「仮の住まい系」は分が悪くなりそうです。狭隘密集した都市部での仮の住まいなら、いっそ自然豊かな低密度の地方へ行ってしまおうと考える人も増えてくるでしょう。
でも、これはかなりわかりやすい構図ですから、こんなことを難問を問う本書でくどくど述べても仕方ありません。想像力を駆使してそれ以外のこと、その先のことを考えてみることにします。
要は人と人とが物理的な距離をとることが求められる、あるいは物理的な距離があってもなんとか社会生活ができそうだということに気づいたときに、人が密度をもって集まることが嫌悪されるとしたら、都市をめぐるこれまでの傾向が大きく変わってくるということです。当然、都市に建つ建築のあり方も変わってきます。
これまでは都心にある立派な超高層に会社があることが社会的な信用を醸しだすステイタスになっていて、晴れやかで巨大なエントランスホールを抜けて、その先にあるエレベータホールに向かうことが何よりの誇りとなっていたような時代は、早晩色あせて見える時代が来るかもしれません。
あんなガラスの箱の人工環境の密閉空間に日がな通って何が嬉しいのか、と多くの人が思うようになれば、都心部にある多くの巨大プロジェクトは瓦解します。開発のプログラム自体に心理的な一抹の不安、すなわちコロナ禍によってバグが入ったのです。みんなが価値があると思えば値段が上がり、みんなが価値がないと思えば値段は下がる。その恐怖が資本主義経済を走らせてきたわけですから、巨大プロジェクトは最大効果を求め、それを前提にして組みあげられてきました。額は大きいけれど、投資と回収の単純きわまりないゲームだったのです。
もしこの資本主義のゲーム自体が破綻を来たすとしたら、東京という巨大都市は超高層ビルという数百の不良資産を抱えこむことになります。これは首都圏を経済のエンジンとして成り立ってきた資本主義社会の危機です。少なくともその引き金にはなります。もし政策立案側に先見の明がある人がいれば、そうならないための術を必死で考えるでしょう。新しい都市の物語を捏造する必要に迫られるはずです。かつて古代ローマのコロッセオは熱狂の坩堝でした。熱狂は社会的な現実に対する人々の目を見えなくさせます。ナチスによるニュールンベルグの党大会もそうでした。神宮外苑の学徒動員の集会もそうでした。超大人数の群衆が超過密に集まると何か不思議な力が人々を支配するようです。ソーシャルディスタンスなんて吹っ飛んでしまう。たぶん都市が滅びないためには、そうした現実から解離した都市的なイベントが企画されるのでしょう。オリンピック、万博、サッカー、ラグビー、eスポーツ、コンサート、なんでもありです。たとえそこが危険であろうと、都市を維持するために為政者はその危険な賭けに出るはずです。
やや呆然とした気分になりますが、建築や都市は何ができるのでしょう。密集を避けるような鉄道や駅、ソーシャルディスタンスを保持できるスタジアム、過密にならないライブハウス。どれも笑えるくらい戯画的です。心ある建築家はそうした施設から手を引くか、あるいはまったく異なる術に挑戦するかしかなくなるはずです。あるいはどちらもあきらめて、心を閉じてクライアントの奴隷と化す道もあるかもしれません。
いずれにせよ建築は誰のためにあるのか、都市は誰のためにあるのか、建築家とは誰なのか、本書で繰り返し問われた問いが繰り返される時代が来るはずです。この問いが繰り返し反芻されるあいだは建築や都市というテリトリーはまだ健全だと言えます。おそろしいのはこれらの問いが発せられなくなったときです。それは有史以来連綿と積みあげられてきた建築や都市という営みが完全に価値を失った時代の到来を意味するからです。
copyright © NAITO Hiroshi 2021
(著者のご同意を得て転載しています)