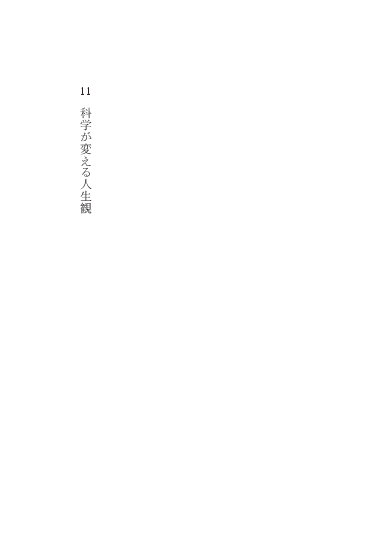
第11章「科学が変える人生観」冒頭(PDF、808KB)
「科学の世界と文学の世界には共通点が多い」との一文で『ガイアの素顔165』は始まる。その心は、いずれも国境や人種の壁を易々と越えるユニバーサルランゲッジだからだという。
そう語る著者フリーマン・ダイソンは、若くして頭角を現した早熟な理論物理学者にして、55歳で出版界にデビューした遅咲きの文筆家である。
ただし、文筆に関してもじつは早熟気味だったようだ。『ガイアの素顔』は、1980年代までに書かれた小文を集めたエッセイ集なのだが、いちばん古い収録作品は、なんと9歳のときに書いた「エロスと月の衝突」と題された未完の短編SFなのである。
『ガイアの素顔』の主題はほぼ一貫して科学と社会だが、知識と興味の赴く範囲が広いうえに、本気とも冗談ともつかない発言が、ダイソンの持ち味でもある。
朝永振一郎、シュウィンガー、ファインマンのノーベル賞同時受賞の業績をわかりやすく語ったかと思うと、有人火星探査は死の惑星に生命をもたらすエコロジーゲームだなどという見解を大まじめで披露するといった調子である。
あるいは、「私は科学者だから、予測不可能なことの専門家だ」という発言が、じつは逆説ではなかったりする。常識を打ち破り、「予測不可能な夢を実現させることこそ」が、科学ばかりか一般社会の課題であるとの着地点が、最後に用意されているからである。
そんな予測不可能性の専門家が4分の1世紀あまり前に下した託宣が、現時点においてなお、きわめて重みがあるから驚きだ。むしろ、科学教育や巨大科学のマネージメントに関する意見には、理科離れや最高の技術を尽くした科学技術のひずみが露呈している現時点でこそ、傾聴に値する点が多いとさえいえる。
ダイソンは、若者が科学を嫌う理由として、(1)権威主義的、(2)実利主義的、(3)核兵器などへの悪しき貢献をあげている。彼は、こうした醜悪な面を隠すのではなく、3つの美しい面とあわせて自由に科学を探求することを教えるべきだという。その3つとは、(1)科学は芸術の一形態である、(2)科学には権威を打破する力がある、(3)国家の枠を越えた国際性をもつことだという。
ダイソン自身が科学にひかれたのは、8歳から12歳までを過ごしたイギリスのプレップスクールでの体験だった。名門パブリックスクール進学準備のためにそこで行なわれていた教育は、ラテン語やギリシア語などの古典が中心で、科学の授業はなかった。強権的な校長と、サッカーフリークの学友たちからの逃避先として、科学に走ったのだという。
曰く、「科学とは無知に対する知の反逆であり、虐げられた者による抑圧者への復讐であり、横暴と憎悪のただ中に息づく自由と友情の聖域である」
『ガイアの素顔』は、首都ワシントンのまん中で土曜の真っ昼間に強盗に襲われ、倒れた地面から木々の緑と青空を見上げ、自然の懐(ガイア)に抱かれた思いを覚えるエッセイで終わっている。米国科学アカデミーの委員会に出席する道すがら、著者55歳のときの出来事だった。
そのときに受けた啓示が、「人間性の複雑さの源は、知性にではなく情緒にある。知的能力が目的を達成する手段なら、何を目的とすべきかを決定するのが情緒である」というものだった。ガイアと情緒の絆を保っているかぎり、人類は健全だと、ダイソンは語っている。
その後ダイソンは、アメリカ先住民のシーカヤックを復元した息子と何十年ぶりかの再会を果たすことになったはずである166。なるほど、人生いや自然は、予測不可能だからこそおもしろい。
世界的に大ヒットした映画「アナと雪の女王167」、日本では略して「アナ雪」とも呼ばれているようだが、原題は「フローズン」。雪と氷を自在に操れる秘密の能力を知られたエルサが氷の城にこもったせいで、国中が凍りついてしまうのだ。その氷を解かすのは愛の力、ただし白馬に乗った王子様の愛の力ではないところが味噌。
大ヒットの原動力は、なんといってもあの歌、一度聴いたら耳につく「♪レリゴー」だろう。
秘密を捨てて吹っ切れたエルサが、日本語版では「ありのままで」と訳されているあの歌を歌いながら氷の城を造るシーンは文句なしに美しい。ウェブで公開されている動画は何度見ても飽きない。思わずいっしょに歌いたくなる。
そのシーンを彩るのが雪と氷の結晶の美しさだ。特にエルサが地味な服を脱ぎ捨ててまとった女王のドレスを飾る繊細な雪の結晶模様。もしかしたらこのデザインも世界を席巻するかも。
ブームの先取りではないが、日本では江戸時代にすでに雪の結晶模様が大流行していた。当時は雪の結晶を雪華(せっか)と呼んでいた。なんとも優美な呼称だ。
雪華ブームの大本は、老中も務めた下総古河(こが)藩の城主土井利位(としつら)侯。利位は、オランダ伝来の顕微鏡を入手し、雪の結晶を観察してそのスケッチを『雪華図説』という私家版にまとめた。雪の結晶には千変万化の変異があることを世に知らしめたのである。天保3年(1832年)のことだった。
雪華ブームの直接の火付け役となったのは、鈴木牧之(ぼくし)が著した『北越雪譜168』。雪国の暮らしぶりを描き、江戸のベストセラーとなったこの書に、『雪華図説』からの図版が再録されていたのだ。
繊細な雪華模様は江戸の人々を魅了し、小物や手ぬぐいから着物まで、小粋なデザインとして採用された。サイエンスが文化に溶け込んだおしゃれな例というべきだろう。
大坂城代の任にあった利位は、大塩平八郎の乱を収めた。また、大坂城の庭で雪の観察をしたと伝えられている。しかしかなりの低温じゃないと、顕微鏡での直接観察はできない。
じつは、当時の日本は江戸小氷期と呼ばれるほど寒冷で、江戸でも大坂でも雪が珍しくなかったらしい。まさにフローズンな世界だったのだ。そんな中で雪見酒にふけることなく、顕微鏡観察に勤しんだ殿様がいたのである。しかも、雪と氷の宮殿と化した大坂城内で。
その100年後、北海道の地でサイエンスとアートを融合させた研究者がいた。夏目漱石の薫陶を受けて随筆家としても名を成した物理学者、寺田寅彦の高弟、中谷宇吉郎である。東京の理化学研究所からイギリス留学を経て北海道大学に籍を得た中谷は、その地でいちばん豊富に手に入る材料を研究対象に選んだ。雪の結晶である。
千変万化の雪華の秘密は、結晶が成長する上空の気象条件にあると睨んだ中谷は、実験条件をさまざまに設定した下での人工結晶の作成に1932年から取り組み、36年に世界で初めて成功させた。そして、雪の結晶の構造から上空の気象条件を推定する方式「中谷ダイアグラム」を編み出した。それを自ら端的に表現したのが、「雪は天からの手紙」という言葉である。
中谷はアートにも通じたサイエンスライターとしても活躍した。1938年に創刊された岩波新書の一冊として、今も読み継がれる名著『雪169』を上梓した。そこでは、人工雪の結晶の研究を始めたのは、科学的、実用的な観点もさることながら、雪の結晶を人工的に作れたら面白いだろうという遊び心だったことが明かされている。
また、雪を題材とした科学映画の制作も行ない、49年には映画プロダクション「中谷研究室」(後に岩波映画製作所に発展)まで発足した。
中谷は「イグアノドンの唄170」というエッセイを書いている。それは終戦の年の冬、羊蹄山山麓で疎開生活を送っていたときの思い出話となっている。雪に閉ざされた夜、子どもたちに「話」をせがまれたため、留学時代に友人からもらったコナン・ドイルの『失われた世界』(8章参照)を荷物から見つけ出し、みんなでストーブを囲みながら語って聞かせたというのだ。
しかも、1938年に南アフリカで古代魚シーラカンスが発見された話をその物語の枕にしたという凝りようである。そんな演出が子どもたちの想像力を大いに駆り立て、二男にいたっては「イグアノドンの唄」と題した詩を作ったという。その二男と長男は夭折したが、長女の咲子さんは長じてジョンズ・ホプキンス大学の岩石学教授、二女の芙二子さんは霧の彫刻で有名なアーティスト、三女の三代子さんはピアニストになった。
――続きは書籍をごらんください――
(165) フリーマン・ダイソン『ガイアの素顔──科学・人類・宇宙をめぐる29章』(幾島幸子訳、工作舎、2005)
(166) ケネス・ブラウワー『宇宙船とカヌー』(芹沢高志訳、JICC出版局、1984/ヤマケイ文庫、2014)
(167) ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ製作、クリス・バック、ジェニファー・リー監督「アナと雪の女王」(2013、アメリカ)
(168) 鈴木牧之『北越雪譜』(岩波文庫、1936)
(169) 中谷宇吉郎『雪』(岩波新書、1938/岩波文庫、1994)
(170) 樋口敬二編『中谷宇吉郎随筆集』(岩波文庫、1988)所収
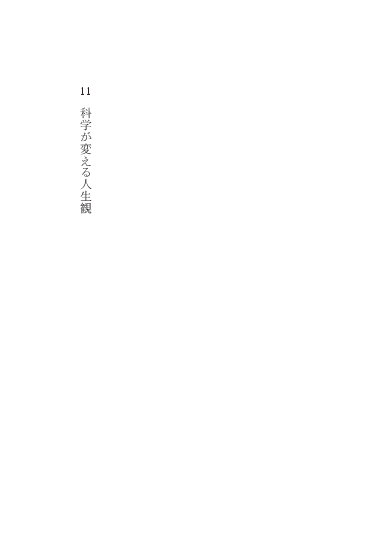
第11章「科学が変える人生観」冒頭(PDF、808KB)
copyright © WATANABE Masataka 2021
(著者の許諾を得てウェブ転載しています)