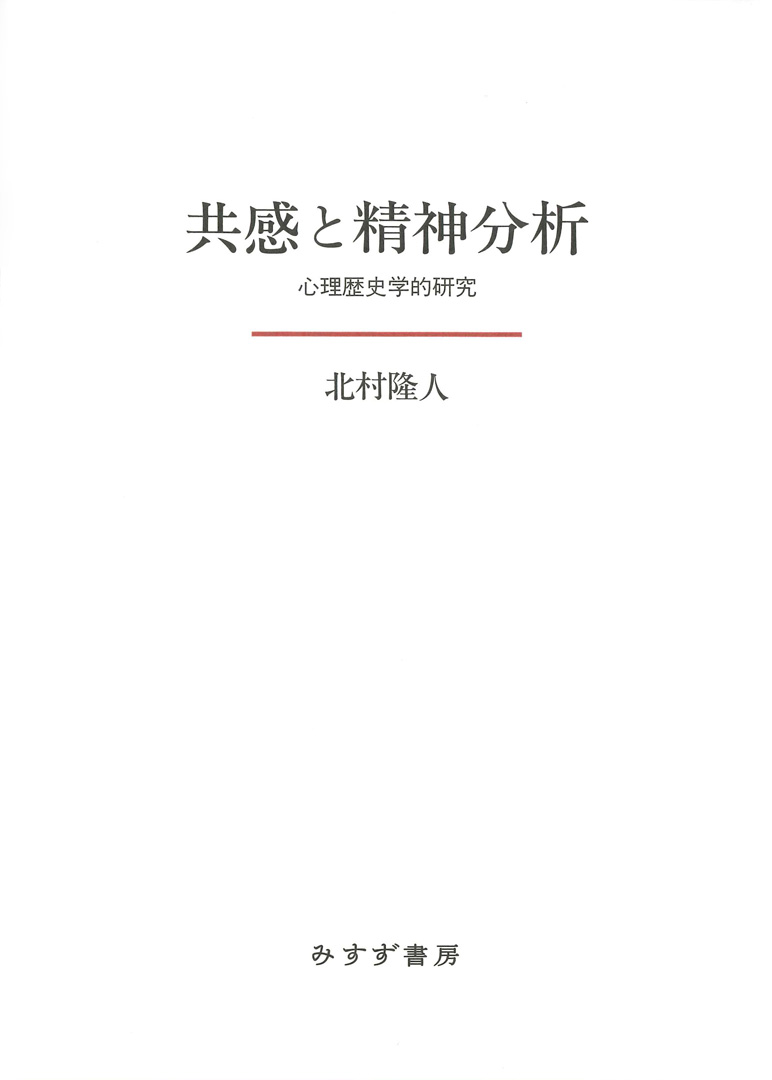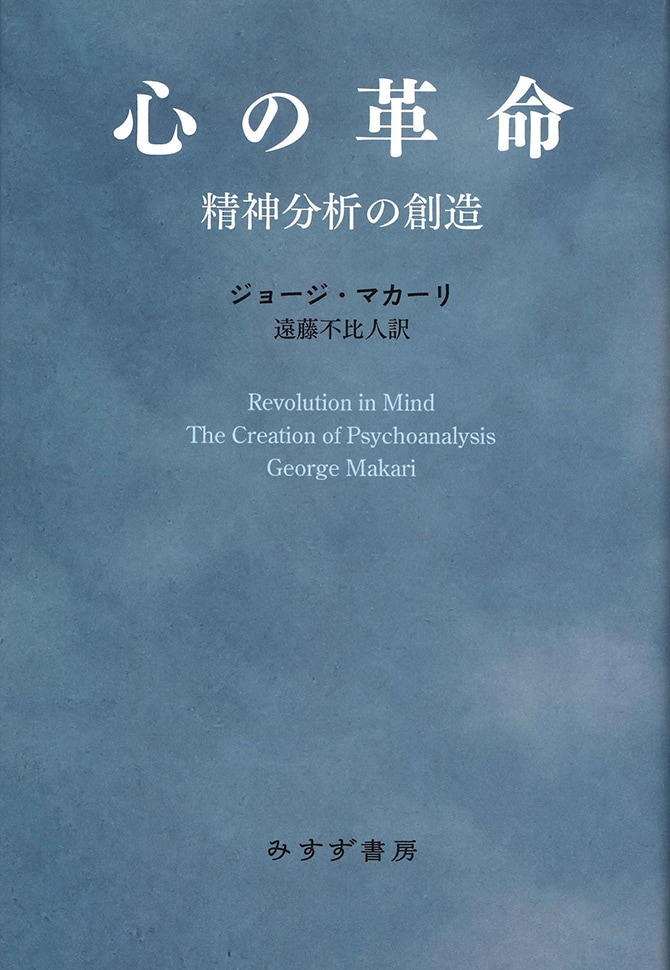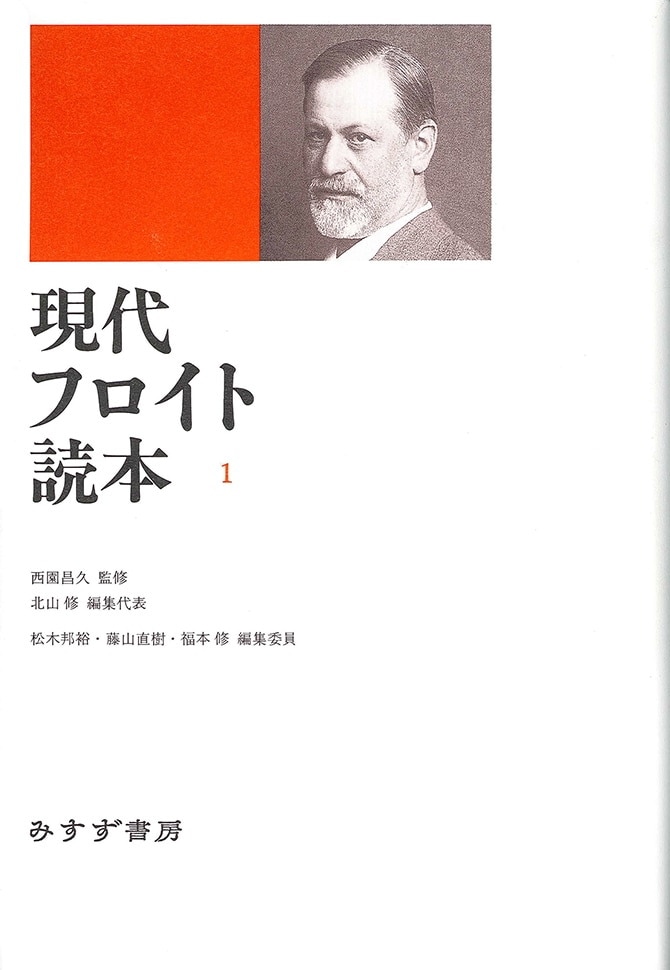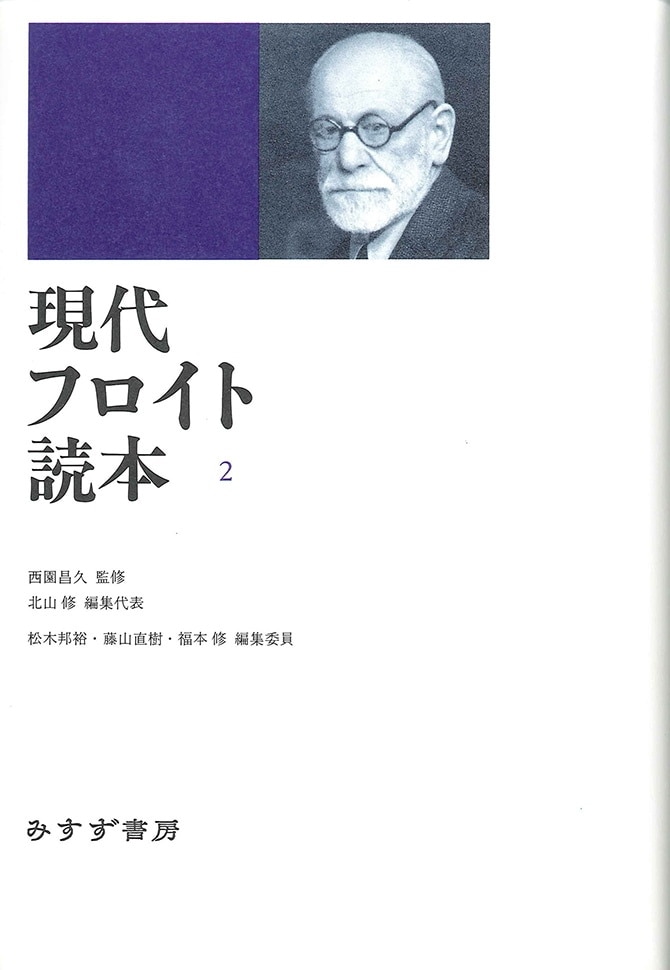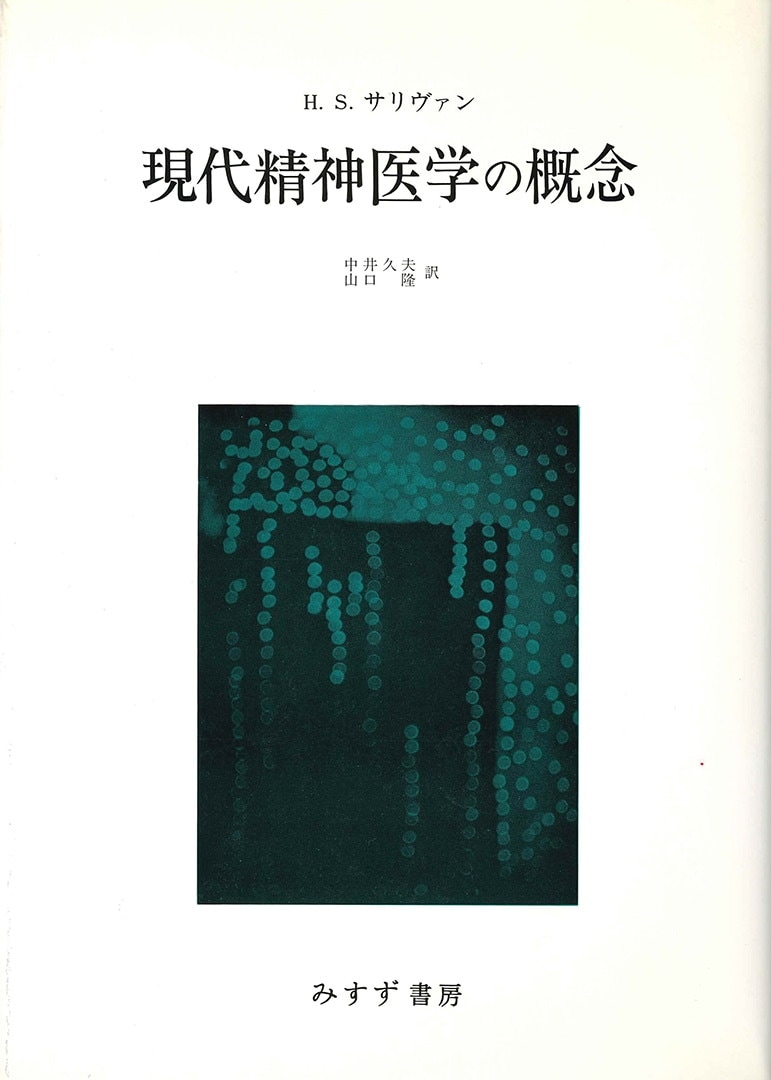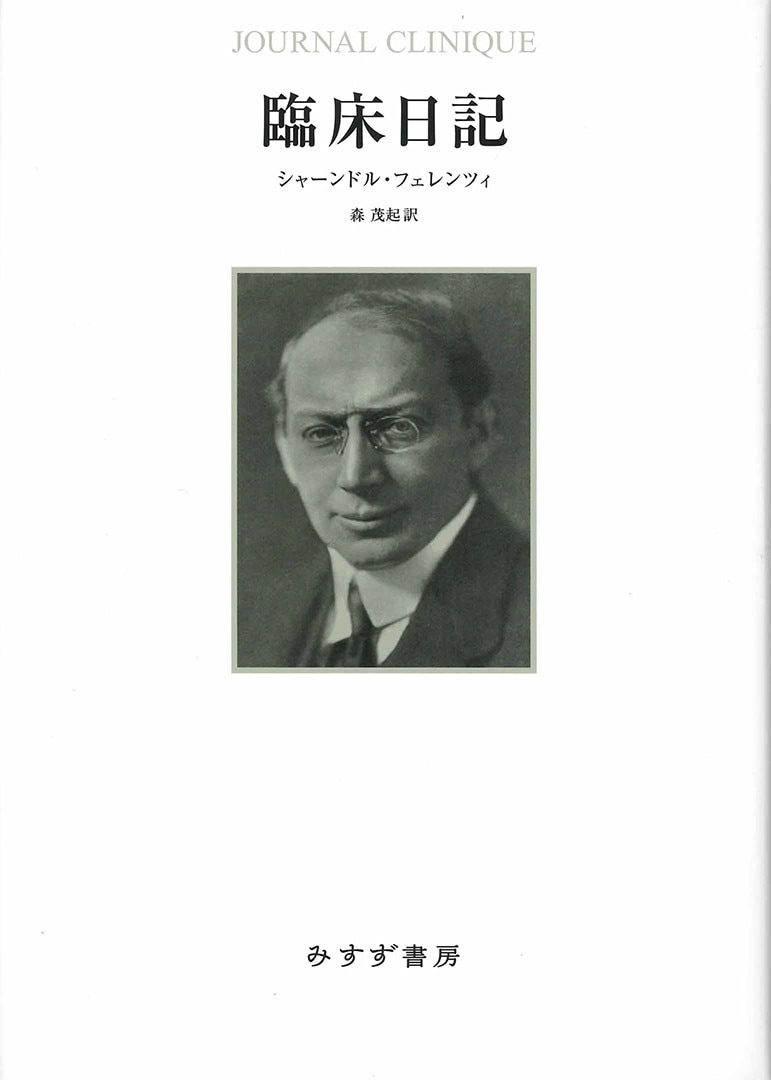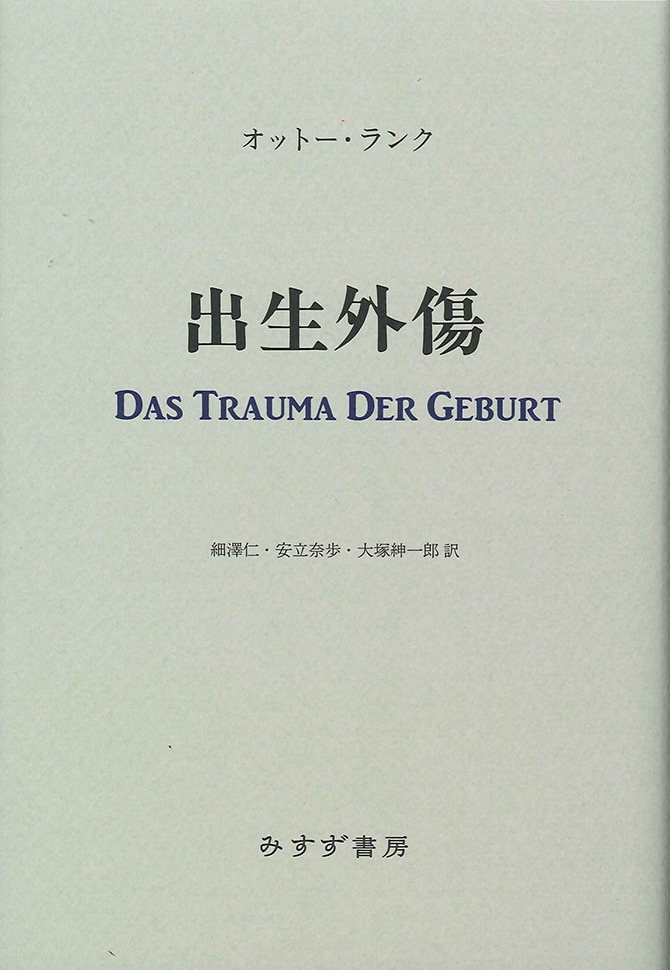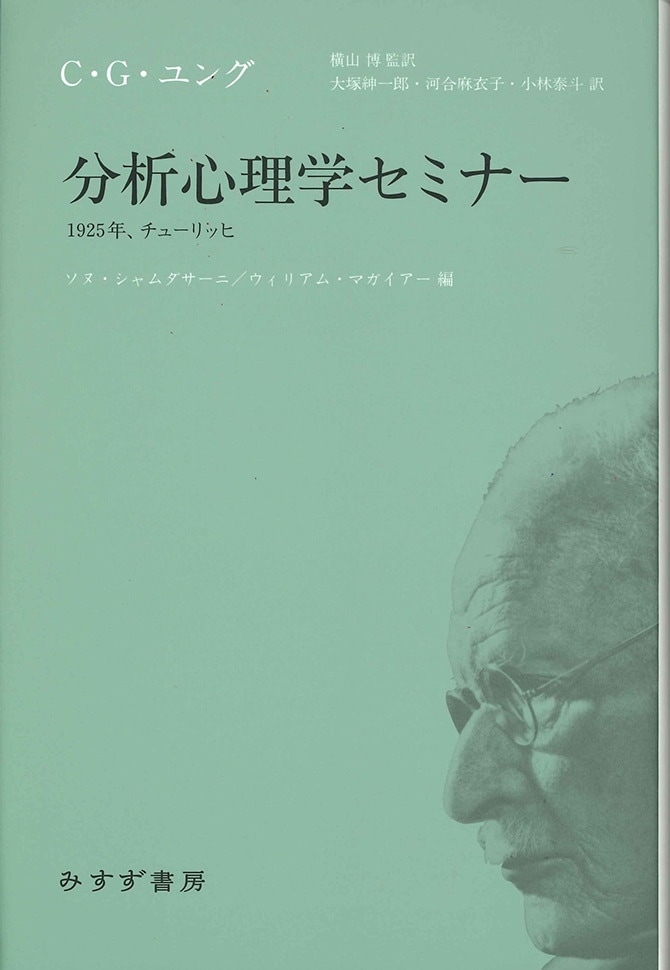(「はじめに」のほぼ全文を以下ウェブでお読みになれます)
北村隆人
近年、さまざまな領域で共感が重視されるようになっている。
特に重視されているのは、対人援助の領域においてだろう。1970年代以降、医療や福祉などの現場で、患者や利用者への心理的援助として共感が注目され、その後、患者中心の支援を行うために援助者が取るべき基本的姿勢の一つに位置づけられるようになった。そうなった理由は、援助者が患者の話を共感的に聴くことによって、患者は自分が抱えている悩みや思いを率直に語りやすくなり、病気や障害を主体的に乗り越える手立てを患者と援助者が共に考えやすくなるからだ。
その効用が注目される中で、次第に他の人間関係においても共感が重視されるようになってきている。最近では企業経営や組織運営の現場にも影響が及び、共感に基づいた経営を推奨するビジネス書が刊行されるまでに至っている。
さらに社会全体に視野を広げても、同様の状況が認められる。たとえば元アメリカ大統領のバラク・オバマは、財政赤字deficitよりも共感の不足deficitこそが社会的分断をもたらす点で深刻な問題であり、共感を涵養することの必要性を説いた(Obama 2006)。
このように共感が重視される動向は、ひとまず良いこととして評価できるだろう。それは、他者の苦しみに共感できる人が増えていけば、互いの個性を尊重しあえる心理的素地が社会の中に作られ、異なる人たちの共生可能性が高まっていくからだ。
ただ共感の良い面だけが強調されると、逆に疑問が浮かぶこととなる。共感は本当に良いものなのか。共感には悪い面がないのだろうか、と。
この疑問を踏まえて、対人援助の場面について考えてみよう。悩みや不安を抱えている患者の中には、援助者から共感してもらえて安心する人が存在するのは確かだ。しかし逆に、援助者から内面に触れられることを不快に思う人もいるだろう。また、そもそも共感なんてしてほしくないと思う人もいるだろう。そうした人たちにとって、共感は良いものとは言えないはずだ。
では社会においてはどうだろうか。たとえば自分と異なる立場の人に共感できる人が増えていけば、互いの違いを尊重しあって生きていく社会が実現しやすくなることは間違いない。しかし中には、排外主義的な発言やヘイトスピーチに共感する人も存在し、そうした人が増えていくと逆に社会の分断が進むことになる。
これらの負の側面を考慮に入れれば、共感を単に良いものと位置づけるわけにはいかなくなる。では私たちは共感をどうとらえればよいのか。そして私たちを駆動する共感という心の働きと、どうつきあっていけばよいのだろうか。
本書は、この問いに対して精神分析の視点から答えるために行った、代表的な精神分析家の人生史とプラクティスを対象とした心理歴史学的研究の試みである。
ここで取り上げる精神分析的プラクティスとは、分析家あるいは分析的治療者と患者が協力して患者の深層心理を探求し、その理解を得ることによって、より主体的・自覚的に生きることを目指すプラクティスである。ただ短期間で症状を解決することが求められる現代においては、数少ない治療者によって細々と行われているにすぎないものである。
そのことを知ると、次のような疑問が浮かぶかもしれない。そのような社会の片隅で行われているにすぎないプラクティスを取り上げて、共感について考えることにどんな意味があるのか。
この疑問には、こう答えておこう。分析家や分析的治療者は、深層心理に遡って人間心理を理解しようと試み、共感の意義と問題点に真剣に向き合ってきた専門家である。それゆえ彼らの苦闘の跡をたどることによって、そこから私たちは共感について多くの示唆を得ることができるだろう、と。
copyright© KITAMURA Takahito 2021
(著作権者のご同意を得て抜粋・転載しています。なお、
読みやすいよう適宜、改行や行のあきを加えています)