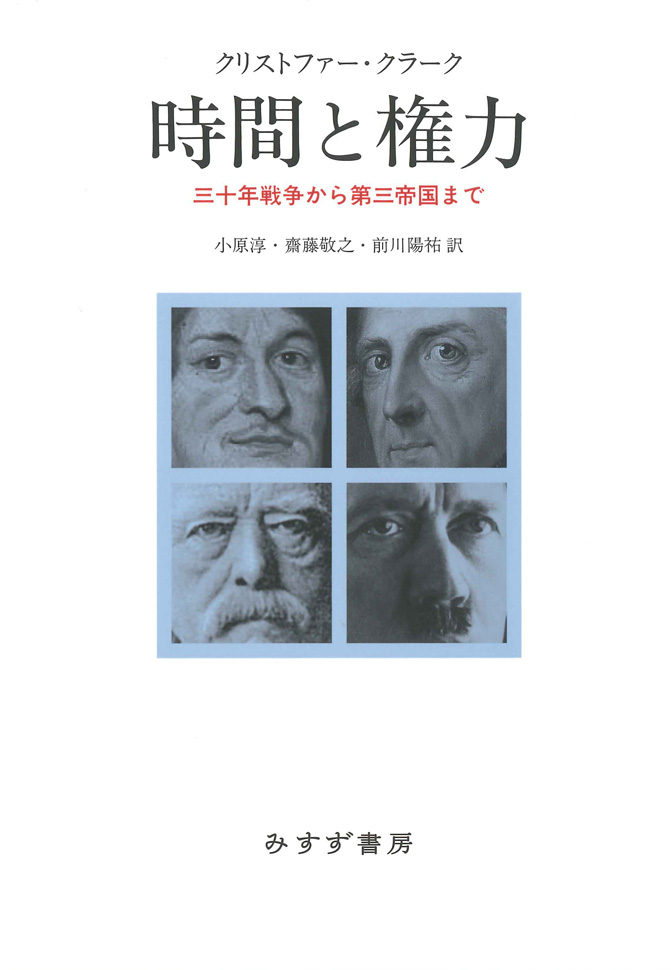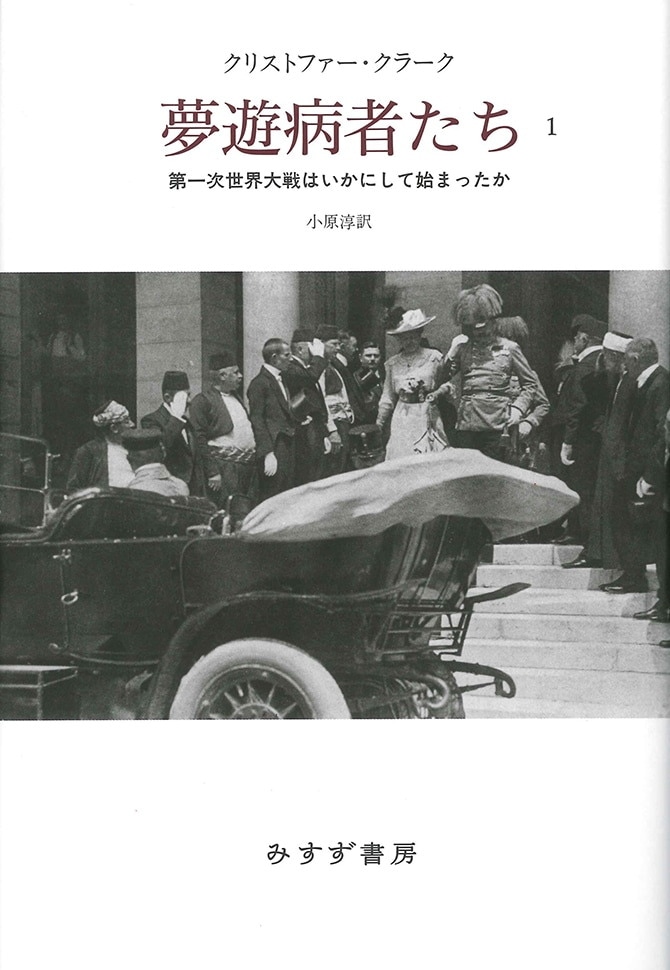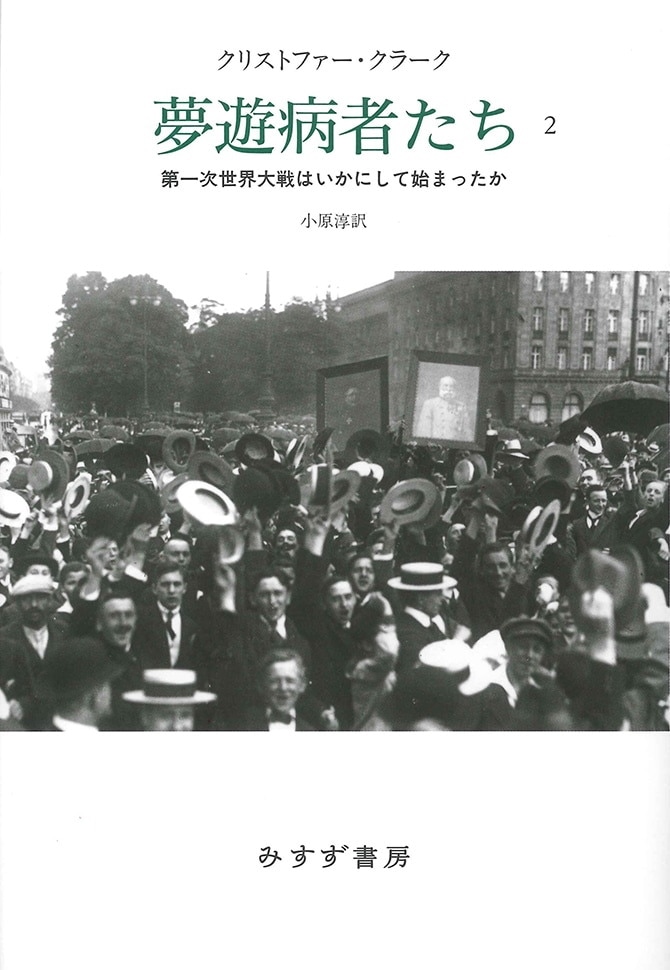小原淳
人は誰しも歴史のなかを生きている。歴史は巨大で強力、そして無慈悲である。か弱い個々の人間が歴史の流れを変えるのは至難の業に思える。流れに抗ったり、そこから脱け出すことですら容易でない。しかし歴史は客観的に実在しているわけではない。歴史が存在しているのは、私たちの想像のなかである。
歴史は、ある者にとっては断絶の繰り返しかもしれないし、別の者にとっては十年一日、変わりない日々の連続かもしれない。人は過去に背を向け、新たな未来への期待に胸を膨らませる場合もあれば、未来を恐れるあまり過去の経験を美化し、古い昔に回帰しようとする場合もある。あるいは未来を現在の延長線上に据えて予測することもできるし、過去の繰り返しとして思い描くこともできよう。
かように歴史の在り様は十人十色だが、しかし反面で、特定の時代や地域に通底し、そこに生きる人びとの思考と感性と行動の大枠を規定する、共通の歴史意識や時間意識がある。この共通の意識が生まれる際に大きな影響を及ぼすのが、政治権力の担い手たちである。彼らによって、そして彼らの操る権力によって、歴史と時間はどのように創出され、改変され、後世に伝えられるのか。
21世紀の歴史学は、この多様で可変的な文化的構築物としての歴史と時間をめぐる考察を積み重ねている最中にある。20世紀の言語論的転回や文化論的転回にも匹敵するこの「時間論的転回(テンポラル・ターン)」を受けて、ドイツ史における時間と権力、歴史と体制の関係を論じたのが本書である。
プロイセンとドイツの歴史、そして第一次世界大戦へと至るヨーロッパ史を論じてきたクラークが、6作目の編著書である本書『時間と権力』のテーマとして、権力と時間の関係という歴史哲学的な問題を選んだことを意外に思う読者もいるかもしれない。しかし本書を読めば、歴史書、回想録、書簡、日記、法令、布告、遺訓、定期刊行物、詩、小説、議事録、演説、講演、絵画、さらには博物館のパンフレットや展示物、チェスの教則本までも史料に用いて、様々なアクターが織り成す駆け引きや人間模様を手際よく描き出す筆致は、まさに『夢遊病者たち』(みすず書房、2017年)の著者ならではのものであると納得するのではなかろうか。また、17世紀以降の300年を政治、社会、文化の各方面に目配りしつつ精妙に、しかし大胆な切り口で論じ、さらにそのこんにち的な意味までを浮き彫りにする技量は、『鋼の王国』(未邦訳)を彷彿させる。
本書はドイツにおける歴史意識や時間意識の変遷を論じるにあたって、17-20世紀の4つの人物と体制、すなわちプロイセンの中興の祖である17世紀の大選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルム、18世紀後半に同国の強大化に尽力して大王と呼ばれるフリードリヒ二世、19世紀後半にプロイセン主導のドイツ帝国創設を成し遂げた宰相ビスマルク、そして1933-45年のドイツを支配したナチ体制を対象としている。これは日本史でいえば、江戸時代の初期から太平洋戦争の終結に至る長期間であり、あえて4つの対象をも日本史に置き換えれば、さしずめ徳川家康、徳川吉宗、伊藤博文、戦前昭和の軍部や政府がそれぞれ歴史と時間をいかに把握し、いかに変容させたのかを論じるのに等しい、スケールの大きな試みである。実際に著者が各人物や体制をどのように語っているのかについてはここではふれないが、それほどに壮大なテーマと対峙するためにクラークは、歴史や時間に関する従来の学説に依拠しつつ、「歴史性」と「時間性」という概念を用いている。以下、本書のキーワードである「歴史性」と「時間性」について簡単に述べる。
「歴史性」はハイデガーからディルタイ、さらにはヘーゲルにまで遡るドイツ哲学のなかで学術的用語として使用され始めた言葉で、英語のhistoricityやフランス語のhistoricitéもドイツ語のGeschichtlichkeitをもとにしておおよそ19世紀後半に成立した造語であるという。しかし、クラークがこの「歴史性」という概念を創り出す際に直接に参照しているのは、フランスの古代史家フランソワ・アルトーグである。アルトーグは2003年に発表した著書『歴史性の体制』において、「歴史性」を「時間を過去・現在・未来へと分節化する働き、およびそれによって成立した時間経験の基本枠組み」という意味で用いた。このアルトーグの用法を参考にしてクラークは、「歴史性」とは「過去と現在そして未来の繫がり方をめぐる一連の仮定」であると規定する。本書は例えば、大選帝侯が自分の生きる時代と三十年戦争という過去、そして予測し難い未来とがどのように繋がっていると考えていたのかとか、あるいはナチ体制が過去と未来の関係をどのように理解していたのかといった問題を検討しているが、まさにこうした事例が各時代の「歴史性」ということになる。
「歴史性」が思索や省察に基づいて形成されるのに対して、「時間性」はより感覚的に醸成される。クラークの言う「時間性」とは、「経験された時間の手ざわり」、すなわち「未来は現在に向かってやってくるのか、それともそこから遠ざかっていくのか。過去は現在を侵蝕しようとするのか、それとも認識の果てへと消え去るのか」といった、直観的な時間意識のことである。この「時間性」という概念に関しては、クラークはドイツの歴史家ラインハルト・コゼレックから大きな影響を受けている。コゼレックは著書『過ぎ去った未来』(1979年刊)に収録された論文「「経験の空間」と「期待の地平」――二つの歴史カテゴリー」において、過去についての経験と未来への期待――正確に言えば、経験とは現在から捉えた過去、すなわち「現在のなかにある過去」であり、期待とは現在から予測した未来、すなわち「現在に実行されている未来」である――は可変的であり、相互に影響し合っていると論じた。すなわち、過去の経験をどのように捉えるかによって、未来に対する期待のもち方は変わるし、そうして未来への期待が変わることで、過去についての経験もまた変わる。例えば、過去に自分がひどい目にあったと考える人は、その反動で薔薇色の未来を思い描き、そして未来への期待が高まれば高まるほど、期待どおりにならない経験がますます蓄積されていくかもしれない。クラークの言う「時間性」もまた、このような過去と未来、経験と期待の両極的な相互作用のなかでかたちづくられる。
ただし、アルトーグがコゼレックを手がかりにして自らの理論を構築したこともあって、クラークは実際に各時代の歴史意識や時間意識を論じるにあたって「歴史性」と「時間性」をそれほど厳密に区別しているわけではなく、むしろ相互補完的に使用している。あくまでも歴史家であるクラークは、概念を厳格に適用し、史実を法則に当てはめて説明するのではなく、史実を読み解くための道具として「歴史性」や「時間性」といった言葉を活用している。したがって、前著の『夢遊病者たち』と同様に本書もまた、一貫した理論に基づいた整然たる解説よりも、無秩序に発生する出来事や登場人物たちの言動に対する行きつ戻りつの熟考こそが持ち味となっている。
Copyright © OBARA Jun 2021
(筆者のご同意を得て抜粋転載しています)