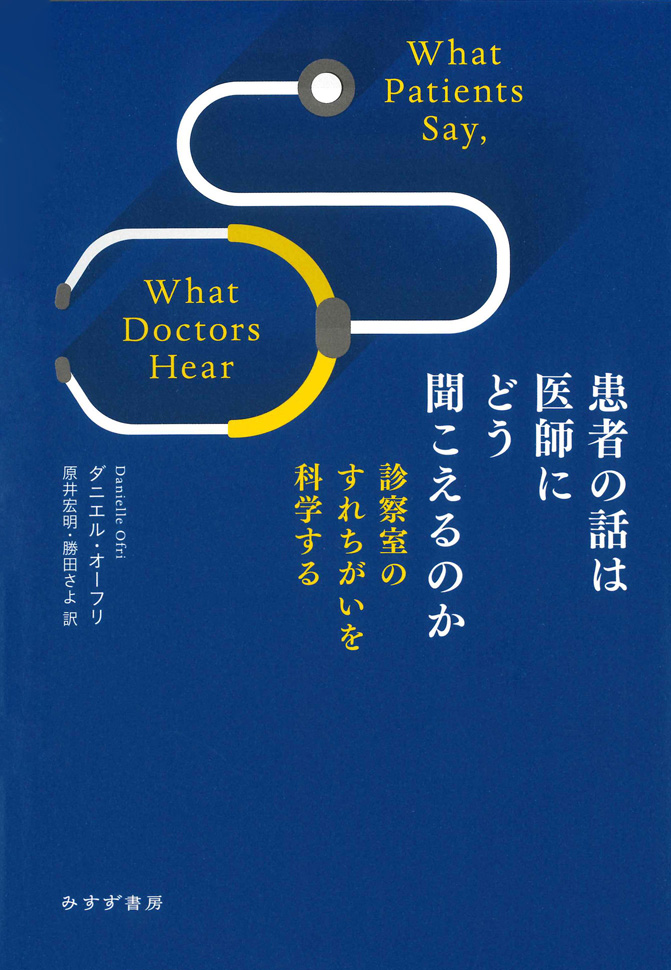(『患者の話は医師にどう聞こえるのか――診察室のすれちがいを科学する』の第1章を以下でお読みになれます)
第1章 コミュニケーションはとれていたか
木曜日の夕方おそく、クリニックのドアから一歩外に足を踏みだしたとき、診察室の電話が鳴った。ウマール・アマドゥだった。「具合が悪いです」と言う。「オーフリ先生に診てもらう必要あります」
陽は沈み、クリニックは仕舞いじたくの最中だ。私も自分のファイルキャビネットに鍵をかけ、コンピューターの電源を落としていた。「今診てもらう必要あります」。アマドゥは繰り返した。強い西アフリカなまりを通しても、はっきりと声にいらだちが感じられた。
初診から数カ月のあいだに、50回は彼の電話を受けたと思う。気になることがあるとか用紙に記入してほしいとか処方箋を書いてほしいとかいつもなにかしら用事があり、ことはつねに急を要した。診察に現れるときは予約なしだ。いつでもその場ですぐ私に診てもらえると思い込んでいた。
だが、同時に、43歳という若さで重い心臓病をわずらう患者でもある。彼が初診時にとりだしたピッツバーグの心臓専門医からの書類の束は、学術書ほどの厚みがあった。そこには、ペースメーカー、除細動器、ICUへの複数回の入院を必要とした重症の心機能不全が、くわしく説明されていた。
だから、木曜日の夕方電話を受けたとき、かんに障る口調に堪忍袋の緒も切れかけたが、私は彼の不安を深刻に受けとめた。症状を尋ね、うっ血性心不全や不整脈がないかどうか確認する。そうした状況なら、すぐに救急治療室に行かせなければならない。
しかし、具体的な症状はなく、なんとなく気分がすぐれないだけだという。金曜日はクリニックでの診療予定はなかったが、心臓の悪い彼を月曜日まで待たせるのは不安だった。
「明日クリニックに来てください。救急科のほうに」と私は言い、自分はいないが同僚の医師が診察すると説明した。
月曜日の朝出勤すると、アマドゥからのひどく立腹した留守番伝言メッセージが入っていた。「金曜日きました。でも先生いませんから帰ります。先生しか診てもらいません」。腹だちまぎれに思わず両手で膝を打っていた。言われたことが理解できなかったのだろうか、それとも単に強情なだけなのか。
続く3日間、二人のあいだを不在伝言メッセージが行き来した。もし具合が悪いなら救急外来に来てほしい。それほどでもなければ普通に予約をとりますと、私はメッセージを残した。アマドゥのほうは「オーフリ先生に診てもらう必要あります」の一点張りで、こちらの伝言はまったく聞いていないようだった。かけなおしたときは、いつも留守番電話が応答した。
木曜日の昼すぎ、5分ばかりランチに専念できるかもしれないと期待しながら午前の最後の患者に「ではこれで」とあいさつしていたとき、視線の先にアマドゥの姿が飛び込んできた。メッセージのやりとりを始めてから、1週間がすぎていた。やせぎすの長身に淡青色のジャージの上下を身につけたアマドゥは、じれったそうに私に合図し、「オーフリ先生、診てください」と叫んだ。「今すぐ」
不意に激しい怒りがこみ上げてきた。午前の診療でくたくたになったあとにランチにありつけるまれな機会が失われようとしていることだけが理由ではない。アマドゥが、突然来てもその場ですぐ私に診てもらえると決め込んでいるのがしゃくに障るのだ。
そう、彼は心臓が悪い。しかし、だからといっていつもわがままを通していいということにはならない。救急を受診せず、1週間メッセージのやりとりでしのごうとしたことを考えれば、気になることがなんであれ、そう悪い状態ではないはずだ。けじめをつけなければならない。
「アマドゥさん」と私は固い口調で言った。「予約なしにクリニックに来るのはやめてください」
「オーフリ先生の診察に来ました」
「そう、そうですね」と答えるそばからいらだちがいや増した。「でも他の患者さんは予約して来ています。待てないのなら、今日救急を受診してください。でなければ、みなさんのように予約をとってください」
「他の先生、いや。先生でないとだめ。今日、どうしても」
今ここで診察を許せば、アマドゥにいつ来てもいいというお墨つきを与えることになる。きっと毎週やってくるに違いない。だが、彼の心筋症が重症であることも理解していた。厄介であろうがなかろうが、危険を冒してよいたぐいの患者ではない。
「わかりました」と言って私は大きなため息をついた。「さっと診察しましょう。次は必ず予約をとってください」
待合室からついてくるアマドゥは満面の笑みで、私はこの判断を後悔するに違いないと思った。彼は、すぐに診察してもらう方法を見つけたのだ。こちらが面倒になって降参するまでしつこく粘ればいい。
メディカルアシスタントもランチに行こうとしていたが、私が「アマドゥさんのバイタルをさっとチェックしてくださる?」と笑顔で訴えると、ためらい、片方の眉をひそめたものの、最終的に譲歩してくれた。私はほっとして、アシスタント室に入るようアマドゥに身振りで指示した。
アマドゥは、2歩進むと、3歩目の途中で動きを止めた。まるで、映画の画面が突然静止し、登場人物の動作が途中で止まってしまったようだった。ひょろ長いからだが宙に浮いたようにみえた。まるで、前後どちらに行かそうかと筋肉が思案している、とでもいうように。もちろんそれはすべて錯覚で、寿命が縮まるような鈍い音をたてて、アマドゥは床に崩れ落ちた。
なにか恐ろしいことが起こったとわかると、必ずぞっとするような――1秒もないに違いないが1時間にも感じられる――静寂の一瞬が訪れる。心身ともにショックを受け、いつもの状態から緊急事態に変わるときの、胃がひきつるようなあの瞬間だ。一瞬とはいえもどかしい時間のずれだが、そこで数回まばたきしてやっと新たな現実を受け入れられるようになる気がする。
私は、ひざまずいてアマドゥの首に指を当て、脈を確認した。「アマドゥさん、聞こえますか?」と大声で呼びかける。呼吸が速く、ドアフレームに背をあずけてへたり込み、ひょろ長い下半身をホールのほうに投げだしている。「どうしました? 痛みはありますか?」。アマドゥは右手を胸に当てた。「心臓が」とか細い声が聞こえ、私は罪悪感の大波にのみ込まれた。
そのころには辺りに人だかりができていた。看護師が血圧を測定している。脈拍は130。指が冷たすぎて、パルスオキシメーターに測定値が表示されない。私は、アマドゥのジャージの上衣の下に聴診器を押し込みながら、酸素とストレッチャーを準備するよう指示した。だらんとしたそのからだをストレッチャーにのせると、私たちは大急ぎで救急治療室に向かった。
絶望的な気分で、ホールを抜けるあいだもアマドゥの手を握り、きびきびした足どりを保って罪の意識を遠ざけようとつとめ、大事に至りませんようにと祈った。救急治療室のトリアージエリアに到着すると、私が救急医に状況を説明するあいだ、看護師たちが彼をモニターにつなぎ点滴を開始した。引き継ぎがすむと、私はもう一度アマドゥを振り返った。じっとり汗ばんだ右手を両手で握りしめると、氷のように冷たかった。
私は、待合室できつい口調でなじったことや、その週連絡不行き届きになったことをわびた。アマドゥは私の言葉で目を開けたが、息切れがひどくしゃべることができない。かすかにうなずくと、弱々しく私の手を握り返した。
ずっとリノリウムの床に目を落としたまま、私は足どりも重くクリニックに引き返した。そうすまいと努めても、なにがいけなかったのかと、さっき起こったできごとを細かく思い返さずにはいられなかった。アマドゥは強引で、それもたぶん度がすぎていた。私のほうも一歩も譲らず、断固たる態度を崩さなかった。
だが、もっと基本的なところに問題があったのかもしれない。二人とも相手の言うことを聞いていなかっただけなのかも。なるほど、私たちのあいだには言葉の壁があったが、彼はかなり英語ができたし、込み入った話をするときは必ずフランス語の通訳がついた。言葉そのものの理解に問題はなかったと思う。それよりも、相手が伝えようとしていることを聞いていなかったことが問題だったのだ。
しゃくに障るふるまいも強引さも、それによって伝えたいことはただひとつ、「助けてくれ」だった。アマドゥは、心の奥では、いつ心臓が止まるかもしれないという恐怖におびえていたに違いない。行動の根底には恐怖があった。そう考えると、彼の執拗さも理解できる。危ういバランスを保って命をつないでいるのだ。「ノー」という答えなど受け入れるわけにはいかない。
だが、私は彼の執拗さに息がつまりそうだった。振り向けば必ずといっていいほど、私の時間と関心を手に入れようとあらゆる手を尽くすアマドゥの姿があった。力になってやりたいとは思ったが、つねに最優先を強要され、私は精根尽きかけていた。自分の欲求より患者の要求を優先しなければならない職業であることは承知していたが、アマドゥの際限のない要求には防御的にならざるを得ず、ついには怒りがわいた。彼の強引なふるまいへの対処に追われ、私は彼の言葉の意味に耳を傾けることを忘れていた。ここから先は譲れないという防御線を張るのに精一杯で、助けを求める彼の声が聞こえていなかった。はた迷惑にふるまうというそのこと自体がSOSであり、恐れと弱さの現れなのだということに思い至らなかったのである。
現代医学には高度な診断ツールがあるとはいっても、医師と患者の会話は、やはり主要な診断ツールである。皮膚科など視覚にもとづく領域や、外科など処置が基本となる領域でさえ、正確な診断には、患者による口頭での病状説明とそれに対する医師の質問を欠かすことはできない。
今では多くの技術がどれほど進んでいるかを考えれば、これはある意味、時代錯誤もいいところだ。SF映画は、患者のからだの上に携帯型の端末を走らせて診断を下せるようになると予想した。そして実際、多くの診断に、MRI、PETスキャン、最先端のCT技術が用いられている。それでも医師と患者の単なる言葉によるやりとりが診断の基礎であることに変わりはない。患者が医師に語るストーリーが、診断や臨床判断、治療への道筋を示す主要なデータとなる。
だが、患者の語るストーリーと医師が聞いたストーリーが同じではないということなど日常茶飯事だ。アマドゥが語っていたストーリーと私が聞いていたストーリーは、同じものではなかった。感情、欲求不満、診察までの流れ、絶望的なあがきなどがいくつもの階層をなしており、二人は別々に会話していたといってもいいかもしれない。
患者が一番不満なのもこの点だ。患者は、医師が本気で話を聞こうとしない、こちらの言おうとすることを聞いていないと感じている。多くが、失望し欲求不満をかかえたまま診察を終える。単に納得いかないだけではなく、誤診されたまま、あるいは適切に治療されずに診察室をあとにする患者も多い。
医師のほうも、患者のストーリーを解き明かす困難さに欲求不満をつのらせている。特に複合的で不可解な症状を呈する患者の場合がそうだ。疾患の多様化と複合化がすすみ医学がより複雑化するにつれ、患者が言ったことと医師が聞いたこと――その逆もだが――のずれもさらに広がっていく。医師と患者が相互におよぼし合う影響を調べ、一つのストーリーが一方から他方にどのように伝わるのかを探るべく、私はこの本を書きはじめた。
医師と患者では、明らかにスタート地点が異なる。患者は、発熱したり、息切れがあったり、首のしこりががんだとパニックになったりしている。より弱い立場からスタートするわけだ。それなのに、患者のほうがリスクはずっと高く、状態が悪化すれば失うものもはるかに大きい。したがって、ストーリーが正しく理解されるよう万全を期す責任はおもに医師側にあるといって差しつかえあるまい。とはいえ、それはやはり、それぞれの偏見、人生経験、長所、弱点が反映された、二人の人間のやりとりなのである。
アマドゥのケースでは、共通のあやまちが病状の悪化を招いた。少なくともどちらか一方が相手の言うことにもっとよく耳を傾けていたら、あの日の午後、集中治療室に向かうことにはならなかったかもしれない。医療は双方の尽力あってのものであり、コミュニケーションはそのための必須条件だ。
本書では、何名かの医師と患者が歩んだ道筋をたどり、一つのストーリーが人から人にどのように伝わるかを考察する。協力の結果や成功はもちろん、課題や落とし穴を調べることで、この最強の診断――そして治療――ツールの医学における役割を明らかにすることができればと願っている。医学が技術的に進歩すればするほど、私たちはストーリーのはたす役割の重要性を再認識させられるのだ。
アマドゥを無事に救急治療室に送り、クリニックに戻ってみると、すでに午後の診療のまっ最中だった。ランチの時間はとっくに過ぎていたが、いずれにせよ、すでに食欲は失せていた。それに、カルテボックスにはもうカルテの山ができている。受付係が最初のカルテを渡してよこした。「ベラスケスさんですが、予約はないんですけど、ちょっと診てもらえないかと言っています」
手にはまだ、アマドゥの冷たい手の感触が残っている。いらいらさせられたとはいえ、助けを求める彼の言葉の数々が、まだ頭の中にこだましていた。「だれが来ても、スケジュールに入れてちょうだい」と言って私はカルテを受けとり、長い午後にそなえた。
アマドゥは、数日ICUに入院した。速脈が弱った心筋の収縮能力を上まわってしまったのだ。ペースメーカーの交換が必要となり、薬の量もぎりぎり平衡が保たれるよう調節された。今回の入院は切り抜けたが、アマドゥの心予備能の低さはつねに心配の種だ。あの日以来、彼から電話があるたびに私は耳をそばだてる。重大な問題がひそんでいないかどうか察知しようと、受話器に当てた耳に全神経を集中しているのが自分でもわかる。診察で顔を合わせたときの二人の会話は、身体診察と同じくらい実体をもつものに感じられる。二人のやりとりはもう、主体性を欠いた型通りのものではない。
アマドゥの存在は、医師と患者のやりとりは、通り一遍の診察の会話などではなく、実はもっとも重要な医療の要素なのだということを、絶えず私に思いださせてくれる。そのやりとりが生死を分けることだってありうるのだ。
(著作権者の同意を得てウェブ転載しています。なお
読みやすいよう適宜、行のあきなどを加えています)