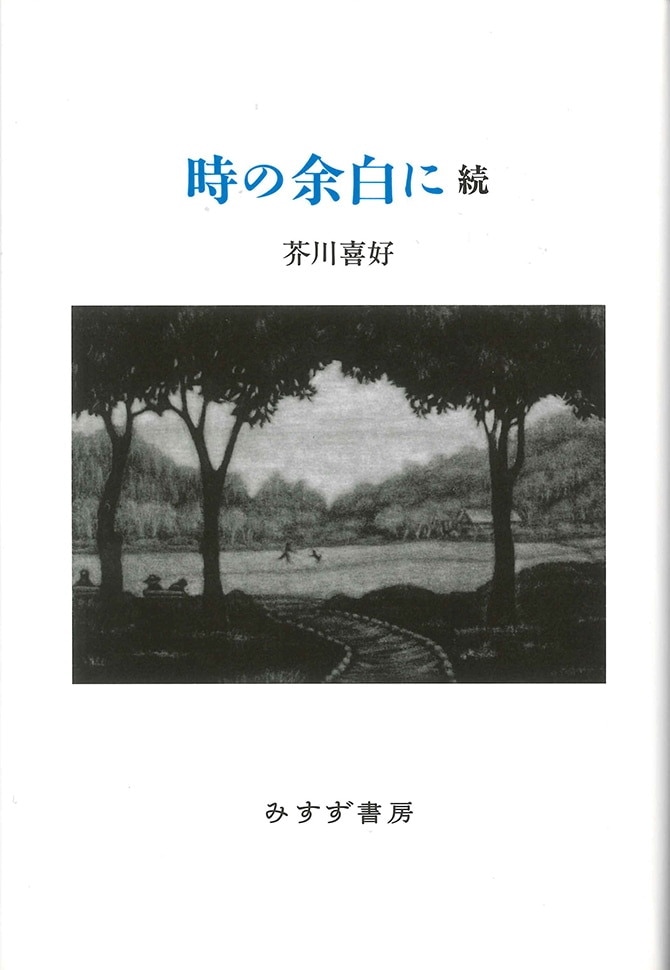芥川喜好
毎月の月末近く、現在は第四土曜日に「よしなし事」を書き続けて十二年が過ぎました。週一度書いていた日曜版や夕刊の美術連載から通算すると、三十七年半の連載稼業ということになります。新聞社の定年はとうの昔に過ぎ、三十人以上いた記者の同期生もすべて社を去り、周囲の風景も社会の環境も一変したのに、締め切りに追われる自分の日常だけは何も変わっていない。考えても意味はありませんが、何でこんなことになったのか、不思議といえば不思議な話です。
「時の余白に」が始まった経緯については前著のあとがきでも触れました。メディアの競合する時代の新聞にとって最も重要な解説・論評の機能を担う面に、時には最前線の緊張感から距離を置いて一息入れるお休み処を設けるということだったと、自分では理解しています。専ら担当してきた美術の分野を中心に、その月に最も書きたいと思ったことを自由に書かせてもらってきました。こちらの関心に従って書けばそれはそのまま世の余白だ、という妙な確信があったような気もします。
これも前著に書いたことですが、好き嫌いがけっこう露骨に出ていることを、改めて読み直してみて感じます。自分にとって善きものは、継続して取材し新しい展開を追っていますから、紙面にも繰り返し出てくることになる。時代がもてはやすものや、今をときめく大物有名人みたいなものが、幸か不幸か自分の「好き」なものの範疇にまったく入ってこないことには、気がついていました。
その意味で、地域情報誌「かがり火」の発行人菅原歓一さんの言葉に出会ったことは、このコラムにとっては一つの光明でした(一五二ページ「地域を照らすかがり火」参照)。菅原さんは、この国は有名になった者が勝ちといわんばかりの社会になってしまったと言っています。政治家、学者、作家、芸能人、誰もが有名になりたがり、名前を売りこむことに汲々としている。その結果、売れるかどうかが最大の関心事になり、売れたものがいいものだという転倒した価値観が定着してしまった。この考えが日本の社会を汚染した――と。
むろん、社会を支えているのはそんな人たちではない。「売れる売れないにかかわらず黙々と自分の役割を果たしている人が世の中にはいる」と菅原さんは言います。そこにこそ救いはあるのに、マスメディアは人間の名ばかり、虚名ばかりを追いかけている、というそれは痛烈な批判にもなっています。
一つの言い方をすれば、現代の日本は実をそっちのけで見せかけを競い合っている社会です。政治家や官僚や企業経営者の生息するあたりは、すでに倫理的崩壊も進行している。そこでは、人間が長い間かけて慎重に吟味し意味を付与してきた言葉の実が、ご都合主義的に使い回されてこれも崩壊に瀕している。しかし実際に社会を支えているのはそういう人たちではない。永六輔さんの追悼(二四〇ページ「無名を愛し 有名を恥じ」参照)にも書いたように、無名に徹して黙々と自分の成すべきことに集中し、その精度を上げようと日々努めている人々こそ、現代の実の部分です。
何だか言わずもがなのことを言いましたが、月々の「新聞の余白」を埋めるにあたって、見せかけの部分と内実とのますますの乖離、ますますの空疎化という時代の現実を感じながら、自分なりの実を求めようとして材料を探したことはたしかです。