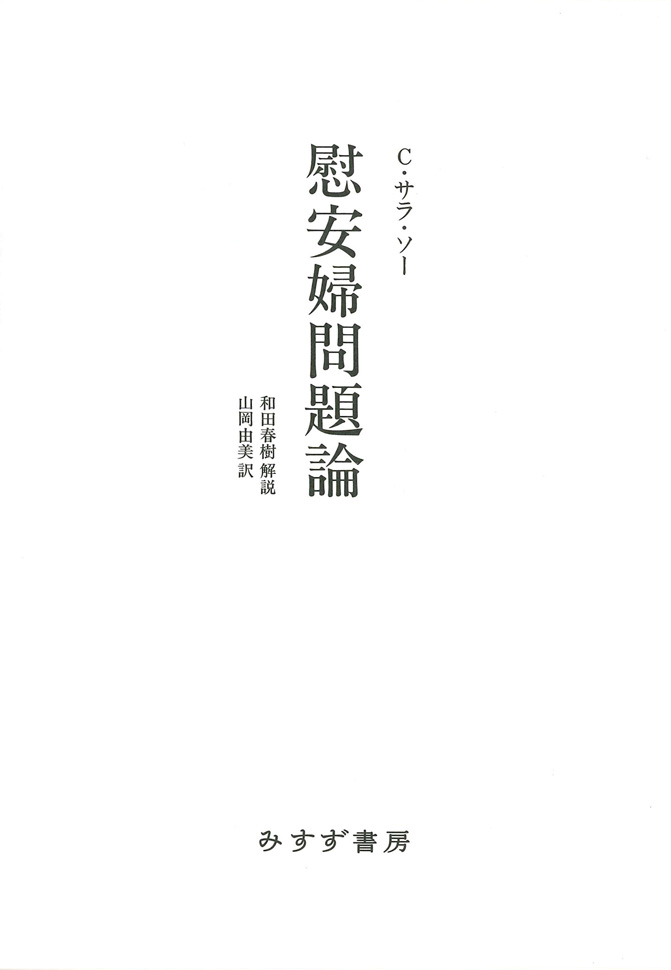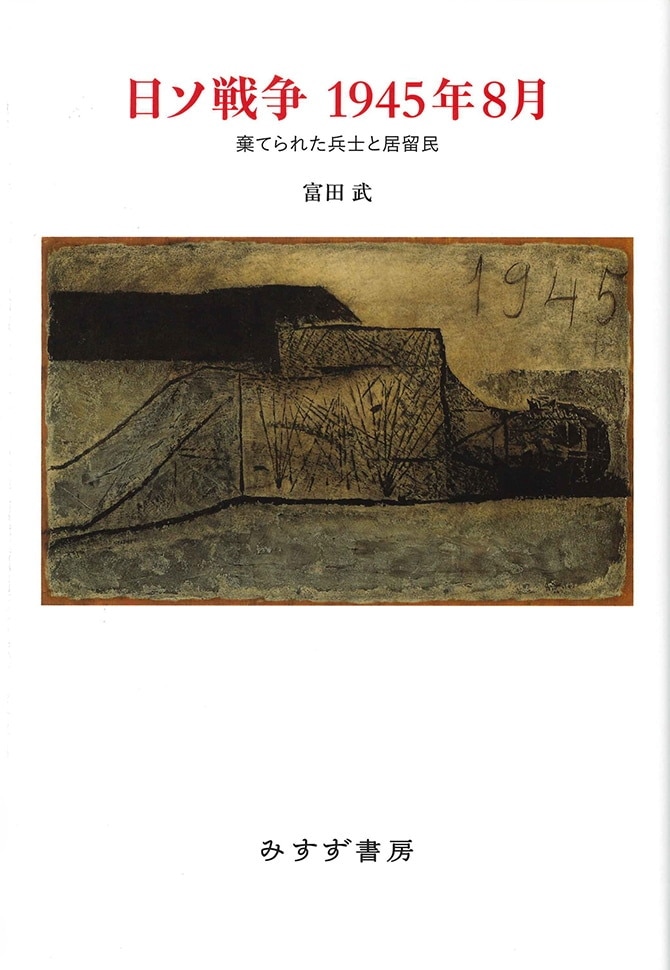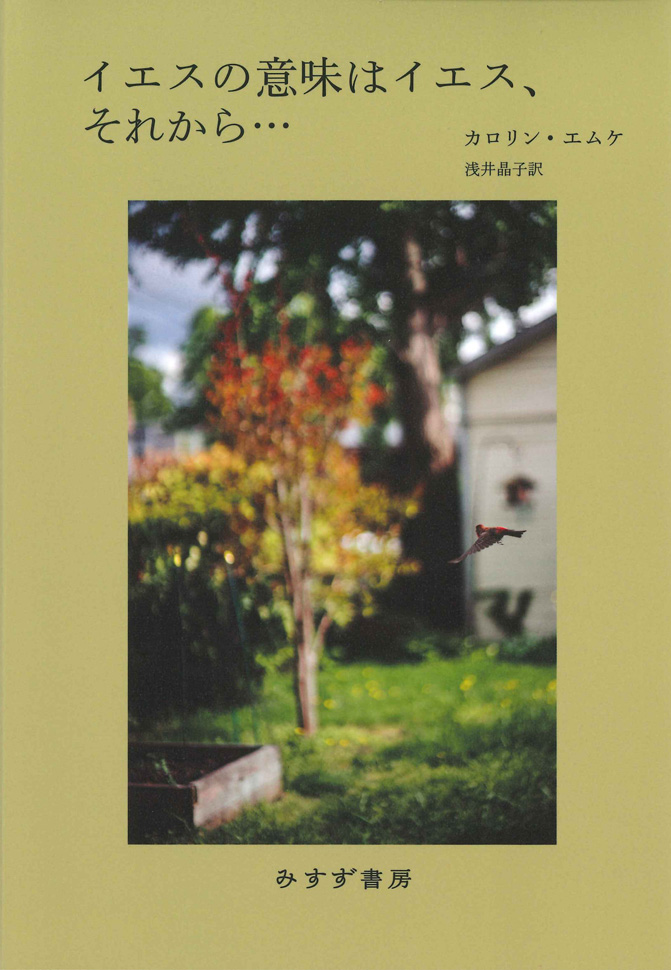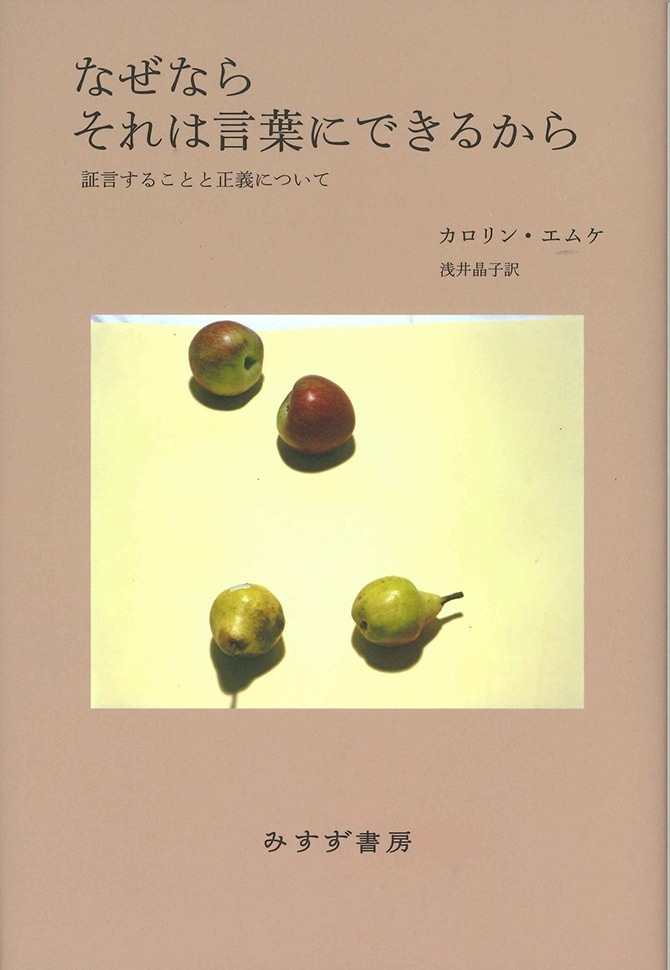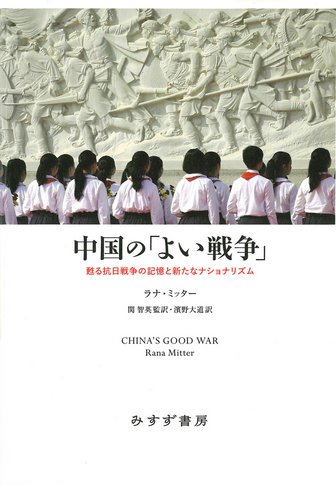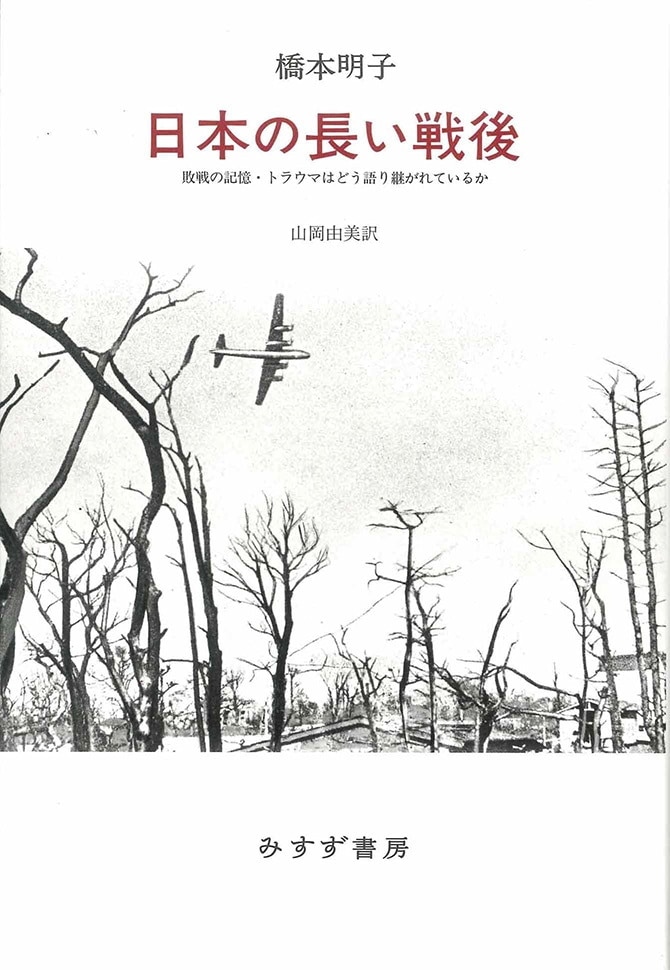本書については、原書で知っていた人が少なからずいるかもしれない。原書初版の2008年から現在まで、本書はときに、著者の意図に反する読まれ方をすることがあった。それは本書が自由な解釈に開かれているからではない。著者は自分の主張を明確にしているし、「文脈を無視して本書の一部を悪用」しないでほしいと、はっきり書いている。にもかかわらず、たとえば、強制連行がなかったことの証拠として言及されることがあった。
本書のなかに、このようなくだりがある。日本人の従軍看護婦が、患者が運び込まれてきたものの空襲が始まって手当をためらっていると、軍医が怒鳴る。「お前たちが無事でいられるのは、こういう人たちのおかげなんだ。それを忘れるな」と。「こういう人」と呼ばれた患者は海軍病院幹部の愛人であり慰安婦である。ここからは、幹部に「愛人」がいるのは普通のことらしいという状況と、それは好ましくない役だという状況が察せられる。そして、その苦役を担った本人ではなく、第三者の男性が、苦役を免れた女性に対して負い目を感じるよう強いている。これは戦時中にはありふれた一幕なのかもしれない。しかしよく考えればグロテスクだ。愛人/慰安婦という立場を作り出したのは、そもそも軍医をはじめとする男社会である。それが負い目を感じるように強いるとは、いったいどういう理屈なのか。
慰安婦問題をめぐって言われることのひとつに、それは「そんなに酷くなかったはずだ」というものがある。たしかに慰安婦となった女性のなかには、慰安婦としての過去をあまり苦にしていないように見える人もあり、本書もそうした人の証言を引用している。本書が分析しているさまざまな証言からは、当事者たちの人格の違いも浮き彫りになる。環境に順応した人、反抗的な態度を貫いた人。先述の愛人は、愛人になることで、従軍看護婦より物質的によい暮らしができたのかもしれない。意に反して慰安婦にさせられた女性も、現実を少しでも凌ぎやすくするため順応することがあったかもしれない。その経験がいかに非人道的で屈辱的であったとしても、順応したら、お金をもらっていた(もらわされていた)なら、物を言う権利がなくなるのだろうか。「ないんじゃないの」。そういう意見を聞いたとき、あの軍医の言葉にどこか似ていると感じた。一見もっともらしいが、それは男性中心主義的な、家父長制的な論理である。しかも反抗的な女性は暴力をふるわれた。
本書はとどのつまり、この家父長制的な論理のおぞましさを問題にしている。その「おぞましさ」が、家父長制的な思考にとって理解しがたいのはある意味当然かもしれない。本書が著者の意図に反して利用され続けてきたことは、この家父長制的思考がいかに盤石かを物語っている。
しかし家父長制は陰謀ではない。特定の人の意識的な悪意だけでそうした社会が作られたのではなく、多くの人の悪意ない惰性や無関心で生き延びている。だとしたら、それがおぞましいと思う感覚は、多くの人に共有される可能性があるだろう。なぜ慰安婦というものが生じたのか。生じさせたのは誰なのか。当時、若くて貧しい女性が生きるとは、生き延びるとは、どういうことだったのか。植民地支配は何をもたらしたのか。彼女たちにとって希望とは何だったのか。慰安所を利用しない兵士は男らしくないと言われる一方で、慰安婦として働いた女性は蔑まれたが、なぜ、どうしてこれほどの不公平がまかり通るのか。女性たちが自分たちの経験したことの悲惨さを訴えると、なぜ執拗な非難を浴びせられるのか。過去の過ちを忘れないための慰安婦像は、なぜ反対されるのか。
これはどれも、歴史上の特定の問題だけに終わらない。そうした認識を、本書は求めている。