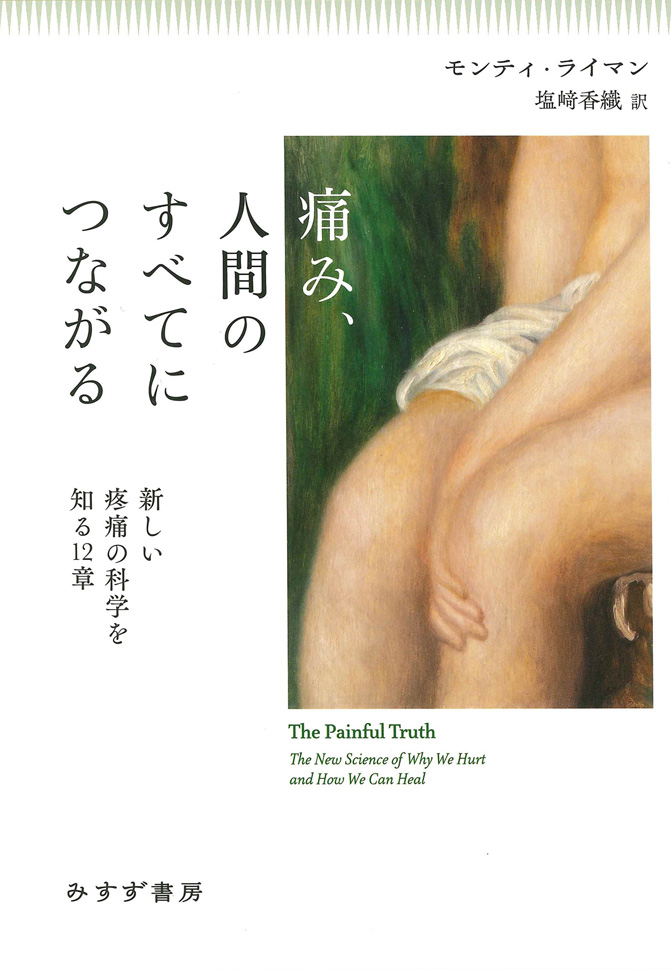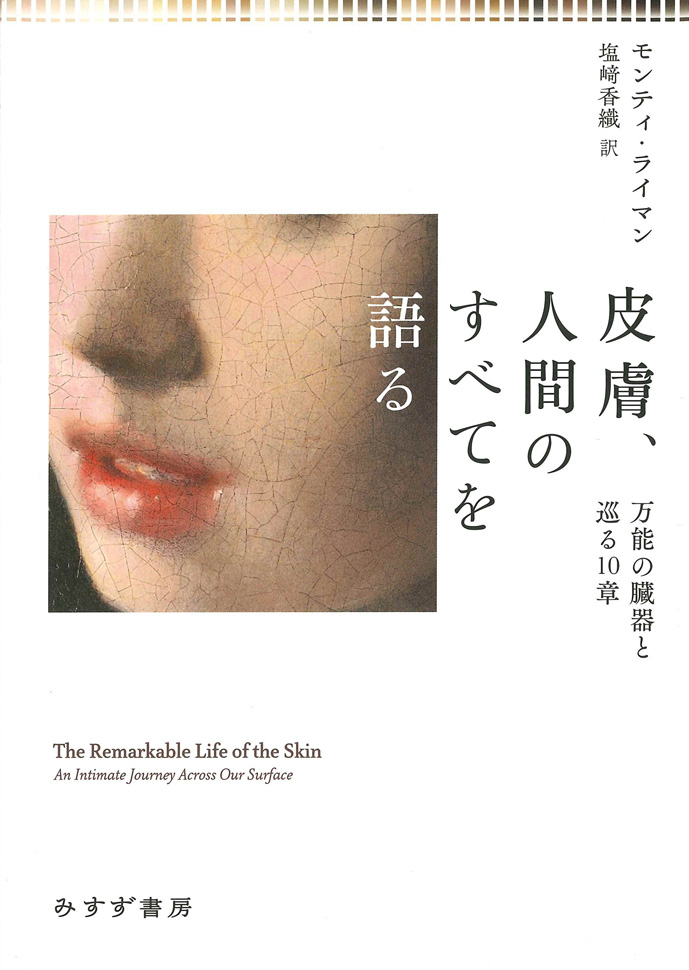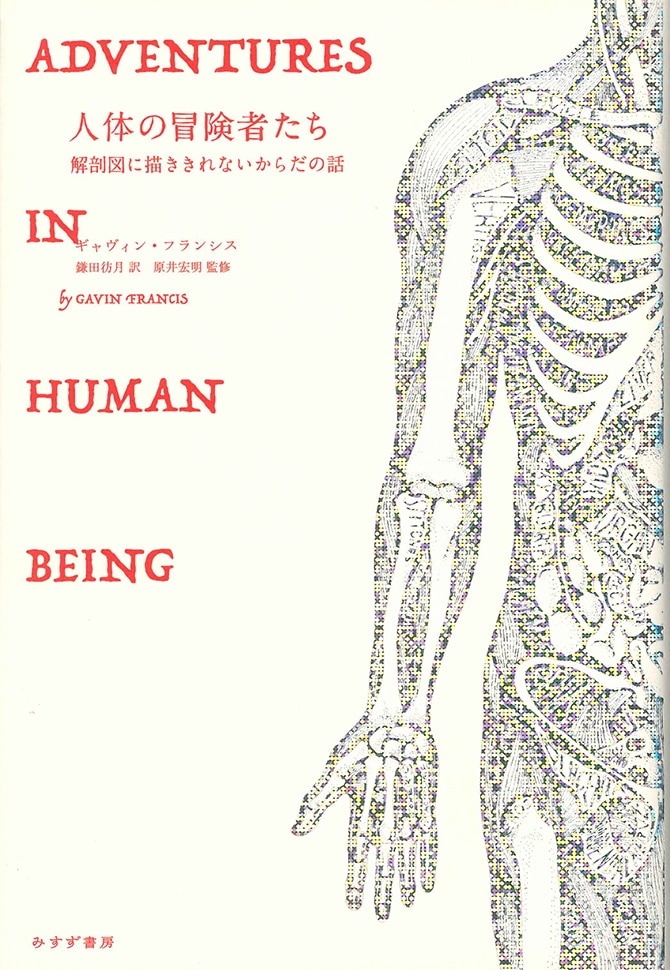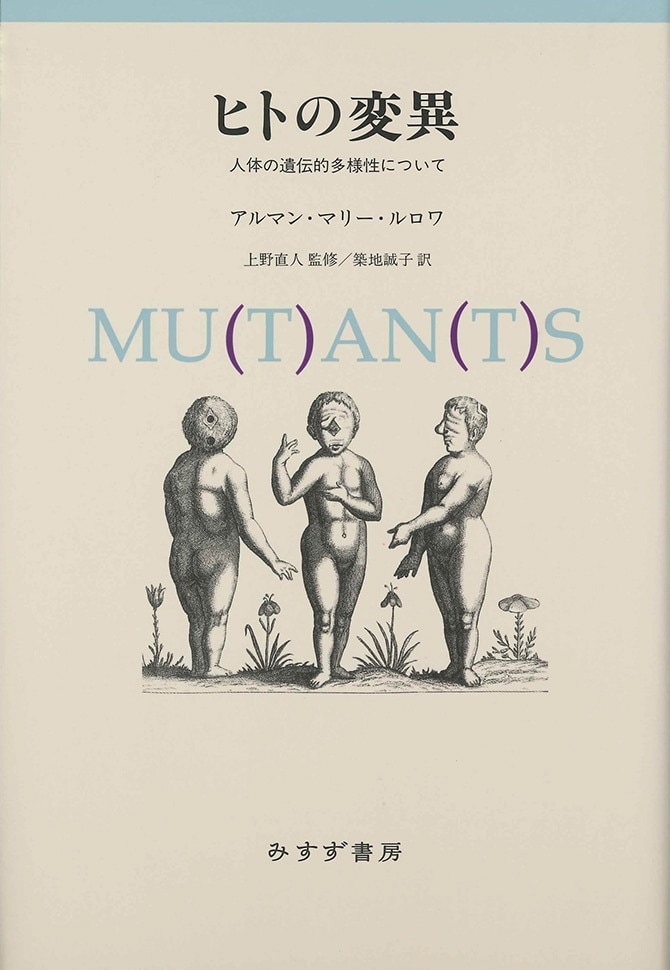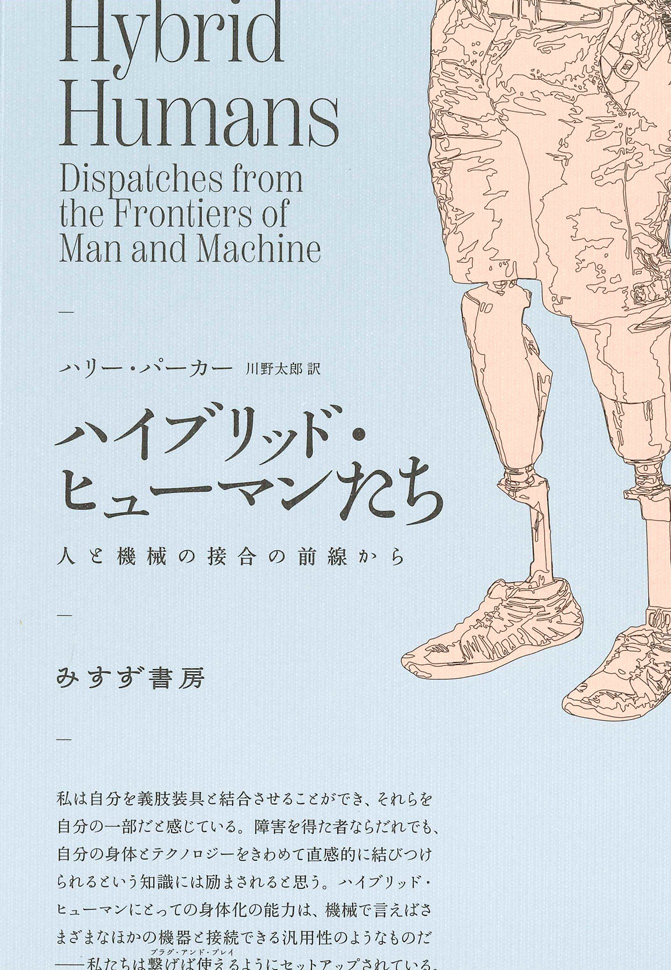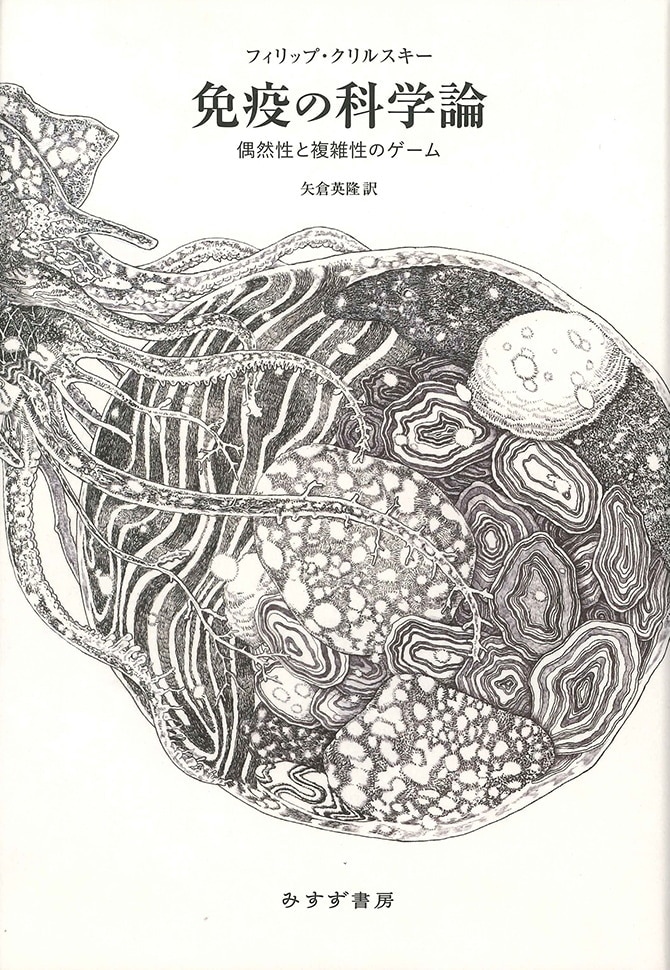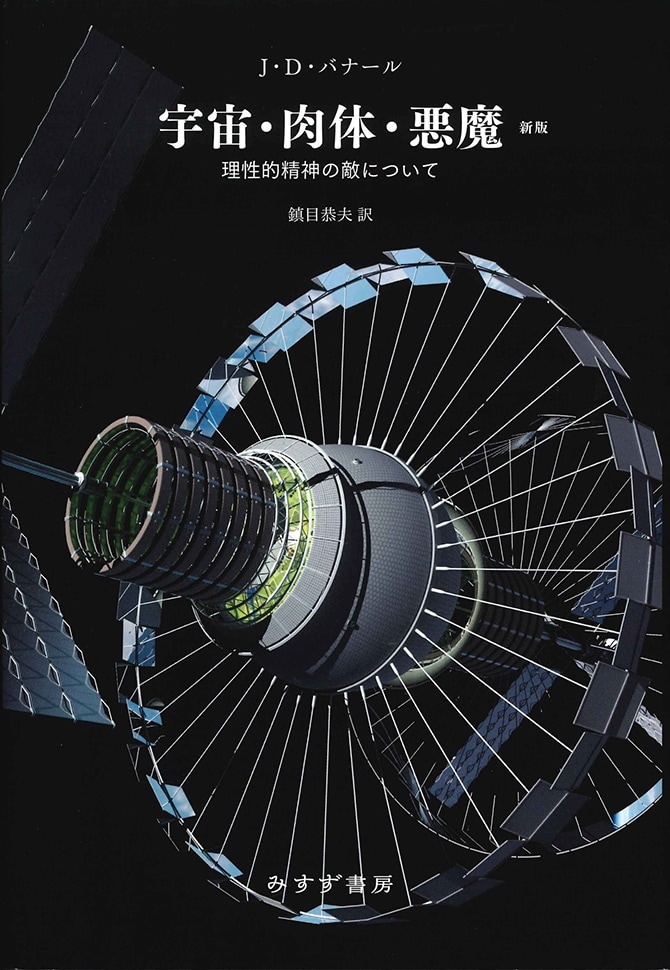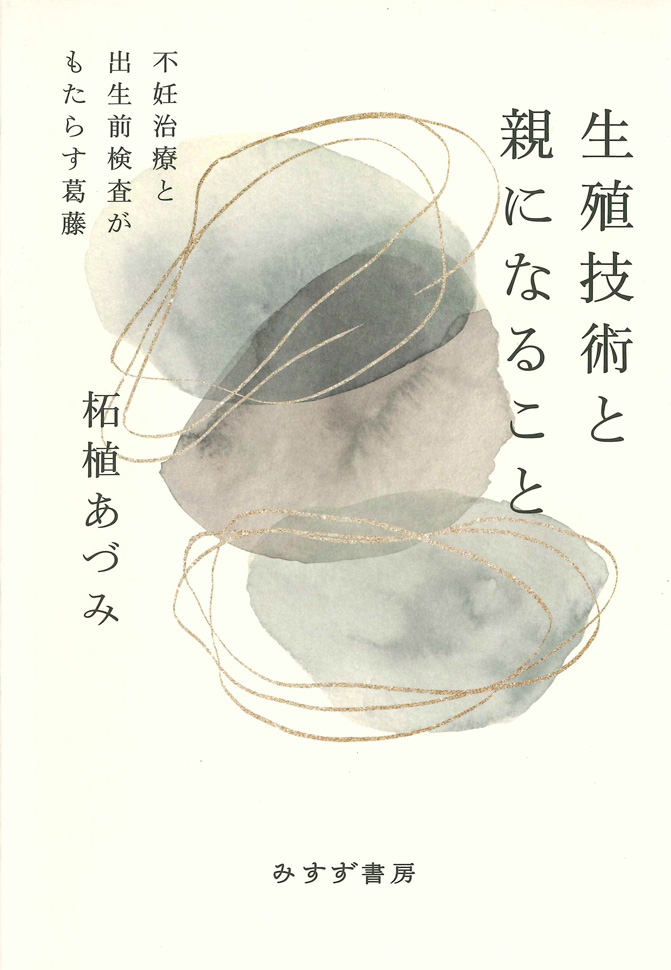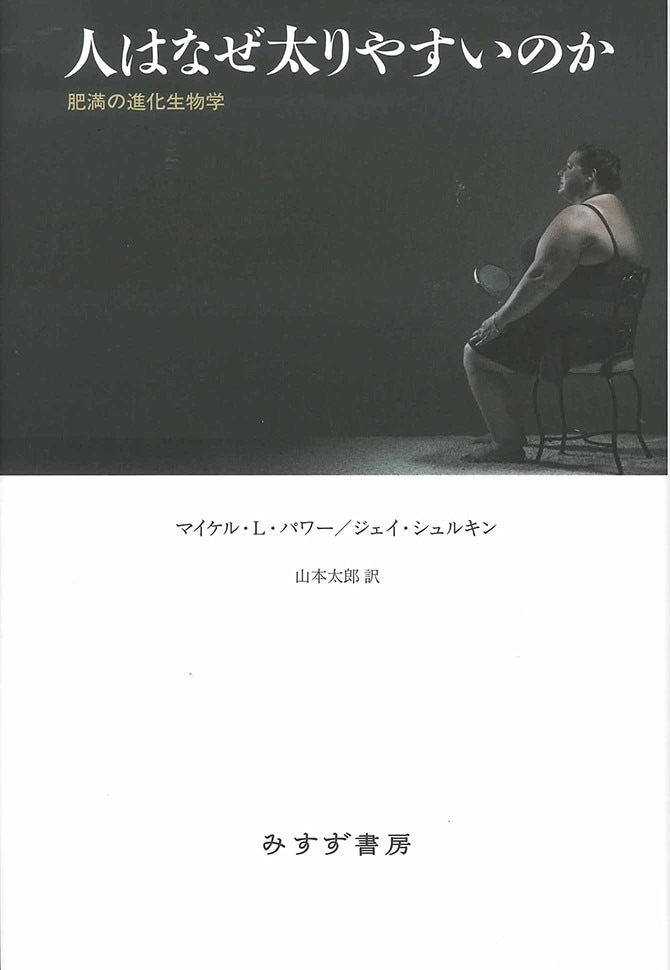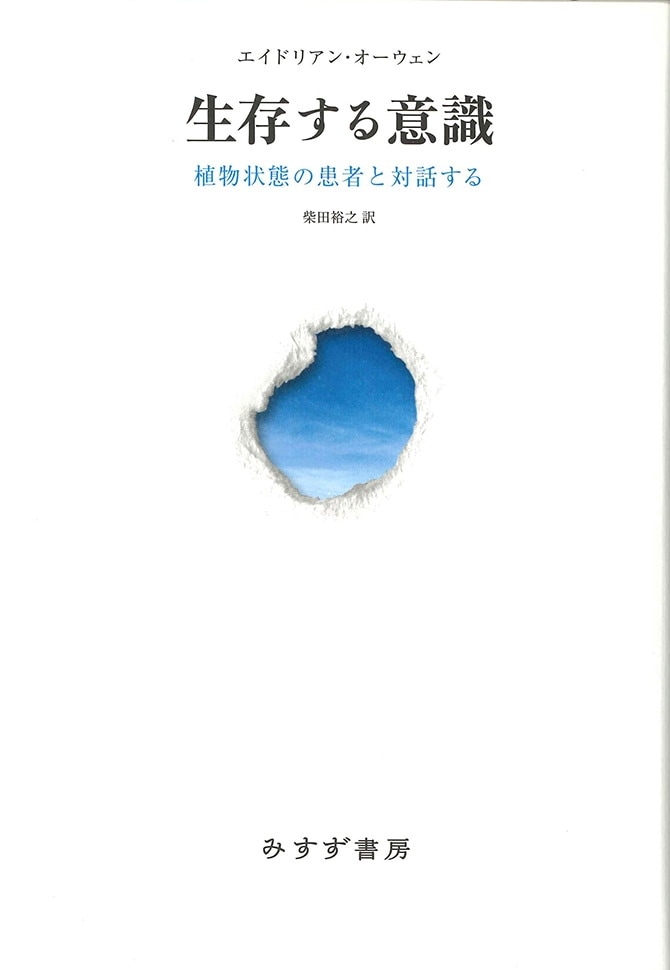私たちのからだに関するとてもエキサイティングな新刊『痛み、人間のすべてにつながる』とあわせて楽しめる、「人間のからだ」に関する本をリストにしました。科学的考察はもちろん、空想や歴史、医療現場や社会制度までさまざまな目線の本を選びました。
1. モンティ・ライマン『痛み、人間のすべてにつながる――新しい疼痛の科学を知る12章』【2024年11月刊】
塩﨑香織訳(2024年刊)
痛みとは、身体に加えられた傷害の程度を測る正確な尺度――ではない。「人間のすべて」とは大きく出たな、と思われる向きにこそ読んでもらいたい一冊。痛みを調べ、知っていくなかで見えてくるつながりは本当にすべてに向いていき、読後あなたは、あなた自身をもっと知ることになるだろう。
2. モンティ・ライマン『皮膚、人間のすべてを語る――万能の臓器と巡る10章』
塩﨑香織訳(2022年刊)
皮膚は臓器であり、人間のすべて――言われてみれば、体全体を包んでくれているのだからそうも言えるか……と納得しそうになった方は、きっと本書を楽しめる。なぜならその納得はいい意味で裏切られ、「体全体を包んでくれている」どころではない驚きの機能に、ページをめくる手が止まらなくなるはずだから。『痛み』とあわせて、モンティ・ライマンの語る「すべて」を味わってほしい。
3. ギャヴィン・フランシス『人体の冒険者たち――解剖図に描ききれないからだの話』
鎌田彷月訳、原井宏明監修(2018年刊)
脳、頭部、胸部、上肢、腹部、骨盤、下肢……。本書の18章は、全部で一つの人体をなす。古代ギリシャの時代から人は身体をどう捉え、現代のわれわれの到達点はどんなもので、これからさらにどこへ向かうのか。ギャビン・フランシス医師の実地での経験と深い見識が、われわれ読者を比類ない冒険へといざなう。
4. アルマン・マリー・ルロワ『ヒトの変異――人体の遺伝的多様性について』【新装版】
上野直人監修、築地誠子訳(2014年刊、初版2006年刊)
「私たちはみなミュータントなのだ。ただその程度が、人によって違うだけなのだ」(p.19)。本書第1章にかかげられるこの宣言は、きわめて重要な意味を持つ。遺伝学と、博物学・文化史・科学史とをあわせた語りが、ヒトの形質とそれをもたらす変異の生物学的意味、社会的意味の深くにまで迫る。
5. ハリー・パーカー 『ハイブリッド・ヒューマンたち――人と機械の接合の前線から』
川野太郎訳(2024年刊)
7月の刊行直後から、「本年度ベストノンフィクション」との賛辞が寄せられた本書。障害をもつ身体が支援機器とつながることの恩恵、痛み、葛藤の現在地を映しだす出色のエッセイ。両脚義足の“ハイブリッド・ヒューマン”当事者としての、著者自身の体験も深い。
6. フィリップ・クリルスキー『免疫の科学論――偶然性と複雑性のゲーム』
矢倉英隆訳(2018年刊)
本書のタイトルが、「科学」ではなく「科学論」なのはなぜか。それは、科学的事実解説の「先」があるから。身体を守る免疫システムの複雑怪奇なしくみに組み込まれた「偶然性」が、人間という機械を、単なる機械とは異なる存在たらしめている、と著者はいう。つまりどういうことなのかは、読んで確かめるべし。
7. J・D・バナール『宇宙・肉体・悪魔――理性的精神の敵について』【新版】
鎮目恭夫訳、瀬名秀明 解説(2020年刊、初版1972年刊)
新しい形態の肉体。四肢の機械化はもちろん、遠隔視装置、遠隔音響感受器、遠隔化学感受器、遠隔感覚器、果ては脳同士をすべてつなぎ合わせた「群体頭脳」……。人間とは何であり、その肉体はどこまで拡張できるのか。あなたの観念をゆるがす、身体の未来予測は3章に。全編通して本文100ページの軽量級でも、噛み応え抜群。
8. 柘植あづみ『生殖技術と親になること――不妊治療と出生前検査がもたらす葛藤』
(2022年刊)
生殖技術は何を引き起こしているのか? わかりやすい科学的説明には表れない、当事者の激しい葛藤と身体への影響が軽視されがちなのが、今の社会の現状だ。技術の発展に制度が追いついていないことで、どんな具体的な問題が起こっているのか。詳細な取材がまざまざと示す。(2022年度第11回日本医学ジャーナリスト協会賞〈大賞〉受賞作)
9. マイケル・L・パワー、ジェイ・シュルキン『人はなぜ太りやすいのか――肥満の進化生物学』
山本太郎訳(2017年刊)
暮らしに卑近なこんなテーマの本も、みすず書房にはあります。本書には、やせるための近道はないけれど、太ってしまう背景にある生き物としてのメカニズムがある。敵を知れば百戦危うからず、の気骨のあるダイエッターに。
10. エイドリアン・オーウェン『生存する意識――植物状態の患者と対話する』
柴田裕之訳(2018年刊)
「『植物状態』とされていたときについてのケイトの思い出は悲惨だ。『介護にあたる人たちは、私は痛みを感じられないと言っていました。とんでもない思い違いです』とケイトは自分を見舞った苦難について書いている」(p.39)。植物状態の人のなかには意識がないわけではなく、応答することができないだけの人がいる――「グレイ・ゾーンの意識」の存在を異論の余地なく実証した驚くべき医科学研究の報告。