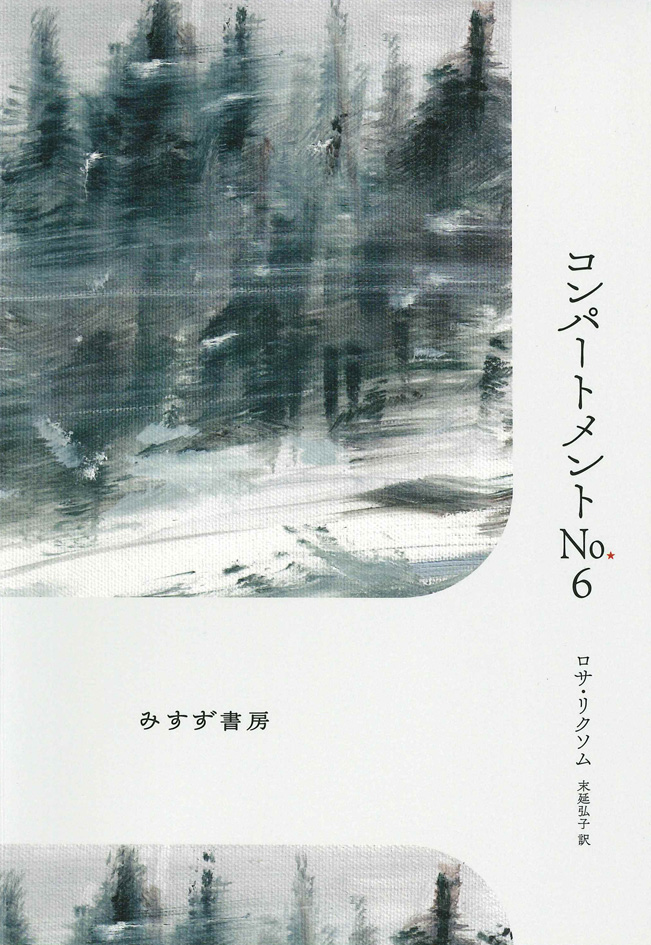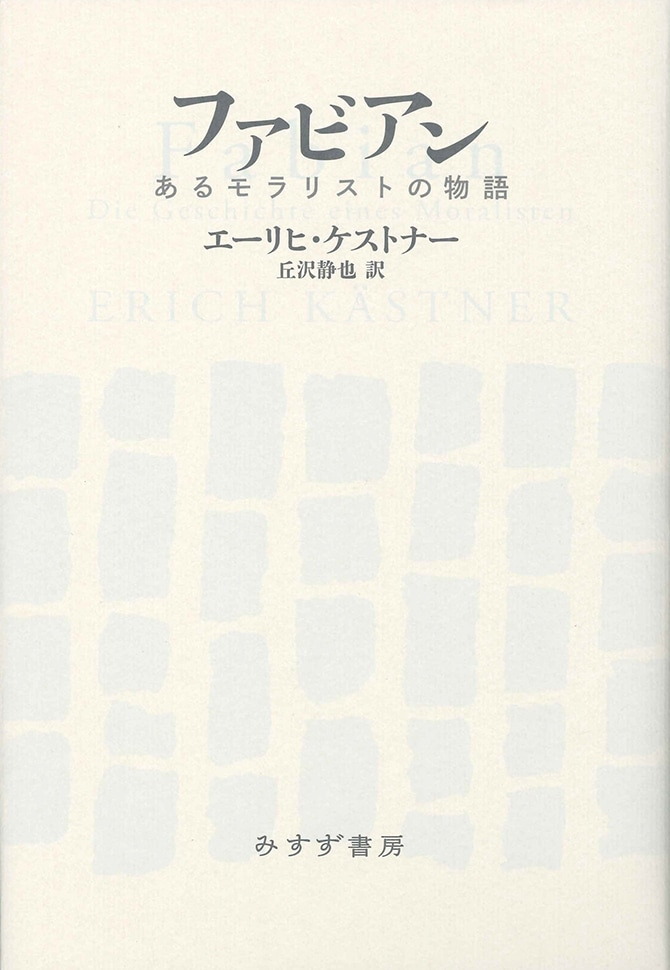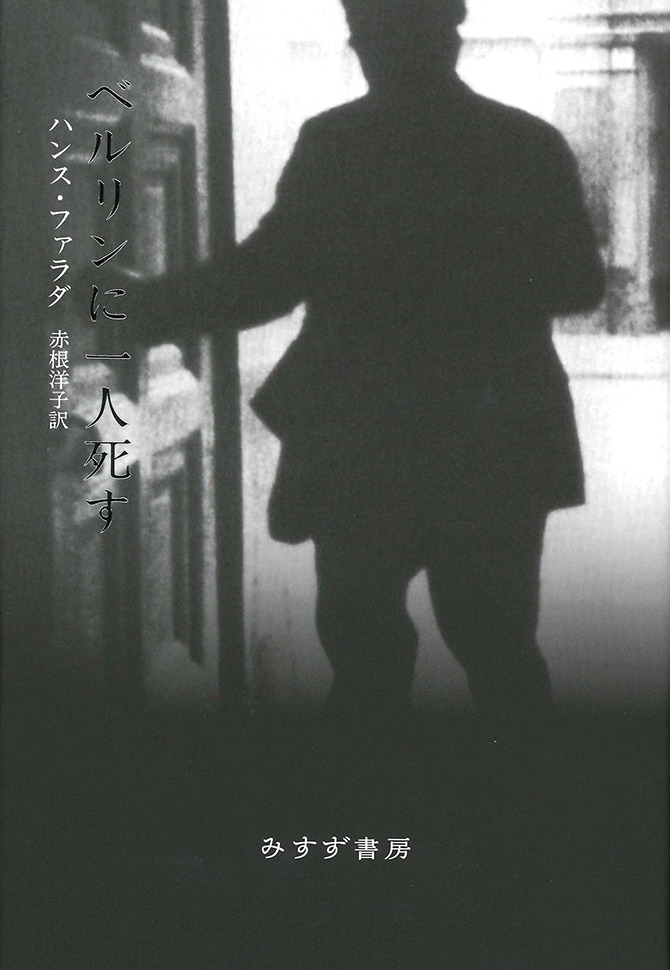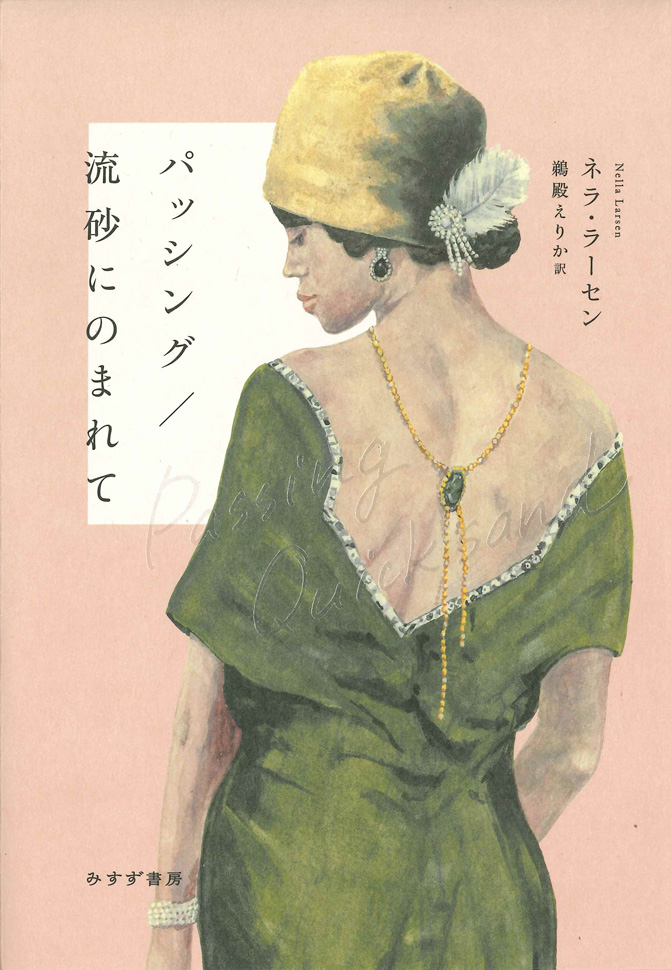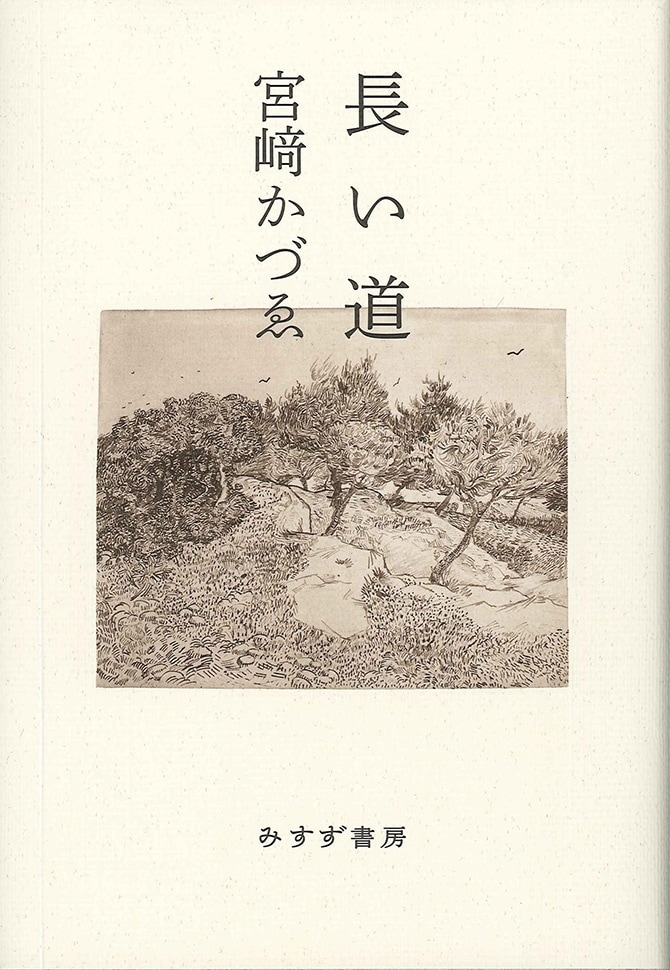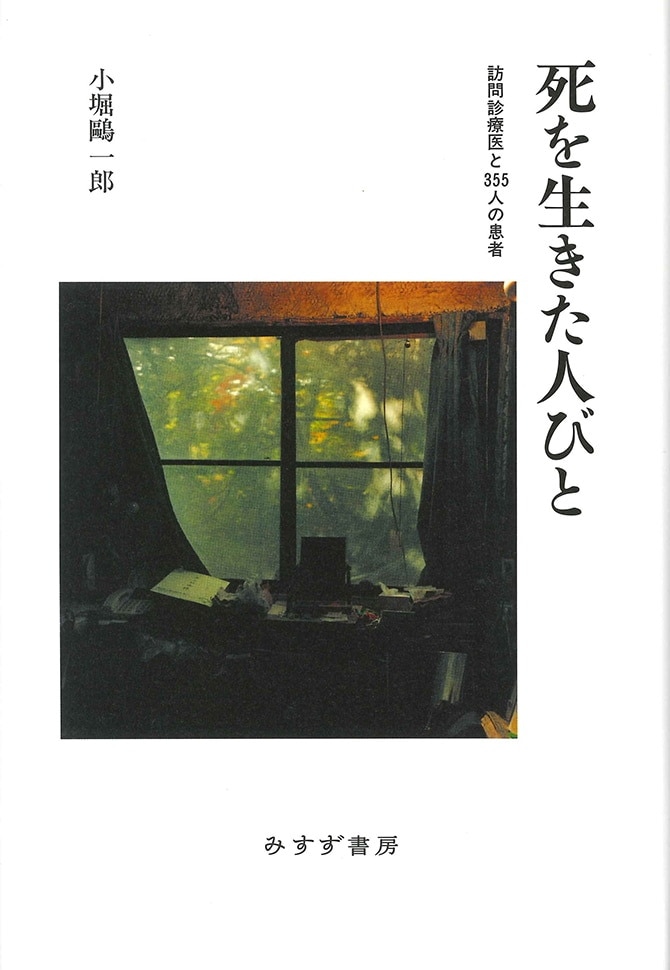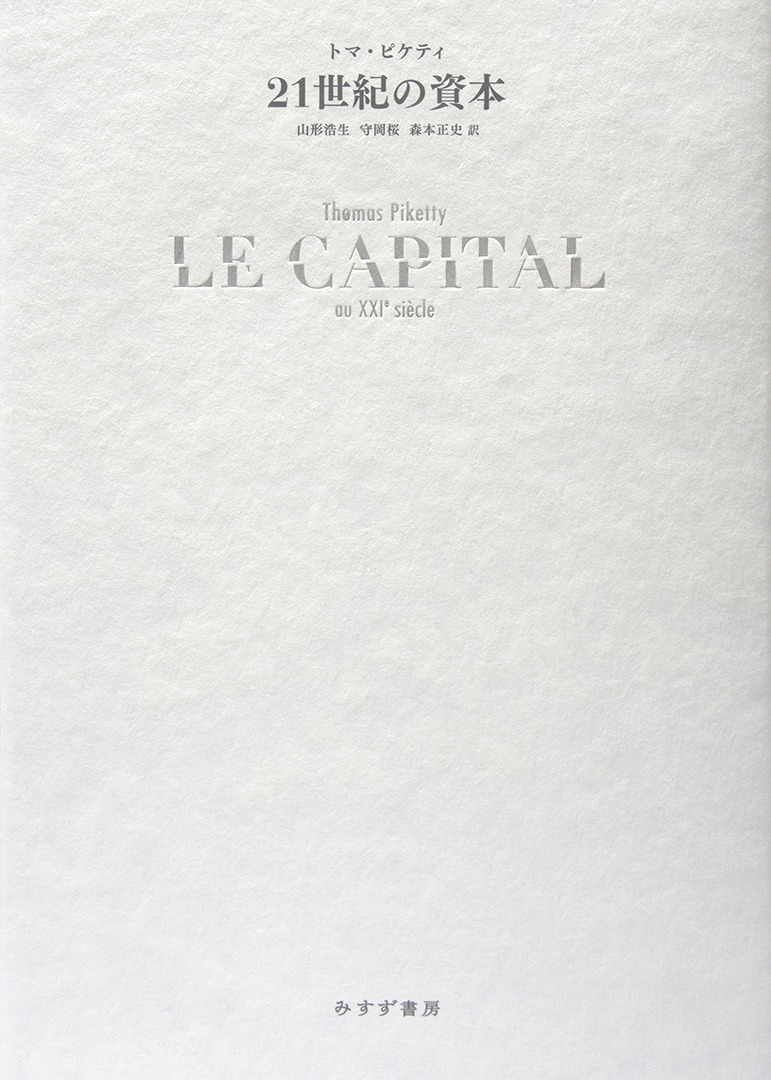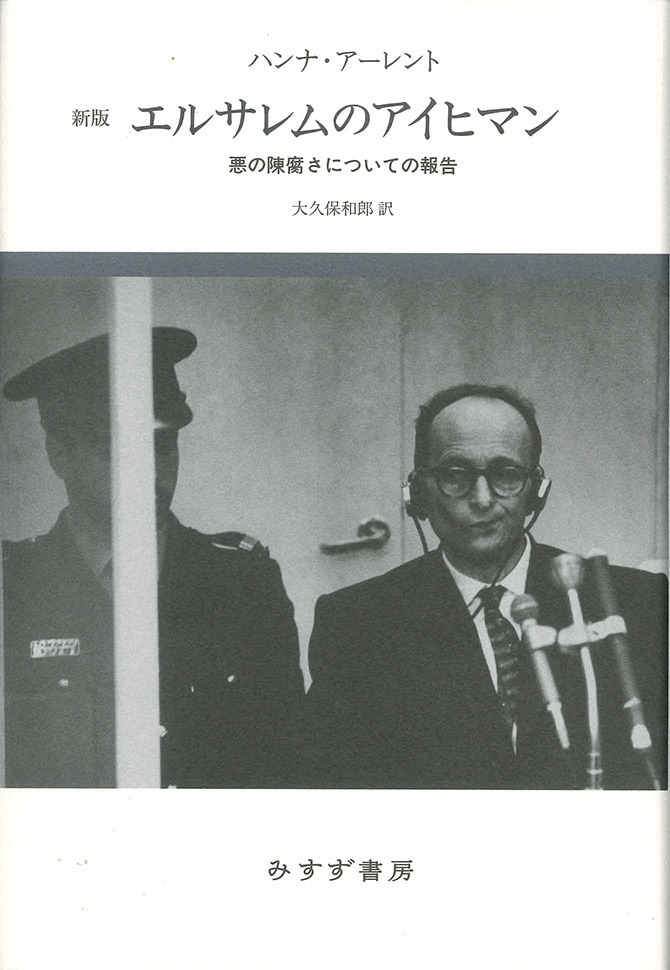7月の新刊『コンパートメントNo.6』は、カンヌ国際映画祭2021のグランプリを獲得した同名映画の原作となった小説作品です。みすず書房の本のなかには、フィクション/ノンフィクションともに、映画作品の原作や着想元となったものがあります。今回は、そんな本の一部をご紹介いたします。(Web配信の情報は、2025年7月時点のものです)
1. ロサ・リクソム『コンパートメントNo.6』【2025年7月刊】
末延弘子訳
憧れのソ連に留学してきたフィンランド人の寡黙な少女と、家族をのこして建設現場へ向かうロシア人の饒舌な出稼ぎ夫。シベリア鉄道の同じ部屋に偶然乗りあわせた二人は、寝台列車の長い旅の中で何を話し、何を思うのか。本書を原作にしたユホ・クオスマネン監督の同名映画は、カンヌ映画祭グランプリをはじめ、世界中で17冠の快挙を達成。原作小説と映画は重なる部分も多いが、人物の設定など細部が異なる。著者と監督のそれぞれの意図を想像しながら読むと一層楽しめることうけあい。
- 『コンパートメントNo.6』詳細はこちら
- 映画『コンパートメントNo.6』(ユホ・クオスマネン監督、2021年)
- 公式サイトはこちら
-
複数の映像配信サービス(サブスクリプション、レンタル)で視聴可能
2. エーリヒ・ケストナー『ファビアン――あるモラリストの物語』
丘沢静也訳(2014年刊)
深さよりは浅さを、鋭さよりは月並みを、曖昧さよりは明快さを大切にした、大胆なモラリストにして辛辣な風刺家ケストナー。児童文学で名を揚げた彼の、唯一の大人向け長編小説が本書である。1931年、ナチスの足音が聞こえてくるベルリンの頽廃的な空気が、ファビアンという男を通して描かれる。本書を原作とした『さよなら、ベルリン またはファビアンの選択について』は、2021年ドイツ映画賞最多10部門ノミネート・主要3部門受賞の秀作。
- 『ファビアン』詳細はこちら
- 映画『さよなら、ベルリン またはファビアンの選択について』(ドミニク・グラフ監督、2021年)
- 公式サイトはこちら
- 複数の映像配信サービス(サブスクリプション、レンタル)で視聴可能
3. シュテファン・ツヴァイク『チェスの話――ツヴァイク短篇選』
辻瑆・関楠生・内垣啓一・大久保和郎訳、池内紀解説(2011年刊)
本短編集の表題作「チェスの話」は、ツヴァイクが亡命の途上で書いた最後の小説。ナチス圧政下でホテルに軟禁されたオーストリアの名士を主人公とした、一冊のチェスの本をめぐって展開される物語。本書表題作は『ナチスに仕掛けたチェスゲーム』という題で映画となった。
- 『チェスの話』詳細はこちら
- 映画『ナチスに仕掛けたチェスゲーム』(フィリップ・シュテルツェル監督、2021年)
- 公式サイトはこちら
- 複数の映像配信サービス(サブスクリプション、レンタル)で視聴可能
4. ハンス・ファラダ『ベルリンに一人死す』
赤根洋子訳(2014年刊)
1940年、ベルリンの街はナチスの恐怖政治に凍りついていた。政治のごたごたに関わらないよう静かに暮らしていた職工長オットー。しかし一人息子の戦死の報せを受け取ったのち、彼と妻アンナは思いもかけぬ抵抗運動を開始する。ヒトラーを攻撃する匿名の葉書を公共の建物に置いて立ち去るのだ。この行為はたちまちゲシュタポの注意をひき、命懸けの追跡劇が始まる……。1947年の作品ながら、2009年に出版された英訳版が世界的ベストセラーに。その勢いも手伝って、2016年に二度目の映画化が実現した。
- 『ベルリンに一人死す』詳細はこちら
- 編集者からひとこと
- 映画『ヒトラーへの285枚の葉書』(ヴァンサン・ペレーズ監督、2016年)
-
複数の映像配信サービス(サブスクリプション、レンタル)で視聴可能
-
5. ネラ・ラーセン『パッシング/流砂にのまれて』
鵜殿えりか訳(2022年刊)
「パッシング」とは、肌の色の白い黒人が自らを白人と称して行動する実践である。幼なじみの女性が再会する。どちらもパッシングができるほど肌が白いが、アイリーンは黒人社会で堅実な家庭を築き、クレアは黒人であることを隠して白人と結婚生活を送っていた。クレアが子ども時代に暮らしていた黒人コミュニティに惹かれ、再接近したとき、事件が起きる。
ジェンダー・人種・差別・LGBT問題の必読書ともいえる本書。表題作「パッシング」を原作とする映画『PASSING 白い黒人』は、全編モノクロで仕上げられた映像。映画は2021年サンダンス映画祭でプレミア上映、女性映画批評家サークル(Women Film Critics Circle:WFCC)最優秀賞を受賞。ジョセフィン・ベイカー賞(有色人種女性の経験を最も表現した作品)、カレン・モーリイ賞(歴史や社会における女性の地位や、アイデンティティを探すことを最も良く表した作品)も受賞。
- 『パッシング』詳細はこちら
- 【編集者からひとこと】越境する人 作者とヒロインたち
- 映画『PASSING 白い黒人』(レベッカ・ホール監督、2021年)
- Netflixで視聴可能
6. 宮﨑かづゑ『長い道』
(2012年刊)
著者は1928(昭和3)年生まれ。10歳で瀬戸内海に浮かぶ島、長島のハンセン病療養所長島愛生園(現・岡山県瀬戸内市)に入園、以来80年余をこの地で暮らす。
家族の愛情に包まれて過ごした幼少期。発病によって故郷を離れ、孤児のような気持ちで過ごした少女時代。『モンテ・クリスト伯』を読みふけり、大海原に心遊ばせた十代。夫のために料理をし、ミシンをおぼえ裁縫に精出した日々。心の支えだった親友の最期。遠い道のりをいつまでも会いにきてくれた母への思い。時々の思いを、瑞々しい文章が伝える。
著者のありのままを映し出したドキュメンタリー映画『かづゑ的』は、ドイツ・Nippon Connection映画祭でニッポン・ドックス賞(ドキュメンタリーの最優秀賞)を受賞。監督・熊谷氏は劇場舞台挨拶の場で「(映画祭では)上映後すぐに席を立たずに余韻に浸る観客が多かった。現地スタッフによれば、これはとても異例なことだそうです」と語った。
- 『長い道』詳細はこちら
- 編集者からひとこと
- 映画『かづゑ的』(熊谷博子監督、2023年)
- 公式サイトはこちら
- Web配信なし
7. 小堀鷗一郎『死を生きた人びと』
(2018年刊)
これまでに355人の看取りに関わった訪問診療医が語る、患者たちのさまざまな死の記録。小堀医師と訪問診療チームの営みの様子は、NHK BS1スペシャル「在宅死“死に際の医療” 200日の記録」(日本医学ジャーナリスト協会賞大賞受賞作)として映像化され、ドキュメンタリー映画『人生をしまう時間(とき)』としてまとめられた。本書に収められた精密な描写は、映像のなかで奥行きをもって立ち上がってくる。一方で、映像だけでは把握しにくい背景情報や小堀医師の思索の深さを、読むことによって感得できる。
- 『死を生きた人びと』詳細はこちら
- 映画『人生をしまう時間(とき)』(下村幸子監督、2019年)
- 公式サイトはこちら
- Web配信なし
8. トマ・ピケティ『21世紀の資本』
山形浩生・守岡桜・森本正史訳(2014年刊)
言わずと知れた世界的ベストセラー経済書。18世紀から現代にいたるまで、途方もないほどに広がってしまった経済格差の、原因とその処方箋を説く分厚い本書には、なんと映画版がある。著者トマ・ピケティ本人が出演し、工夫された映像ではっきりと、しかし精密に本書の要諦を伝える。J. スティグリッツ、F. フクヤマなど著名な学者も多数登場。
- 『21世紀の資本』詳細はこちら
- 映画『21世紀の資本』(ジャスティン・ペンバートン監督、2019年)
- 複数の映像配信サービス(サブスクリプション、レンタル)で視聴可能
9. ハンナ・アーレント『エルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告』
大久保和郎訳、山田正行解説(新装版2017刊)
近年ますます研究が深まっている〈悪の凡庸さ〉概念を、初めて世に問うたのが本書。発表当時大いに物議をかもし、そのために著者アーレントは激しいバッシングを受けることになる。映画『ハンナ・アーレント』は、本書のアイヒマン裁判を中心としてアーレントの生きざまを克明に描いた作品。日本での公開当時、東京・岩波ホールで異例のロングランヒットとなった。
- 『エルサレムのアイヒマン』詳細はこちら
- 映画『ハンナ・アーレント』(マルガレーテ・フォン・トロッタ監督、2012年)
- 公式サイトはこちら
- Apple TV、Amazon Prime Videoでレンタル視聴可能