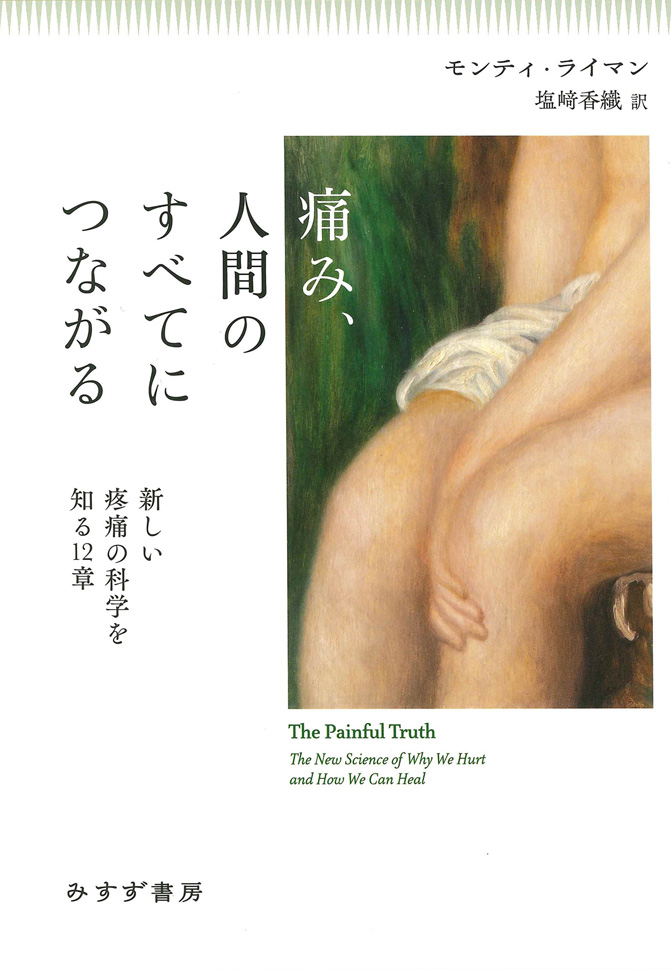「痛み」はその人らしさを作るか、奪うか?
【書評】モンティ・ライマン『痛み、人間のすべてにつながる』
2024年12月2日
私事になるが、精神科医生活にひと区切りをつけて、一昨年から北海道の山間にある孤立地区であるむかわ町穂別でへき地医療に取り組んでいる。当地も高齢化率が高く、勤務している診療所の病棟で人生の最期を迎える人も多い。
そこで問題になるのは「痛みの有無」だ。がんの終末期となり都市部の病院から「先生、穂別で死にたいんだよ」と転院してくる人も、「痛みが出ないように頼むね」と言う。高齢者施設入所者が肺炎などになって入院となり、そのまま命が尽きることも少なくないが、駆け着けた家族はまず「痛がってなかったでしょうか」ときく。逆に言えば、激しい痛みさえなければ、多少、呼吸に支障が出たり腎機能が悪化して尿毒症になったりしても、ほとんどの人は穏やかに、その人らしい臨終の時を迎えることができる。「痛みがあるかどうか」は人のQOL(quality of life)ならぬQOD(quality of death)を大きく左右するのだ。
人生の重大な局面において、「その人らしさ」を奪おうとする痛み。本書『痛み、人間のすべてにつながる』において著者は、医学者らしい緻密さで痛みの機序、とくに神経が送ったどんな信号が、脳のどの部分でどのように認識されて痛みとなるのかについて、最新の知見も紹介しながら解説していく。ただ、そうであれば末梢神経や脳の特定の領域をブロックしさえすれば痛みの感覚は消えてなくなりそうなものだが、誰もが「そんなに単純なものではない」と知っている。著者は言う。
「痛みは感覚的なものであると同時に情動的なものでもある。この二つの要素は脳の物理的なスペースにおいて、また私たちの実体験という面でも、重なり合い、絡み合っている。」
ここで「痛みは情動的なもの」というフレーズを聞くと、「ほら、やっぱり痛みは気の持ちようなんだ」と思う人もいるかもしれないが、それは違う。著者は繰り返し、痛みには私たちの身体に危険が迫っていることを警告する「安全装置」としての役割があると述べるが、それを考えれば、不安や心配、恐怖といった心理的な因子がある「私たちの脳はこの警報の出力を増幅させようとする」という説明にも納得がいく。つまりストレスやトラウマがある状況では、通常ならスルーできる信号にも脳が「過剰警戒」をする結果、強い痛みととらえてしまうのである。
こういった知見から、著者は痛み、とりわけ慢性疼痛は、広く「生物・心理・社会モデル」で取り扱われるべきだ、という結論に達する。鎮痛剤の投与ももちろん必要だが、本人が置かれている環境の調整や、考え方のクセを修正する認知行動療法、ときには意識のコントロールが及ばないところにアクセスする催眠療法や瞑想なども使いながら、全方位的にアプローチすることが必要となる。
ここまで読んで、私はつぶやいた。「これは痛みへのアプローチではなくて、痛みは単なるきっかけにしかすぎず、その人そのものを脳、身体、心理すべてから包括的にとらえるということではないか。」
冒頭で私は、「終末期の痛みは、その人がその人であることを妨げる」と記した。しかし一方で、痛みはその人がその人であることや生きてきたプロセスを形成している、とも考えられる。あえて一文にまとめると、「痛みはその人らしさそのものであり、また同時にその人らしさを奪うものでもある」と言えるのではないだろうか。痛みにより人はその人となり、痛みにより人はその人でなくなる、ということだ。
最近、生物学者や医学者が研究でさかんに用いる「脳オルガノイド(ES細胞やiPS細胞などの多機能細胞から分化誘導された生体と似た構造を持つ三次元脳組織)」を巡る倫理的議論でも、この「痛み」がトピックとなっている。複数の神経細胞を持つ“ミニ脳”ともいえる脳オルガノイドは、脳の発生学の研究だけではなく、さまざまな神経疾患の病態解明や薬の開発にも有用とされるが、将来的には「意識(めいたもの)を持つ脳オルガノイド」が作られるようになるともいわれる。そのとき、それはどこから「生命」あるいは「人間」と見なされるべきなのか。
澤井努広島大学大学院准教授(生命倫理学)との対話の中で、東京大学大学院の永石尚也准教授(法哲学)は言う。
「これから先、人々の間でのコミュニケーションにおいて『痛み』や『意識』を備えたものとして受け入れられるような脳オルガノイドが生みだされ、さらに社会に位置付けられれば、自分たちの同胞としての『人』としての価値を社会が見いだし、脳オルガノイドもまた『人』だといえる日が来るかもしれない。」(「脳オルガノイドは『人』と見なせるか 若手の生命倫理学者と法学者が別々の観点から考察」『サイエンスポータル』)
この先、「痛みの研究」がさらに進めば、本書にあるような疼痛の神経回路を忠実に再現した脳オルガノイドが作られる可能性もある。
本書の著者によれば、痛みは単なる生物学的な反応ではなくて社会的な意味を持つものなので、その点では「脳オルガノイドの疼痛反応は人間の『痛み』とは違う」と言えるだろう。しかし、刺激により痛みの電気信号が走り、脳の痛みを感じる領域が活性化されるのを目の当たりにしたとき、私たちは「それでもこれは人ではない」と冷静でいられるだろうか。
今も病棟には、最期の時間をすごす高齢者が入院している。朝、回診のときにその人は、「おかげさまで痛みはなくなったよ」と柔らかなほほ笑みを浮かべた。そのほほ笑みは、元気なときのその人のやさしさや穏やかさを表すものであろう。とはいえ、痛くなったら遠慮なく「痛い! なんとかならないの!」と要求してほしいとも思う。「こんな先生に診てもらうんじゃなかった」と言ってくれてもよい。痛みにより引き起こされる攻撃性や後悔の念も、またその人らしさそのものであることは本書によりよくわかったからだ。
病棟から医局に戻る廊下で、「痛みこそが私たちの主人」という言葉がふと頭に浮かび、急いで振り払った。そんなわけはない。私たちは痛みを超えて、自分の意思に従い主体的な人生を送っているはずだ。いくらそう思おうとしても、「いや、それでも…」という声が繰り返し本書から響いてくる。厄介で、そしてたまらなく魅力的な本を読んでしまった。
(香山リカ むかわ町国民健康保険穂別診療所 総合診療医・精神科医)