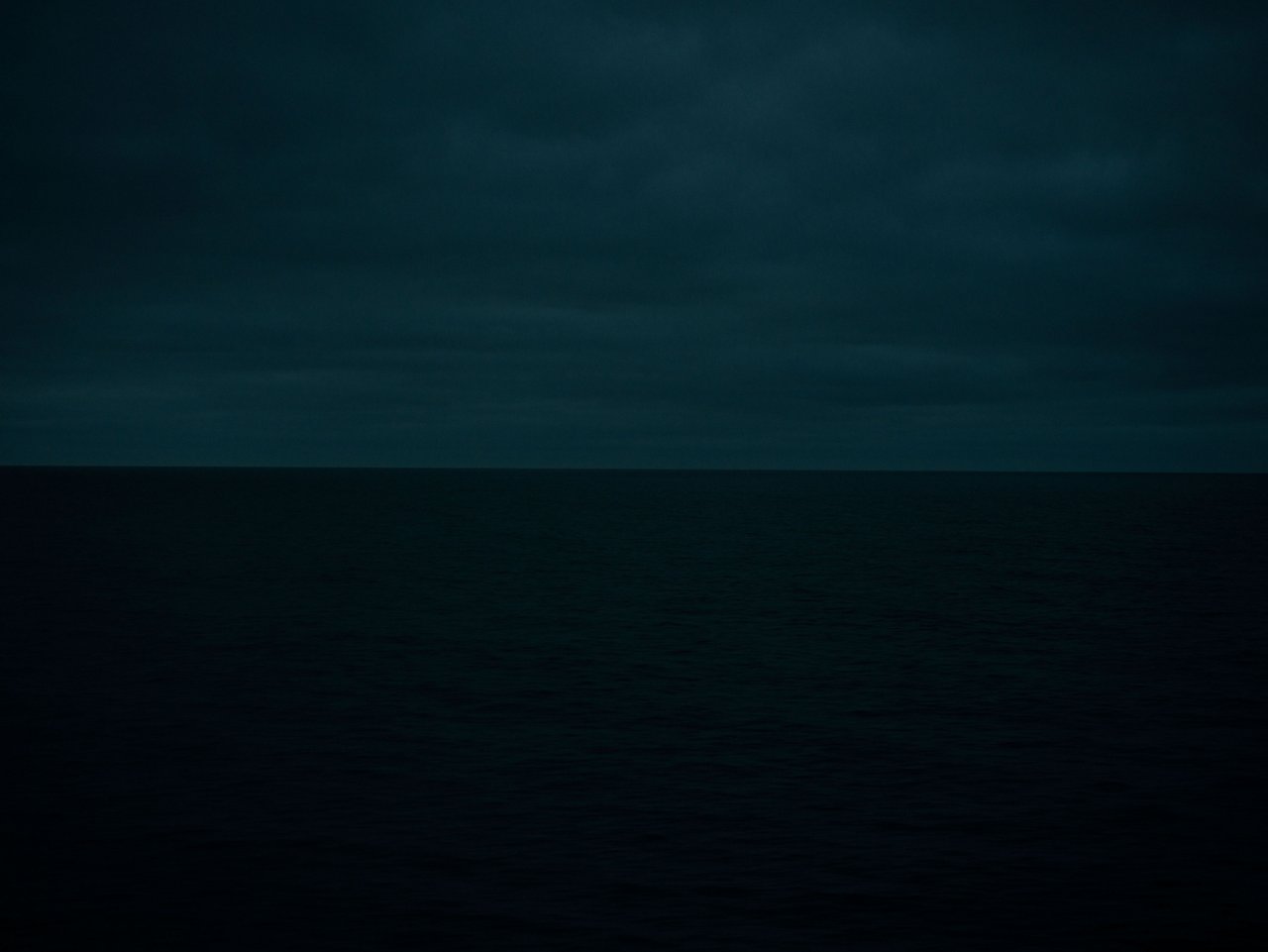
過ぎ去った時間の遠近は不思議だ。一つの同じ時点が、遥か遠方のようにも、すぐ直近のようにも等しく感じられてしまうこともあれば、異なる時点の遠近が逆転して感じられることもある。
今、その家へ行けば、小学生の彼女が「キムチ、山盛りやで」と私を迎えてくれそうなのに、大人の方の彼女は、私が手を伸ばしても絶対に届かない彼方に一人でいる。人が死ぬと星になるというのは…そうか…遠く遠く、小さく小さく、でも、歴々と、そういう記憶になることを言っているのか……
でも、50歳の背が見えて、再びその彼女が近づいてきたとも感じる。死後の世界の有無など無関心だけれど、29歳の彼女にまた会って話ができそうなこの感じはいったいなんなのだろう…。二十歳を過ぎる頃から、諍いが多くなった。そのとき、二度と遊ばないと思っても、仲直りを繰り返して、それでも会う機会は減って、それを取り返そうとして連絡を取っていた。諍いのさい、彼女は私にひどいことを言った。私もまた、負けず劣らずひどいことを言った。あのころ、私たちはお互いに自分自身に理由もわからず苛立ち、それを相手に転嫁していたのだと今はわかる。だから私だけに非があったとは思わないけれど、私が浴びせた悪口、それだけは謝りたいという気持ちが抑えられない……
トイレに立ったかと思っていたまっちゃんがドライヤーを手に戻ってきた。糞を乾かすことがそれほど気に入った? いいよ、まっちゃん、好きにしぃ…
なぜ、人は線引きが好きなのか? いたるところにくっきりとした境を与えたがる。人と人の間に、地面に、海に。そして時間にまで時代名をつけて線を引く。そして、それらの線で、自分を縛る。
津南で撮影を始めた最初の数年、私は「津南町」を越え出ないようにしていた。私は人の引いた境を墨守し、滞在で人々との交流が広がりだして、津南と言えば、毎年の冬の到来のニュースで「雪が一晩で1メートル以上積もった」と、そればかりで紹介される紋切り型のイメージを、自分の写真で一新すると張り切ってさえいた。そういうことは起きたとしても作品に結果的に伴うことで、とうてい作品のテーマでも目的でもなかったのに、滑稽でしかない。雪深い山中の町境に立ってみれば、そこには何もなく、雪は、人の引いた線などいささかの構いもなく降り広がっていた。それに気づいて、町境を越えて、シャッターを切りだしたとき、私はようやく本当の撮影が始まったと感じた。私が雪に与えていたイメージのさきに、本当の雪が見えてきた。街に属する場所さえもまた新たな様相で立ち現れてきた。それほどに自縛を解くことには開放感があった。水に大気に姿を変えて雪が通年で時を律するこの地の本当の境は、濡れた布に垂らした染料の、滲む模様の境のように、緩やかなグラデーションで淡く消失し、でも水面のように厳然としている。たとえば、その境の向こうでは植生も変化してしまう。この雪の領野にかろうじて対応できた名辞は「奥信越」で、私は作品紹介に「津南を中心に、奥信越で撮影」と書くようになった。
さかなの目で見るなら、水面はどのように現れるのだろう?揺らめいているのは水ではなく、その上の空気の面と見えるかもしれない。そこから先は生きてゆけない世界の境界面、それが揺れていると。
私は、子供の頃に、いや、成人してもなお、父と母から「なんでお前は普通にできひんのや」と叱られつづけてきた。幾度、そう言われたことだろう。そのたびに、『普通て、なんや!』と私は怒りまじりに塞ぎ込んだ。その私が付き合った男たちは、共にいる時間が長くなるにつれて、「なんで、お前は俺の言うことが聞けないんだ?」と怒るようになっていった。私が独裁者を好み、その上で独裁者を怒らせることを趣味にしていたのではもちろんなく、今では彼らの言が、両親が私に散々言ってきた「なんでお前は普通にできひんのや」と同じ意味だったと分かる。人が社会に引いた様々な線が輪郭線となって現れる「価値観」、それとも「社会の空気」というものに、どうやら私は生まれつき不感なのだ。両親の怒りも男たちの怒りも、私には意味不明だけれど、しかし社会的に見るなら、そう、「普通」となる。そこには善も悪も混交し、悪であっても、ある場所ある時代にはまかり通る「普通」、私はその存在を知るのに私は40年以上もかかった。子供の私に、「あの子、あっちの子やねんで。日本人と違うんよ」「なんでここにおるんや。日本人やろ」と言った大人たちも、その「普通」を纏っていたのだ。その差別に関しては、改めて『あほくさ』と思う。
ある場所、ある時代、そこに生まれ育ち生活しているとほぼ無自覚に纏ってしまうのが「普通」だ。善は「普通」の様をしていなければ、現実離れの理想と煙たがられ、悪も「普通」の様をしていなければ、当然忌避される。謂われのない優劣の差異化、すなわち差別が、それとわかってもなお維持されてしまうのは、それが「普通」の様をして社会に入り込んでしまっているからだ。それは長い糸となって、思いがけぬ広範囲に及んで、社会に織り込まれている。「普通」の中には、感得して身につけておいた方が良いものもあることを、私は実地に学んできた。良いも悪いも「普通」の様をしている。良い糸も悪い糸も表面的には「普通」に見えて、それが交差をして、ある場所ある時代のその社会を織りなしている、だから、「普通」は厄介だ。「普通」の様をしているから、世代が移っても、人はそれを受け継いでしまう。だが、「普通」は、その語の意味合いとは裏腹に、常軌を逸して、狂気としか言いようのないレベルに達することだってある。
私は10代の頃「非行」に走ったけれど、その中には、人に迷惑をかけたり、心を傷つけてしまうものが混じっていて、それは「普通」を纏っていれば避けられた。「普通」を体得できなかったが故に、私には、回避できた悪もあれば、招いてしまった悪もあった。その招いてしまった悪は、「普通」を纏っていたら、回避できたけれど、今度は「普通」を纏ったが故に、別の悪を招いてしまう。そう、その意味でも厄介だ、「普通」は。
私は今も、「普通」に不感のまま。 私のすることは、昔と変わらずとんちんかん、「普通」を外れてしまう。…ご免…それに、これからも。…申しわけありませんが、私には「普通」は無理、もうこのままで…
まっちゃんが糞をドライヤーで吹き過ぎている。また糞が散ってしまう。
「まっちゃん、そのくらいにしとこ。糞、飛ばすと、掃除機が面倒やん」
「うん」
私に出来るようなったのは、その程度のフォロー。
「普通」は身につけられなくても、その結果を繕うための経験は、いくらか積めた気がする……
エサの時間や、とまっちゃんが小箱を手に取る。
「まっちゃん、どんなん?」
蓋を開けた箱が差し出される。
小さな薄片で、淡い紅と黄の色。
それは指を離れて宙にあるうちはほとんど見えないのに、水面に触れて浮くや、透過光の紅や黄が瞭然となった。まっちゃんが水槽に覆いかぶさるように立っただけで一斉に水面を目指した小ざかなたちは、見上げる水面に不意に現れては広がる紅と黄の薄片を、その水面の拭き掃除を始めたみたいに瞬く間に食べてゆく。
隣の水槽の小ざかなたちは、いつでも水底の砂上に身を置いていて、今もエサを求めて一斉に浮上したりはせず、1、2匹が気が触れたみたいに身をよじって上昇して、エサの一片を捕えるや直ちに水底にまた懸命に身をよじって戻ってくる。水面に漂っている薄片は水を吸うと1枚また1枚と沈み始め、水中をスノードームさながらに舞い落ちてゆく。水底の小ざかなたちは、左右にわずかにひらめく薄片の数々がいよいよ近づいてきてはじめて活気づき、口でそれを捕らえだす。低学年の子供たちが校庭で空に手を差し伸べて、落ちてくる綿雪を待ち構え、最後に跳ねて捕まえていたのを、授業中の教室から見たことがあったけれど、それみたいだ。下校の道、まだ降りつづいていた雪を、傘をささずに身に受けて歩いた。手袋の毛糸の上に浮くようにとまった綿雪は、束の間そのままであったのが、ふと、やさしい崩壊を起こして微細な水滴に収斂していった……
「雪のさき」と名付けた展覧会で、私は奥信越で形をなしたスチール写真の二つのシリーズに合わせて、真夜中の降雪のさまを映した動画も展示した。暗闇を背景に、粉雪がゆっくりとした雨のようにただ落ちるさまもあれば、縦横無碍に乱れて渦巻くさまもあった。津南の1月の凍える夜、100時間を超えた撮影を、7時間ほどにまとめたその作品で、私は、「今」というものを表現しようとした。
一夜をとおして雪が同じ調子で降りつづくことはなく、雪の闇夜の中を小鳥が啼きながら飛んでゆくような思いがけない事件も起きる。そして降雪を眼前にした私の心にも、記憶の欠片や、ふとした思い、様々なものが去来した。そうして迎える朝に、撮影の当初は、長い長い映画を見終わったような気分に私はなった。やがて私は、変転する事象に物語(変化や事件)を見なくなり、また、心の動きも顧慮しなくなり、目の前の事象、ただそれだけを見はじめた。雪の降りかたが変わったと思うには過去の記憶を必要とする。心に湧いてくる想念に関心を転じれば、外界を捉えることは疎かになる。降る雪の「今」を見つめるほどに、変化を識る記憶は成立しなくなり、心の内も消失し、「私」という自意識さえも希薄になって、そうして心も体も雪の「今」の時の流れに同化して浮遊するようになった。降る雪の見せる、過去も未来もない「今」に刻まれ浮遊する「時」、それが純粋な「時」の姿と私は思う。
水槽の揺らめき揺らめく水面、それをただ独りで見つめるならば、純粋な「時」に浮遊することができるだろう。川の流れを見つめても、焚き火の焔を見つめてもまた。 なぜか、いくつかの事象は、純粋な「今」の経験へのゲートとなりやすい。ただただ水流を見つめること、ただただ火焔を見つめること。 その果てに開示される、「今」。
私の自己放棄は、水の揺らめきや流れ、焔のたゆたいを見て、見て、見ること。「今」の時の流れに同化するとき、私は「私」から最も遠のいている。
カメラのファインダーに世界を捉え、シャッターを切るその瞬間、そのときも私は「私」から最も遠のく。
「私」から最も遠のいて、対象を捉えた写真が、それまで、私の中にありながら閑却されていたものに気づかせてくれる…この不思議な背理。
揺らめき、揺らめく水面、ただそれだけの今……
奥信越が豪雪地となったのは、対馬海流の流れが変じて日本海を北上するようになった8000年前、それまで乾燥した寒冷地であったところに、暖流のもたらす蒸気が雲となり、高山にぶつかって多量の雪を降らすようになったからと言われている。8000年前のある日、最初の綿雪のひとひらが地面に触れた瞬間から、人ではなく雪が境を創り出した「この地」が始まったのだ。
半年前、真冬の厳寒期、私は北海道を訪ねて最北の稚内を拠点にひと月を過ごした。対馬海流が辿り着く果ての「海」が見たくて。
そこは、新潟で見た日本海と、やはり気配が共通するように感じられた。曇天のもと、小高い場所から見渡す海は、沈鬱で厳しい表情の灰色の波を次々と陸へと寄せていた。けして大波ではなかったけれど、無数の波はどこか狂おしい激しさを秘めていた。潮騒は耳を圧するようなのに、怒りに押し黙っているような沈黙の印象があった。陸に近づいて伸び上がった波の頭は白く迸り、波が崩れるや、その丸い背中に、泡が長い白髪のように広がっていった。海の色は沖に向かうにつれて、まず濃い灰色の帯に、次いで鈍い緑色の帯に、そしてやはり鈍い青色の広がりとなり、膨大な距離を折りたたんで水平線に迫っていた。その色の境の曲線は緩やかでも明らかだった。
私が見ていない時も、誰も見ていない時も、海は揺らめき、波を陸へ陸へと寄せている。6月の、たった今も……
「な、まっちゃん、水槽の水面見上げてたら、なんか海の中に潜ってるみたいで、息が苦しくなってくるなぁ」
「そうやなぁ」と、優しいまっちゃんは合わせてくれた。「このあいだ、水族館に行ったんやけど」と、それは水生動物好きのまっちゃんには至福の時間の思い出のはずなのに、声が浮き立っていない。「そのあと、白魚の踊り食いを食べてん」
話の筋が見えてきた。大切に飼育され、生きているさかなを見た後、小ざかなとはいえ、生きているさかなを食べてしまった、しかも生きているそのまま。
誰もが、一度はぶつかる問題、それとも矛盾。私は子供の頃早々と「そういうもんや」と片付けてしまったけれど、私の友人には、大人となってから野良犬の保護活動のボランティアを始めたことをきっかけに、肉食ができなくなって、それが嵩じてビーガンとなった者もいた。
何を食物にするか否かの線引き。有毒・無毒が決める線引きとは異なるそれ。食べ物を粗末にしてはいけないと散々言われたけれど、ひとたび屑かごに捨てられたものはゴミだからけして食べるなとも言われ、子供の私は同じものがいったいどこで真逆のものに変じるのやろと思った。見えない線がこちらとあちらを生み出し、見えない線をこちらから通過してあちらへ入った瞬間、意味も価値も、いともたやすく転移し、正反対の意味・価値となるさえ珍しくない、同じものなのに。神命に従い、牛は食べるが、豚は食べない者もいる。戒律によって菜食の者もいる。牛を食べるのは残酷ではないが、鯨を食べるのは残酷だ、と声高に糾弾する人もいて、それは明らかに人が引いた線だ。
動物であれ植物であれ、それを食することは、その命を奪うことであるのは確か。
それにしても、まっちゃんが私に白魚の話をしたのは、昨日、私が子供の頃にカエルを壁にぶつける遊びをしていたことを話したことが影響しているのだろうか? 「なんで、そんなかわいそうなことをしたん」とまっちゃんは私に言った。でも、翻って、自分だって、生きていた白魚を…と思ったのだろうか。〈遊ぶ〉と〈食する〉ははっきりと異なるとは教えてあげられるけれど。
「白魚、口の中で動いてたやろ」
「うん」
「美味しいよな、白魚」
「うん」
それでいいんとちゃう、とまでは言わないでおこう。人それぞれの答えでよい。
私はまっちゃんのお腹をくすぐる真似をする。こらっ、白魚を食べたお腹め!という感じで。
まっちゃんは触られていないのに逃れるようにして笑い声を立てた。
稚内から道東へ廻り込むと、海には流氷が見られるようになった。気温はマイナス20度を切り、朝目覚めれば、車の中でもマイナス10度、買いおきのペットボトルの水は氷になっていたし、バナナも薄茶色に変色して凍っていた。私自身の防寒は十全だったけれど、それでも夜を通じて体をこわばらせていたからなのか、肩にそんな痛みが残っていた。海辺の雪まじりの風は、もはや気体の流れではなくて、凶々しい力そのものだった。目出し帽にフードで臨んでも呼吸は奪われた。体はその場になぎ倒されないように踏ん張って立っているのがやっとだった。物事をまず視覚で捉える私なのに、それが出来ないとんでもない状況に、常に波立っている海水の凍りついてしまうことが不思議でもなんでないと実感された。流氷は砕けて海岸に打ち上げられ、大きなものは波に洗われて角を丸め、小さなものは波に揉まれて球となっていた。その流氷の球は、ガラスのように澄んだものもあれば、中に糸くずのような海藻を封じ込めたものもあって、しゃがみこんで見つめていると、その一顆一顆が「海」と感じられた。水平線をなす海原と着岸した流氷の球の間には、比較にならないスケールの違いがあるのに、どちらも「海」だった。細部と全体のさきに見えてくるものは等しいと私は写真を始めてから学んできた。今度はいったい何を見ることになるのだろう……
はぁい、というまっちゃんの突然の声に、私はびっくりした。
二間が細長く連なるあちらの座卓に友人が食事を並べていた。
「お昼、少し過ぎたわ」と友人は典雅な京なまりで言う。
子供は身軽、まっちゃんが駆けてゆく。
私はと言うと、昼寝から不意に目覚めたばかりのよう焦点の定まらないここちで、まっちゃんと居て水槽の水面を見上げるように眺めて心をさまよわせていた、どこか不思議な時間に、まだ尻尾を掴まれているかのようだった。
急に食欲が来て、すっかりいつもの自分に還ったのを感じる。友人に食事を作らせて何も悪びれず、『お腹すいた』ともそもそ這って近づき、どうもどうもと骨董の猫足の座卓に着く私……
友人は、そんな私を咎めることなく、
「菜央ちゃんは、まっちゃんとほんまに仲良しやわぁ」と言った。
2023 秋
