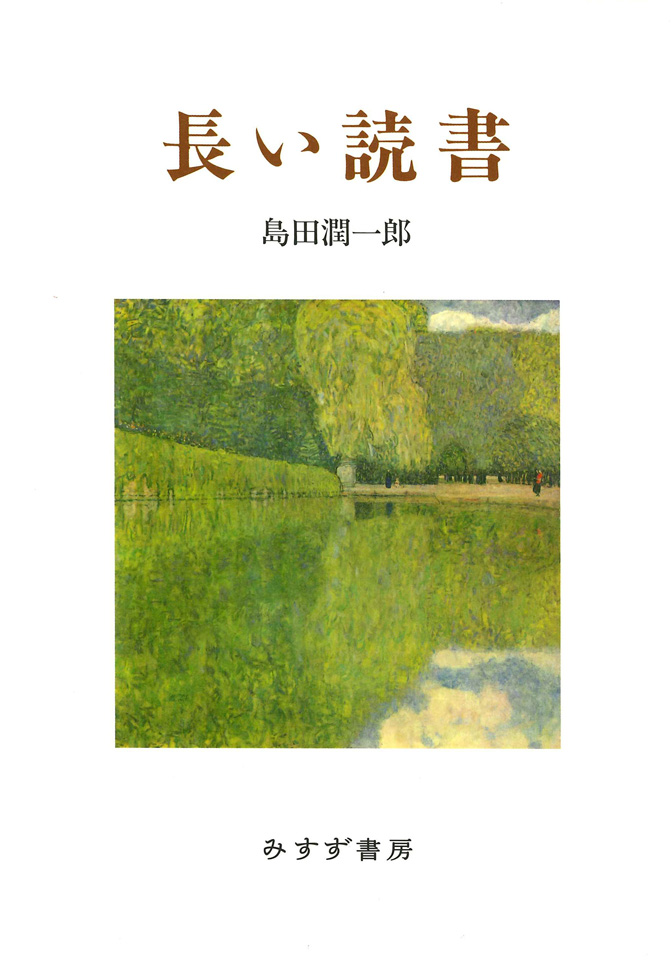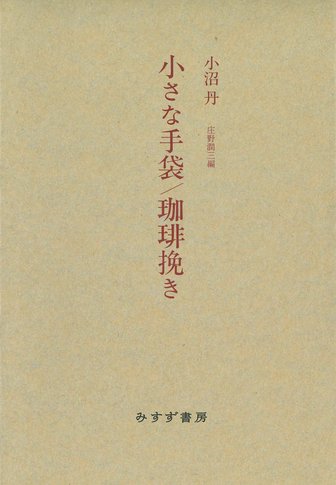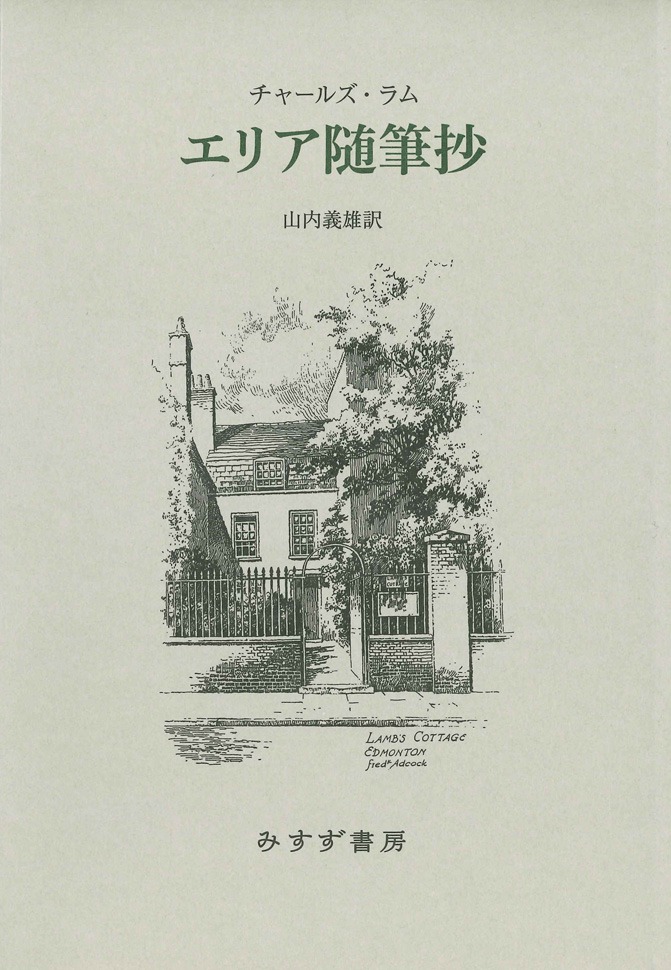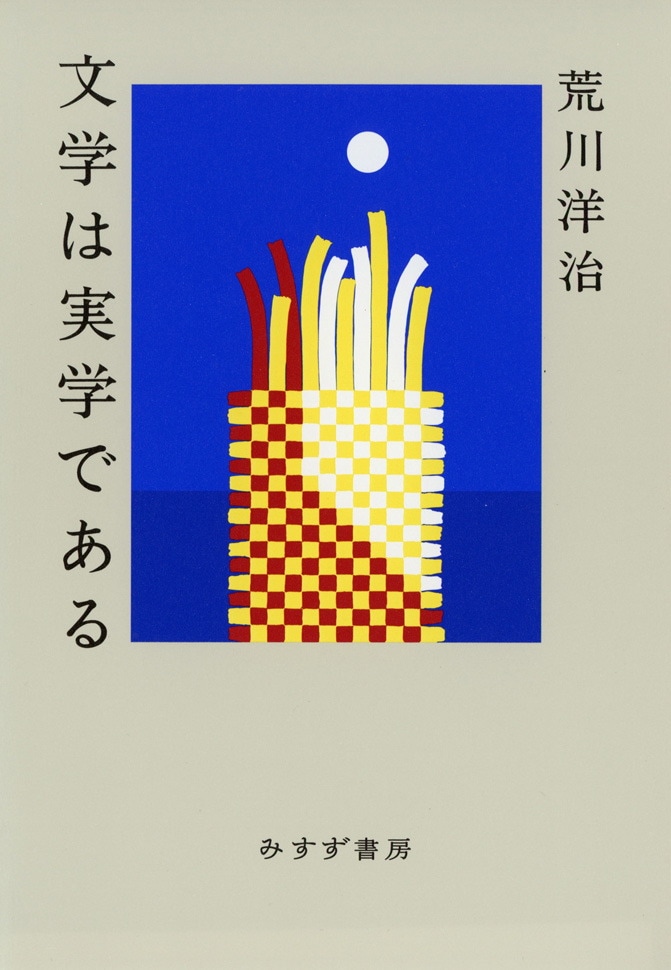2024年4月、島田潤一郎『長い読書』の刊行にあわせ、いくつかの書店で著者のトークイベントが行われました。当日ご都合のつかなかった方や、参加した日をふりかえりたいという方に向けて、この記事では、3つのイベントに参加した担当者が、会場の模様とトークの一部をお伝えします。
東京 吾妻橋・OUET(ウエ) トークイベント
『長い読書』と現在
2024年4月19日(金)
墨田区両国の書店、YATOが手掛ける2階建ての新スペースの杮落しイベントとなったこの日。浅草駅からスカイツリーに向かって徒歩で約8分、小さな工場や住宅街が並ぶ吾妻橋エリアに新店舗「ORAND/OUET」がありました。1階の飲食スペースを抜け、2階に上がると小さなライブハウスのような雰囲気のスペースに到着。週末の夜ということもあり、30席の丸椅子は、幅広い世代の方で満席でした。

この日は店主の佐々木氏と、著者島田氏との対談。著者の一冊目の本『あしたから出版社』(単行本は晶文社刊、現在ちくま文庫)を、10年ほど前、佐々木氏が仕事を辞めた頃に読んだ話からはじまり、就職するのではなく自分で仕事をつくって生きること、そこに本がどのように影響したのか、という話題を中心に、約1時間半にわたり言葉が交わされました。印象に残った部分は以下のようなお話。
島田「今日話そうと思ったのは、少し抽象的な話になるかもしれないですけど。…普通、本を読むときっていうのは、私(わたくし)は変わらずに、本から何か知見を得る。でもぼくの場合は違って、主体が変わらざるを得ないような強烈な読書体験がやっぱり、好きなんです。それを読むとその後とは「私」がまるで変わる。それがいいのか悪いのかはわからないんですが。…それは、どういう体験によっておこるかというと「私はこれをわかった。学んだ」ことによって変わるわけではなくて「わからないな」とずっと思って読んでいくうちに、何かが変わらざるを得ないというか。…物事の見え方が変わるし、理解できる範囲が変わりますよね。そういう力、強烈に力をもっているのがすぐれた本で、それが文学、哲学の強さだという気がします。」
このほか、島田氏からの「具体的に、これはよかったなあという本はありますか」という質問に対し、佐々木氏がバーナード・マラマッドの短篇小説「最初の7年間」を挙げ「ぼくも何かを7年くらい耐えてみようと思った」とご自身の体験を重ねて語った話が印象的でした。店主が影響を受けた「長い読書」の例ではほかに、エリー・フォールの長大な「美術史」シリーズ(全7巻、国書刊行会刊)などへの言及も。
書店「YATO」は地下鉄両国駅から歩いて5分ほど、こちらには店主の佐々木氏が豊かな読書体験からセレクトした人文・芸術書を中心とした本がぎっしり並んでいます。店内でサーブされるコーヒーもすごくおいしいお店です。
神戸・1003(センサン) トークイベント
2024年4月27日(土)
ゴールデンウィークの初日にあたる土曜の夜、神戸元町・栄町のビル5階に2020年移転オープンした書店「1003」(開業は2015年)のイベントは、著者がハンズフリーのマイクをかけて語るプレゼンテーションスタイルの講演でした。本書『長い読書』ができるまでのいきさつと、本にこめた思い、著者にとって本とはどういうものかという主題を語る濃密な一時間半。こちらも熱心に聴き入るお客様の姿が印象的でした。

「本とはどういうものか」について語られた箇所について、少しここでご紹介します。
島田「本とはどういうものか。それは図鑑であろう、というのが、ぼくの見立てです。本当はちがうけれど、そこに「全てがある」と思うから、読者はくつろぐことができる。限られたページの中に全てがあるというフィクション、虚構を、著者と編集者、そして読者とで作り出すことが重要なんです。たとえば「神戸のおいしい中華料理店」という本をつくるとして、1000ページの本、500ページの本、300ページの本、160ページの本があったら、みなさんはどれがいい本だと思いますか? 挙手してみてください。はい。ちなみにぼくは300ページの本が読みたいです。160ページだと、遊びが少なすぎる気がするので。インターネットの空間は1000ページの本と似ていると感じます。読者にとって1000ページの本が一番いいとは、いえませんよね」
この「限定された情報によって一冊の本という全体が立ち上がる」という話は、本に関わる仕事をする一人としてとても刺激的なものでした。個人的にも、インターネットをずっと見ているときに感じる息苦しさのようなものから解放する媒体として、紙の本を作り、売り続けることの意義を学んだ講演でした。
ちなみに、本書『長い読書』のなかには、本や書物の「全体」という概念について島田氏が記したエッセイ「アルバイトの秋くん」が収録されています。本書を読んでから上の記述を読むと、また違った発見があるのではないでしょうか。
1003は新刊だけでなく古書・リトルプレスも扱っているお店。社会学関連の人文書や海外文学なども充実した硬派な品揃え。すぐ近くには中華街。散策が楽しい街にあるお店です。
奈良・ほんの入り口 トークイベント
長い入り口
2024年4月28日(日)
この日のイベントは日曜朝10時のスタート。駅前の車道を鹿が優雅に歩く近鉄奈良駅から歩いて約15分「船橋商店街」の中ほどにある「ほんの入り口」は、2023年の春にオープンした新刊書店です。明るい店内には、店主いわく「本をむっちゃ読む人ではない人たち」を想定した、ふだん本を読みなれない人へ「入り口になる本」が、幅広いジャンルからセレクトされています。読書会やワークショップを数多く開催しているのもこちらのお店の特徴です。

当日は快晴、20席ほど丸椅子が準備された店内は、幅広い年齢層のお客様で埋まっていました。演劇経験があり、よく通る声の店主の服部さんが司会となり、著者と対談する形でトークは軽快に進みます。この日の中心的な話題は「書店と読書」。「同時代の風がある書店が好き」という島田氏が、関西の書店を営業で回ったときに、何人もの書店員に励まされてきた体験談から始まり、トーク中盤では読書の魅力が語られました。「自分の経験を総動員して人の話を聞くことが読書」であり、その「能動的な体験が本」であり、ほかのメディアと違うという話、書き手のことばによって「忘れていた自分の記憶に光が入り」心の土が耕されるという読書論はまさに『長い読書』の内容を補完するものでした。このほか「精神的な不安に陥らずにどうやって生きるか」が自身の中心的なテーマのひとつであること、「本がいいものだ、と証明したくて本を書いている」と著者の執筆動機が語られるシリアスな場面など、穏やかでありながら、熱のこもった1時間半でした。
おわりに
「ほんの入り口」のトークで島田氏は「新刊が、書店の既刊を輝かせる」と語っていました。
新しい本、話題を集める本だけでなく、古い本にまで手を伸ばすことはいつも精神的な体力のいることですが、様々な読書体験が描かれる本書『長い読書』に収録された著者の声を、読書の伴走者としながら、長い本、難しい本に挑戦してみることは、自分を変えるきっかけになるかもしれない。今回のイベントに参加して、改めてそんなことを感じました。『長い読書』には小説だけでなく、精神医学の本、育児書、雑誌やコミックも登場します。お読みになった方は、本書で言及された出版物とともに、著者が手がける夏葉社の本、著者が敬愛する作家・庄野潤三の関連書や、本書が生まれるきっかけの一つになった荒川洋治のエッセイも、ぜひお近くの書店に足を運んで、手にとっていただけると嬉しいです。(編集担当・河波雄大)
『長い読書』著者・島田潤一郎氏が代表をつとめる「ひとり出版社」夏葉社のウェブサイト
https://natsuhasha.com/