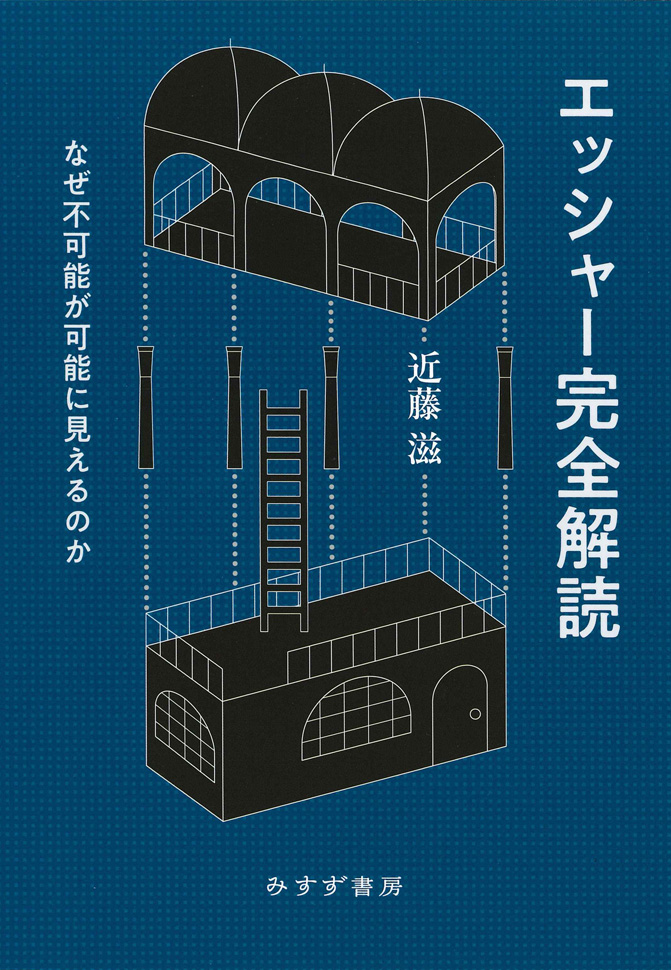近藤滋
まずは、ここまで読んでくれた読者のみなさんに心よりお礼を申し上げたい。本書は内容の性質上、ややこしい幾何学的な説明が多くなっている。そのため、読み解くのに苦労する部分があったかと思う。もしそれに見合うだけの発見の楽しさもあったのであれば、とても嬉しい。
本書を読み始めた時、おそらく読者の多くは「これほど有名なだまし絵に、本当にまだ未発見のトリックが残っているのか?」と疑っていたのではないだろうか。実は、それは私も同じだった。だから最初に「《物見の塔》のテラスと囚人のトリック」を見つけた時は本当に驚き、得意になったことを覚えている。しかも、発見はそれだけにとどまらなかった。どの作品でも発見が続いたことで、自分が作品をどれほど浅くしか理解していなかったかを思い知らされることになった。
振り返ってみれば、本書で見つけたトリックの数々はそれほど発見しにくいものではないように思う。たとえば、《物見の塔》の屋根や牢の囚人の存在はあまりに不自然である。疑いを持って鑑賞すれば発見できたのではないかと思う。《描く手》のあの影なども、怪しいものを意図して探せば容易に見つかるだろう。ではなぜ、これまで知られていなかったのだろう。
この本を書いている間、ずっとこのもう一つの謎が気にかかっていた。だから、同じトリックを指摘した人が過去にいたかどうかをかなり真剣に調べてみたのだが、見つからなかった。ということは、そのような文献は存在しないか、あるいは少なくとも広まっていないということになる。不思議でたまらない。エッシャーのだまし絵は世界中のたくさんの人々に何十年も愛されており、展覧会も頻繁に開かれている。それだけの人が見れば、誰かが気付きそうなものだ。それに、いったんこんな面白いネタに気付いたら、誰かに言わずにいられるはずがないではないか。
あまりに不思議なので、この「あとがき」の場を借りて、この「もう一つの謎」の答えを考えてみたい。
まず一つ目の可能性は、「本当にこれまで誰も気が付かなかった」ということである。本書でも述べたように、エッシャーはこれらのだまし絵については「作者」というより「手品師」として振る舞っている。トリックの存在に気付かれないように、錯視図形だけを「これがトリックです」と強調し、鑑賞者を納得させ、それ以上の詮索をさせないようにしている。鑑賞者が素直な人たちだけなら、それに引っかかるのも仕方のないことだろう。
だが、エッシャー愛好者の数は莫大である。なかには素直でない鑑賞者もたくさんいるはずだ。あるいは、だまし絵を参考にして自分の作品を創作した人もいたのではないか。自分で実際に作ろうとしてみれば、遠近法の問題は意識せざるをえない。だから、気が付いた人が皆無であるとはとても思えない。となるとその誰かは、せっかくこんな面白いトリックに気付いたにもかかわらず、なぜかそれを発信しなかったことになる。
その理由として最初に思いついた仮説は、「何らかの機関がそのような不届き者の声を消してしまうために知られていない」であった。まあ、落ち着いて考えればさすがに無理がある。もちろんそんな妨害は一切なく、その証拠に、今あなたはこの本を読んでいる。そんな謎の機関は存在しないのだ。ということは、やはり発見者が「自発的に公表を控えた」のだろうか。
実は本書を執筆している間、ある思いが心の底にわだかまっていた。それを一言で表現すれば、「手品のネタばらしはご法度なのではないか?」ということになる。せっかくエッシャーが見事な手品を披露し、それを世界中が賞賛してきたのに、そこにのこのこ出てきて「この手品のトリックはですね……」とネタばらしをするのは、いかにも無粋ではないか。トリックがあえて隠されたままになっているのなら、種明かしなどやるべきではない。トリックに気付いた人のほとんどがこのように思ったために、秘密が守られてきた可能性はあるかもしれない。そうなると、本書を出版しようとしている私は「エッシャーファンの中でもっとも無粋な人間」ということになってしまう。まあ、確かに無粋であることは否定しないが、ちょっと言い訳もさせてほしい。
本書を書き終えた今、私としてはこのテーマに取り組んで本当によかったと思っている。この素晴らしいトリックを、ぜひ他のエッシャーファンにも知ってほしいと思う。なぜなら、少なくとも私は、これらのトリックを知った後にエッシャー作品に対する興味がなくなるどころか、以前よりももっと好きになったからだ。
遠近法の感覚をハックする素晴らしいアイディア、計算しつくされた構図、人物の配置。しかも、画面中にトリックがあることに気付かせない、鑑賞者の注意の誘導。それらを発見した驚きと興奮は、だまし絵を単に「錯視図形を利用した作品」としか認識していない状態では決して得られないものだ。
また、それらの技法を編み出していく過程におけるエッシャーの工夫や思考に、多少なりとも触れることができたように思えたことも、大きな喜びだった。大げさな言い方をすれば、誰も入ることのできなかったエッシャーの庭園を訪れることができたと感じたのだ。
エッシャーは、自身が持つすべての技術、思考、熱意を創作に投じており、作品はそれらが具現化したものである。だから、エッシャーが作品の核心について詳しく語らなかったとしても、作品について深く考察することでエッシャーの心に触れることができる。もし読者がこの本をきっかけに本棚の作品集を引っ張り出し、これまでとは違う発想であれこれ考えながら作品を眺めるようになれば、その先にはエッシャーの庭園があることだろう。
急に庭園の訪問者が増えたら、エッシャーはどんな顔をするだろう。きっと困ったような不機嫌な顔をしながら、でも内心は、真の理解者が増えたことを喜ぶのではないだろうか。
2024年10月
copyright © KONDO Shigeru
(著作権者のご同意を得て転載しています。なお
読みやすいよう行のあきなどを加えています)