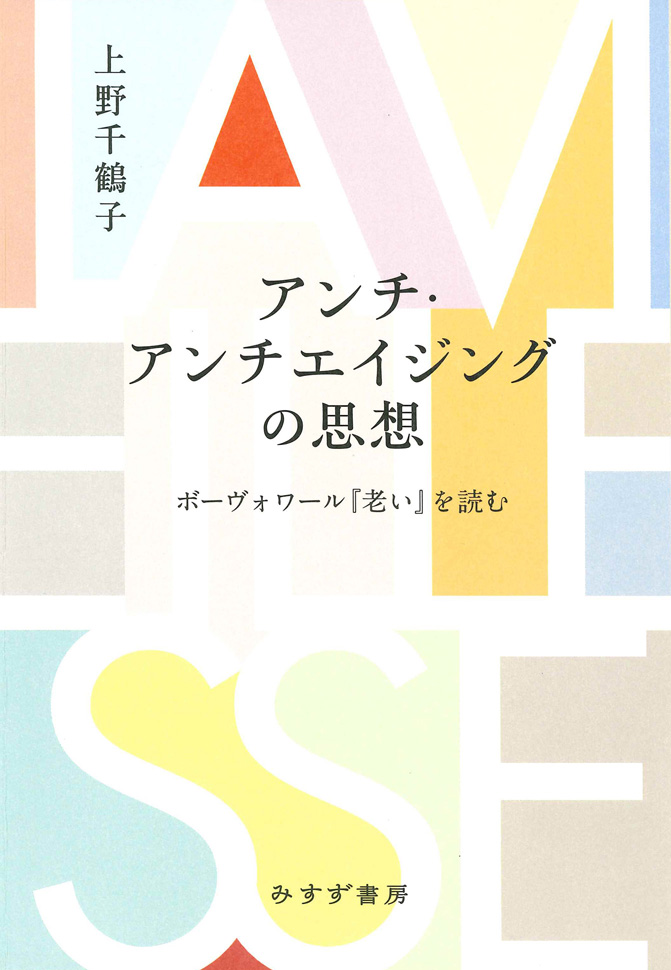老い衰え、自立を失った人が尊厳をもって生きられる社会は、どうしたらつくれるのか? 社会学者・上野千鶴子がフランスの思想家ボーヴォワールの名著『老い』を下敷きに、現代日本の老いの現場への取材と考察を加えた、老年学の集大成といえる新刊『アンチ・アンチエイジングの思想』。4月16日の本書刊行に先駆け、第1章「老いは文明のスキャンダルである」の一部を特別公開いたします。
はじめに
「老いは文明のスキャンダルである」
いつの頃からか、この文章がわたしのなかに鳴り響いていた。シモーヌ・ド・ボーヴォワール、62歳の時に書いた『老い』[Beauvoir 1970=1972]のなかの一文である。
ボーヴォワール(1908‒1986)は『第二の性』[Beauvoir 1949=1997]で、世界中に知られるようになった。その21年後に『老い』を書いたが、こちらはあまり読まれなかったようだ。わたしは序文にある冒頭の一文に頭をガンとぶんなぐられるような思いをしたが、細かい活字のつまった全2巻上下2段組み計704ページの分量に恐れをなして、いつか読もうと思いながら、積年の「宿題」を果たせずにいた。
どんな書物にも出会い時というものがある。全世界の時間が止まったように思えたコロナ禍の自粛生活のなかで、この本に手が伸びた。そして、そうだったのだ、わたしが読みたかったのはこの本だったのだ、と感じた。
執筆時のボーヴォワール62歳。わたしはいま、73歳である。当時のフランスで女が老いることは、今のわたしたちが想像するよりも苛酷な経験だったはずだ。女性に年齢を聞くのは失礼、という「礼儀」がまかりとおっていた時代のことだ。婚姻上のステイタスが女性の敬称を分かつフランスでは、ジャン= ポール・サルトルと正式の結婚をしていないボーヴォワールは、歳をとっても「マドモワゼル」と慇懃無礼に呼びかけられもした。年齢と婚姻とが女を相応の「指定席」にふりわけた時代は、フランスでも近過去である。
老いることはなぜこんなにも忌避されるのか? わけても女の老いは、なぜ「加齢恐怖症」と言われるまでに、怖れられるのか? その恐怖はどこから来るのか? 誰のせいなのか?
それらの問いに鳴り響いた回答が、ボーヴォワールのこの一文だった。
「老いは文明のスキャンダルである」
このなかに答えがあるという直観に突き動かされて、わたしは、この本を時の金庫のなかに入れておいた。だがそれをとりだしてもよい季節が来た。わたし自身が老いたからだ。
ボーヴォワールが本書を書いた年齢に見合う年齢になってみて、彼女が何を見、何を考えたかを知りたくなった。準備は整ったのだ。遅かったかもしれない。だが遅すぎてはいないだろう。
「廃品」になる人間
「老いは文明のスキャンダルである」ということばを、わたしはどこに見出したのだったか。始めるにあたって、訳書を当たってみた。だが、それに正確に該当する文章は原文にはなかった。代わって見つかったのは「序」の中のこの一文である。
「人間がその最後の15年ないし20年のあいだ、もはや一個の廃品でしかないという事実は、われわれの文明の挫折をはっきりと示している。[…]この人間を毀損する体制[…]を告発する者は、この言語道断な事実を白日の下に示すべきであろう。」[上12]
訳者の朝吹三吉は「スキャンダル」を「言語道断な事実」と訳した。他のところで、ボーヴォワールは「社会にとって、老いはいわば一つの恥部であり、それについて語ることは不謹慎なのである」とも言う。訳すなら、「スキャンダル」の原語に近く、「醜聞」とか「破廉恥」としてもよかっただろう。
その「スキャンダル」とは以下のようなものだ。
「老いた人たちに対して、この社会はたんに有罪であるだけでなく、犯罪的でさえあるのだ。それは発展と豊富という神話の背後にかくれて、老人をまるで非人のように扱う。」[上6]
社会が共謀して隠しておきたい醜聞を暴く者は、忌み嫌われる。
「しかし、それだからこそ、私はこの書物を書くのである、共謀の沈黙を破るために。」[上6]
「人間たちがその生涯の最後の時期において人間でありつづけるように要求することは、徹底的な変革を意味するであろう。そのような結果を獲得するためには、体制を無傷のままに放置して、たんに限定された改良によるだけでは不可能である」[上13]と、ボーヴォワールは宣言する。
その前段で彼女は、階級差別 classism と性差別 sexism との闘いに言及している。彼女がここで挑戦したのは、今では年齢差別 ageism と呼ばれているものだ。それは個人の心構えやアンチエイジングの努力、気の持ちようで対処できるようなものではない。それどころか、老いに抗うアンチエイジングの思想こそ、エイジズムそのものにほかならない。この闘いは価値観や体制、生き方や構造、感情や身体、そしてそれをかたちづくる歴史と社会……すなわち文明総体を相手にした闘いだからである。(中略)
老いは他者の経験
老いはなぜ忌避されるのか?
ボーヴォワールは本書で老いのネガティブなイメージをこれでもか、と書く。
第5章の冒頭でゲーテの言葉を引いて「老齢はわれわれを不意に捉える」[下333]という。
ボーヴォワール自身の経験を引こう。
「早くも40歳のとき、鏡の前に立ちつくして、「わたしは40歳なのだ」と自分に向かってつぶやいたとき、私はとうてい信じられなかった。」[下333]
50歳のときには「あるアメリカ人女子学生からその友人の言葉を告げられて、愕然とした。「じゃ、ボーヴォワールって、もう老女なのね!」」[下339]
彼女はこのことばに傷ついた。なぜなら「老女という言葉は、長い伝統によって悪い意味を負わされている」からであり、「侮辱のようにひびく」[下339]からである。だから「文学作品のなかでも、実人生においても、自分の老いを快く思う女性には私は一人も出会ったことがない」[下350]。ボーヴォワールはもちろん、自分自身も例外にしていない。
『第二の性』は「女として」書かれた。『老い』は「老女として」書かれている。この当事者性も、彼女の魅力である。
「われわれはみな次のような経験を持っている、――誰かに出会い、ほとんど見分けがつかないのだが、相手も面くらった様子でこちらを見ている。われわれは心の中で思う、彼はなんて変わったんだろう! 私もなんて変わったんだろう、と思われているに違いない! と。」[下340]
老いとは他者になる経験である。
「老いとは、客観的に決定されるところの私の対他存在〔他者から見ての、また他者に対するかぎりにおいての、私という存在〕と、それをとおして私が自分自身にもつ意識とのあいだの弁証法的関係なのである。私のなかで年取っているのは他者、すなわち、私が他者たちにとってそうであるところのもの、であり、しかもこの他者は、私なのだ。」[下334]
わたしは何人かの友人たちに、「人生で最初に老いを意識した出来事」を聞いてまわったことがある。一番多いのは電車のなかでシルバーシートを譲られた経験である。「そうか、オレは(ワタシは)他人からはそんなに老けて見えるのか」と。それに対する反応は、せっかく親切心から座席を譲った若者を気まずくさせるほどの困惑、ためらい、辞退、拒絶などである。相手のせいではないのに、怒りを示すひとさえいる。こんな反応に出会ったら、座席を譲ることにひるむ若者がいても、不思議はないだろう。
あるいは買いものや街の中で、「おじいさん(おばあさん)」と呼びかけられた経験。ショウウインドウに映った白髪の老女が自分だと知って驚いた経験。同窓会で同じ年齢の男女の老け方にショックを受け、自分もまた彼らから見れば同じようなものなのだと認めないわけにいかない経験。どの経験も不快な記憶として残っているはずだ。
老いるとは「他者になる」経験だ、とボーヴォワールは書く。なぜなら社会が、そして自分自身が、老人を「他者化」してきたからだ。『第二の性』は他者としての女性を論じたものだ。なぜならタイトルどおり、女性は「第一の性」としての男性にとっての「他者」だからだ。男が女になる可能性を考える必要がないように、彼らは安心して女を「他者化」していられる。だが、老いはそうではない。ほかならぬ自分が「他者化」してきた「老人」に、自分自身が変化するからだ。ボーヴォワールがいうとおり、「この他者は、私なのだ」。
「われわれの未来の姿として、老人たちがわれわれに示すイメージを見ても、われわれは信じられないのである、われわれの内部のある声が、それはわれわれには起こらないだろう、と不条理にもささやく、すなわち、それが起こるときにはもはやわれわれではない、ということだ。それがわれわれに襲いかかるまでは、老いは他者にしかかかわりのないことなのである。それだから、われわれが老人のなかにわれわれの同類を見ないようにすることに社会が成功するのも理解できる」[上10]。
他者のなかに自分自身を認めること、あるいは自分が他者であることは、もちろん痛苦に満ちた経験である。「しかし」、と彼女は言う。
「ごまかすのはやめよう。われわれの人生の意味は、われわれを待ち受けている未来のなかで決定されるのだ。われわれがいかなる者となるかを知らないならば、われわれは自分が何者であるかを知らないのだ。この年老いた男、あの年老いた女、彼らのなかにわれわれを認めよう。もしわれわれの人間としての境涯をその全体において引き受けることを欲するならば、そうしなくてはならない。」」[上11]
超高齢社会は恵みだ、とわたしがいうのはその意味である。この死ぬに死ねない社会で、誰もが「老い」という経験から逃れることができない。どんな強者もいずれは老いて弱者になる。わたしたちはかつての世界の権力者、マーガレット・サッチャーやロナルド・レーガンが認知症になった姿を見てきた。老いには誰も抗えない。
そしてその老いの課題は、個人の努力でどうにかなる性質のものではないことを、ボーヴォワールははっきり宣言する。老いが惨めなのではない、老いを惨めにしているのは文明の方なのだ。
「老齢者たちの不幸は、われわれがそのなかで生きている搾取の体制を白日のもとにさらす。」」[上11]
だからこそ「老いは文明のスキャンダルである」と、原文にない一文を刷り込まれていたわたしは、ボーヴォワールの問いの核心をつかんでいたともいえる。そのとき、わたしは30代だった。
――つづきは書籍をごらんください――
(著者の許諾を得て転載しています)