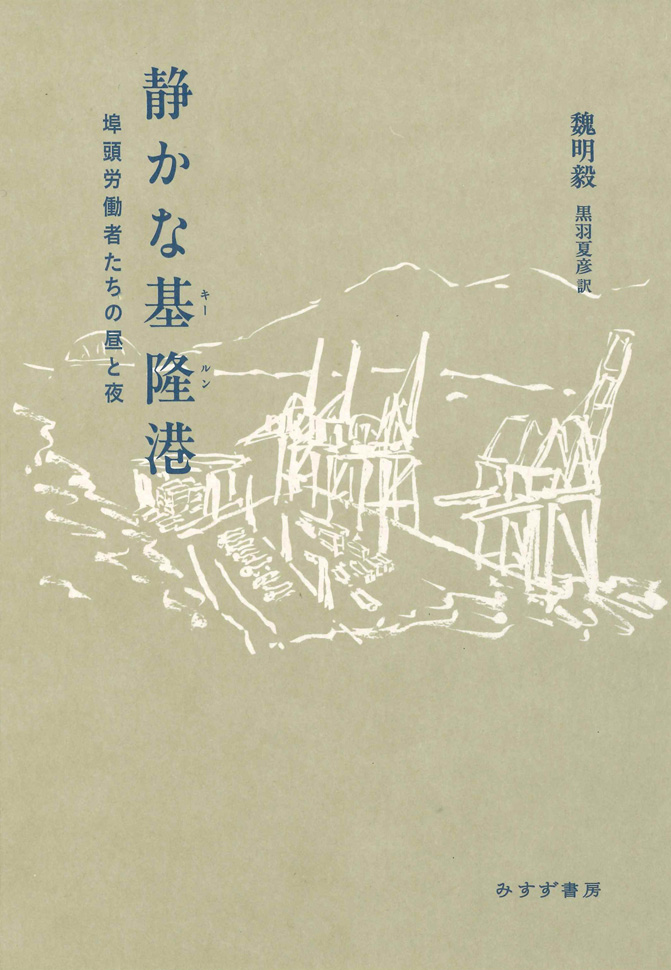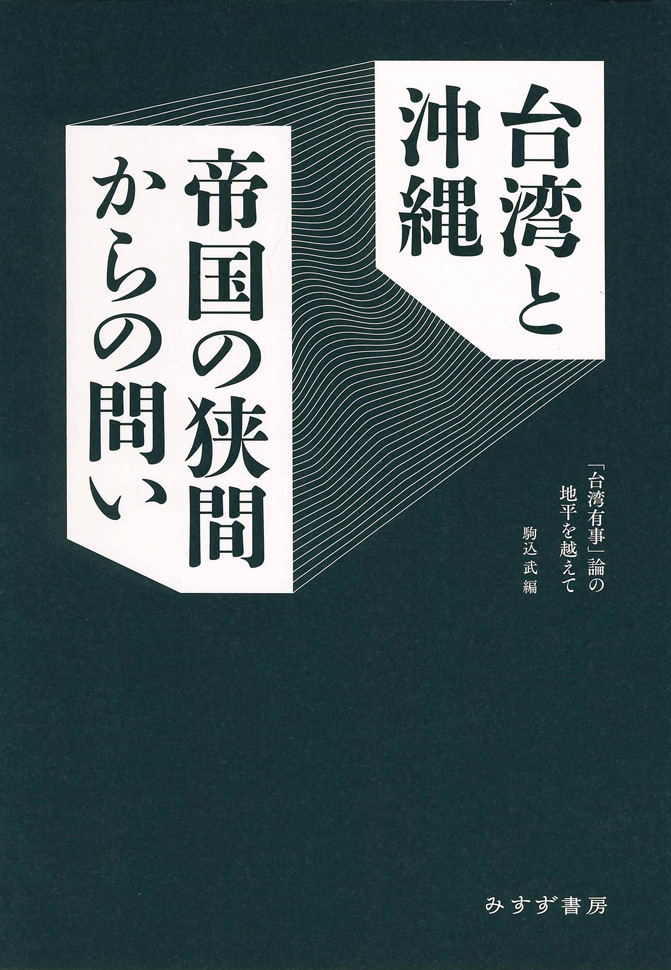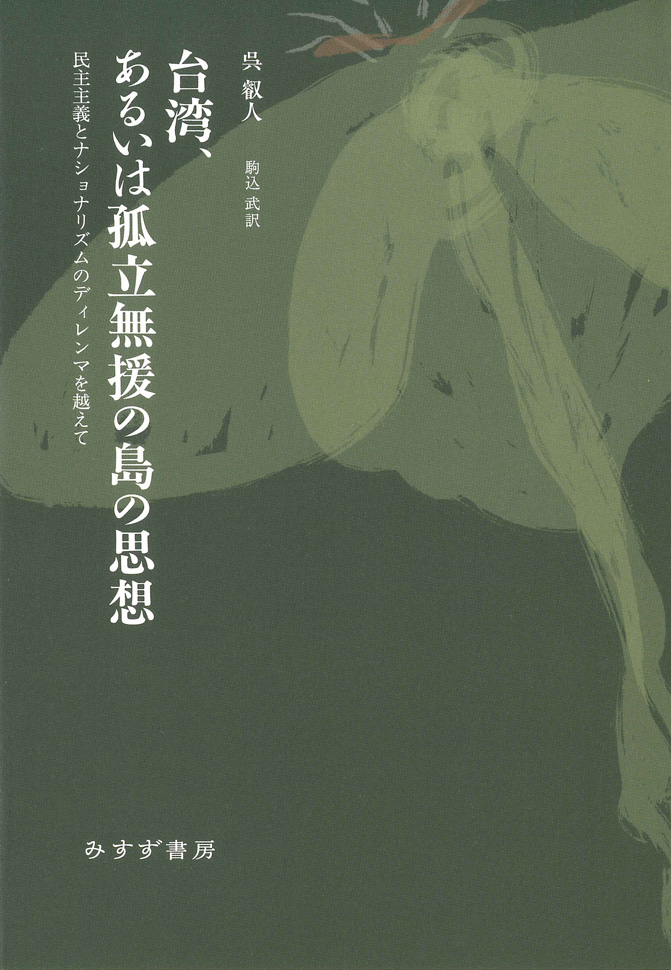本書では、戦後における基隆の港湾労働者の境遇について、次の三つの段階に分けて叙述している。第一に1960年代までの「苦力の時代」、第二に1970年代から90年代にかけての「工人頭家」の時代、第三に90年代末以降の「底辺の時代」である。
第一段階の「苦力の時代」は、読んで字のごとく、労働者が「つらい肉体労働」を担った時代である。ところが、台湾が国際海運業の変化に巻き込まれたことで、港湾労働そのものが大きく変化していくこととなる。
従来、貨物の海上輸送では、トラックや列車で運んだ荷物を港に集め、それらを一つひとつ船に積み替える必要があった。これを劇的に変化させたのが、コンテナ輸送の導入である。アメリカでトラック事業を営んでいたマルコム・マクリーンが、トラックのシャーシと荷台部分とを分離し、荷台部分を大きな箱(コンテナ)にして、箱ごと船に積み込む方法を考案した。それによって陸運と海運を結びつけるシステムを構築し、事業化したところにマクリーンの独創があった(9)。
貨物の積み替えにはクレーンが用いられるようになった。こうした荷役作業の機械化によって、手作業で荷物を積み卸しするコストは大幅に省かれていった。コンテナの利用は、運送時間を短縮できることに加えて、貨物の損傷事故や抜き荷の防止にも役立ち、損害保険料も節減できる。こうした一連の荷役の合理化は、裏を返せば、埠頭で重い荷物を担ぐ男たちの多くがいずれ必要でなくなることを意味していた(実際、コンテナ化がいち早く進んだアメリカでは、労働争議の末に、輸送会社による一定の生活保障と引き換えに、仲仕たちは港湾から徐々に姿を消していった)。
マクリーンは1956年4月、世界最初のコンテナ船「Ideal-X号」をニュージャージー州のニューアーク港からヒューストンまで運行させた。その後も紆余曲折を経ながら事業を拡大させ、1960年にはみずからの会社をシーランド社と改称する。1966年には、USライン社、シーランド社などが相次いで大西洋においてコンテナ船の定期航路を開始した。
輸送のコンテナ化の特徴は規格化・標準化にある。巨額の初期投資さえクリアできれば新規参入は可能であるため、1970年代にかけてコンテナ船は急速に全世界へ普及した。当初はコンテナとほかの貨物を一緒に搭載する混載船が中心であったが、そのメリットを最大化するため、やがてコンテナ輸送に特化したフルコンテナ船が主流となっていく。さらに、一度の航海でより多くの貨物を運送できればコスト減につながるため、コンテナ船は大型化していった。
台湾にコンテナ船が現れたのは1967年5月のことで、最初は高雄港へ来航した(10)。世界的なコンテナ化の趨勢を嗅ぎ取った台湾政府は、政策的措置を講じ、基隆港でいち早くコンテナ埠頭の建設に着手した(1972年運用開始)。前述のとおり、コンテナ化のポイントは海運と陸運の連結にあったが、台湾でも1971年から中山高速公路の建設が始まり、基隆から高雄までを繫いで国土を縦断する陸運網の整備が進められた(1978年に全通)。こうしたなか、台湾の海運会社も次々とコンテナ化を進め、1984年には基隆港のコンテナ取扱量は世界第7位となった。
台湾海運業の発展は基隆の街に大きな繁栄をもたらし、1960年代末以降、港湾労働者の境遇も徐々に変化していった。こうしてもたらされたのが、第二段階の「工人頭家」の時代(1970-90年代)である。「工人頭家」とは、肉体労働者(「工人」)でありつつ、自身も人を雇って親方(「頭家」)のような立場になるという、二重の属性をもつ者を指す語である。1970年代に荷役作業の機械化が一般化すると、港湾労働者たちの仕事は目に見えて減り、暇をもてあますようになった。しかし、労働組合が機能していたために、彼らの収入が減ることはなかった。こうした状況のなかで、労働者の一部が副業に流れ、同僚に代理で仕事を頼む者が出はじめる。そのような者たちを「工人頭家」と呼んだのである。
基隆の港湾労働者の「仲間文化」は、この金余りの時代に築かれた。労働者たちは茶屋や飲食店に入り浸り、おのれの男としての甲斐性(「ガウ」であること)を誇示しつつ、人間関係のネットワークを形成していった。また、この時代には、荷役に従事する肉体労働者とは別のタイプの労働者も基隆の港に引き寄せられてきた。陸上でコンテナを輸送するトレーラーの運転手である。業務のうえでは彼らのあいだにはほとんど交流がなかったものの、埠頭の外では運転手たちもまた「仲間文化」のネットワークに加わり、その一翼を担うようになっていく。こうして基隆は、「夜空までもが煌々とするほどにぎわっていた」(本書127頁)と表現される、極盛の時代を迎えるのである。
しかし、そのような繁栄を見せた港湾産業も、1990年代に入ると陰りが見られるようになる。台湾内部の産業構造の変化によって貨物の引受量が減少したことに加え、経済規模を拡大させた中国をはじめとする東アジア各地の港に、ハブ港としての地位を奪われてしまったためである(11)。1996年時点で64.54%だった基隆港の港湾使用率は、2012年になると37.32%にまで落ち込んだ。こうした低迷に伴い、港湾関連産業に依存していた基隆全体の経済が必然的に衰退へ向かうこととなり、失業率が上昇して、台北市や新北市など近隣の大都市へ仕事を求めて流出する人が増えていった。こうした基隆の苦境について、都市計画研究者の張容瑛は、「基隆は1980年代までは港湾経済に、1990年代には台北都市圏に、2000年代からは国家財政による補助金に依存してきた」と整理している(12)。
衰退のしわ寄せを直接的に被ったのは、本書に登場する埠頭労働者たちであった。第三段階「底辺の時代」の到来である。1999年に荷役作業が民営化されると、労働組合によって保護されていた労働者たちは、たちまち「コスト削減」の対象となった。同時に、コンテナ海運業界自体が熾烈な国際競争にさらされていたために、失業を免れたコンテナ業務の作業員やトレーラー運転手たちの人件費も切り下げられていった。港湾労働者の失業や減収は、おのずと埠頭周辺の商業の繁栄をも掘り崩し、「仲間文化」はその足場を失って、やがて消失していった。職や居場所を失った男たちは、やむを得ず、長らく留守にしていた家庭に戻ることとなる。しかし、彼らの家族との信頼関係はとっくの昔に崩壊しており、男たちはもはやそこに夫/父親としての居場所はないという現実に気付かされるのである。