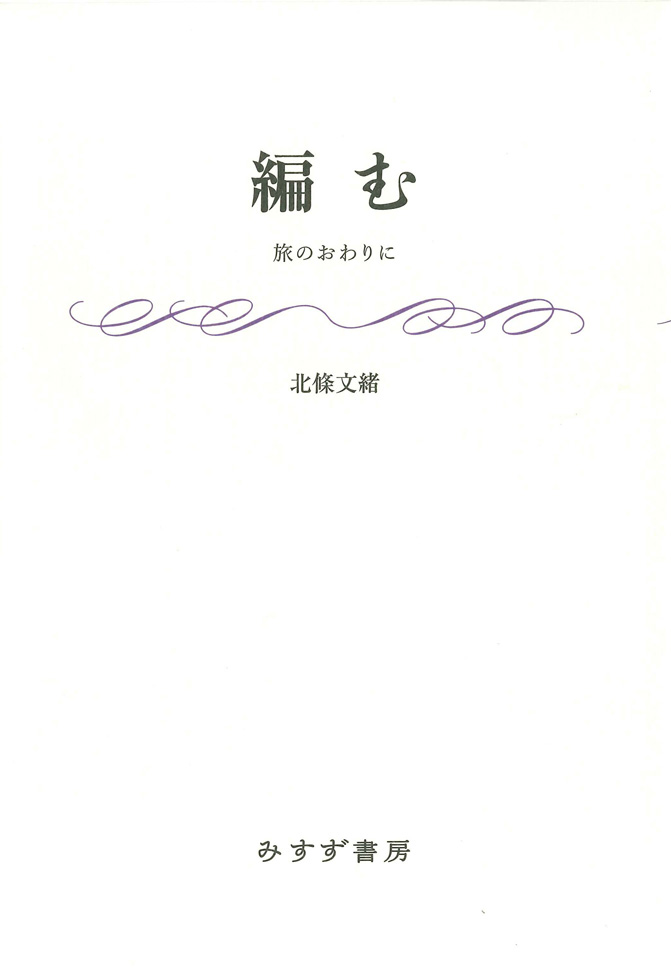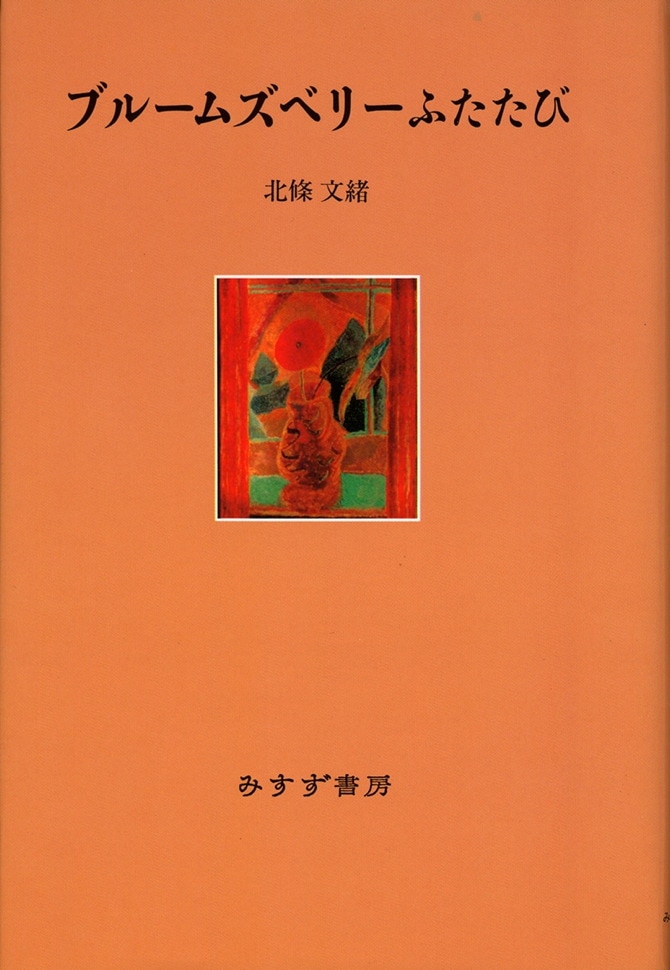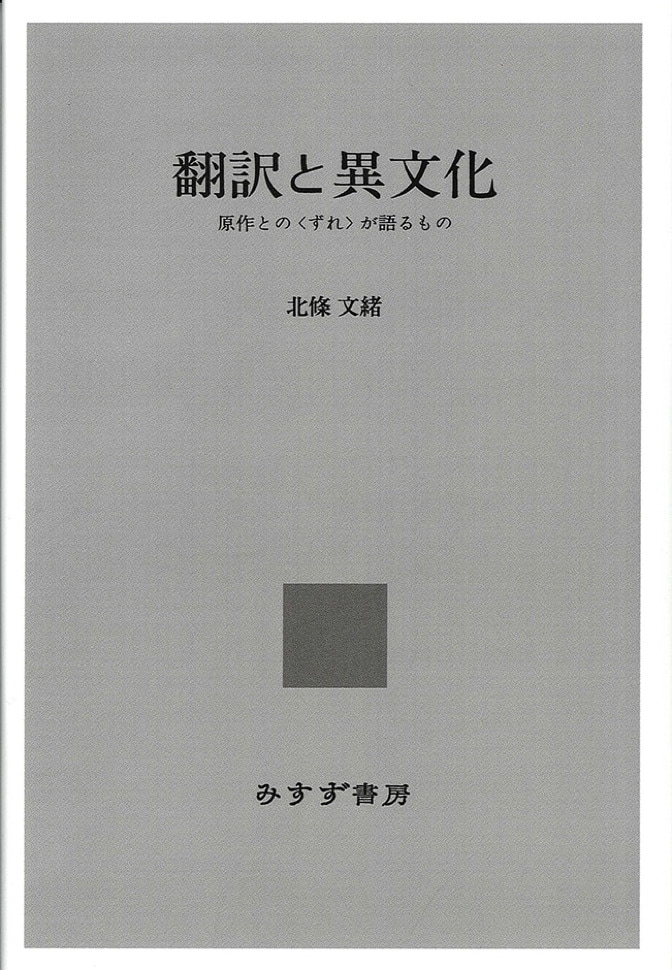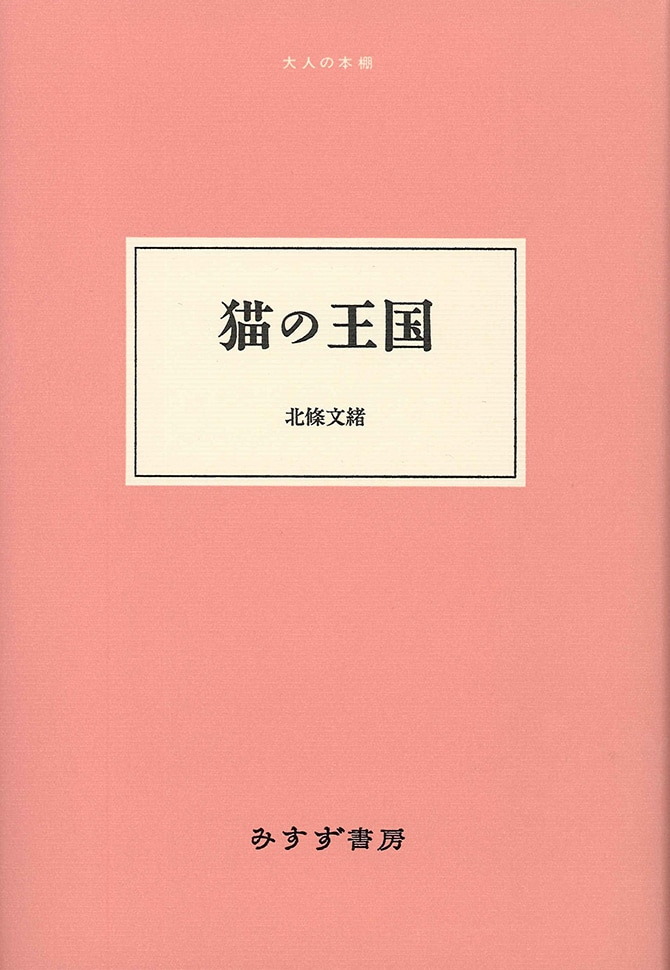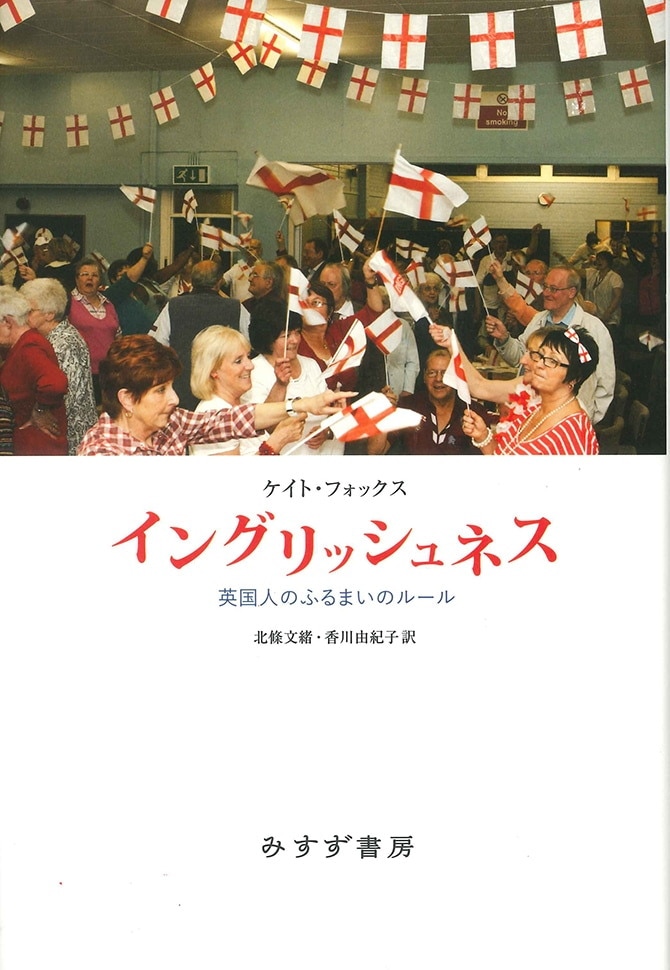1996年に書かれた「トルコ・クレタ島紀行」。著者はじめてのこの紀行エッセイは、ギリシアを飛び立った飛行機が成田空港へ到着し、旅というアクセントを挟んで、東京での日常にふたたび入ってゆこうとするところで閉じられる。
そこに、印象的なあるイメージが描かれている。
……以後、私のなかにたゆたうギリシアがある。ふつうの人間にとってこれが旅行の効用ではないだろうか。フェタ・チーズはやがて黴びて捨ててしまったし、持ち帰ったラキも魔法からさめればどうということはない焼酎である。だが頭の片隅に、ギリシアを入れて薄いカーテンで仕切った小部屋のようなものが生まれ、折にふれてそこからイメージや色彩や、断片的な知識が蘇る。
……E. M. フォースターが入り口だった私のギリシア体験は、ブルームズベリー・グループの人々をはじめギリシアに憧憬を寄せたイギリスの作家たちとの付き合いのなかでさらに深められ、ギリシアを入れた小部屋のカーテンはそのたびに揺らめいて、その奥にあるものに少しずつ鮮明な輪郭を与えてゆくだろう。
(『ブルームズベリーふたたび』1998所収)
旅に出る。薄いカーテンで仕切った小部屋がひとつずつ増えてゆく。
4篇の紀行エッセイが『ブルームズベリーふたたび』にまとめられたあとも、「人生の日暮の時期」にはじまった著者の旅は続いていった。ブータン、南イタリア、韓国、アメリカ西海岸……
旅から持ち帰ってきた無形のものが、薄いカーテンで仕切られた小部屋に収われるまでの時間に1篇1篇書き溜められていった6つの文章――いちども人の目にふれることのなかった旅の記憶は、著者がこの世界から旅立っていった1年後に、「編む」というタイトルをもった本になった。
あるていど時間が過ぎ去ったところから読む、ある時代の、ある国を旅した、きわめて個人的な記録。その中に、北條文緒という女性の声が、存りし日のままに聞こえてくる。
心躍る旅ばかりではない。見知らぬ外国どころか、行き慣れた信州のもうひとつの家ですごす非日常の時間も、また旅だ。
雪の舞う日に給湯管の破裂に見舞われ、お湯も暖房も使えない。そんな災難の中、なんとか作り出した居心地のいい空間で、土地の人からもらった甘い林檎をかじってウィスキーを味わい、「ぽかぽかの繭のなかに入った」ような音の絶えた世界で、著者はひとりつぶやく――I have a good life.
なぜか英語でそう思うのは「いい人生」では大げさだし「いい生活」では薄っぺらだからかもしれない。
(「湯田中のカステラ」、本書『編む』所収)
文章を書くということが、手すさびの愉しみではありえず、自分の繰り出すことばを、ひとことひとこと編みつづけて逝った著者。短いエッセイの中で繰り返される「I have a good life」ということばは、私たちへの、やさしい別れの挨拶なのかもしれない。