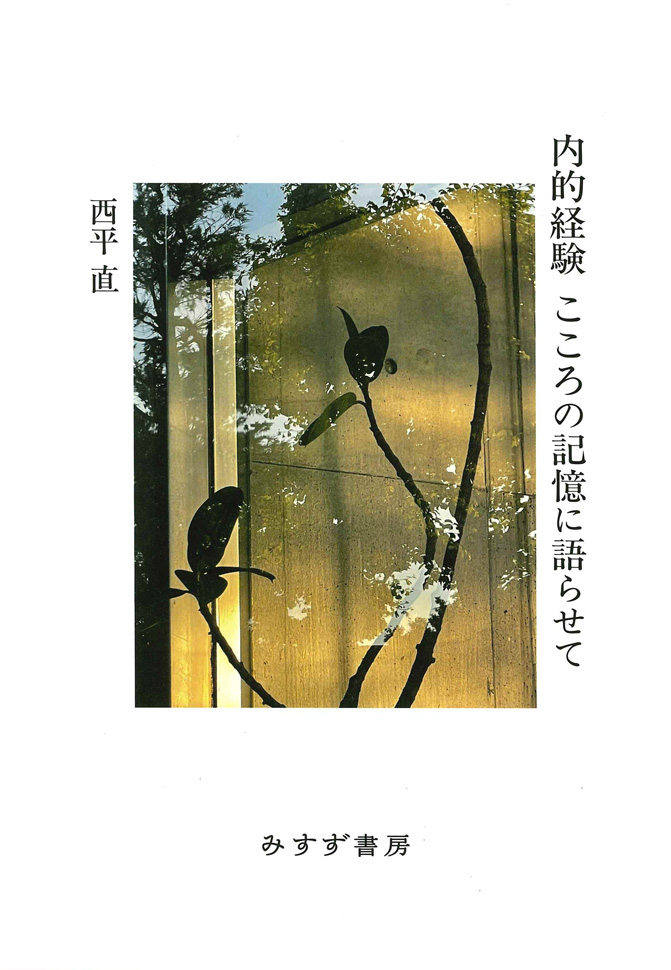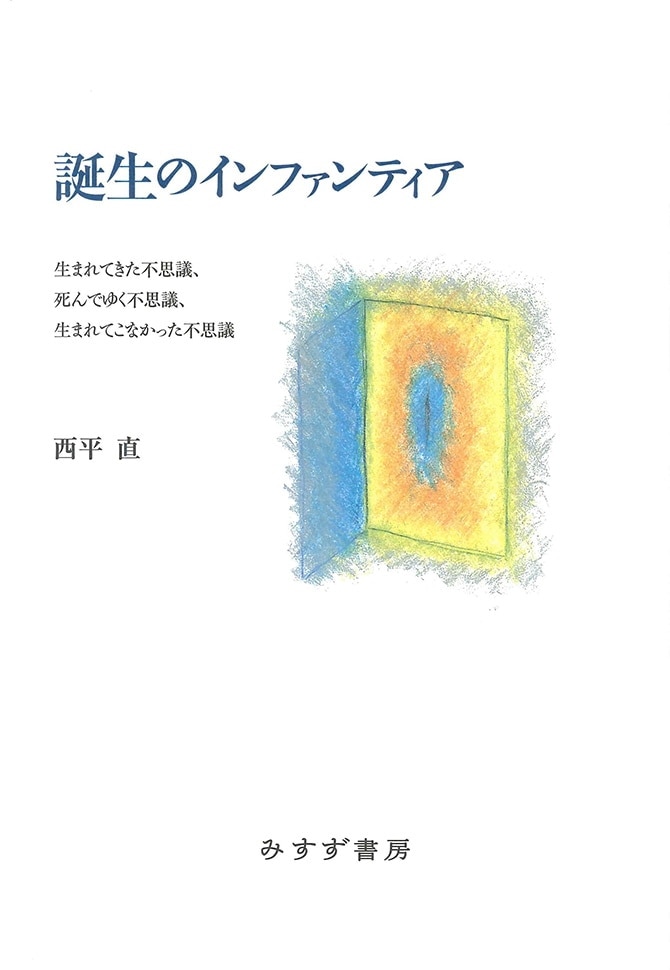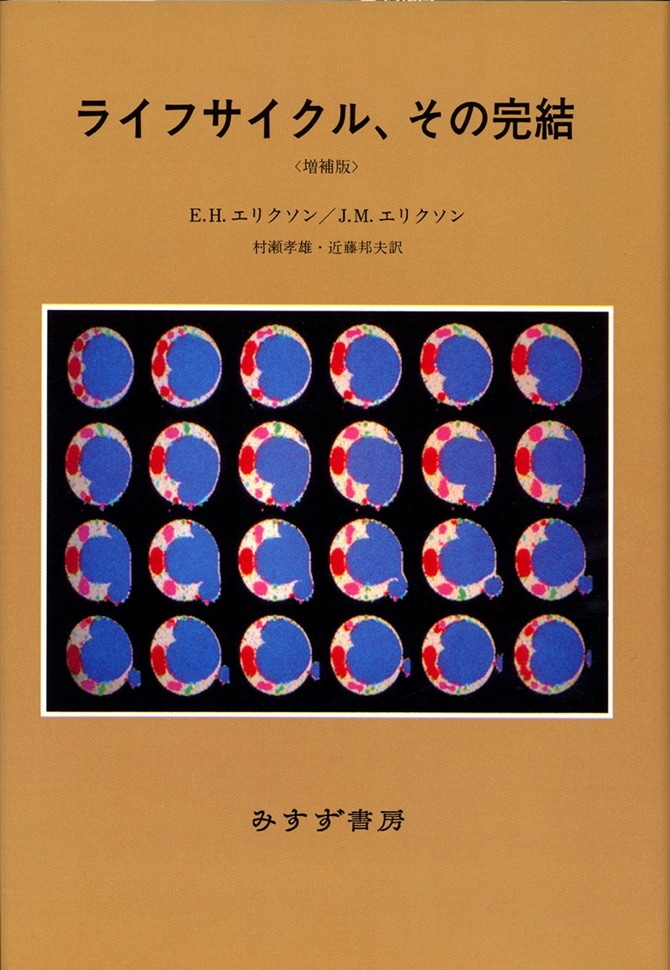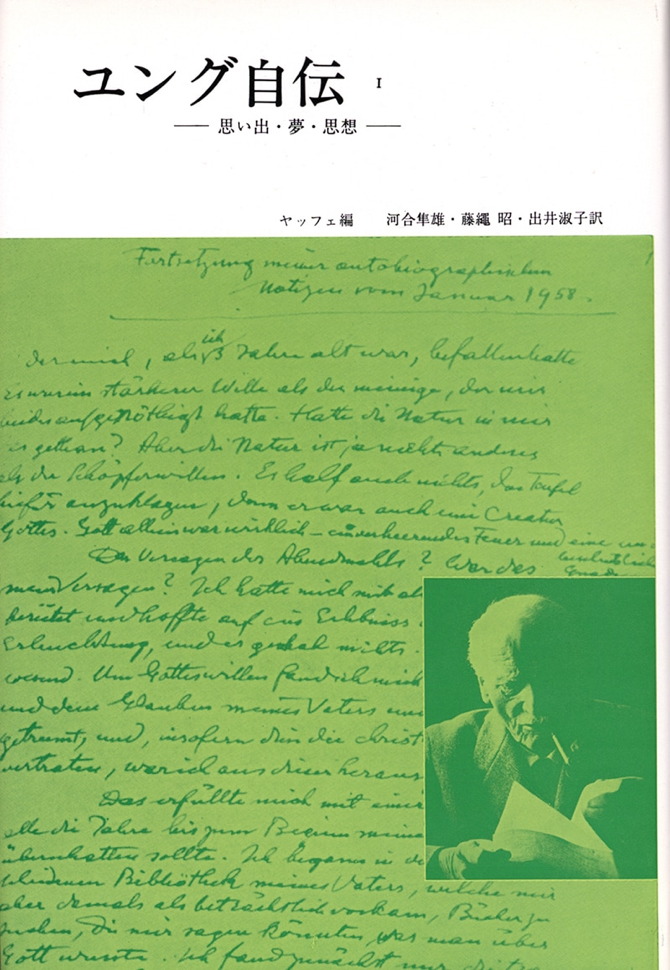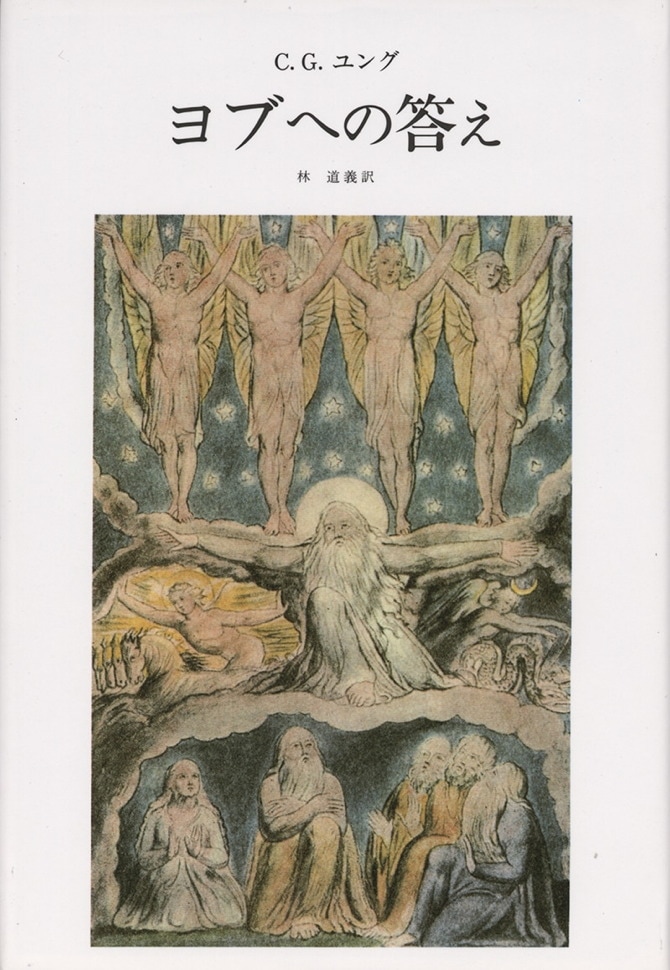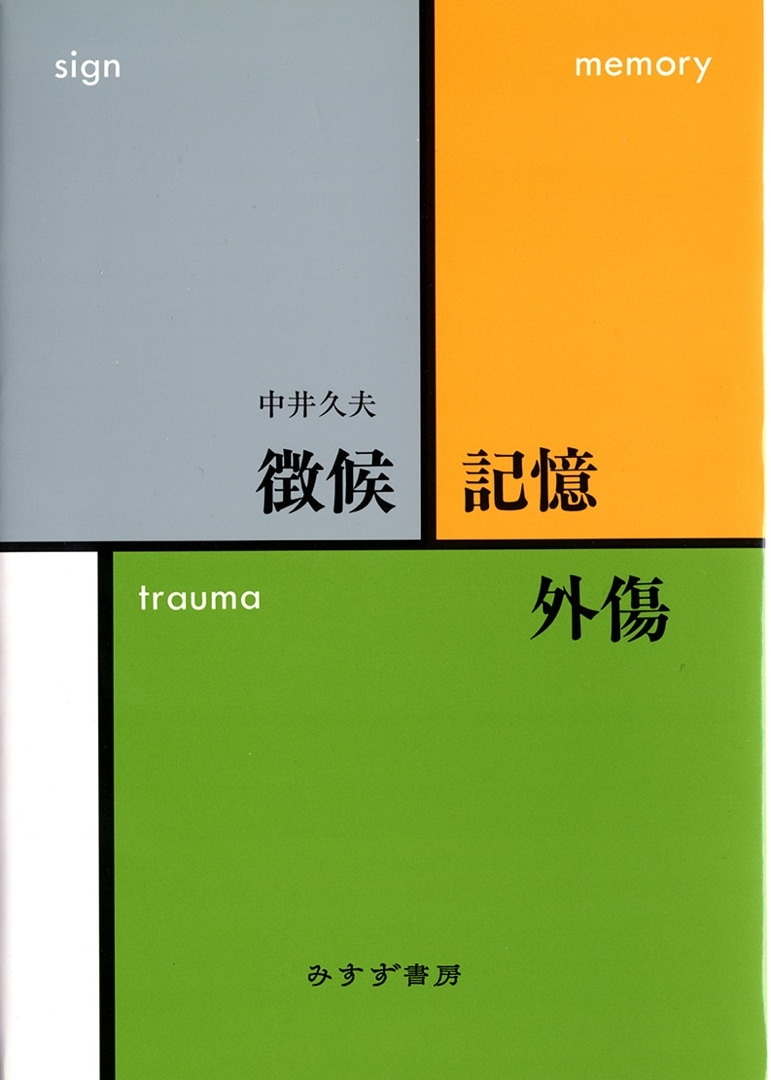本書には、あとがきがない。
著者にとってはじめての「あとがきのない本」ができあがるまでに折々に聞いた言葉たちを、その書かれなかったあとがきのかわりに、ここに書きつけておきたい。
子どもの頃を思い出す、ということ。
たとえば、自分が「いる」という不思議。
たとえば、自分の内側から「来てしまう」、自分ではコントロールできない「内的な促し」という不思議。
「回想ではない。書いているうちに、氷が溶けてゆき、子どもの目になる。大人の目で懐かしむのではなくて、少年の目で少年の世界を見ようとする。新しい何かを発見しようとする」。
ウェブ媒体に変わる前の、雑誌『みすず』連載中にいつも感じていた、一見やさしそうに見えて、じつは難しい、そして深い文章たちはそんなふうに書かれていった。
「形ははっきりしない。雲のように流れてゆく。その流れについてゆく。繰り返される問いの前で、同じ問いのまわりを何度も廻りながら、言葉が生まれてくるのを待っている」。
子どもの頃の「もの思い」を思い出すこと。
たとえば、困難な暮らしを一日一日、祈りながら生きる人びとへの尊敬と、悲惨なニュースを目にするたびに感じてきた素朴な問い。なぜこの人たちが苦しまなければならないのか、なぜ神は助けないのか。
「〈宗教〉という言葉になる前の、〈もの思い〉に近い、こころの揺れ。それを、そのまま生け捕りにする。同時に、大人になってから学んだ思想と重ねてみる」。
たとえば、東洋の伝統思想と。
たとえば、精神分析の知恵と。
さらに、著者が教育人間学の内側で感じてきたこと、スピリチュアリティ研究の手前で揺れてきたこととも重ねられ、エッセイというかたちになった素朴な記憶のかけらたちは、一見やさしいようで、やはり、てごわい。