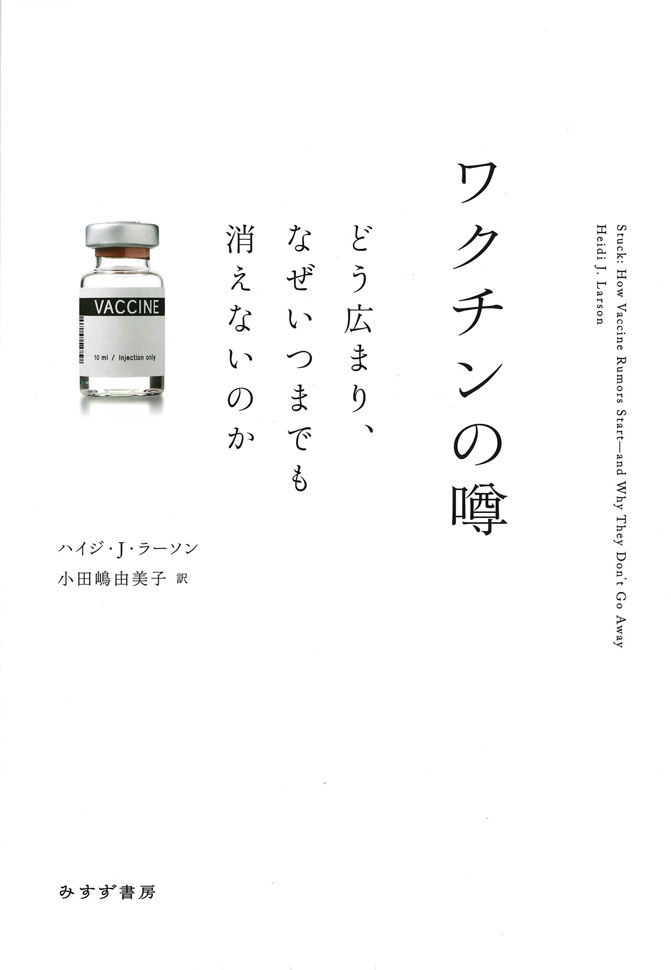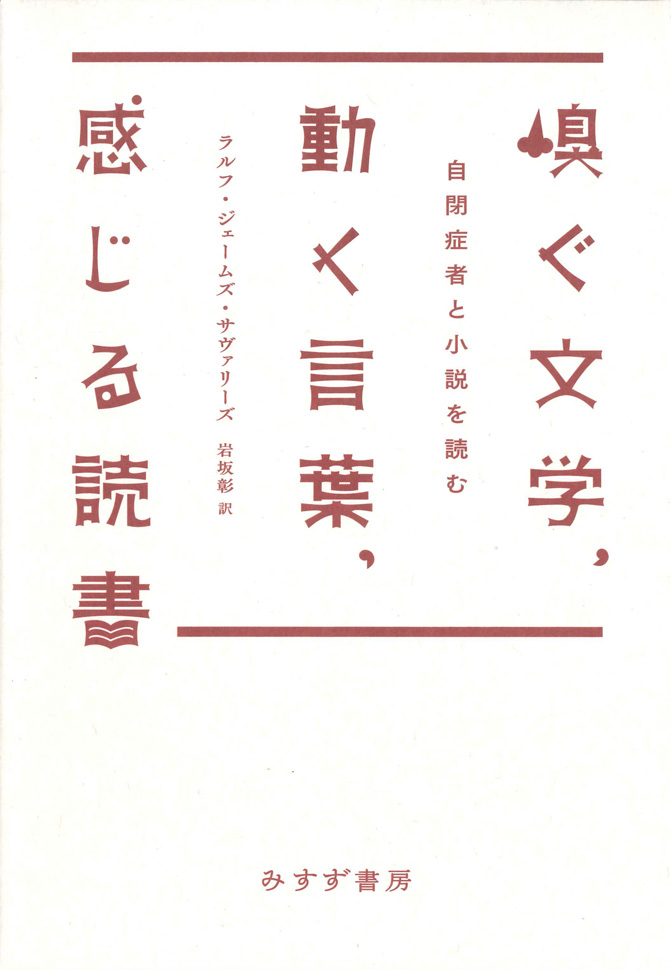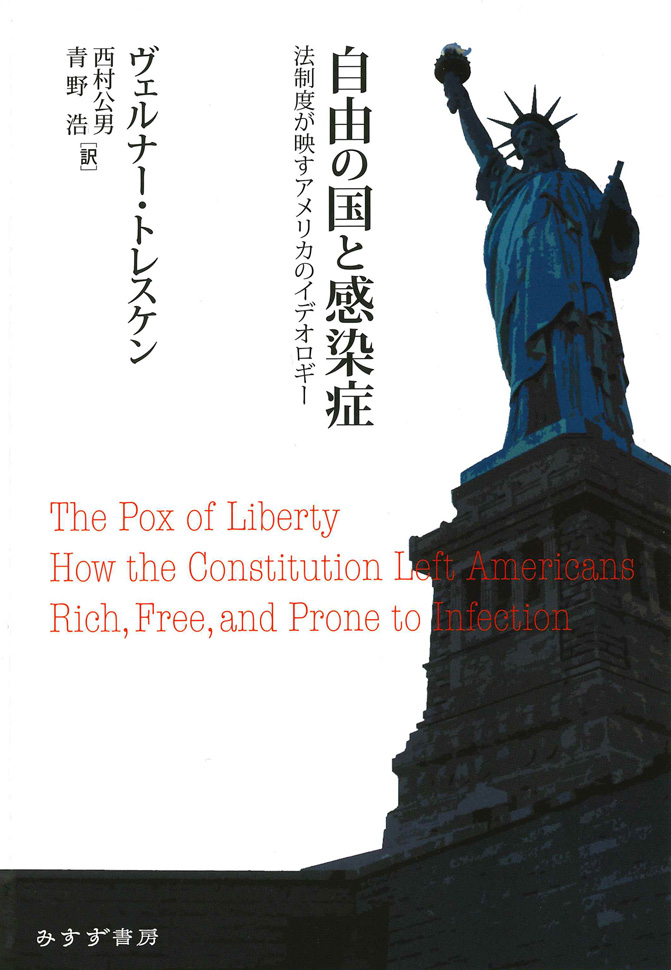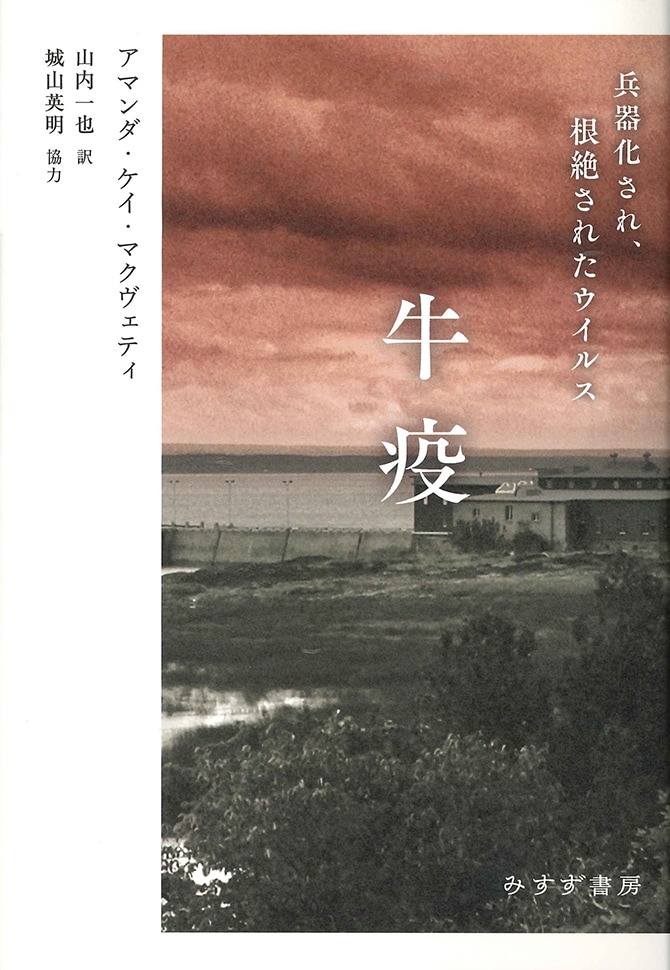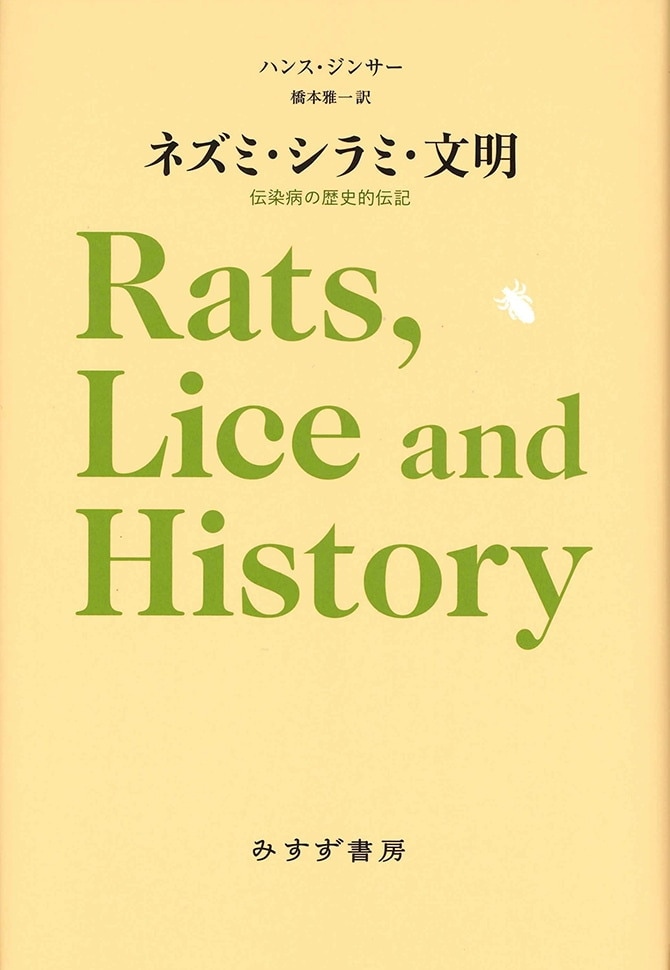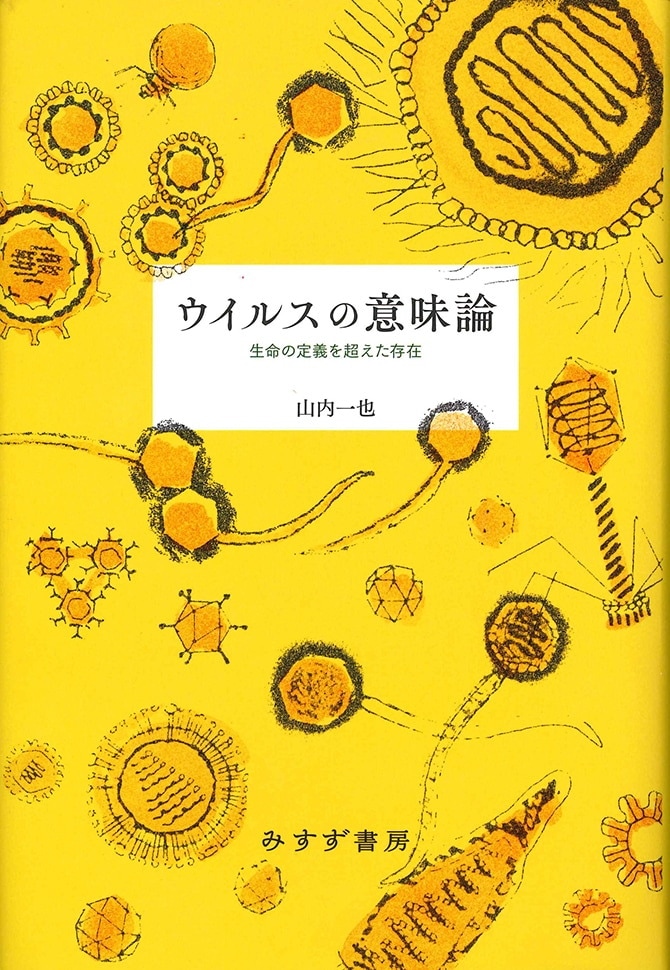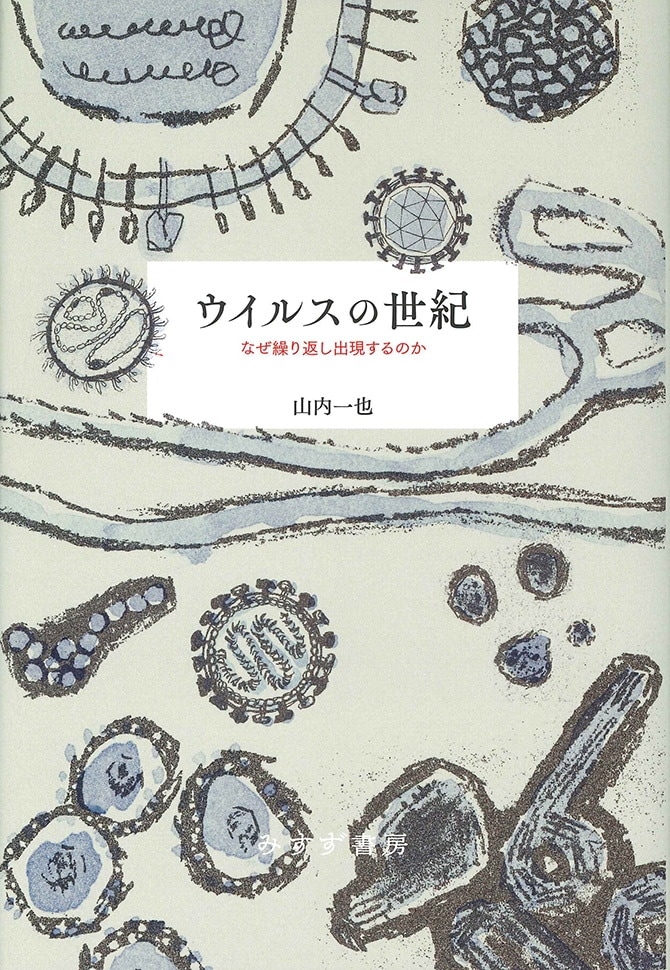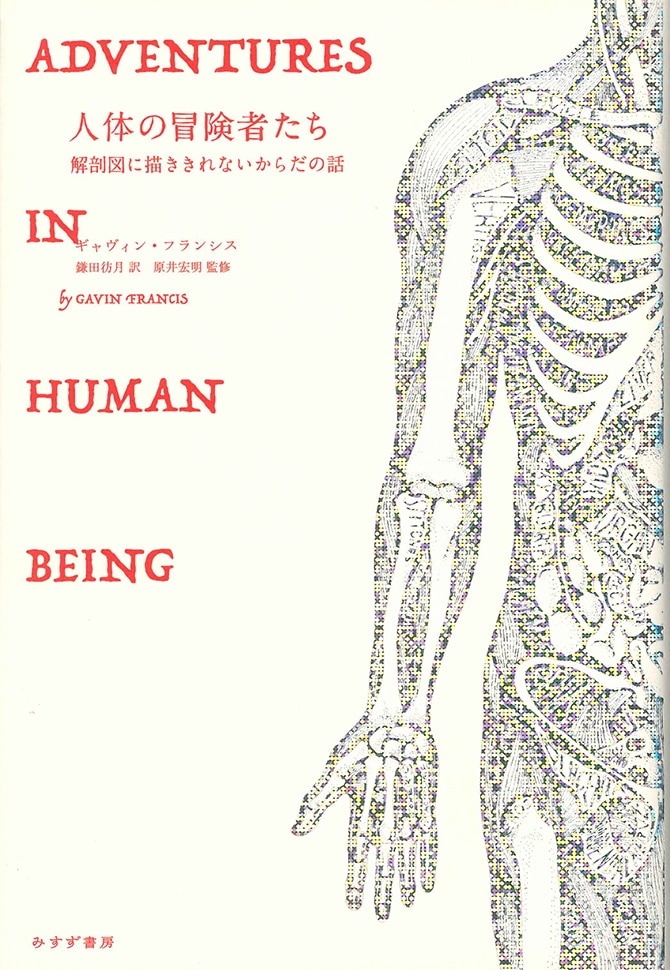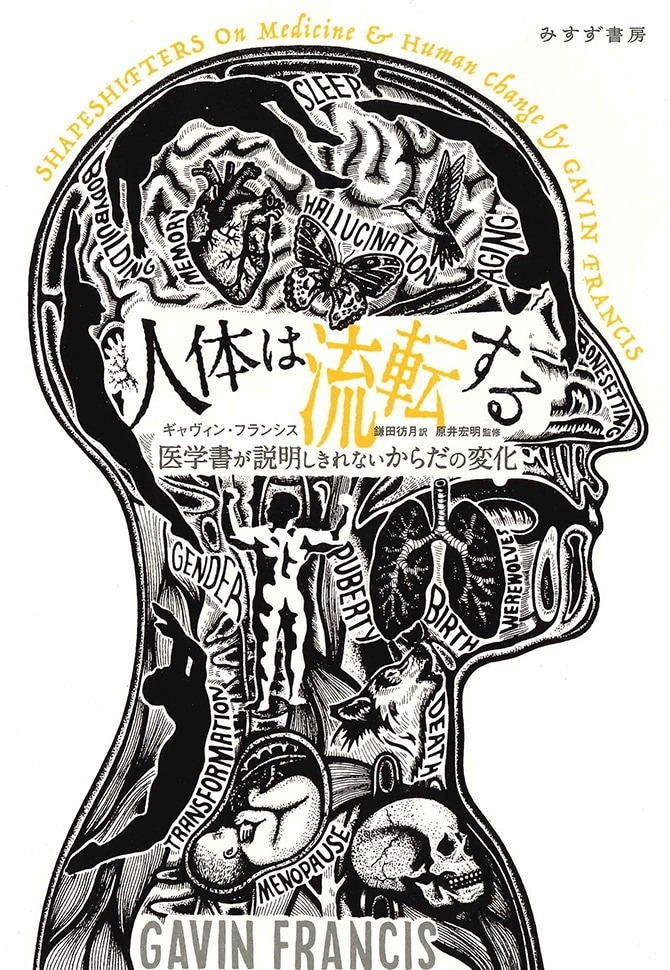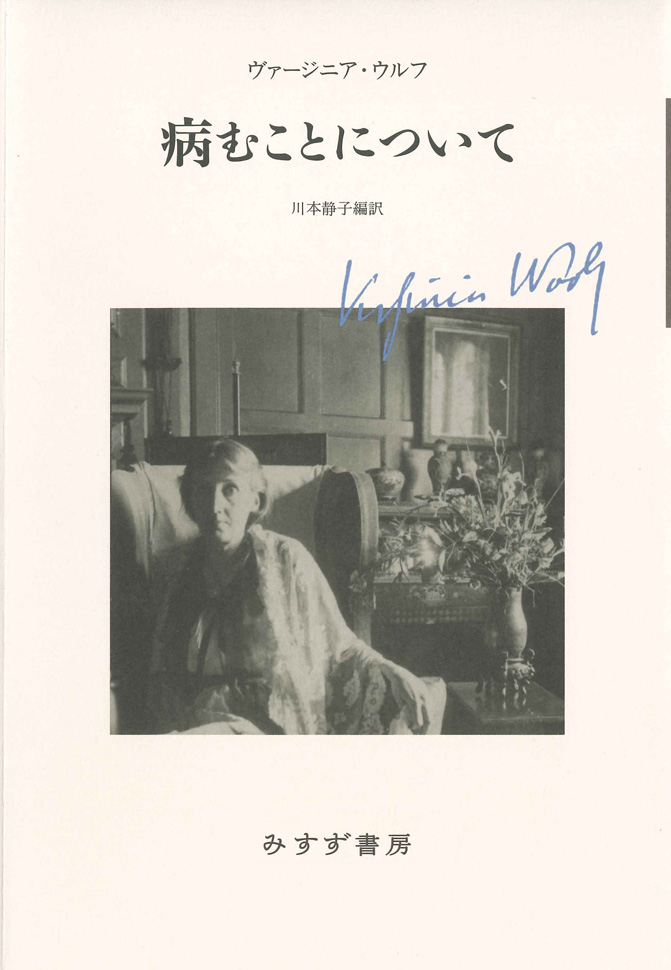訳者あとがき
桐谷知未
著者のカリ・ニクソンがこの本を書き上げたのは、2021年の始めごろだ。2022年7月の今、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの状況は、残念ながら大きく改善したとは言いがたい。世界の累計感染者数は5億6000万人を超え、死者も600万人を超えた。ウイルスは変異を繰り返し、なかでも感染力の強いアルファ株、デルタ株、オミクロン株などが流行の波をつくって、現在ではオミクロン株の変異株BA. 5が世界で猛威を振るいつつある。日本でも感染者が急増し、7月15日には全国で一日の新規感染者数が10万人を超え、ニュースは「第7波」に入ったと報じている。
2020年末にはファイザーやモデルナなど大手製薬会社によってワクチンが開発され、順次接種が進んだことで感染や重症化をある程度抑えられるようになった。しかし、ウイルスはどんどん変異するのでワクチンの有効性が下がってしまい、獲得した免疫も時間とともに減少するので定期的な追加接種が必要になるなど、感染の封じ込めには程遠い状況が続いている。治療薬の開発も進んではいるが、一般の人に安定供給が可能な経口治療薬ができるまでにはまだ時間がかかりそうだ。
今回の波で感染者はどこまで増えるのか、この波が収まってもまた次があるのか、いったいパンデミックはいつまで続くのか。何ひとつはっきりわからないまま、わたしたちはできるかぎり感染対策をして、日々の生活を続けていくしかない。
19世紀の社会・文化と感染症の関わりに詳しい医療人文学者である著者は、歴史的な事例から、こういう事態が発生することを予測していた。そして、今だからこそ過去に起こったパンデミックから学ぶべきことがあると考え、それを広く伝えようと一冊の本にまとめ上げた。
しかし読み始めてすぐにわかるのは、単に過去の事例とその教訓を並べただけの本ではないということだ。著者はわたしたちに、今回のパンデミックを機に、根強い偏見から脱して新しい考えかたを身につけなければならないと何度も語りかける。自分は偏見を持たずに物事を柔軟に受け入れられるタイプだと思っていた人も、読み進めるうちに、どれほど現代の社会や文化にとらわれた発想をしていたかに気づいて愕然とするのではないだろうか。
まず、序章の病気の定義からして驚かされる。病気とは、「人の体に何かが起こり、そのせいで悩んだり苦しんだりしていることを表す言葉」。つまり、人が認識して初めて、病気は病気になる。これは第9章の「何をもって性感染症というのか」の問題とも関わってくる。病気について、一からすべてを考え直すことを求める本なのだ。
各章では、天然痘、ペスト、コレラ、腸チフス、インフルエンザ、エボラ出血熱など、1700年代から現代までに人々を襲ったさまざまな流行病が取り上げられている。それぞれの病気をめぐるテーマも多様で、各章に三つずつ示された教訓に沿って論が展開される。たとえば、天然痘を扱った第1章では、予防接種が西欧社会に受け入れられるきっかけをつくった女性のエピソードを軸にして、主流から外れた人々の声に耳を傾ける重要性や、公衆衛生がもたらす個人の自由と集団の利益の葛藤について考察する。ダニエル・デフォーの『ペスト』から学ぶ自主隔離とソーシャルディスタンス、経済の流れを保つことの大切さを扱った章も興味深い。ほかにも、1880年代の病原菌の発見以降に生まれた「リスクを完全に排除できる」という誤った考えと科学への過剰な信奉が、現在までどれほどの悪影響を及ぼしているかや、HIVやエボラ出血熱を自分とは関係のない病気と考える偏見や差別意識、外国人嫌悪が病気の蔓延をどれほど助長しているかなど、今すぐ真剣に考えるべき課題がいくつも提示されている。
COVID-19パンデミックの様相は刻々と変化し、著者の執筆時とは異なっている部分もあるが、差し出される教訓はどれも今の状況を正確に言い当てていて、驚くほど説得力がある。パンデミックの行く末を何年もあとまで見据えて書かれている証拠だろう。
特に著者が繰り返し強調しているのは、人がみんなつながっていること、病気がそのつながりをあらわにすることだ。それを無視したり拒んだりすれば、逆にウイルスの格好の餌食になってしまう。だから著者は、現代の社会の分断にたいへんな危機感をいだいている。政治的に意見の合わない人とも「共通の基盤」があることを認め、ひとりひとりの創意工夫で社会を改善していく──それこそが明るい未来につながると、著者は信じている。
本文中の自己紹介にもあるとおり、カリ・ニクソンはウィットワース大学で教鞭をとる英文学教授だ。医療人文学とヴィクトリア朝文学を専門とし、娯楽メディアに登場するゾンビについてなど、ユニークな研究でも知られる。オンラインメディア『ハフィントンポスト』や『イエス!』誌、CNNなどで、公衆衛生に関する研究を一般読者向けに発表する機会も多い。最近では、ポスト植民地主義の母性への期待、生存者と医療人文学の視点から見た代理ミュンヒハウゼン症候群についての研究プロジェクトに取り組んでいるそうだ。夫と娘ふたり、たくさんのペット(現在は犬2匹、猫2匹、馬1頭、ハムスター1匹)とともに暮らしている。ノルウェー語が堪能で、本人のSNSへの投稿によると、7月初旬に2年間の予定で一家そろってノルウェーに引っ越したという。人生を思いきり楽しむ著者らしい決断だ。
著者はこの本のなかで、「死を恐れてはいけない」、「死すべき運命を受け入れなければならない」と何度も繰り返す(だから傍若無人にふるまっていいという意味でないことは、きちんと読んだかたには明白だろう)。しかしこれは、たいていの人にとってむずかしいことだと思う。誰だって死ぬのは怖い。著者のような境地に達することはなかなかできそうにないのだが、まずは「他人事にしない」という心構えから始めるのはどうだろう。感染症からも死からも目をそむけずに、「自分の身にも起こりうること」と考える。それが、「パンデミックの向こう側」を全員でめざすために必要な視点なのかもしれない。
2022年7月
Copyright © KIRIYA Tomomi 2022
(筆者のご同意を得て抜粋・転載しています。
なお読みやすいよう行のあきを加えています)