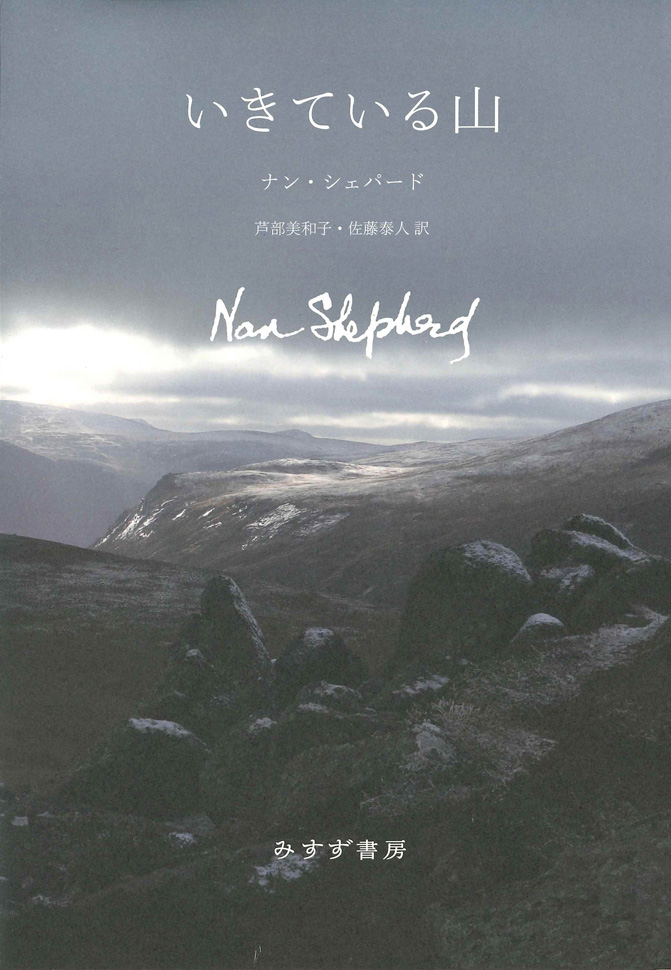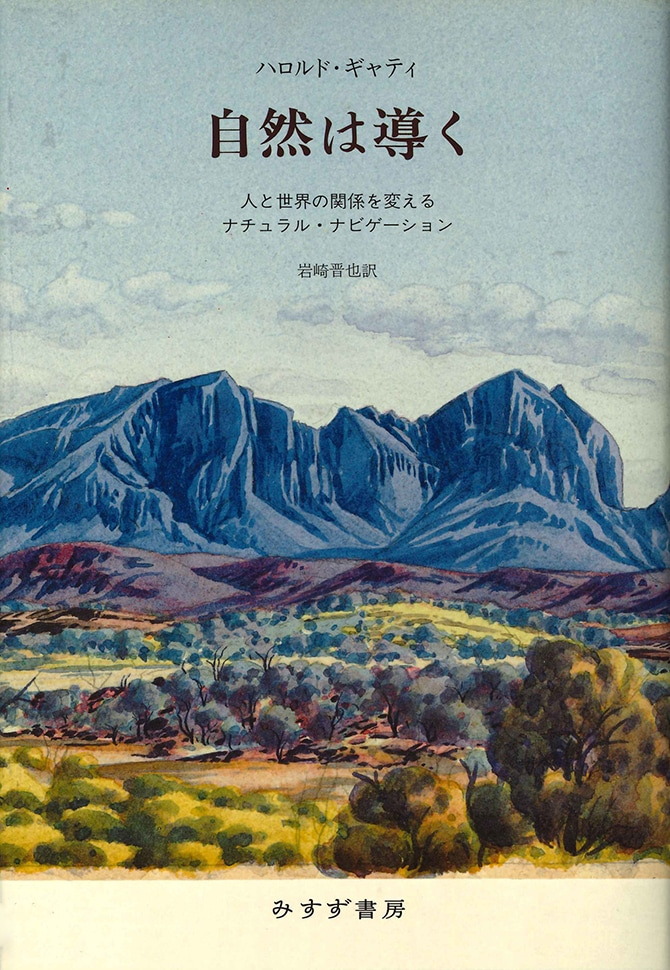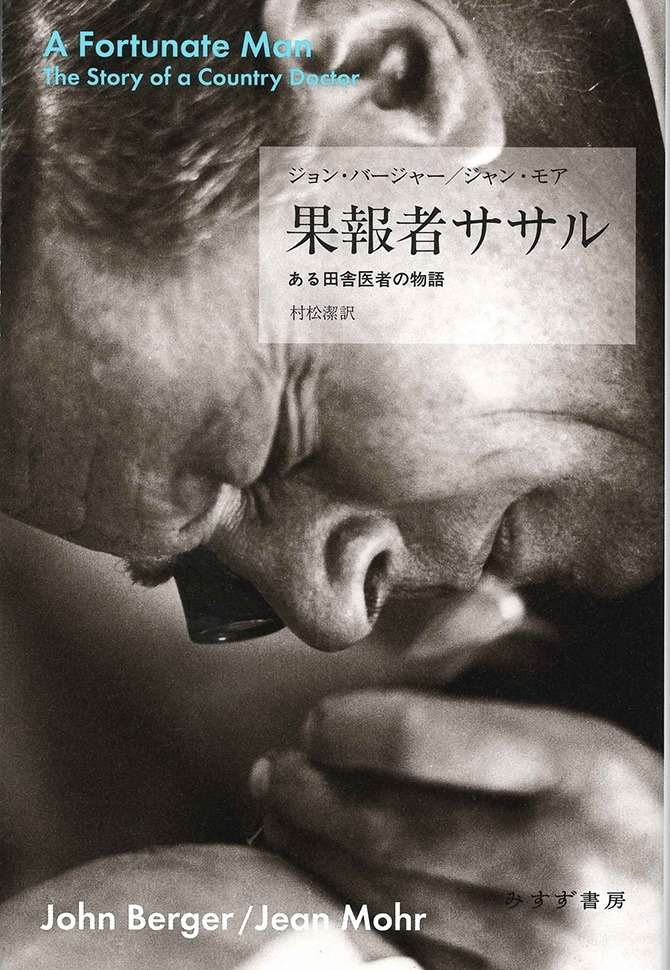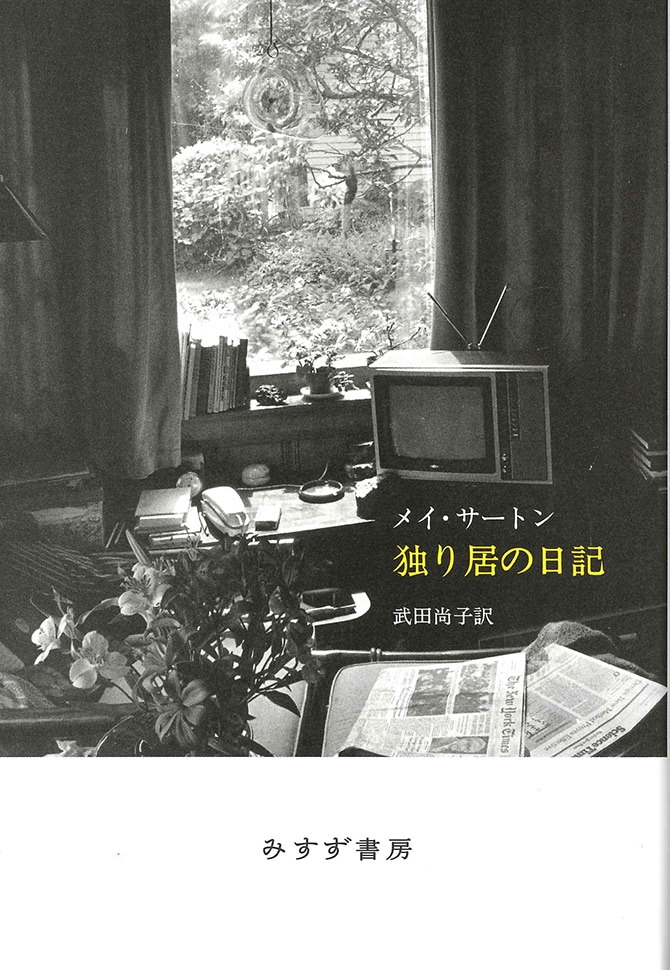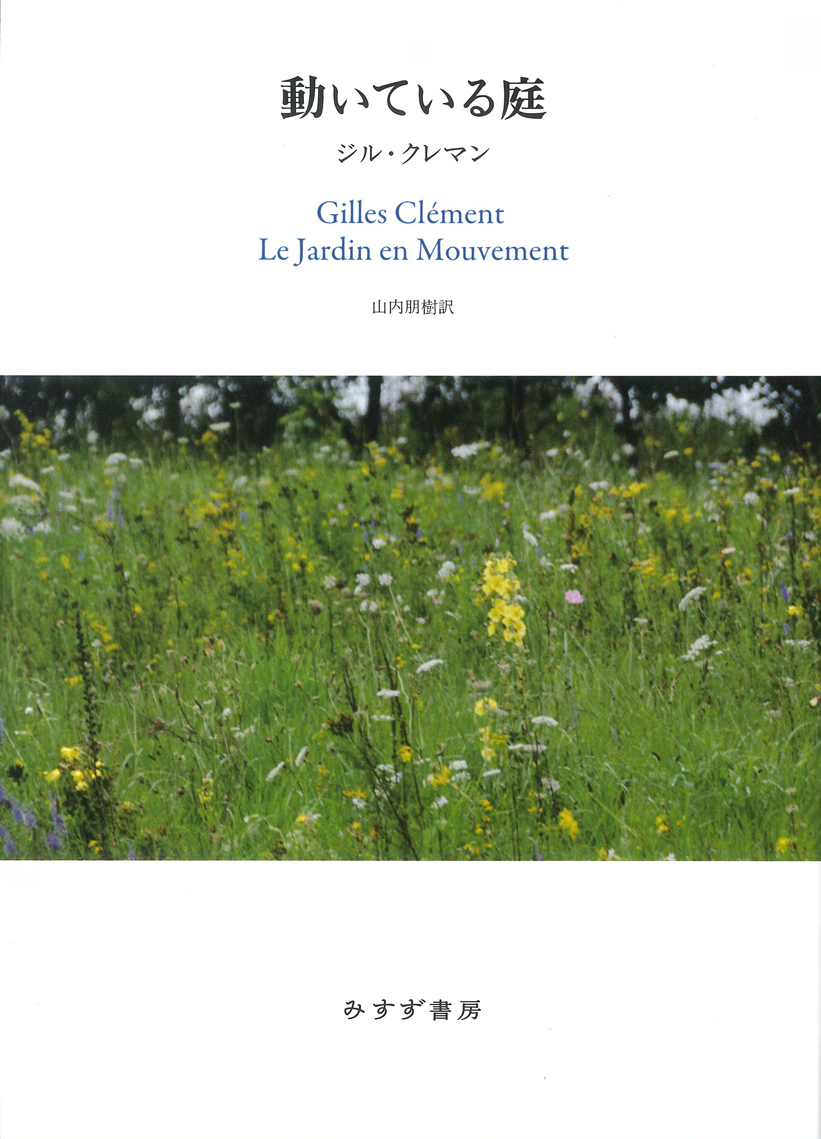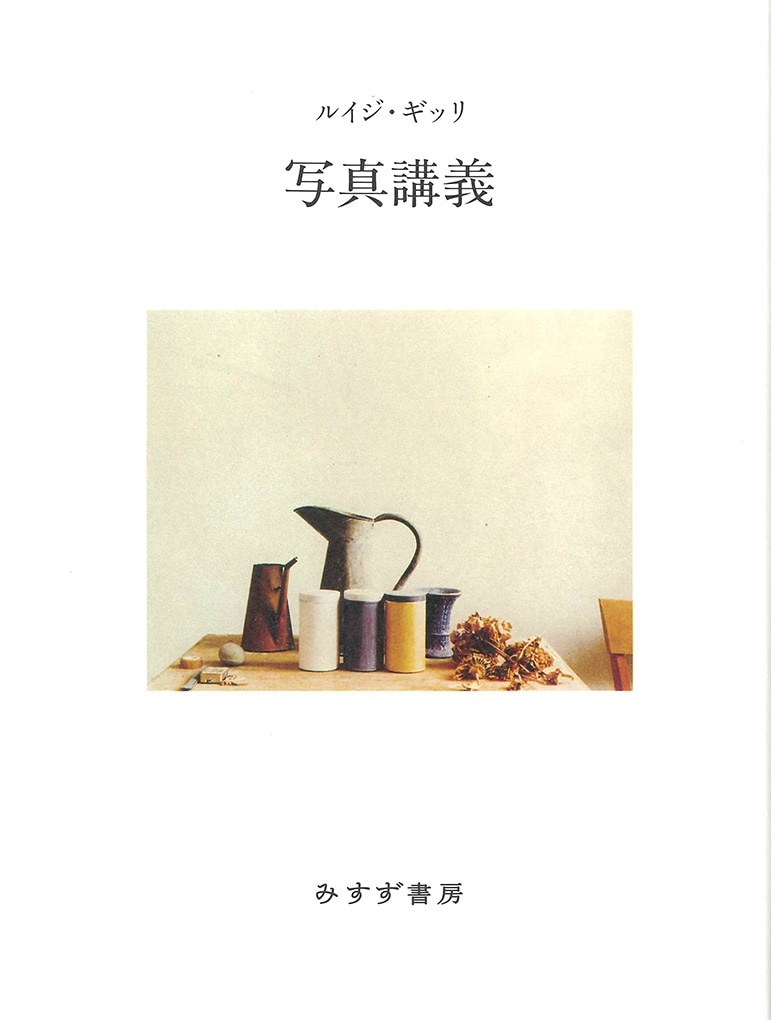芦部美和子
2021年10月、シェパードが「彩り豊かな月。六月よりもずっと色鮮やかで、その強い光は八月よりも鋭い」と書いた10月、そして、「見るものすべてがウイスキーの黄金色に輝く」と表現した豊かな季節に、私たちはケアンゴームの山々を歩いていた。登山者たちにとって短くも貴重な夏が過ぎ、スキーシーズン到来にはまだ早すぎるとはいえ、山では不安になるほど人に会うことが少なかった。1977年の本書出版当時でさえ、シェパードは執筆後の30年間でケアンゴームがいかにリゾート地化され、「人間の存在そのものがあからさまに」なってしまったかについて言及しているが、近年のハイカー急増、山頂付近の渋滞、ゴミ問題の深刻化など気がかりな事前情報は絶えず、本書に描かれるケアンゴームの姿とはかなり違っているかもしれないことを覚悟していた。しかし、コロナによる移動制限もあってか、一度山に入ってしまうと、すれ違うのはせいぜい数組のハイカーのみ。ケアンゴームの奥部に近づけば近づくほど、人の気配は遠のいた。今思えば、これはシェパードが歩いていた頃の様相に近かったのかもしれない。
ケアンゴーム初心者が、シェパードに倣っていきなり10月の夜にビバークというわけにはいかなかったが、毎日ただひたすらに歩いただけでも、くるくるとその装いを変える驚くべき世界を目の当たりにすることができた。まだヘザーがそこかしこに生い茂り、夏の名残を残していた10月初め。しかし、数日のうちに雪が降り始め、山の稜線付近はすっかり雪化粧を纏った。もう冬の到来かと思った矢先、今度は10月らしからぬ強烈な日差しが雪を溶かすと、その下からは植物たちが目に眩しい鮮やかさで輝き、山は一斉に燃え上がった。初夏を思わせる暖かい日があったかと思うと、突然吹雪に見舞われる。シェパードを気取って「この山々にあって、急ぐことは何の意味も持たない」などと悠長にしていたら命を落としかねないと思いながら、雪に、雨に、風に打たれて先を急ぐこともあった。
ケアンゴームでは、思わず目を疑わずにはいられないものにいくつも遭遇した。たとえば〈色〉。なかでも想像をはるかに超えてきたのは、青と紫を往還するような色相域。または、突然現れたり消えたりする山や湖。いく度となく距離感が狂わされ、視覚の曖昧さなるものを身をもって知ることとなった。こうしたすべてが、これまでの価値観を根底から揺るがす強烈さを持っていた。あの時目にした光や色、山や湖の姿は、はたして現実だったのか――脳裏にこびりついて離れることなどないと思っていたのに、少しずつその輪郭がぼやけ始めている。今すぐにでも、あの時見たものを確かめに戻りたい衝動に駆られてしまう。シェパードは次のように書く。
人はこれを見に戻らずにはいられない。さらにはもうひとたび。なぜなら、これと離れているあいだ、記憶のなかであの明るさを再現することは不可能だから。(…)与えてくれたすべてを持ち帰ることはできないし、持ち帰ったものが現実だったのか、必ずしも信じられるわけではない。
(一、プラトー)
非現実的なものとの邂逅に対して、現実的な出逢いは動物たちだった。丘の稜線に目を走らせていると、ふいに動いてその存在を知らせる小鹿。夕暮れ迫るプラトーに突然走り出て来るコバシチドリの子ども(本書のカバーをめくると現れる、ライチョウの幼鳥にも似た鳥は、この瞬間をおさめたものだ)。どちらも、その警戒心のなさにこちらの方が心配になる。または、杭の先端にさりげなく鎮座するイヌワシ。それと気づかなければ、間違いなく通り過ぎていただろう。そして、小さな体をふるわせ、うっとりするような歌声を聴かせてくれるミソサザイやコマドリたち。森を立ち去るのが、どれほど名残惜しかったことか。欧米の山々を20年近く歩いてきたが、これほど生命力に溢れた場所は珍しい。
シェパードの説明にもある通り、ケアンゴームの山々には私たちが想像するような山頂らしい山頂はなく、山頂といわれる場所には平坦なプラトーが一面に広がる。ゆえに、山行を忘れがたいものにするような瞬間がいつ、どこで訪れるかわからない。天候、光の具合、そこに居合わせた動植物、水の状態、石の一つ一つにいたる「山の一部」、すなわち、シェパードがいうところの「山にとって不可欠な存在」が奇跡的な確率で交差したとき、その瞬間は訪れる。どんな山であれこうした瞬間に遭遇すると、登山は登頂することがすべてではなく、高さや速さなどでその価値をはかれるものでもないということを改めて思い知る。
シェパードより16歳年下ではあるが、シェパードとほぼ同時期に登山を始めた英国人作家のエリザベス・コックスヘッド(Elizabeth Coxhead, 1909-1979)は、彼女の登山体験をつづったエッセイ「初めての山(‘First Mountain’)」(1955)のなかで次のように述べる。
すべての山は初めての山だ。(…)同じ景色や状況は二度とくり返されない。たとえば雪、霧、強風、ブロッケン現象、色彩や光の初めて目にする強烈な作用など。まったく同じ登山など二つとないのだ。(強調は筆者による)
西洋のアルピニズムにおいては、数値化された記録と並び、初登頂や未踏ルート踏破など「一番/最初(first)」であることが評価の対象とされてきた。その結果として、登山は競技スポーツ的な要素を色濃くしてきたといえる。これに対し、コックスヘッドの主張は、誰かと先を競い、初登頂にこだわる登山観とは対照的だ。同じ「first」でも、一番になることではなく、同じ山であっても初めて体験する登山の価値、すなわち登山の一回性を主張する。むろん、どちらか一方の価値観が良く、もう一方が悪いといっているのではない。むしろそうした二元論に当てはめて論じることは危険を孕む。とはいえ実際、山はその時々の自然現象によってその姿を変えるし、登山者の心の状態や体調によってもその見え方は異なる。シェパードの登山観も、コックスヘッドの態度と多くを共有するものだ。両者は共に、山頂に到達すること、誰かに勝利することにではなく、山そのものを知ることに価値を見出し、山から学びうる知に注目した。これをコックスヘッドは主に小説作品を通じて、シェパードは詩や散文作品を通じて、山の生と人間の生を交錯させながら紡いでいく。シェパードにとって、一回一回の山岳体験は、知っているはずのものに「もう一度出会い直す(recapture)」ためのものであり、「山の本質」を解き明かしてくれる一ピースだった。彼女もまた、登山の一回性を認めていたからこそ、時間をかけ、生涯同じ山々に登り続けたのだろう。「もう一つ、もう一つと知ることに終わりはないのだ」から。本書2011年版の「序文」を執筆したロバート・マクファーレンは、本書が登山文学というより、山岳文学にカテゴライズされるという指摘をしているが、コックスヘッドやシェパードのこうした登山に対する価値観を鑑みれば、本書はいわば、主流とは異なるひとつの登山観を示した登山文学でもあるのだ。
『いきている山』が様々な観点――たとえば、エコクリティシズム、現象学、美学、文化人類学など――から議論可能な作品であることは間違いない。ここでそれら一つ一つについて詳細に語ることは控えるが、スコットランドの片隅で一教師として生涯を終えたシェパードが、どれほどの慧眼を持っていたかについては驚嘆に値する。実際、静かにではあるが、着実に彼女が注目を浴びるようになった近年、本書は彼女の代表作として各分野の研究者のみならず、あらゆる表現芸術に関わる人々に強い影響を与えている。これは、本書が肉体あっての感性を知性で覆い隠すことなく、固定観念や予定調和にとらわれない世界の見方を示したものであることを考えれば、当然のことかもしれない。
しかし、本書は山や登山に興味がある人、表現活動にたずさわる人、文学研究者など限られた人のためだけの本ではないことを強調しておきたい。本書を手に取った人誰もが、ケアンゴームという(ほぼ間違いなく)未知の場所について書かれたテクストを通じて、何らかの共感を覚え、インスパイアされ、その人が必要としているものを見出すはずだ。なぜなら本書は、山という特殊な状況を描きながらも、自然とも肉体とも無縁では生きられない私たちが、感覚を介して世界と接続されうることを描き出した作品であり、また、「平凡なものを輝かせる」ことを追求したシェパードが辿りついたひとつの答えでもあるからだ。
対象を貫くほどの愛と敬意をもって見つめ、その〈声〉に耳を傾け、対象に触れることでそれを感じ、その匂いを嗅ぎ、時に舌で味わう。彼女はこれらの感覚を通して対象の〈中へ〉と入っていき(シェパードは〈内部〉、〈中〉というものに、執拗なまでにこだわった)、ただじっと対象に寄り添う。そうして、焦ることなく対象を「知って」いく。そこにあるのは徹底した受動性。シェパードの文章は登山文学が陥りがちな押しつけがましさとは無縁だ。彼女はこうした一連の経験について、次のように書く。
これは育つ経験なのだ。特別なことなど起こらない日々ですら、欠くことのできない要素が書き足されていく。
(十二、存在)
シェパードの山岳理解の中核にあるのは、「山はひとつ、分かつことなどできない」「全てなる山」という概念だ。全12章にわたり、山にとって不可欠な存在が緊密に絡み合いながら次々と描き出されるが、そこには山に存在する生きとし生けるもの――動植物のみならず、山に生きる人々、シェパードのように山を歩き回る人間まで――をはじめとして、土、岩、水といった山を構成するものから、山々が纏う空気や山に吹く風、山のはるか上空にたなびく雲までもが含まれる。生涯をケアンゴームに生きたビッグ・メアリもそのうちのひとりだ。90歳でこの世を去った彼女の葬儀で、シェパードは彼女に捧げられた花輪に目を留める。
誰かが(本当にありがたいと思う)メアリのために花輪を編んでくれていた。それは、ヘザー、ナナカマドの実、オーツ⻨、大⻨、ジュニパーといった、彼女が日々目にし、手にしていたものたちで編まれていた。
(九、いのち――人間)
山に生まれ、山に暮らし、「大地のような泥臭さと嵐のような激しさ」をその特質とする「不屈の人」メアリの生を象徴するのが、この花輪だ。「鳥が急降下するラインを思わせる荒野の⻑い傾斜、輝く崖、そして家を取り巻く風」、こうしたものをいつしか自身のうちに取り込んでいたメアリは、シェパードにとって〈山の全体性〉を体現したような人だった。花輪に編まれている山の植物――そのどれもが、メアリが「日々目にし、手にしていたもの」――同様、彼女もまた、山をとりまくあらゆるものと有機的に結びつき、山という全体に編み込まれた「全てなる山」のひとつの姿なのだ。そうした視点をもって何気ないこのくだりを読むとき、この花輪は特別な輝きを放ち始める。つまり、平凡で日常的なものが、普遍的なものとして輝き始めるのだ。何よりも、本書がケアンゴームという特定の山について書かれた本でありながら、特殊な場所の話にも、山の話にもとどまらず、時代も地域も超えた普遍性を持ちえた話となりえているという事実が、その証であろう。
ケアンゴームの「全てなる山」を描き出すことを通じて、他者を理解するということについての、ひいては世界を知ることについての方法を示した本書は、ケアンゴームの自然のみならず、この世界のあらゆるささやかな生に捧げられた賛歌なのである。
Copyright © ASHIBE Miwako 2022
(筆者のご同意を得て抜粋転載しています。なお
読みやすいよう改行を加えるなどしています)