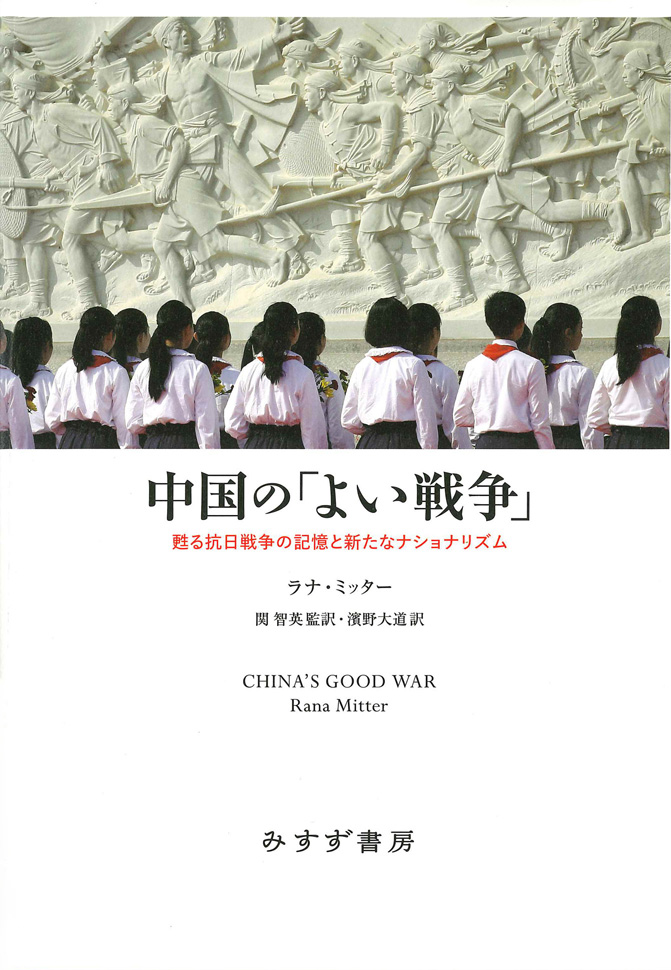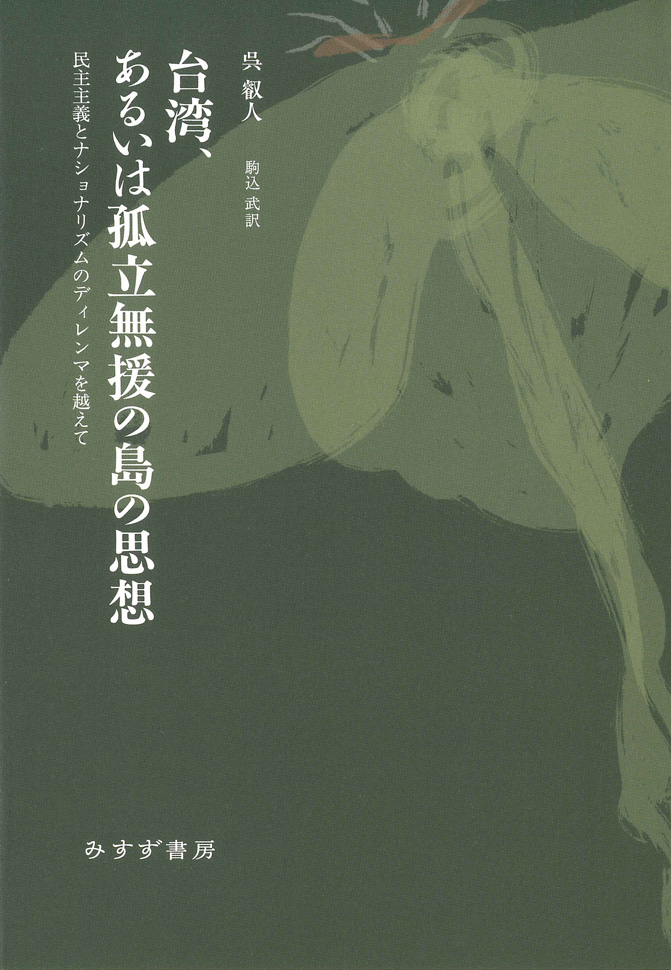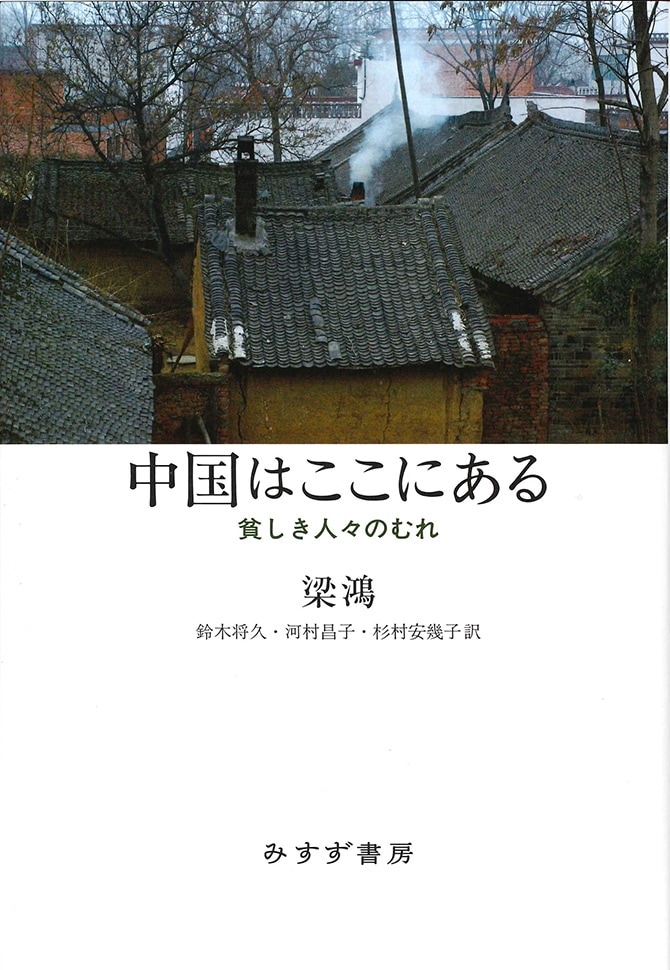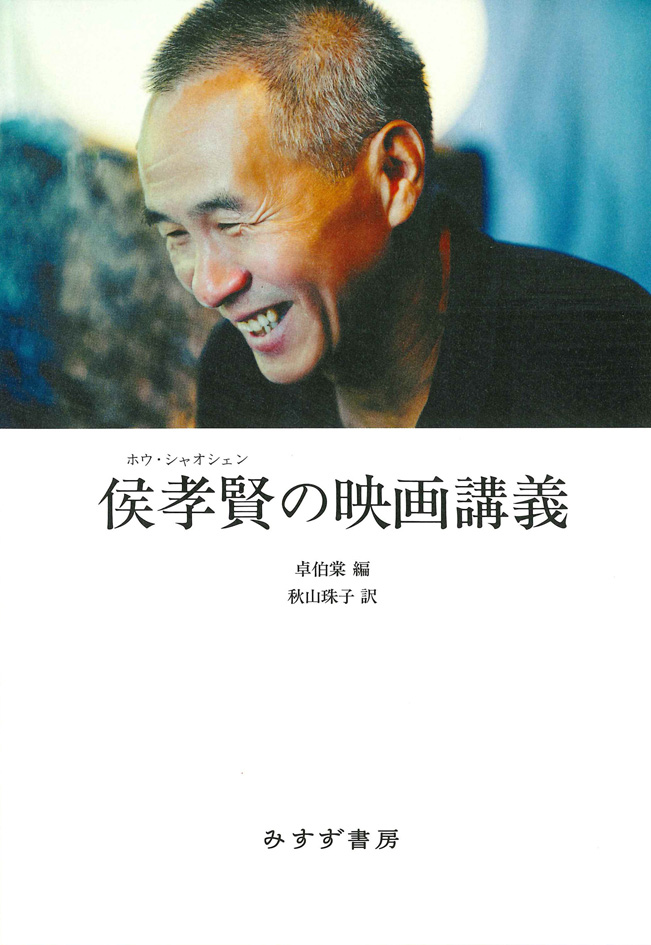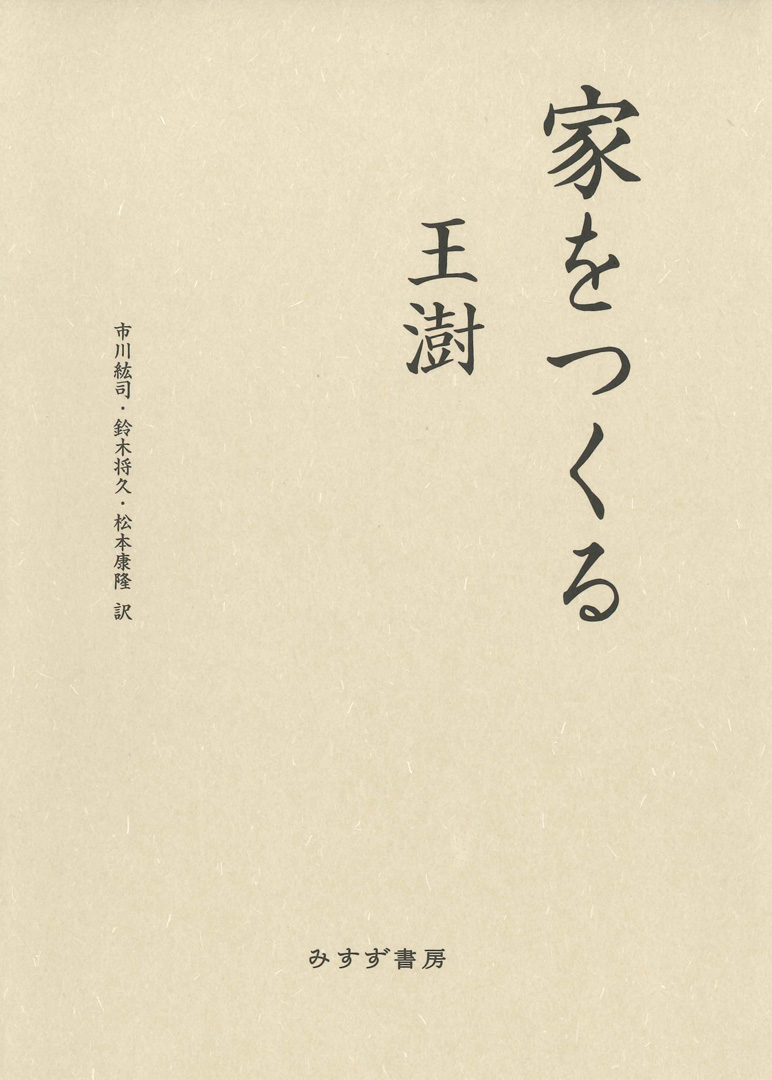倉田明子
本書は三聯出版(香港)有限公司の「古今香港シリーズ」第1冊として刊行された魯金『九龍城寨史話』(1988年刊)を題名のみ改めて復刊した、「香港文庫・新古今香港シリーズ」第1冊『九龍城寨簡史』(2018年刊)の日本語訳である。著者の魯金(1924-95年)は、本名は梁濤といい、本書での筆名である魯金の他にも魯言や夏歴など多くの筆名を持つ。マカオ生まれの広東人で、ジャーナリストとして新聞業界で働きながら、戦後定住した香港で郷土史家として多くの著作を残した。「古今香港シリーズ」全体の編者も梁濤である。
本書は、植民地香港の中にありながら香港政庁もイギリス政府も中国政府も管轄することができなかった「三不管(サンブーグアン)」の地、九龍城寨の歴史を述べたものである。九龍城寨は日本では「九龍城」「九龍城砦」と呼ばれ、独特の人気を集めてきた。日本人の「九龍城」イメージと言えば、ビルにビルを重ねたような異様な外観、薄暗い路地、無法地帯、「魔窟」……などではないかと思う。香港返還前後には日本でも九龍城の写真集や関連書籍がいくつも出版された。川崎には九龍城内部の様子を再現した館内装飾で話題を呼んだゲームセンターもあった(ウェアハウス川崎「電脳九龍城」、2019年閉店)。そんな九龍城好きの方々が本書を手に取ってくださっているだろうか。
ただ、本書は日本の九龍城イメージとは少し離れ、アヘン戦争以前の中国辺境の防衛拠点だった時代からその歴史を説き起こす。1842年、南京条約によって香港島がイギリスに割譲され、植民地香港が誕生すると、九龍城寨は香港監視拠点としての役割も担うことになった。その後、第二次アヘン戦争の結果1860年に結ばれた北京条約で香港島対岸の九龍半島(界限街以南)も割譲され、さらに1898年に新界租借条約によって深圳河以南の地域と周辺の離島(新界)が99年の期限で租借地となる。九龍城寨は新界の中にありながら、新界租借条約によって中国の管轄が認められた陸の孤島だったが、新界租借からほどなくして清朝の実質的な管理下を離れてしまう。以来、九龍城寨はその特殊な位置付けゆえに中国の歴代政権とイギリス政府との間でしばしば外交問題となってきた。
しかし戦後、新界の租借期限となる1997年に向け、香港の扱いをめぐってイギリスと中華人民共和国の間で交渉が重ねられ、1984年12月19日に発表された中英共同声明によって、香港島と九龍半島を含む香港全体の主権が1997年7月1日にイギリスから中国に移譲されることになった。香港返還が決まったことで九龍城寨をめぐる外交問題は消滅することが明白となり、返還前に香港政府が九龍城寨を解体し公園として整備することに中国政府も同意、1987年1月、香港政府は突如九龍城寨の解体を発表する。城寨内の住民の転居とそれに伴う補償問題などが現実味を帯びていく中で、完全に姿を消す前に九龍城寨の成り立ちから解体までの記録を残そうとしたのが本書である。
著者の梁濤は戦後の九龍城寨の歴史を自らの目でつぶさに「観察」した人物でもある。本書後半の「暗黒」時代の描写や解体決定後の城寨をめぐる様々な記録の残し方にはジャーナリストとしての梁の手腕が光っている。一方本書の前半では広範な歴史資料を引用しながら、九龍城寨の歴史的変遷が述べられている。ただし、著者は歴史学研究者ではないため、史料の選択や解釈には学術的な厳密さ、正確さを欠く部分もある。訳出にあたっては可能な限り史料の原典に当たり、細かな文言や引用箇所の誤りは権利者の了承を得た上で訂正した。また、原書には著者の事実誤認や誤解と思われる記述も散見されたが、日本語版では適宜訳注をつけたほか、場合によっては権利者の了承を得た上で改訳ないし割愛している。
訳者としては、本書を通して読者の方々に歴史学的な正しい知識というよりは、梁濤が本書執筆にかけた情熱や動機を感じ取っていただければと願っている。そのためにも、本書の刊行および復刊の経緯と背景について若干の解説を加えておきたい。
本書を収めた最初のシリーズである「古今香港シリーズ」の刊行前に、梁濤は『香港掌故』シリーズの執筆、編纂を開始し、1977年から1991年にかけて計13巻を刊行している。どちらのシリーズも香港の歴史にまつわる逸話や資料を紹介する内容で、これらのシリーズの刊行を呼び水に、以後香港では数多くの香港史にまつわる書籍が出版され続けてきた。香港史にまつわる逸話集のような書籍は戦前からその系譜はあるものの、これほど息の長い香港史出版ブームが続いている理由は、やはり香港返還の決定とその後の香港の歩みと無関係ではないだろう。
戦後の香港史を振り返っておけば、1940年代末以降、内戦や政治的混乱から逃れるため、中国大陸から香港に大量の避難民が押し寄せた。急増する人口を抱えながら香港は経済発展を遂げ、独自の社会と文化を構築し、1970年代には市民の間に広く香港人アイデンティティが芽生えたと言われる。香港の街は、そこに暮らす人々にとっての一時的な滞在地ではなく、「家」になっていった。梁濤が香港史にまつわる逸話を熱心に集めた背景にはこうした香港市民の意識の変化がある。香港返還が決まり1997年へのカウントダウンが始まると、香港史への関心はさらに高まった。九龍城寨解体もまさにそのきっかけの一つであった。
他方で、香港の人々は自分達のルーツである中華文化や歴史に対しても愛着と誇りを持っていた。中国共産党政権への警戒や不安はあったとしても(そして本書第1版の刊行直後の1989年に起こった天安門事件はさらにその不安を増大させることになったが)、香港返還とは植民地からの脱却であり、文化的、歴史的な祖地への復帰であることは確かだった。本書において梁濤がイギリスに批判的であり、他方でアヘン戦争における清軍の戦いや後々の清朝及び中華民国の外交交渉を高く評価しているのにはそうした背景がある。香港人としてのアイデンティティと、中華の文化や歴史への誇りは矛盾するものではなかった。
返還後も香港市民の香港史への関心は薄れることはなかった。むしろ、新界の村落の伝統行事や郊外の自然環境の豊かさに都市部の市民が関心を示すようになるなど、香港独自の多様な歴史や文化、すなわち香港の「本土文化(「本土」は日本語の「地元」「地場」といった意味だが、徐々に「郷土」のニュアンスを帯びるようになった)」への関心が広がっていった。その結果として香港の歴史的な建造物や環境への保護意識が高まり、それらの保護運動が新たな市民運動を生み出すことにもなった。そして、こうした市民運動や民主化を求める社会運動が展開していく中で、2010年代に入ると若者を中心に香港中心主義的な新しいアイデンティティが顕在化する。中国とは異なる香港人のあり方や価値観を重視し、中国とは距離を置くタイプの香港人アイデンティティである。2014年の雨傘運動以降、こうした意識は一部の若者の間でさらに先鋭化していき、香港だけを自分たちの「本土」とみなし、中国大陸との関係性を否定ないし拒否する「本土派」と呼ばれるグループが台頭した。「本土」という言葉の持つ意味合いも変化したのである。一方で、この間、彼らの脱中国化の志向や多分に嫌中的な言動を許容できない層も顕在化してくる。こちらもまた一部は先鋭化し、従来の中華文化への帰属感に根ざした緩やかな「中国人」アイデンティティから、積極的な共産党政権支持派へとシフトしていった。
本書の復刊を含む2018年の「香港文庫・新古今香港シリーズ」はまさにこうした社会背景のもとで刊行されてきた。日本語版では割愛したシリーズ全体の「総序」で同シリーズの編者である鄭徳華は以下のように述べている。
今日では、われわれは意識もせずに香港はイギリス人がやって来たときはただの「一つの漁村」に過ぎなかったと言っている。こうした言い方は史実から見れば偏っており、しかもこのような誤りが若い世代に帰属感の錯覚を生じさせ、19世紀半ばにイギリス人がやって来たことで初めて香港の歴史が始まったという言説をいとも簡単に生み出し、歴史的変遷の過程が部分的に覆い隠されてしまったのである。したがって、古代の香港の歴史を理解することは、ある意味では、自分たちの社会と文化の根源を知り、今日香港が祖国に復帰したのが歴史の必然であることを知ることにもなる。そのため、「香港文庫」叢書においてわれわれが特に重視した主旨は、香港の19世紀中期以前の歴史を研究し、整理することに注力することであった。
新シリーズが本土派的なアイデンティティや香港認識への危機感から生まれていることがお分かりいただけるだろう。本書の復刊もその文脈の中に位置づけられたのである。
2019年、香港のほぼ全域を巻き込んで大規模な反政府運動が展開する中、運動の参加者、支持者の間で香港ナショナリズムとも言うべき強烈な感情が醸成されていった。本土派的な香港意識がより広範囲に共有されたと言ってもいいだろう。だが、コロナ禍を経て国家安全維持法のもとに置かれた現在の香港では、こうした感情を表出することはできなくなり、むしろ共産党政権下の中国に対する愛国心を表明することが明確に求められるようになった。今後は香港独自の歴史や文化に注目すること自体がタブー化していく可能性もある。香港史の出版ブームにもついに変化が訪れるのかもしれない。
香港がこうした状況にある中、香港史出版ブームの火付け役とも言うべき本書の日本語版が出版されることになったことは、訳者としては感慨深いものがある。本書翻訳の依頼を受けたのは2018年9月だったが、結果的に、目の前で激変していく香港の「今」と、それによって意味合いを変えていく「香港史」に向き合いながらの翻訳作業になった。「親中派」、「民主派」、そして「本土派」と、香港人の中での分断に注目が集まってきた昨今だが、本書の中に垣間見える香港愛は、そうした政治的スタンスを超えて今なお広く香港の人々の間に根付いているようにも訳者には思えるのである。
Copyright © KURATA Akiko 2022
(筆者のご同意を得て抜粋・転載しています。
なお読みやすいよう行のあきや改行を加えています)