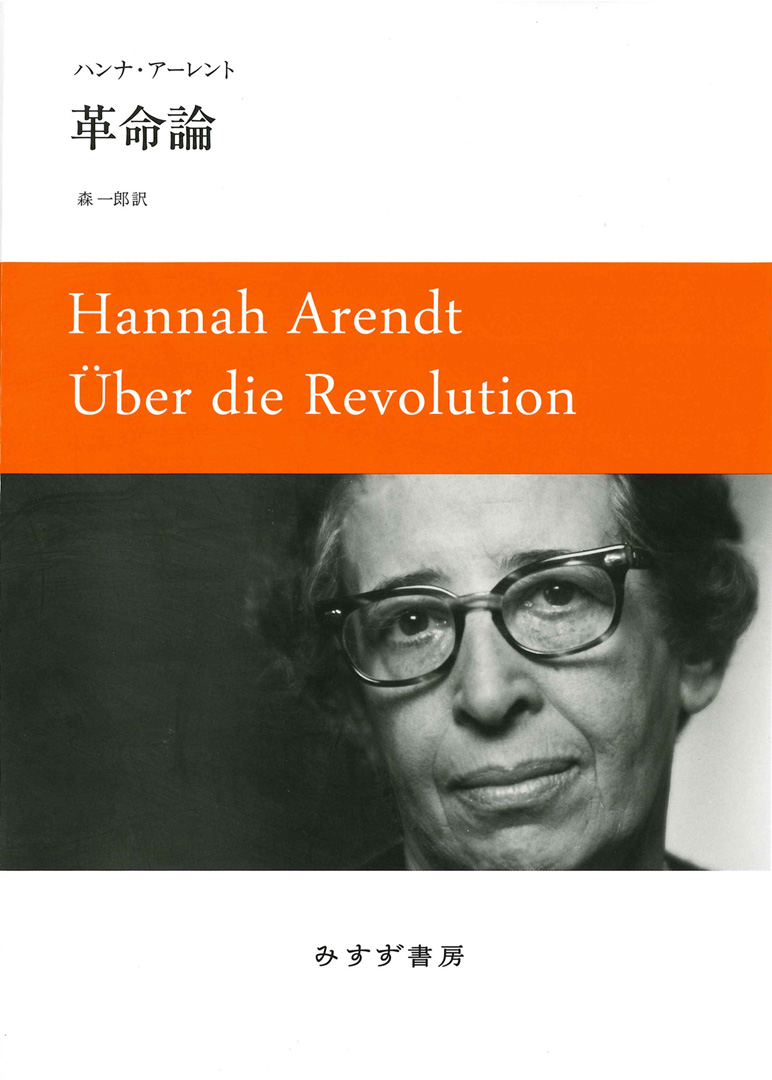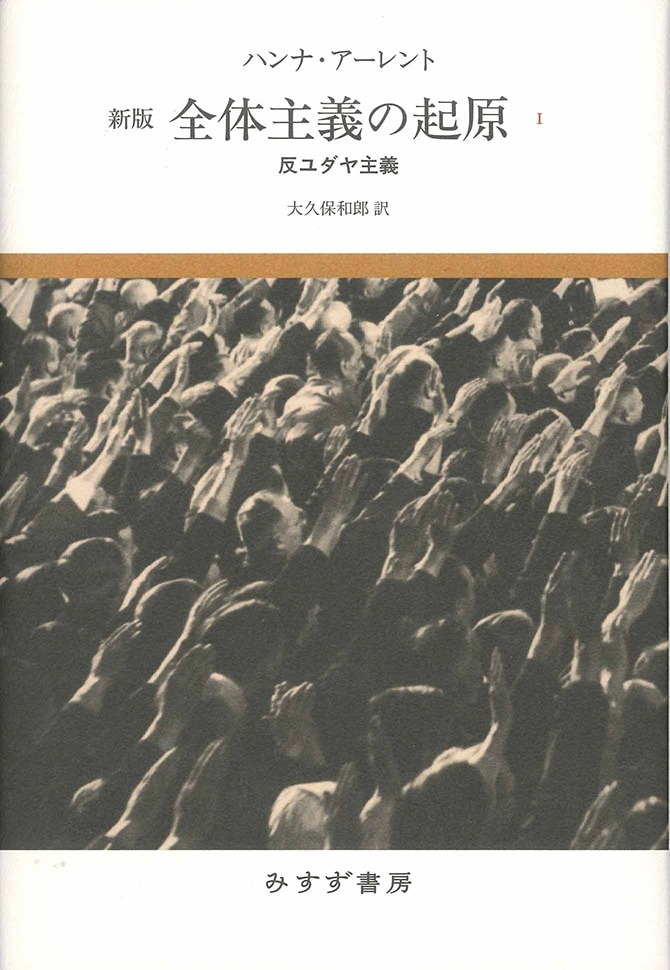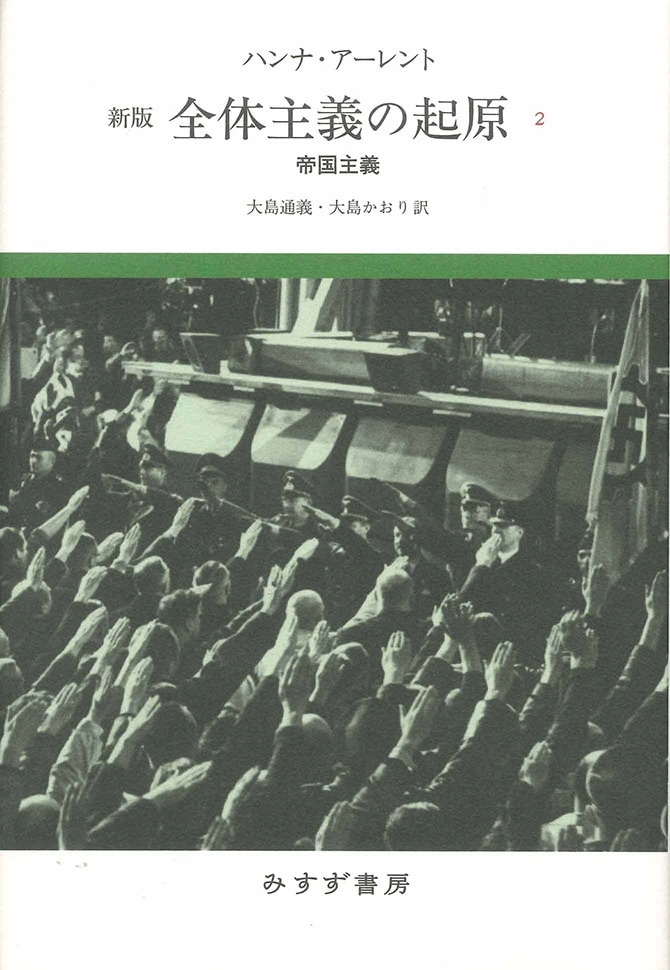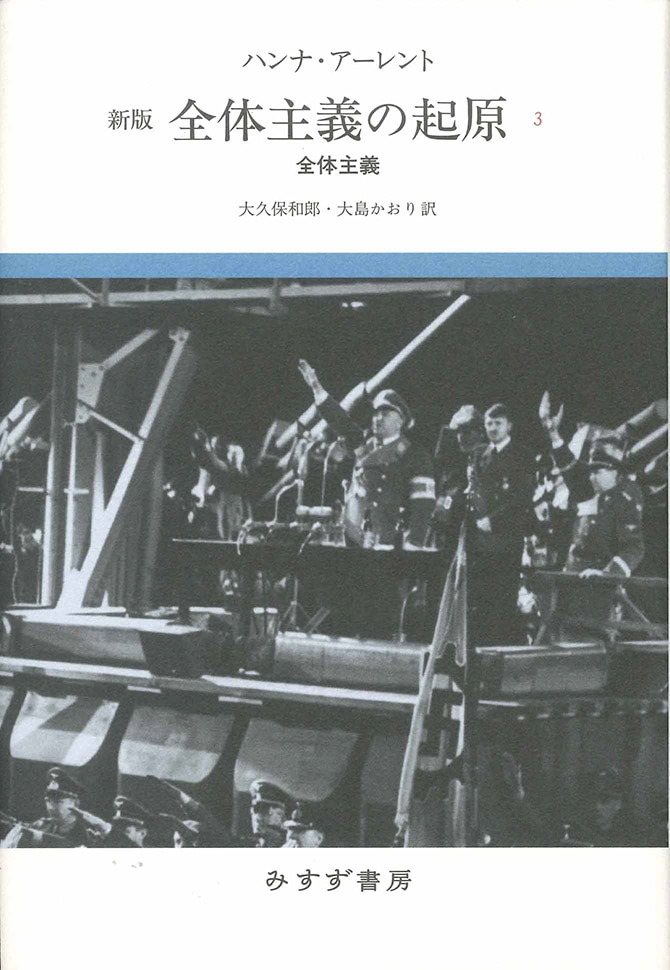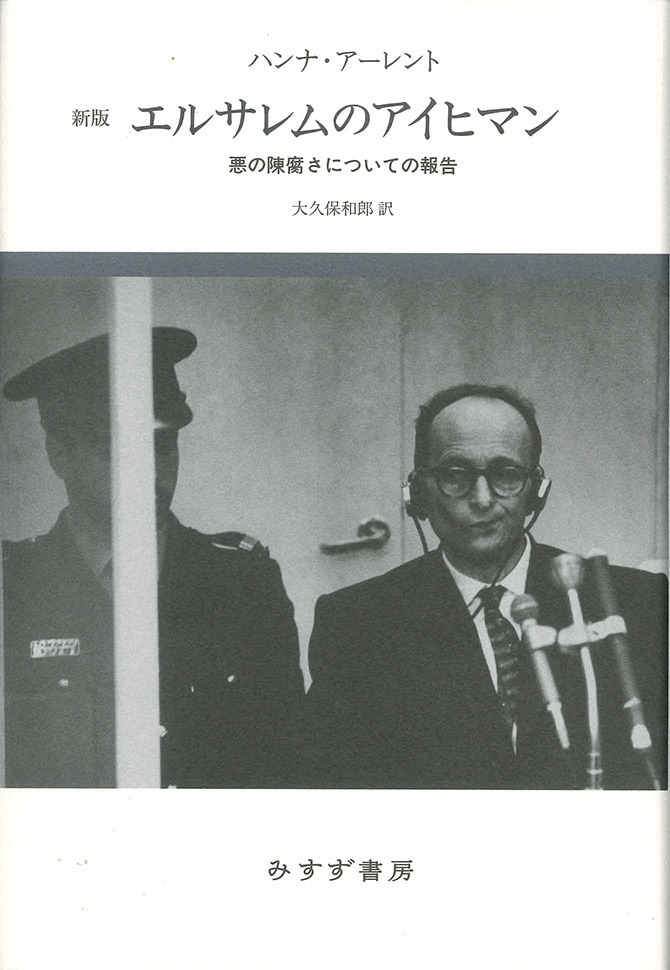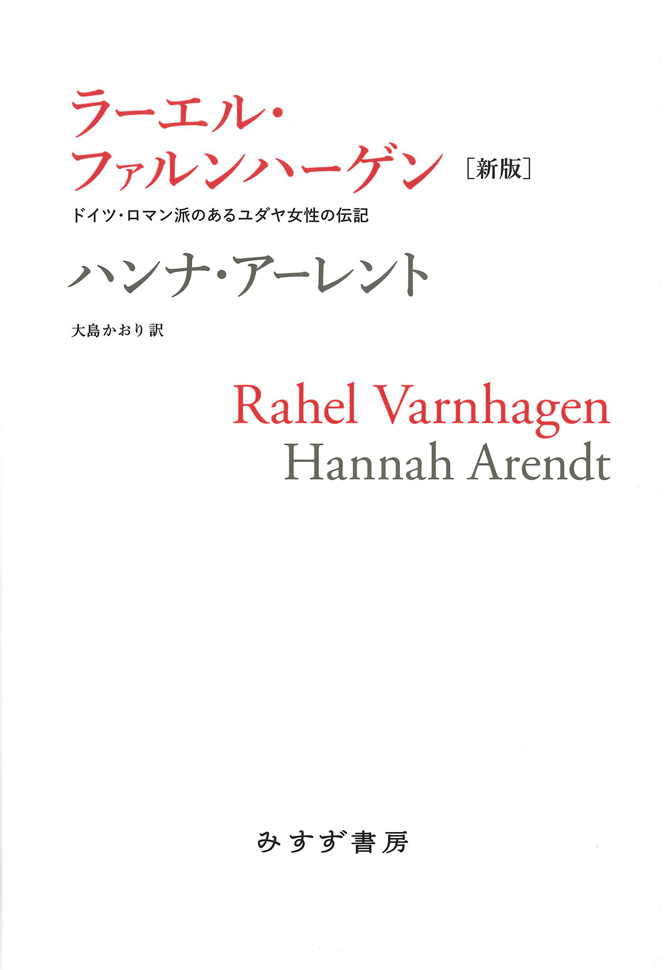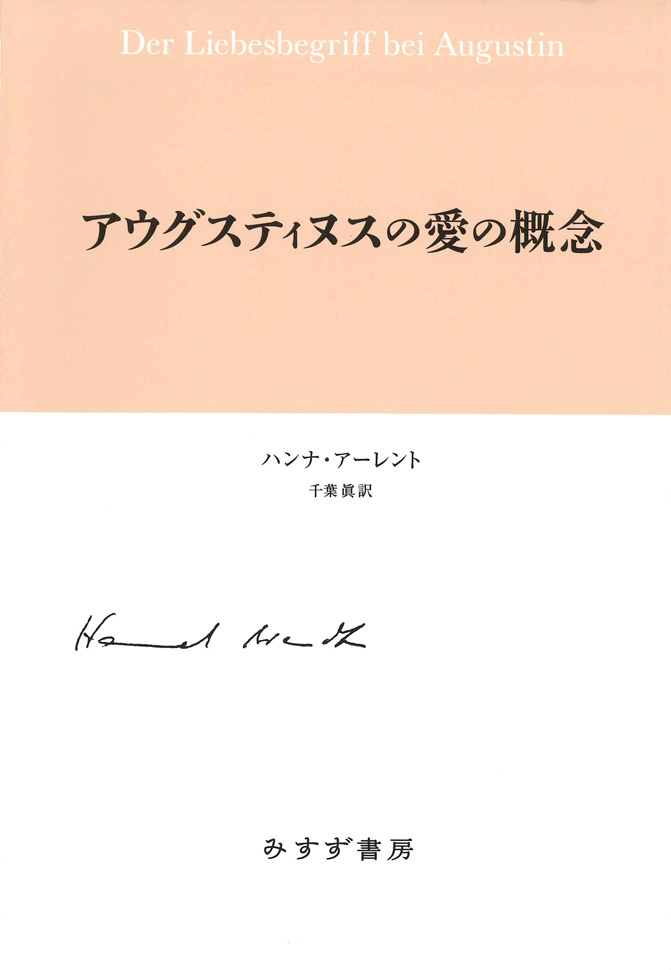本書『革命論』は、『活動的生』に続く、ハンナ・アーレントの第二の哲学的主著である。現代における政治哲学の可能性を拓くうえで頼もしい道しるべとなる20世紀の古典を、新訳でここにお届けする。
本書の英語版Hannah Arendt, On Revolution, 1963は、つとに志水速雄氏によって日本語に訳され、広く読まれてきた(『革命について』合同出版、1968年。改版:中央公論社、1975年。文庫化:筑摩書房、1995年)。しかしそれとは別に、ドイツ語版Über die Revolution, 1965から新たに訳すことに意義があると私は考え、『活動的生』の邦訳刊行(みすず書房、2015年)に続いて、翻訳作業に取り組んできた。
翻訳を進めていく中で、私は本書に、英語版からの既訳に付けられた書名『革命について』ではなく、ずばり『革命論』というタイトルを冠したいと考えるようになった。それはたんに英語版からの訳書と区別するためではない。本書がその内容からして、学問上の対象「について」論ずるものではなく、真っ向勝負で革命の本義を問う正真正銘の「革命論」の書だと確信するに至ったからである。むろん本書を読んだからといって革命を成し遂げられるわけではないが、新しい始まりを志向する者にとって不朽の洞察が本書にはちりばめられている。理論的かつ実践的な革命論があるとすれば、本書はまさにその名に値する。
その一方で、内容的には、英語版とドイツ語版にそれほど大きな違いはない。英語版と比べてドイツ語版のほうが『革命論』と題するにふさわしい、などと主張したいわけでもない。にもかかわらず、ドイツ語版からの翻訳にこだわる理由は、アーレント本人が母語に訳したテクストには、著者自身が訳すさいに言い換えたり敷衍したり付加したりした箇所が夥しくあり、面目を一新したそのテクストに日本語からアクセスすることができれば、それだけ日本の読者が本書の内容を理解するのに役立つと思われるからである。
英語版とドイツ語版との記述上の違いは、挙げればキリがない。明らかに有意と思われる相違点のある箇所にかぎって、訳注で指摘するようにした。その概略のみここに記す。
形式的にいちばん目立つのは、章のタイトルの違い、節分けの違い、とりわけ段落分けの違いである。段落数は、総じて英語版よりドイツ語版のほうが多い。ドイツ語版では記述が膨らんで、一つの段落が長くなり、改行する必要が出てきたためであろう。増量の目安にもなると考えられるので、節ごとの段落数の英・独版の違いを、訳注で逐一明示しておいた。ドイツ語版にのみ見られる原注のうち、重要と思われるものも、注記しておいた。本文のドイツ語版での加筆箇所も、とくに注目に値するものは指摘するよう心がけた。逆に、英語版のほうが充実した記述となっている箇所もあり、それがとくに目立つ場合には、訳注で英語版の当該箇所を訳出して補うようにした。
章ごとのドイツ語版の段落数増は、次の通り。序論:1増。第一章:4増。第二章:2増。第三章:1増。第四章:14増。第五章:20増。第六章:14増。本書後半に増補が著しいことは、この数字から明らかであり、それは、第五章と第六章では節が一つずつ増やされていることからも歴然としている。
最も顕著なのは、訳注にも記しておいた通り、第五章の締めくくりの箇所である。ドイツ語版には、英語版になかった2段落が丸ごと、章の最後に付加されている(本訳書279-280頁)。「誕生性」が論じられているこの注目すべき箇所については、拙論「誕生、行為、創設――アーレント『革命論』における「始まり」について」(『思想』第1141号、2019年5月、岩波書店、所収)で取り上げたので、参照されたい。ドイツ語版『革命論』成立事情についても、拙論で少し触れておいた。
ここで気になるのは、英語版『人間の条件』とそのドイツ語版『活動的生』との違いと、本書の英語版とドイツ語版との違いを、同じように考えてよいか、という点である。
拙訳『活動的生』の「訳者あとがき」にも記したように、アーレントは『人間の条件』をまずシャルロッテ・ベラートにドイツ語訳してもらい、その下訳に大幅に手を入れて刊行している。これに対して、『革命論』はアーレントみずから英語版をドイツ語訳して仕上げ、刊行するに至っている(vgl. Hannah Arendt, Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk, mit einer vollständigen Bibliographie, herausgegeben von Ursula Ludz, Piper, 1996, S. 290 u. 300)。これだけ聞くと、アーレントが独力で訳出した『革命論』のほうが、テクストとしての価値が格段に高いようだが、話はそう単純ではない。
アーレントはヤスパース宛書簡の中で、英語版On Revolutionをドイツ語に翻訳する作業に難渋したことを、溜め息混じりに洩らしている(1962年7/8月頃書簡と9月17日付書簡および1963年2月8日付書簡、『アーレント=ヤスパース往復書簡 3』大島かおり訳、みすず書房、2004年、17頁と19頁および40頁を参照)。友人に下訳を作ってもらい、それに手を入れるのは自他ともに大変だったから、今度は最初から自分で訳そうとしたが、じつはそのほうがよほど大変だった、という事情であったと察せられる。著者兼訳者の難渋ぶりがテクストに反映して、ドイツ語版の読者もまた難渋する、といった具合なのである。アーレントなりにドイツ語ならではの記述にしたいという意気込みが伝わってくる反面、よどみのない平明な訳文というわけにはいかず、そうでなくても屈折した内容のうえにドイツ語の表現としての韜晦が重なり、迷宮のようなうねうねした叙述が続くことになる。
翻訳ではふつう、訳者が原文を勝手に変えたり加えたりすることは許されない。ところが著者がみずから訳す場合には、そういう改作や翻案がいくらでも可能である。独立した作品として認められるからである。ただしそれが気楽な作業とはかぎらない。往年の公刊著作を再刊するさいに著者が改訂を施すのと違って、母語でない言語で書き上げたばかりの書物を本人がまた一から母語に訳し直す場合、改変や増補をそこに入れ込もうとこだわり始めるや、際限がなくなる。訳者アーレントのそういった思い入れが押し合いへし合いしているドイツ語版『革命論』は、それゆえ、語の正当な意味で、著者自身による「超訳」と言ってよいテクストなのである。
『活動的生』の場合、『人間の条件』をドイツ語に直してもらった下訳に加筆するだけで済んだ分、まだしもゆとりがあり、比較的のびのびと増補改訂作業にいそしむことができたのではないかと推測される。これに対して、『革命論』の場合、英語をドイツ語に直すという基礎作業のうえに、著者としての練り直しや書き足しの追補作業もこなさざるをえず、ドイツ語の文章をなめらかにする余裕に乏しかったのではと憶測されるくだりも散見される。そう言ったからとて、ドイツ語版『革命論』のテクストの価値を減じることにはならないだろう。曲がりくねった論述の滋味を含めて、著者ならではの秀逸な翻訳作品に仕上がっていることは誰の目にも明らかなのだから。
私は『活動的生』の訳者あとがきで、ドイツ語版Vita activa oder Vom tätigen Lebenを、英語版The Human Conditionの「増補改訂第2版」と呼んだ。これと対比して、ドイツ語版Über die Revolutionは、英語版On Revolutionの「オリジナルな超訳」と名付けたいと思う。
アーレントの苦心惨憺ぶりが表われている豪華絢爛たるテクストを、その屈折した味わいのまま日本語に生き生き再現することは、いかにして可能か――このほとんど見込み薄の問いにたえず悩まされて、私は翻訳作業に携わってきた。そうはいっても、日本語として読むに耐えない訳書を出すわけにはいかない。できるだけ通りのいい訳文にしようと、これでも工夫したつもりである。苦行が快感に変わる瞬間もまれにはあったと記憶する。訳者としては、茶目っ気たっぷりの皮肉屋の言葉遣いと息遣いを、日本語でいささかなりとも伝える訳文にしようと努めた。結果的にどの程度それが達成されているかは、読者諸賢の判断に俟つほかない。
2018年から、ドイツのヴァルシュタイン社から全16巻の予定で『ハンナ・アーレント批判的全集』の刊行が始まった(Hannah Arendt Kritische Gesamtausgabe, Wallstein, 2018-)。2021年12月現在、すでに3巻が出版されている。
第11巻のOn Revolution/ Über die Revolutionは、2024年刊行予定である。その巻担当の編者ロジャー・バーコヴィッチRoger Berkowitz氏は、アーレント夫妻の墓のあるアメリカ・ニューヨーク州のバード大学にあるハンナ・アーレント研究センターHannah Arendt Center for Politics and Humanitiesの所長であり、私が2018年夏に同センターを訪れたおりには、編集作業の抱負と苦心を語ってくれた。おそらく、英独対照鮮やかな文献学的価値に富む一巻が世に送り出されることだろう。英語版とドイツ語版の詳細な比較検討については、批判的全集版の刊行を待つべきである。私としては、『人間の条件』/『活動的生』に続くアーレントの主著が、英語版とドイツ語版のどちらも日本語訳で読めることになったことを、まずは喜びとしたい。