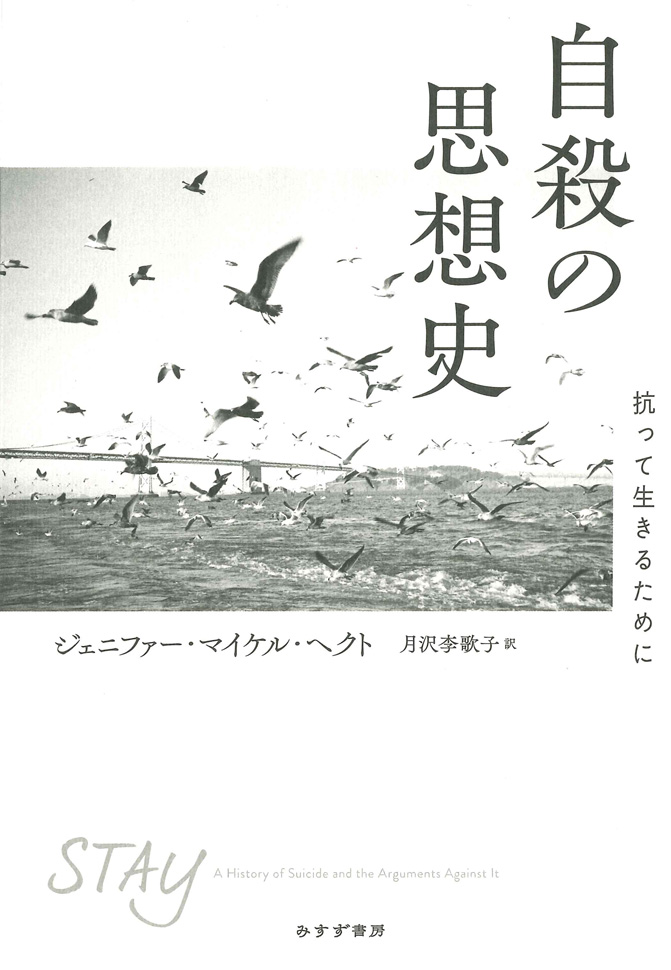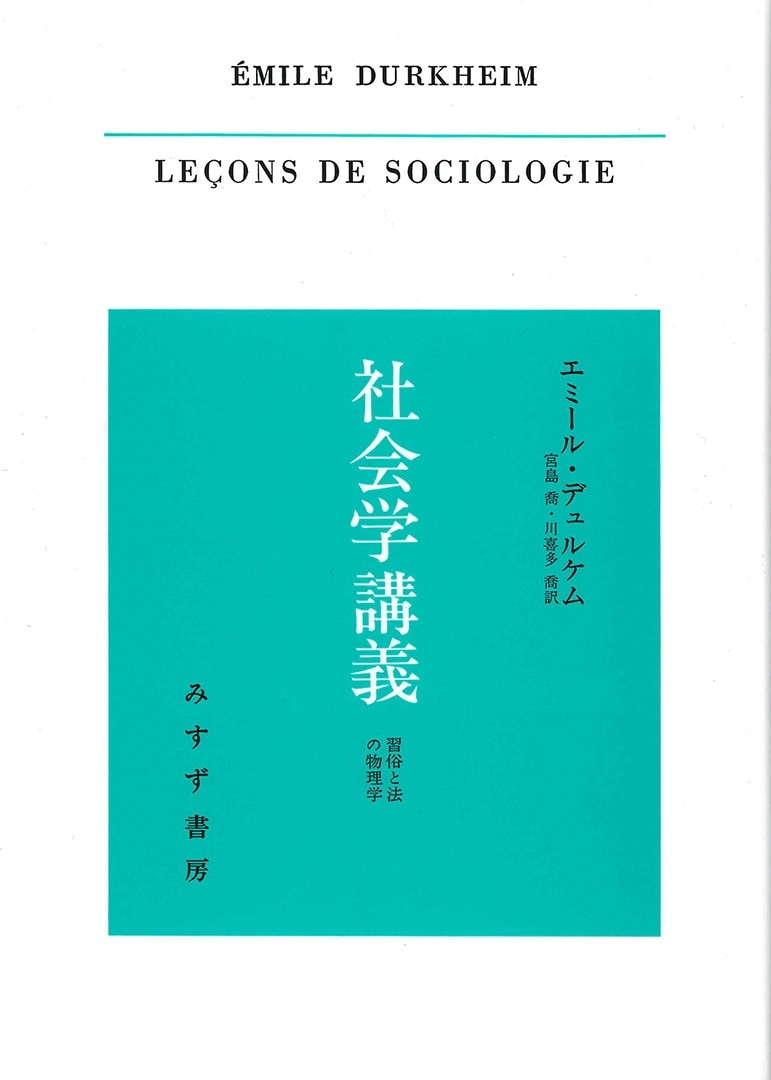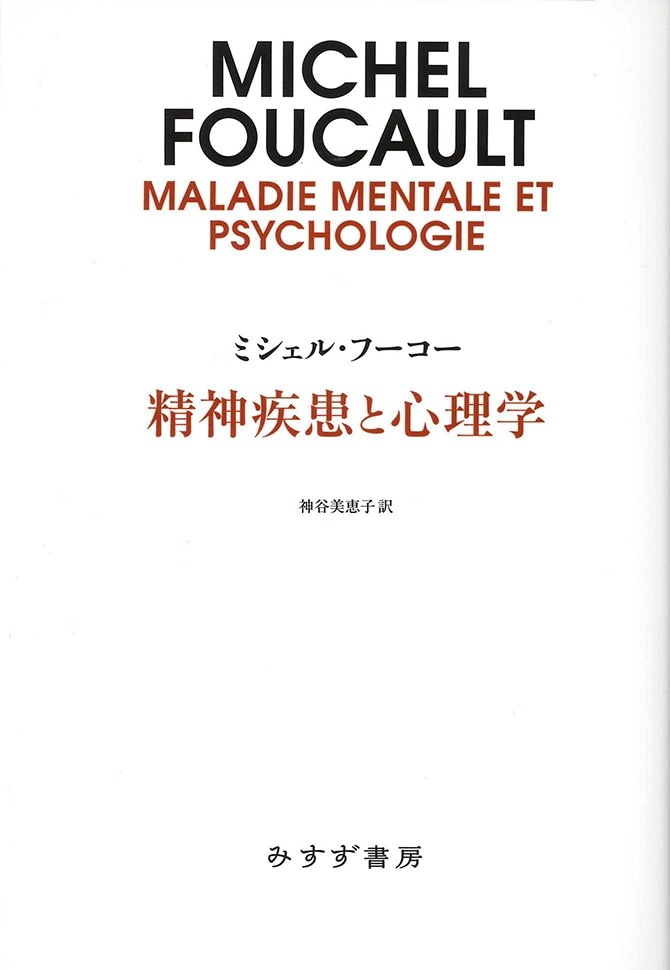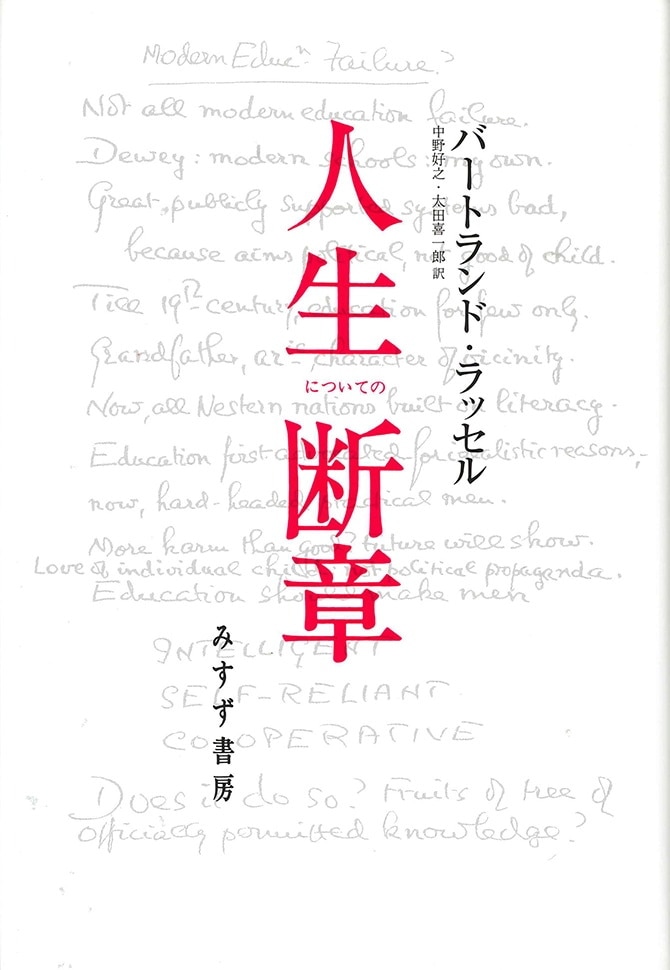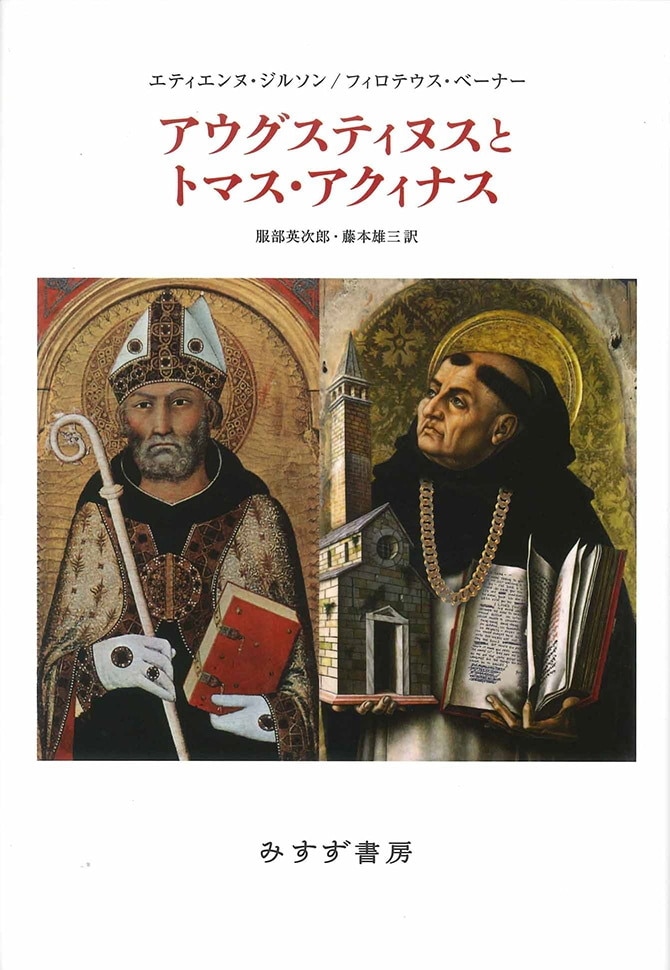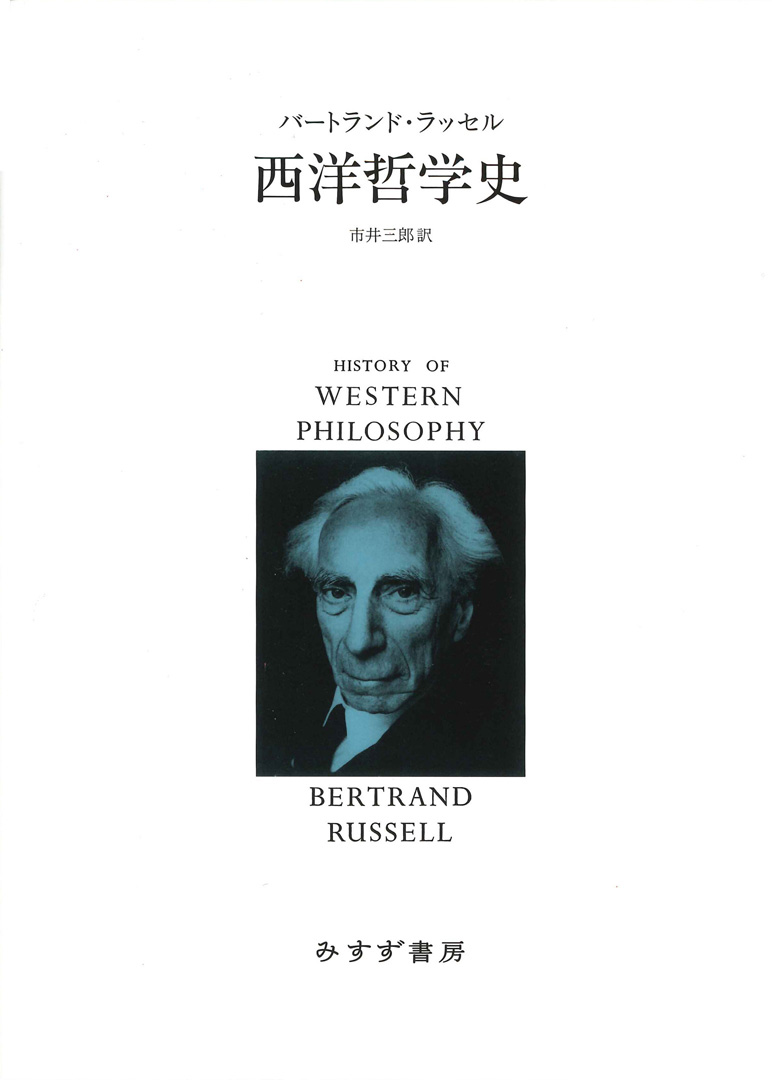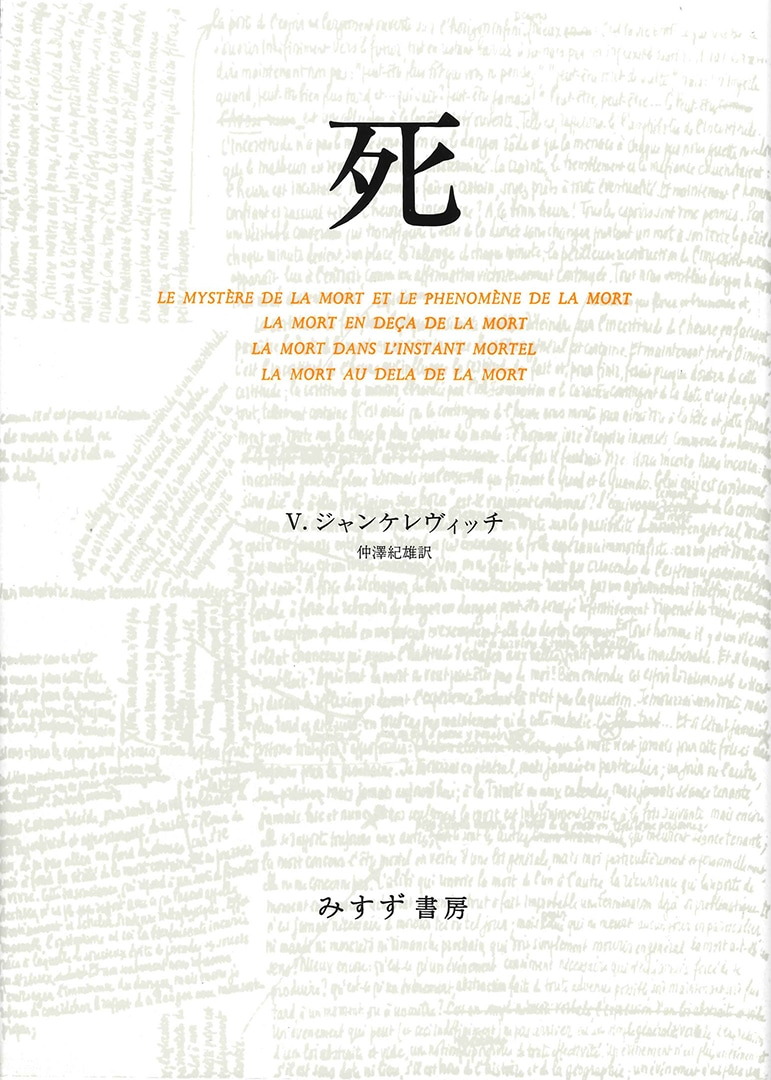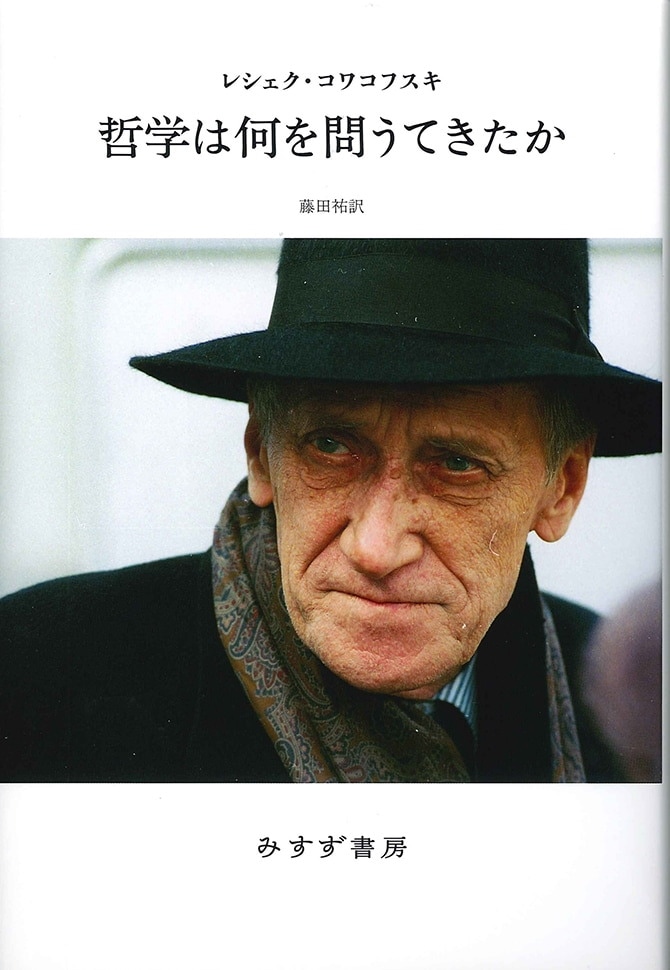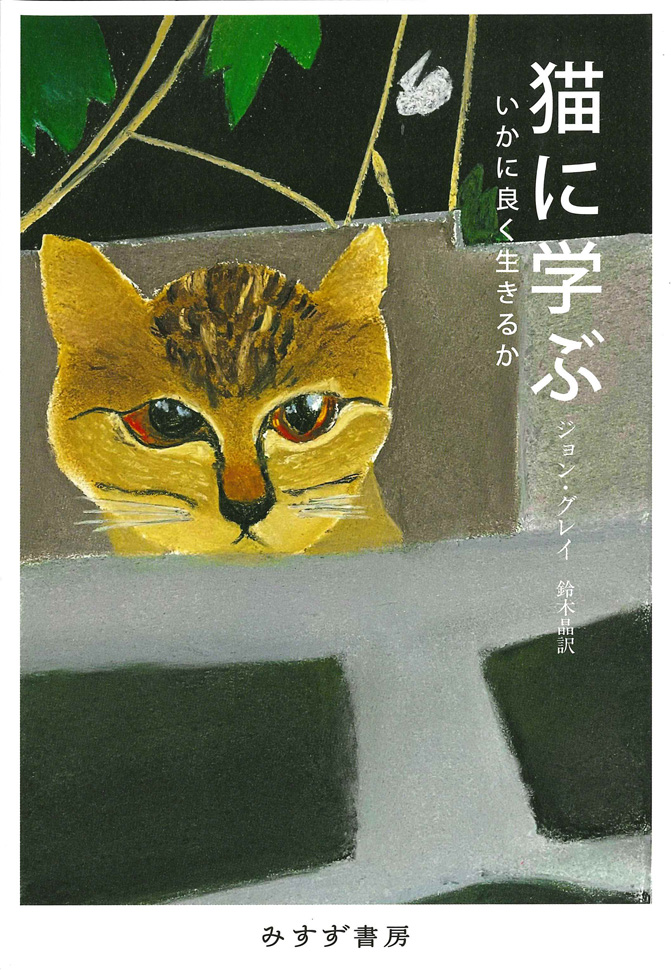「自殺」というテーマは、多くの人にとってなるべくなら触れたくないものだろう。けれども、身近な人や自分自身が、いつそれを考えないとも限らない。自殺は遠くにあるように見えても、意外にも近くにあったりする。
本書は、宗教や哲学思想、戯曲や文学から社会学まで文献を広く渉猟し、自殺がどう考えられてきたのかをまとめ上げた思想史の本だ。いわゆる「安楽死」のような話題は取り上げず、「絶望による自殺」に焦点を絞っている。
実在・架空を問わず、自死した人物の話題をさまざまに取り上げながら、社会や市井の人びと、作家や宗教者や哲学者が「自殺」をどのように考えてきたのかを紹介する。自殺の方法や遺体の無慈悲な取扱いを描写する記述もたびたびあるため、気楽に読める内容ではないかもしれない。さまざまな考え方が淡々と紹介されていく文章運びも手伝って、地味な本と評価されても仕方がないと思う。
ただ、本書は強かでシンプルな、一つのメッセージを込めて書かれている。それは「自殺をしないでほしい」というメッセージだ。
本書で指摘されることだが、「自殺をしてはいけない」とはっきり言うための根拠は、宗教的なものが中心になる。非宗教的な、比較的新しい思想に目を向ければ、自殺という選択を個人の自由や権利としてとらえる考え方のほうが目立つ。こうした状況にあっては、自殺を考えている人が、思いとどまるためのよりどころがないままに自らを手にかけてしまいかねない。それに、身近な人から自殺念慮を打ち明けられたとき、思いとどまるように促す言葉にも力がこもらない。著者はそんな状況を憂い、筆を執った。はっきりと自殺を否定するための根拠を思想史の中に探し、提示するためにこの本が書かれた。
理屈ではないかもしれない。本当に思い詰めて自殺を考えている人の耳には、思想が導いた「自殺をしてはいけない理由」は届かないかもしれない。それでも、こうした議論を知っておくこと、議論があると知っておくことだけでも、一つの抑止力になるのではないか。そしてなにより、「自殺をしないでほしい」という動機から綴られたメッセージには、なにか心を動かす力があるのではないだろうか。
本書に綴られる議論の積み重ねは、自殺に対抗する一つの武器であり防護壁である、と著者は述べている。それが必要な時に使えるかどうか、適切な仕方で使えるかどうかは、その時がやってこないとわからない。それでも、その武器/防護壁は手元に置いておいても損はないはずだ。