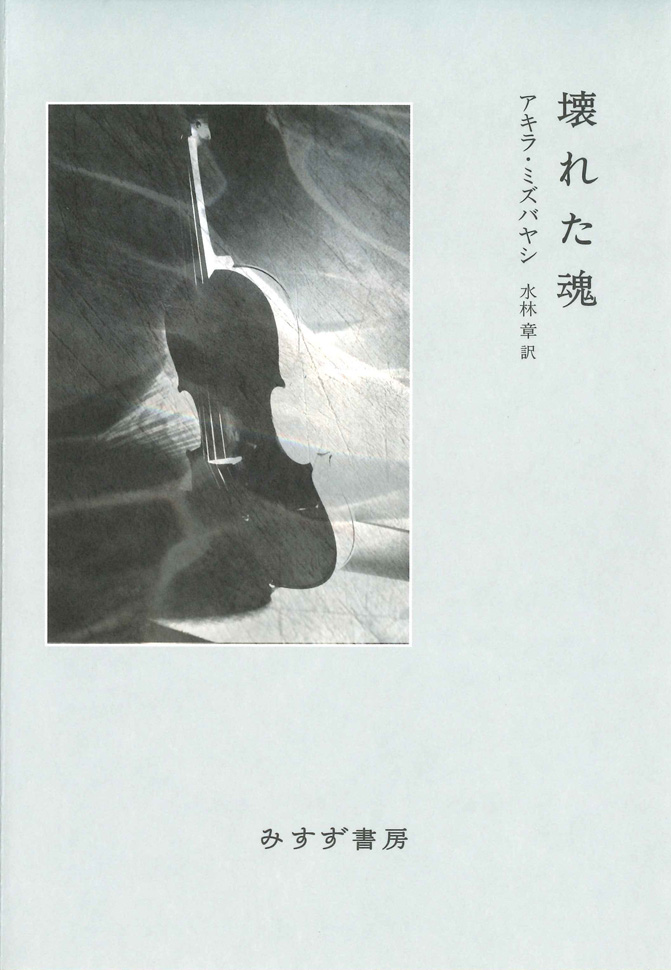2019年10月。ガリマール書店から刊行まもない小説Âme briséeの著者と読者の討論会が、パリの書店で開かれた。質疑応答の時間になり、どこに行ってもたびたび尋ねられる質問が参加者のあいだから出た時のことだ。
「あなたの本は日本語版も出ていますか?」
「これまでに出た7冊のフランス語の本のうち、日本では1冊も訳されていないのです」――著者の答えに、質問者が不思議そうな顔で席につくと、40人ほどの参加者の最前列に座っていたフランスでの生活が長い一人の日本人女性が、
「海外で認められないと日本では評価されないということがよくありますから、あなたのフランス語による著作が⽇本語に訳されるには、あなたがノーベル⽂学賞をとるか、あるいはあなたが死んでしばらく時間がたつか、そのどちらかだと思いますよ」
と言ったという。
「日本語に訳されることもないし、自分で訳すこともないだろうと思っていた」――刊行後、フランス国内で8つの文学賞を次々に受賞し、各国語への翻訳も進行中のベストセラー、Âme briséeの生みの親は、かつて淡々とこう言っていた。
「ぼくの書くものは、いまの日本ではまったくの異物ということは大いにありうることでしょう。主題的にも文体的にも。日本語版が出なくても不思議はありません」
そのアキラ・ミズバヤシの、フランス語で書かれた作品の初の翻訳が本書である。ふとしたきっかけでみずから翻訳の筆をとることになり、わずか2か月のちに、Âme briséeは水林章訳『壊れた魂』として生まれかわっていた。
(フランス語のタイトルにあるÂmeは「魂」という意味のほかに、弦楽器の表板と裏板をつないで楽器本体の内部で支えとなる「魂柱」と呼ばれる部品のこともさす。この二重の意味――壊れた魂=壊れた魂柱――は、日本語からは抜け落ちてしまうのだが)
日本とフランス、過去と現在を往き来しながら紡がれるこの小説の執筆と翻訳は、日本からフランスへ、フランスから日本へと、国を越え、言語を超えるそのつど、まるで文化の重訳とでもいえるような現象をくぐり抜ける。別な⽂化、異なる思想のあいだを往きつ戻りつして、やがて、異物であるものが異物でなくなり、最初から日本語で書かれた小説であったかのように感じられても、見えない深いところでは、異なる文化の地層が何重にもかさねられている。
自分にとっての「いま・ここ」と別な文化、異なる思想ということでは、もうひとつ不思議なことがある。
1951年生まれの著者は戦争を知らない世代。軍国主義の雄叫びが響きはじめた1938年の東京にはじまるこの物語の主人公、礼は、年齢的に著者とは重なろうはずもないのに、著者は、自伝的な要素はまったくないと思って書いた自分のフランス語の作品を訳してみて、はじめて「ここにはまぎれもなく自分がいるという感慨に打たれた」(訳者あとがき)。
⽗と⺟の戦争の記憶を受け継ぎ、実際には経験しなかった戦争に取り憑かれているようなところがある、と著者は言う。
戦争によって正気を失った世界が無残に壊したヴァイオリンと、その修復に一生を費やした男の物語が通奏低音として響くなか、礼をはじめ、何人かの登場人物の壊れた魂と、その再生と癒し、復活の物語が、長い時の流れのなかで奏でられる。
物語のなかで、「戦争」は露わにはその姿をあらわさない。私たちは、戦後何十年後のミルクールやパリ、東京、上海にくりひろげられるいくつかの人生を追いかける。そこに、激しさよりは静けさを、憎しみよりは愛を、傷よりはそこにそっと置かれる手のあたたかさを、感じる。それでいて、そこには、かつて「戦争」が壊したもの、喪われたものの悲しみもひそんでいるのだ。
「彼らの」文学が「私たちの」文学に生まれ変わった。日本では、どんな読者が、どんなふうにこの本を読んでくれるだろうか。