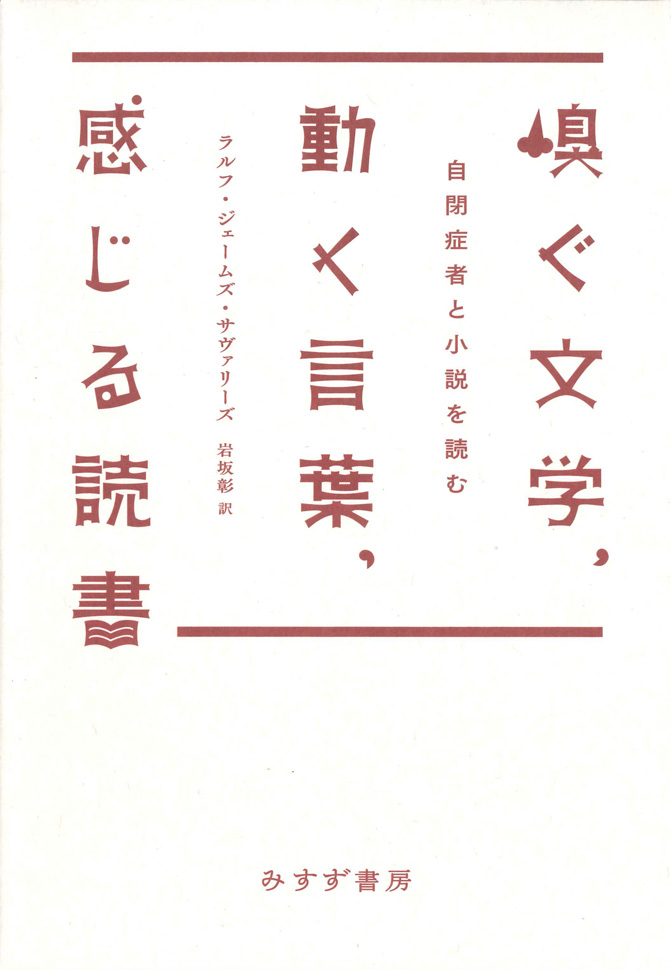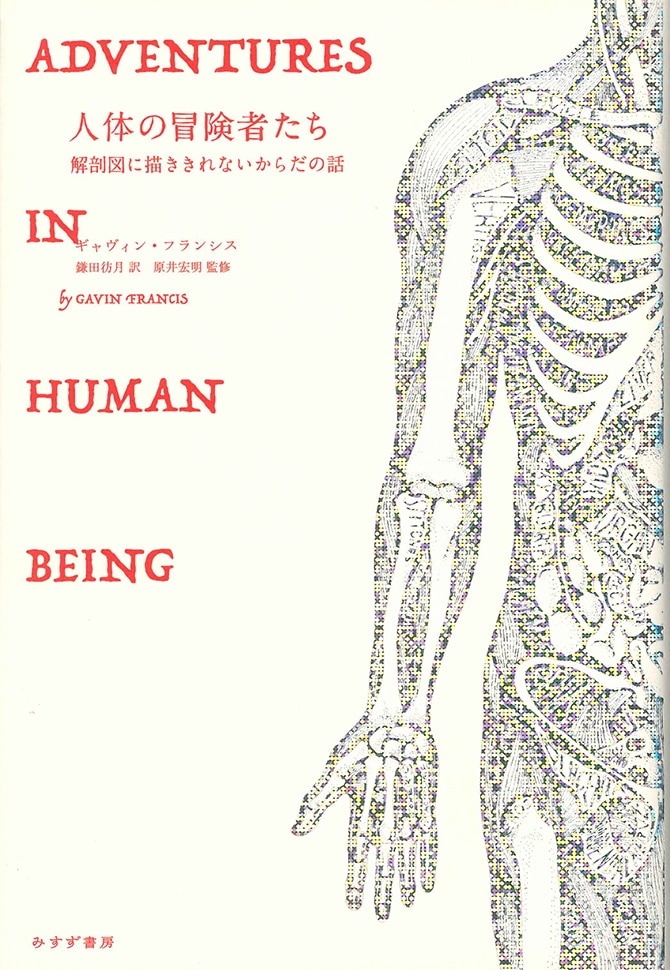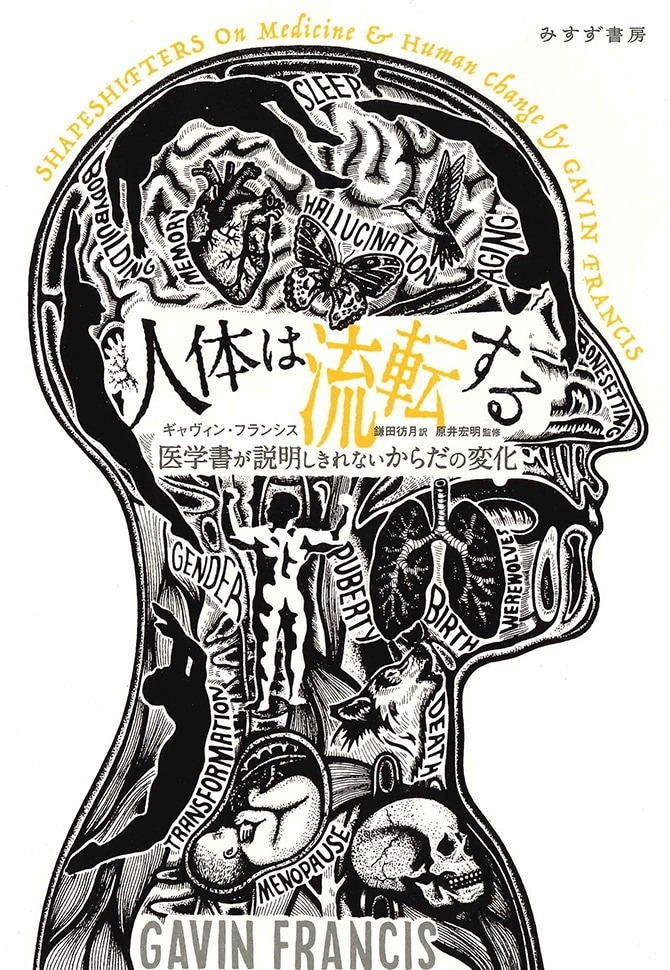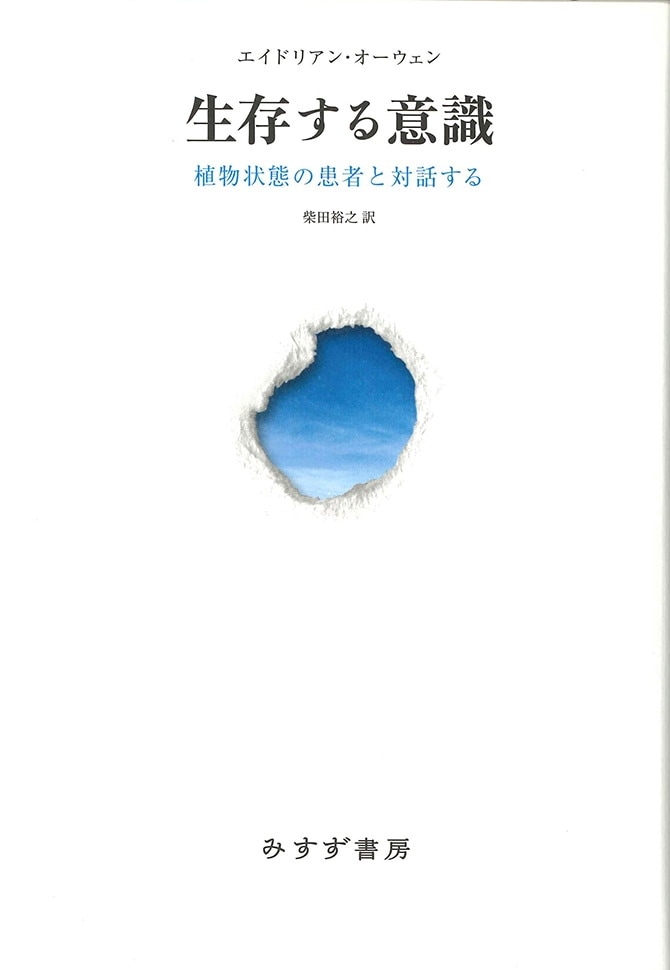幸せな記憶は、心の治療薬――翻訳を終えて
今、本書『海馬を求めて潜水を――作家と神経心理学者姉妹の記憶をめぐる冒険』が出版に至り、読み返してみて思うのは「人生は記憶でできていて、記憶とは人生そのものだ」ということだ。そんな当たり前な、と思う人も、そういえばそうだな、と思う人もいるだろう。でも完全に否定できる人はそんなにいないのではないかと思う。
そして本書を訳してみて、どれだけ自分の行動が深く記憶に左右されているかに気がつき、驚いた。
ほんのわずかな間だけ、目を閉じてこれまでの自分の人生を振り返ってみてほしい。どんな場面が浮かぶだろうか。嬉しいこと、楽しいこと、辛いこと、悲しいこと、どんな出来事が目の前によみがえってきただろうか。本書によると、人は過去に起きたことを想起する時にさまざまな新しい物事を経験した10代~20代の出来事を思い出しがちなのだという(本書でも紹介されるこの現象は、「レミニセンス・バンプ」というそうだ)。だから小学校の高学年から中学や高校、大学から社会人になって2~3年の間を思い出す人が多いかもしれない。
小学校の遠足、家族旅行、誕生日のケーキ、初めて友人同士で行ったカフェ、親や先生に叱られたこと、引っ越してしまう友人との悲しい別れ、立ち直れないほどの失敗、人生が終わるんじゃないかと思うほど辛い失恋などなど。20代なら、自分が必死でプレゼンした企画が通って商品化されたといった誇らしい記憶もあるかもしれない。その逆に、何度も練り直してプレゼンした企画が通らなかったことだってもちろんあるだろう。
こういった場面はもちろんあなたの記憶であって、いわば頭の中にあるハードディスク、そして思い出のアルバムだ。記憶のひとつひとつが私たちの人生を形づくり、私たちの魂の血や肉となっている。その中でも幸せな記憶は、私たちが本当に辛い出来事にあった時に心の傷を癒やし生きる希望を与えてくれる、ハッピーピルの役割を果たすのだそうだ。
さて、ではハッピーピルとして心を癒やしてくれるようなこういった記憶は、誰が作るのだろう。それは本人だけではなく、周りの家族だ。どれだけ楽しいことをしたとしても、どうやらその間にあった嫌な記憶、例えばアイスクリームを落としてしまった、騒ぎすぎて誰かに叱られたといった記憶の方が子どもの心には残りやすいらしい。ショッキングなことの方が脳に刻まれやすいのだ。しかもだいたい5歳くらいまでの記憶は幼児期健忘によって子どもたちの頭からはいつしか消えていってしまうという。こういった幼い頃の出来事を楽しい記憶として子どもに残してあげるにはどうしたらいいのだろう? それは周りの大人が幸せな思い出として、子どもに後から話してあげることなのだという。1歳の誕生日を迎えて、初めてのバースデーケーキを前にした時の子どもの様子、初めて子どもが立ったりおしゃべりをした時にどれだけ親が嬉しかったか、スキーに行って、子どもが初めて滑ることができるようなった時どれだけ親子で楽しんだか。そういった出来事はたとえ子どもの記憶から消えてしまっても、お母さんやお父さんの記憶には残るだろう。それを本人に話してあげることで、子どもは自分は楽しいすてきな人生をおくってきたんだと、ポジティブな想いを持つことができる。親から子どもへ、すてきな人生をプレゼントするようなものではないだろうか。そしてこうやって楽しい思い出を話して聞かせるのは、子どもがすっかり大人になってからでも遅くないのだという。このエピソードは、全ての親たちに希望を与えるのではないだろうか。夕飯を食べる時に、一緒に過ごした思い出をほんのわずかな時間語り合うことが、子どもたちの心の傷を癒やし、自信を与えるのだから。
または学校や幼稚園で、この方法をぜひ先生方に試してみてほしいと思う。学期や一年間の終わりに、クラス全員の名前をあげて楽しかった思い出を語り合う。ルールは絶対に誰のことも否定したり揶揄(やゆ)したりしないこと。それだけでその一年間は楽しかったと、子どもたちの心に残るのではないだろうか。(ちょっと脱線するが、娘の小学校時代にこれをとても上手に実践している担任の先生がいた。その前の学年の時に登下校中に娘に意地悪をしていた男の子が、この先生の下で同級生になり、なんと娘の折り紙仲間!になっていて大いに驚いた。自尊心が養われると、人はお互いに優しくなれるのかもしれない)
本書では未来方向への記憶についても紹介している。私たちは、将来のビジョンや計画、夢、空想を思い描く。この能力を持っているのはおそらく人間だけで、この能力があるからこそ、さまざまな発明が生まれ、文明が発展してきたとも言えるだろう。
ここでひとり、私の友人を紹介したい。私の翻訳パートナーのUさんという女性だ。Uさんとはもう20年来の付き合いなのだが、彼女との出会いは仕事とは関係なく、友人の結婚式だった。Uさんはスウェーデン出身で、私はスウェーデンの留学から帰ってきたばかりだったので、互いにスウェーデン語で挨拶を交わした。その後8年くらい経ってから、彼女のことをふと思い出して連絡を取った。赤ちゃんだった娘の世話をしながら産業翻訳の仕事をしていた私は、大量の仕事をひとりでこなすことに限界を感じていて、誰か翻訳パートナーになってくれる人を探していたのだ。
Uさんはかつて不思議なことを言っていた。彼女は、自分が叶えたいと思う夢はほとんど実現させることができるのだという。そのために寝る間も惜しんで努力をしたり、ツテを探したりしなくても。私が電話をした頃、Uさんも幼い娘さんたちを見ながら家でできる仕事はないかと考えていた。そんな折に私から連絡があったのだという。また彼女は常々スウェーデンと日本の文化の架け橋になりたいと思い、この二カ国の文化や制度を比較したり、生活のちょっとしたアイデアなどを紹介するブログを書いていた。いつかそれを本として出版したいと思っていた。すると彼女のブログを見た出版社の人から、本にしませんかと申し出があったのだそうだ。さらに不思議は続く。彼女は20代の頃、大物お笑い芸人さんがやっていた番組にたまに外国人枠で出演していた。そして子どもたちが大きくなって手が離れた頃、再びテレビ出演の機会を増やしたいと考えていたのだという。そうしたら外国人が出演する番組のレギュラーが決まる。彼女は特にどこかに営業をしたわけではないという。何か叶えたい夢ができたら、自分のノートに書くのだそうだ。そんな不思議なノートが欲しい、と思わず歌いたくなってしまったが、聞いた時には「羨ましいけど、そんなことある? まさかー」と話半分で聞いていた。映画の『デ◯ノート』の真逆で、ドリームノートとでも呼ぶべきか。「夢が叶うUの幸せドリームノート」と名前をつけて商品化したら売れるんじゃないか…というのは冗談だが。
だが本書を翻訳してみて、ひとつ腑に落ちた。本書の第3章に「人生脚本」という言葉が出てくる。人は子どものうちに、このまま人生が進んでいったらどうなるかといった予測をたて、自分の脳の中で脚本を作るのだそうだ。そして人生はだいたいその通りに進んでいくのだという。もちろんその脚本には、夢を叶えるためのキャリア形成も入っている。Uさんの人生脚本には若いうちに自分が母国を飛び出して外国に住むようになること、母国の文化と日本の文化を紹介するようにキャリア形成をしていくことが書かれていたのではないだろうか。そこで培われたキャリアに基づいて、新たな夢を描き、実際のノートに書き込むと同時に自分の人生脚本にも書き加えていった。彼女が本の出版やテレビ出演の仕事を得た時にはすでにキャリアは積み重なっていて、出版社側やテレビ局側のイメージに合う人間像になっていた、というわけだ。逆に人生脚本の方が、そろそろこういうチャンスがやってくるよとUさんにささやいていたのかもしれない(とはいえUさんの不思議なドリームノートがやっぱり欲しいなと思う自分がどこかにいるが)。
記憶はこれまで述べてきたように、過去にも未来にも働いて、私たちの人生そのものとなる。もちろんトラウマのような辛い記憶がよみがえってきて、心を傷つけることもあるが、それを幸せな記憶が癒やしてくれることもある。どこかパンドラの箱のようだ。人生を築いていく時の重要な材料であり、ふと振り返った時に抱きしめたくなるような大切な思い出だ。私たちが死ぬ前に振り返ったら、記憶の真珠が連なった美しいネックレスができているに違いない。
脳科学は一見難しく思えるかもしれないが、実は人生がちょっと幸せになったり、実生活に活かしていけたりするヒントがいっぱい散らばっている。『海馬を求めて潜水を』は、私たちが人生のヒントにできるような、記憶の話がギュッと詰まった宝箱のような本だ。もしかしたらUさんの件のように、これまで不思議に思っていた謎を解く、鍵が隠れているかもしれない。Q&A式に悩みに答えるように書いてあるわけではないが、作家と神経心理学者の姉妹が語るひとつひとつの逸話を読み進めていったら、ああ、これまで私が不思議に思っていたのはこういうことだったんだ、と理解できることがあるかもしれない。
脳の働きや記憶に興味のある人々、育児中の親御さん、ミステリー好きの人々が本書を読んで、記憶の働きを知り、読み終わった後には記憶をめぐる冒険をしてきたような気持ちになってくれたら、大変嬉しく思う。翻訳を終えて、訳者が1年間の長い記憶をめぐる冒険を終えたような気持ちになったように。
訳者を代表して
中村冬美
copyright © NAKAMURA Fuyumi 2021