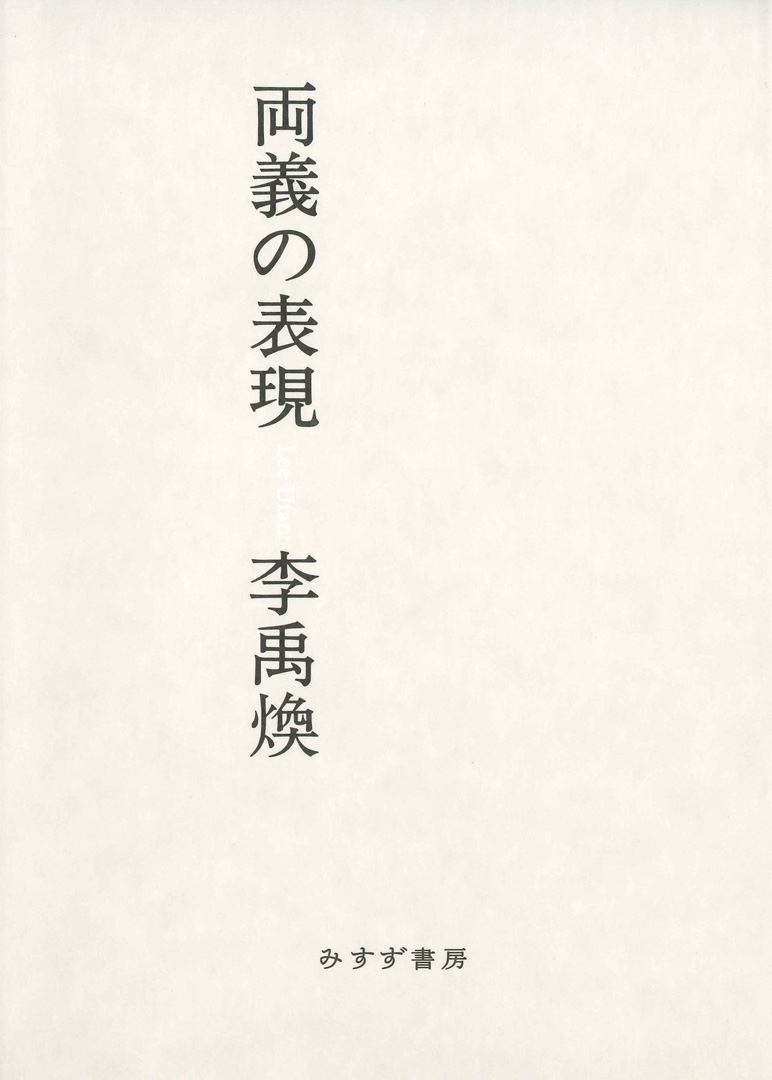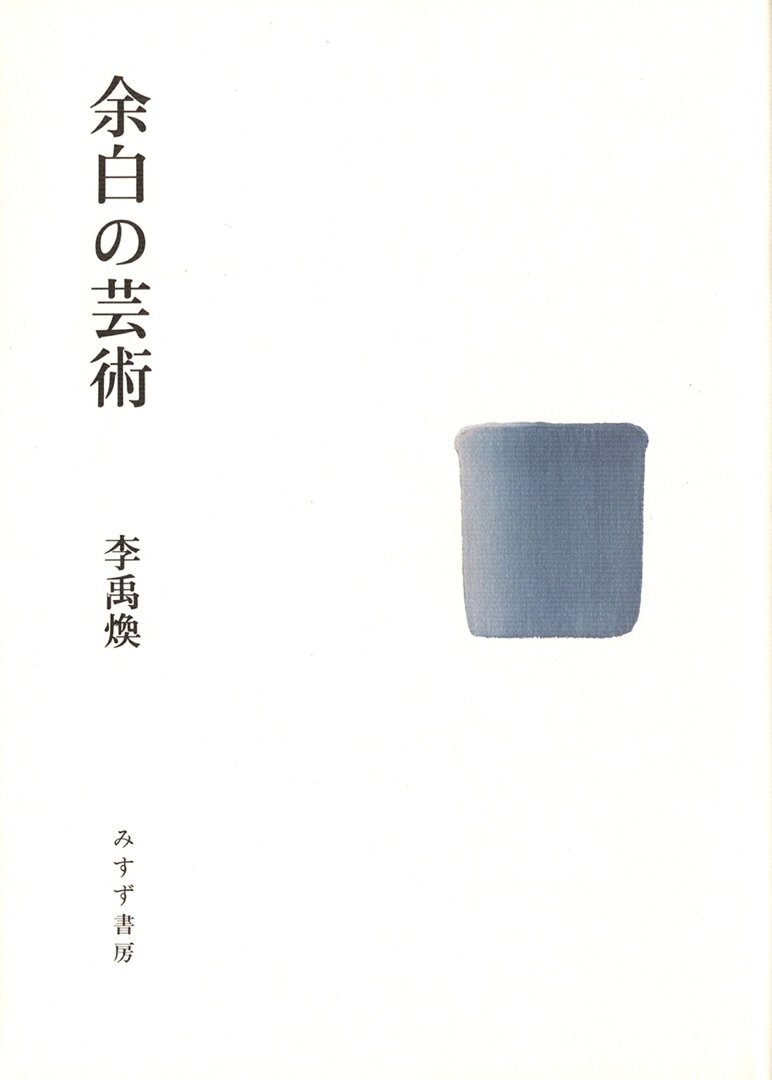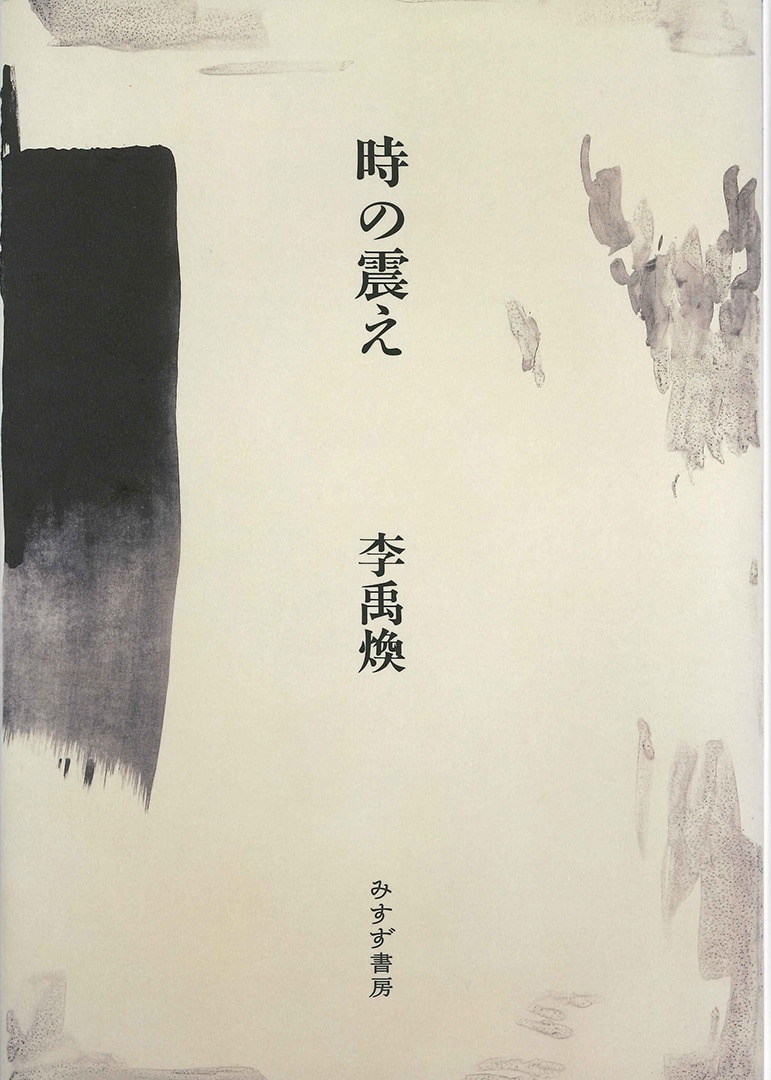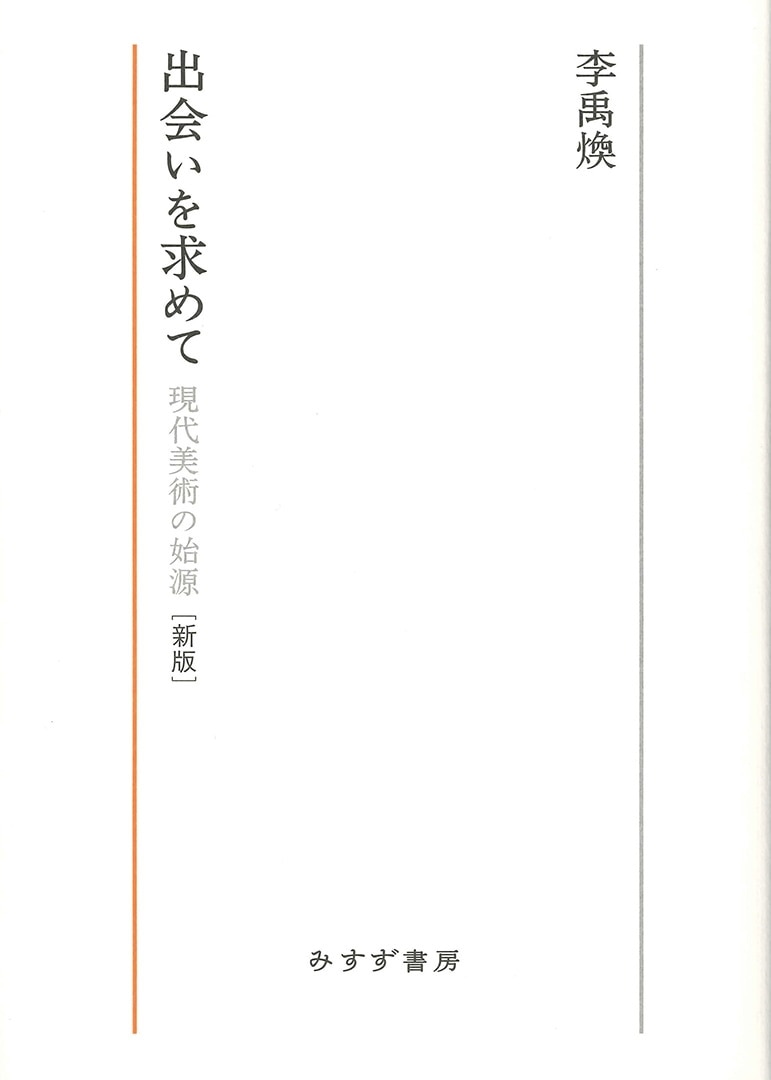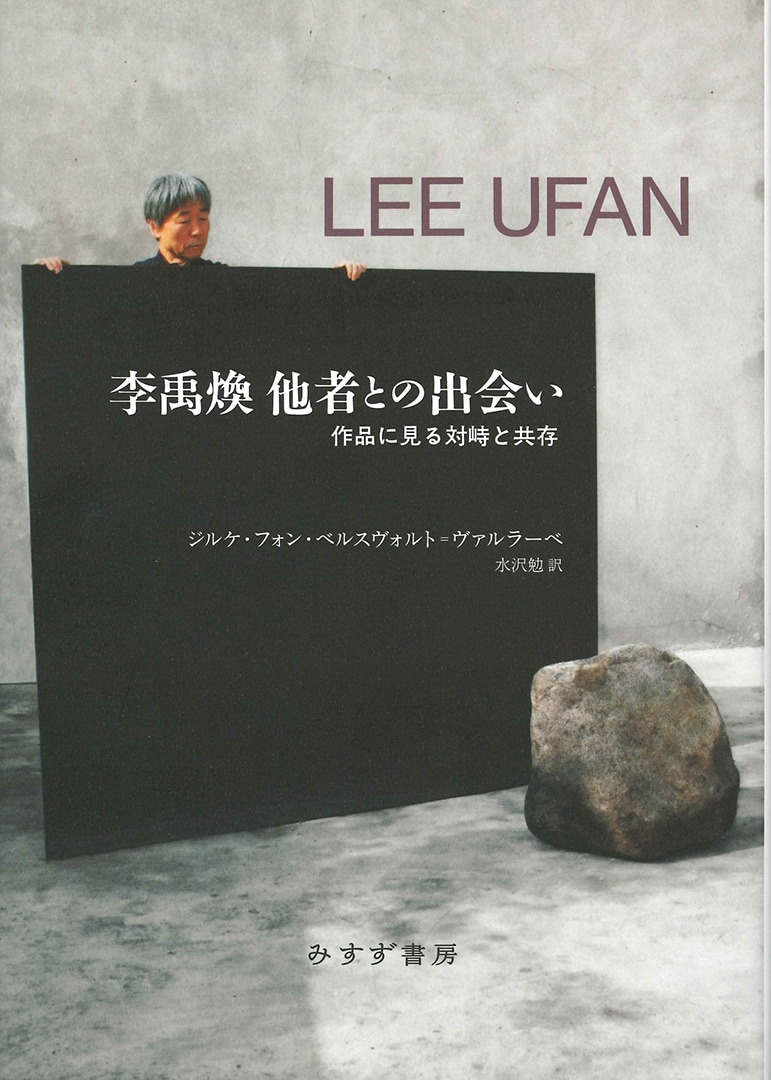私はキャンバスを立てて、それと向き合いながら描くのではなく、床にねかせて身体ごとキャンバスに投身しながら描く。(……)考えと身体とキャンバスの呼応の出来事として、絵がもよおされる必要があるからだ。床の大きなキャンバスの上に踏板を渡し、頭をキャンバスに向けて背を弓形に曲げる。左手は左ひざの上に置き腰を据え、右手はたっぷりと絵具を含ませた筆を握り締めて、大きく吸い込んだ息を止めて静かにゆっくり力強くストロークを引いてゆく。50センチ幅の筆だと60センチあまりの長さのストロークを1分30秒から2分近く息を止めたまま全身の力を筆先に集めて引く。苦しい時はかすかに息を吐きながら事を行う。呼吸が荒れたり雑念が浮かんだり気が散ったりして、集中力が崩れると大抵失敗する。一つのストロークが出来るまでは、気を抜くことなく何度も同じ作業を重ねる
これはもう、アスリートといっていいのではないか。芸術家の制作とは、この世から半分抜け出たようなところで行われているのか。その時間は一瞬のようでもあり、永遠のようでもあるのか。
そうしてできあがった作品が作り出す、透明で静かな空気感の秘密が、作家自身の言葉のあわいから少しずつ、少しずつ見えてくる。
『余白の芸術』から20年が経ち、作品の制作と並行してずっと書き続けてきた文章は膨大な数に上るものの、新たな一冊にまとめるのは、今でなければできないことだった。
パリやニューヨーク、ソウルと飛び回り、日本にいることもほとんどない、制作、制作の日々。それが2020年春、新型コロナのパンデミックによって突然、途切れた。世界中のあらゆる人びとが、それぞれの生活と仕事、人生の流れの中で立ちどまらざるを得なかったように。
一冊にまとめるにあたって届けられたワープロ原稿を見て、驚いた。
いちばん古いものは1973年、最新は2020年――ほぼ半世紀にわたる。国内の新聞や雑誌、あるいは日本語で書かれた原稿が翻訳者を経由して韓国の『現代美術』誌やヨーロッパで発表されたあと、数年おいて、場合によっては何度も何度も表現に手が入り、彫琢された跡が見える。
どうしてもこの本に入れてもらいたいが、原稿がどうしても見つからない――そんな文章もあった。最後まで出てこなかった「カシミール・マレーヴィッチ 万華鏡のようなカタルシス」は、英語に訳されて発表したものをもう一度日本語に訳し直し、ようやく私たちも読むことができるようになった。
李禹煥の絵や彫刻は、たった一度の出会いの場であり、出来事の現場であるけれど、その文章が完成形になるのには、まったく逆の道を辿っているわけで、もしかしたら、本当の意味で「完成形」になることはないのかもしれない。それでいて、白いキャンバスの上に生まれる作品とアーティストその人のたたずまい、そして紡ぎ出す文章に、ほんのわずかのブレもない。
国内外の展覧会の予定はすべてキャンセル、工場でアルチザンに独自のレシピで作ってもらうキャンバスがいつフランスから日本へ届くのか見込みも立たない……そんな日々に書かれた「新型コロナウイルスのメッセージ」「籠りの彼方に」まで、68の文章。
AIは芸術の世界を変えるか。新型コロナによって世界に大きな変化がもたらされたその先に、表現は、芸術と人間の在りようはどうなっていくのか。
ある人が言った「李禹煥の書く本は予言書みたいだ。やってくる時代がいつも見えている」が思い出された。