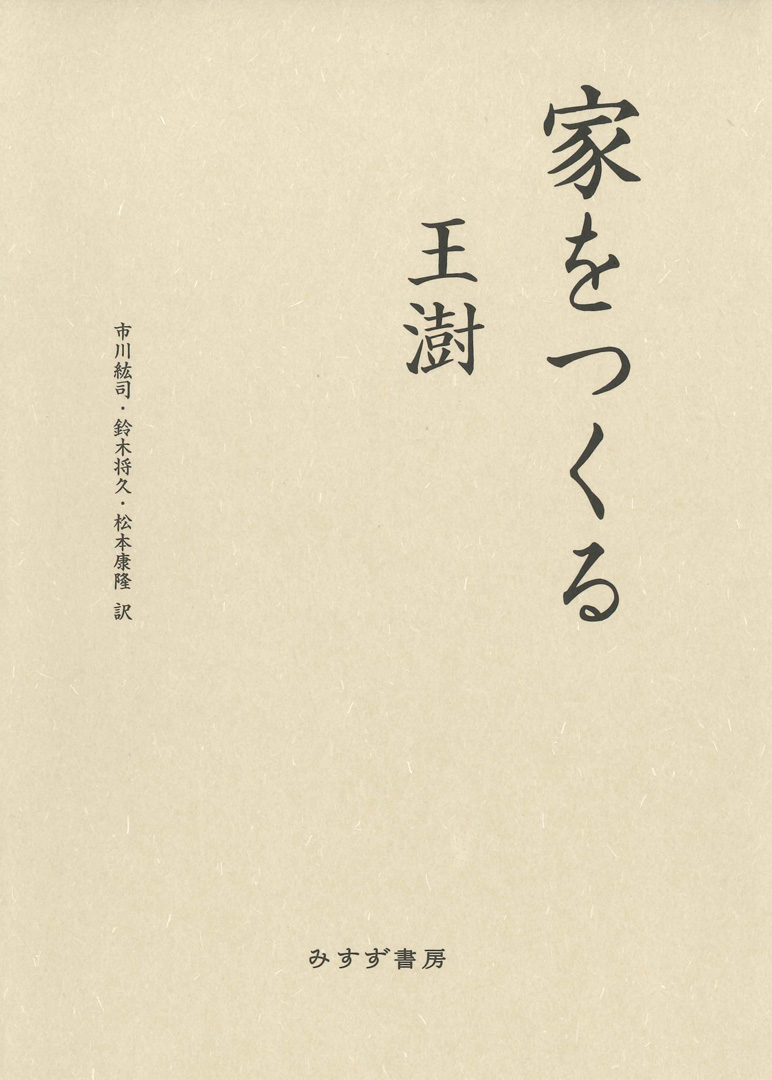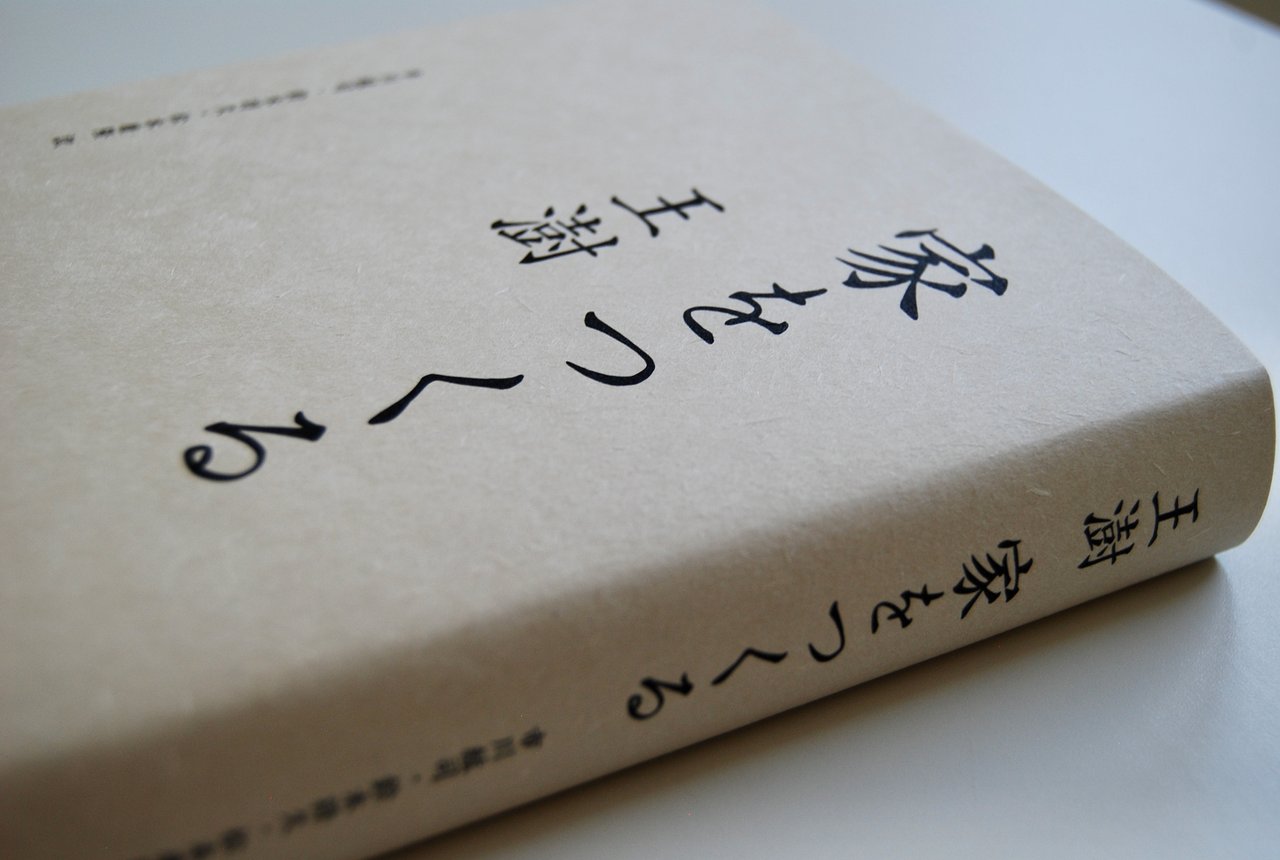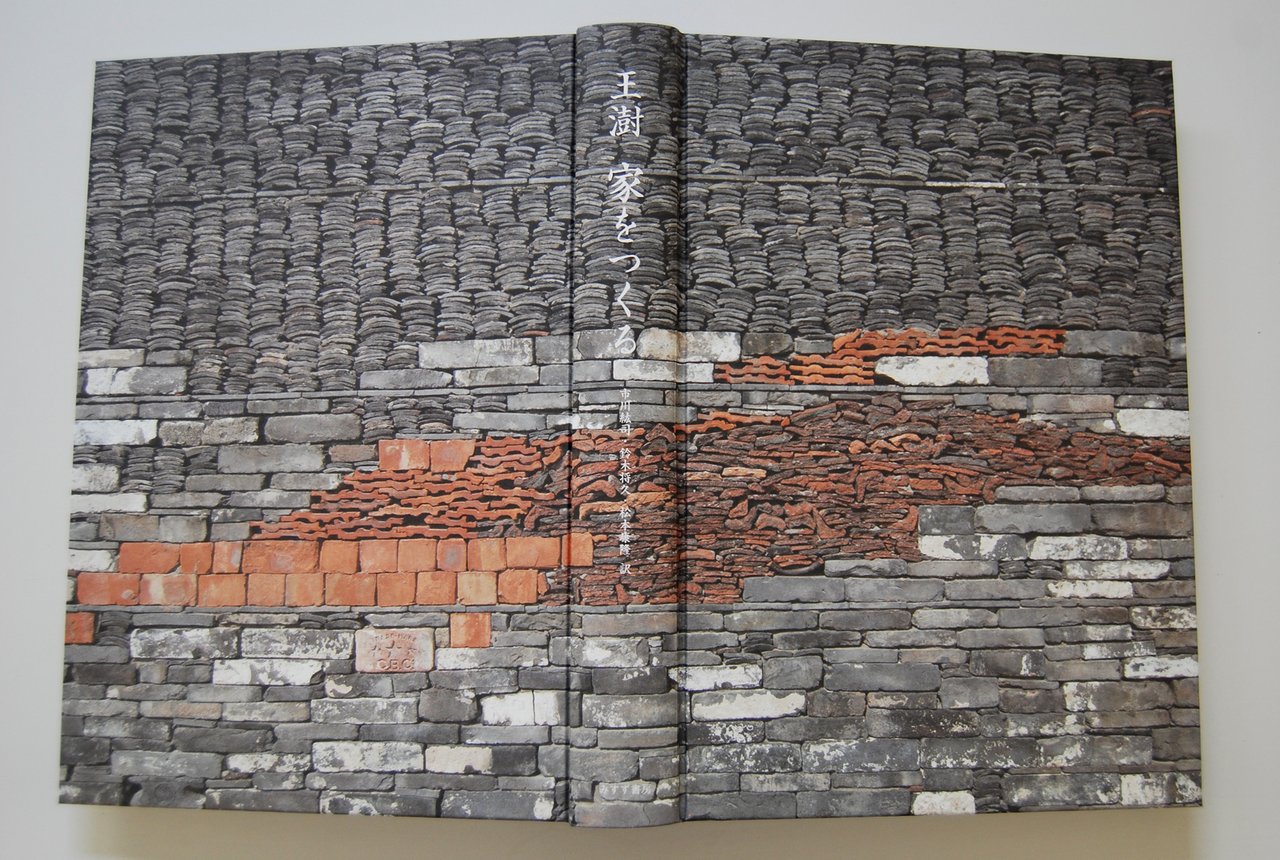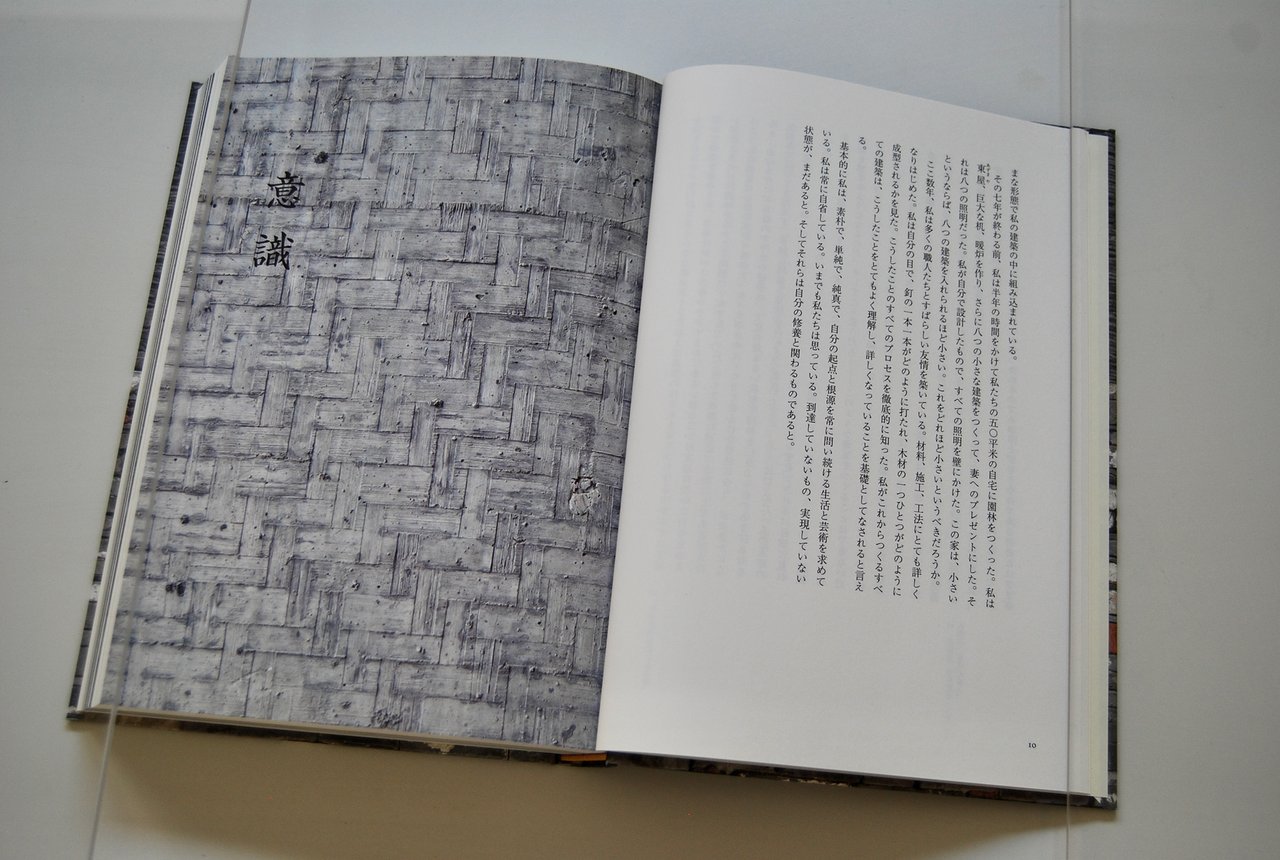建築史家の市川紘司氏による「訳者解題」を一部抜粋して掲載します。
別のユートピアを想像する
市川紘司
ナショナル≠ガバメント
21世紀に入って急速に発展を遂げた中国現代建築のなかでも突出して世界的に知られているのが、本書『家をつくる』の著者である王澍(ワン・シュウ)だろう。その理由は、ほぼ違いなく、彼が中国人建築家としてはじめてプリツカー賞を受賞したからである。
1979年の設立から毎年1名の建築家(あるいは建築家チーム)に授与されるプリツカー賞は、建築家界の「ノーベル賞」とも称される名誉ある賞だ。王澍はこの賞を2012年に中国人建築家としてはじめて受賞した。それゆえ、やや下品な言い方をすれば、王澍は国際的な建築家ワールドにはじめて“認められた”中国の建築家と言ってよい。ちなみに、ルーヴル美術館のガラスのピラミッドで知られる華人建築家のイオミン・ペイ(貝聿銘)も1983年に受賞しているのだが、彼は青年時代の1930年代に中国大陸からアメリカに渡っており、建築家としてのキャリアのベースがアメリカにある。現在の中国、すなわち中国人民共和国に生まれ、国内で建築教育を受け、さらにその後の設計実務も中国を拠点に展開する「中国純粋培養」の建築家としては、やはり王澍には前例が存在しないのだ。
中国人建築家としてはじめて国際的な認知と評価を勝ち取った王澍は、現在の中国という「国」を代表する建築家という意味で、国家的建築家すなわち「ナショナル・アーキテクト」と呼ぶにふさわしい存在である。2012年におけるプリツカー賞の授賞式は、中国の「国民広場」である天安門広場に建つ人民大会堂(日本で言えば国会議事堂に相当する)において華やかに執り行われたのだが、この式典には王澍、審査員、プリツカー賞を主宰するハイアット財団に加えて、当時国務院副総理だった李克強などの中国政府の要人たちも参列した。それはまさに、20世紀末から高度経済成長を続ける新興国家・中国が待望した、世界的名声を兼ね備えたナショナル・アーキテクトの出現を祝う国を挙げてのセレモニーにほかならなかった。
日本において王澍を理解する際、補助線となるのは丹下健三かもしれない。丹下はモダニズムと日本の伝統建築カルチャーを昇華させた戦後日本を代表するナショナル・アーキテクトであり、1987年には日本人建築家としてはじめてプリツカー賞を受賞した。同賞最初の中国人受賞者であり、建築・園林・山水画・書などの中国的伝統を多面的に参照する王澍の姿態は、なるほど丹下と多くの部分が重なって見える。また、戦後焦土となった日本が復興し経済成長するなかで活躍した丹下の時代背景も、大躍進政策と文化大革命という停滞と混乱の時代から経済成長に向かう改革開放時代のなかで登場した王澍のそれとよく似ている。
だが、王澍と丹下健三には決定的な違いもある。丹下が建築家として戦後日本を代表したのは、モダニズムと「日本的なもの」を昇華した、その独自の建築スタイルばかりではなかった。東京オリンピック(1964年)の代々木競技場、大阪万博(1970年)のお祭り広場、あるいは首都計画(東京計画1960)や国土計画など、戦後日本の復興と成長を象徴するプロジェクトを構想したからこそ、丹下はナショナル・アーキテクトであったのだ。丹下健三研究で著名な建築史家の豊川斎赫は、丹下を「戦後日本の構想者」とまで呼ぶ。(注1)
翻って、王澍は丹下のような国家スケールの仕事にはいっさい関与していない。本書巻末に掲載した作品譜を参照してみてほしい。美術館など文化施設を中心に大きな(日本から見れば、だが)公共建築を多数手がけているし、国家的イベントである上海万博(2010年)では農村建設のモデル展示館も手がけている。しかし、前世紀末からの経済成長によって引き起こされた未曾有の都市開発熱に沸く中国の建築業界にあっては、王澍のプロジェクトはあくまでも小さく周縁的な存在にとどまるものである。本書所収のエッセイ「自然に還る道」によれば、プリツカー賞受賞時には「業界で私を知っている人は少なく、多くの人が“王澍とは誰だ”と聞くほどだった」(本書290頁)という。また、やはり作品譜から明らかなように、王澍のプロジェクトは彼が活動拠点を置く浙江省杭州市、そして浙江省や上海市を含む江南地方にほとんど集中している。例外的にあるのは、ヴェネツィア建築ビエンナーレなど海外でのインスタレーション的作品のみだ。つまり彼はひとつの地域・場所に根付くローカル・アーキテクトなのであり、首都北京や広い中国国土の各地で、ましてや世界を股にかけてプロジェクトを展開するような建築家ではない。
さらに言えば、王澍は単に「周縁」の建築家であるばかりでなく、「中心」に対する明確な批判者でもある。本書でもたびたび話題に上っているとおり、中国現今の近代化された建築生産システム、あるいは経済成長を国是として歴史的空間を薙ぎ倒しながら進められてきた都市開発に対して、王澍は一貫して懐疑的である。このような態度は建築家にして思想家でもある王澍の最大のキャラクターと言ってよいが、後述するとおり、それは彼が自らのアイデンティティを近代西洋的な意味での建築設計の専門家ではなく、伝統中国における文芸のアマチュアとしての「文人」に置いていることと深く関係している。
結果として王澍の立場は一見捻れたものとなっている。中国という国を代表する建築家であるのは間違いないが、それと同時に、建築と都市の中国的現状に対して明らかに批判的存在でもある、というように。言うなれば、彼は中国のナショナル・アーキテクトではあるが、建築の専門家として国にデザインやプランを提供するガバメント・アーキテクト(注2)ではない。これが戦後日本の丹下健三とは大きく異なる点と言えよう。丹下においては「ナショナル・アーキテクトであること」と「ガバメント・アーキテクトであること」はある程度重ねることができる。しかし、王澍はそうではないのである。
中国人建築家の「第4世代」
王澍の生年は1963年。出身は新疆ウイグル自治区の大都市ウルムチである。ただし、幼少期は母方の生家のある北京とを頻繁に往復する生活であったという。非常に巧みな建築ドローイングで知られる王澍だが、これはウルムチと北京を往復する鈍行列車(片道4日!) のなかで通り過ぎる風景を描写することで培われたものである。その後、西安での生活を経て、1981年に南京工学院建築学科(現・東南大学建築学院)に入学している。南京工学院は中華民国時代に創設された近現代中国の建築名門校だ。卓越したドローイング能力のみならず、学部2年時には論文コンペに入選して全国的な建築雑誌に論文が掲載される(注3)など、出色の学生であったらしい。1985年に卒業すると、修士課程へと進学し、1988年に修了した。
修了後の王澍は浙江美術学院(現・中国美術学院)に就職し、おもに古い建築の改修や環境的観点からの建築調査に従事した。転機は1995年。美術学院の仕事を辞して、やはり建築名門校である上海の同済大学建築與城市規劃学院の博士課程に進学した。博士学位の取得は2000年のことであり、同年に中国美術学院建築芸術学院教授に着任し、現在に至る。また2007年からは同学院学院長も務める。中国美術学院は、日本の東京藝術大学のような位置づけのアートスクールと考えてもらえればよい。その建築教育のトップが王澍というわけだ。
アカデミックなキャリアを順調に積んだと言ってよい王澍であるが、その傍らでは建築事務所を1997年に創設している。これが「業余建築工作室」(アマチュア・アーキテクチュア・スタジオ Amateur Architecture Studio)である。共同主宰者である妻の陸文宇も中国美術学院で教授職を務める現役の建築家であり、王澍の公私におけるパートナーだ。それゆえ、王澍はプリツカー賞を夫婦連名で受賞することを望んだらしい。しかしほかならぬ陸文宇のほうが難色を示した結果、王澍一人の受賞に至ったという。(注4)
さて、以上のような経歴をもつ王澍を、中国近現代建築史の文脈のなかで理解するためには、ありきたりではあるが世代論を用いるのが手っ取り早い。建築史家の楊永生が提起した中国人建築家世代論(注5)にもとづけば、王澍は「第4世代」に属する。
中華民国時代の1920-30年代に海外留学(おもに米国留学)をし、西洋的な意味での「建築」をはじめて体系的に学んだ「第1世代」、社会主義建設に邁進する毛沢東時代初期の中国で活躍した1910-20年代生まれの「第2世代」、そして社会主義イデオロギー全盛の時代の中国国内で建築教育を受け、改革開放後の主流派建築の中心を担った1930-40年代生まれの「第3世代」に続くのが、1950-60年代に生まれた王澍ら「第4世代」の建築家たちである。参考までに第4世代以前の代表的建築家を挙げておくと、第1世代には梁思成や劉敦楨、第2世代には張鎛や張開済、第3世代には何鏡堂や斉康などがいる。斉康は王澍の指導教員でもあった。
中国人建築家の第4世代を考えるうえで重要なのは、彼/彼女らが改革開放(1978年)直後の開放的なムードのなかで建築教育を享受したことである。1976年に毛沢東の死去と四人組の失脚によって文化大革命が終わると、中国は鄧小平の主導のもとで改革開放へと舵を切る。そして長らく停止していた大学入試制度も77年に復活し、高等教育が再開した。その教育環境は改革開放以前とは劇的に異なる。社会主義イデオロギーの支配性は後景化し、代わって資本主義世界の思想や文化に触れることができるようになったのだ。
第4世代とは、こうした「自由」な教育環境のなかで新しい理論や手法を貪欲に摂取した社会主義中国最初の世代にほかならない。ゆえに、その建築表現も先行世代(とくに社会主義時代に学び、活躍した第2・3世代)とは大幅に異なる宿命にあった。この点で、彼/彼女らは中国映画の監督世代論における「第5世代」とよく似ていよう。張芸謀や陳凱歌、田壮壮らが著名な中国映画監督の第5世代は、やはり文革終結後に復活したばかりの大学入試をパスして映画学校で学び、従来の社会主義リアリズムとは異なる個性的で実験的な表現手法を追究した世代であった。
このような時代背景から登場した第4世代には、いくつかの顕著な特徴がある。
第一に、資本主義世界で20世紀に発展したモダニズムからポストモダニズムまでの建築思想やスタイルを積極的に受容し、自ら実践したこと。以後、中国の現代建築は西欧中心で編まれる一般的な「世界建築史」に合流することになる。冒頭で述べたとおり、王澍は中国最初のプリツカー賞受賞建築家であるが、そもそもそれほどの国際的評価を勝ち取る建築家が2010年代まで中国に登場しなかったのは、社会主義リアリズムを金科玉条とする毛沢東時代の中国現代建築史が、長らく「世界建築史」の域外で鎖国的に形成されてきたことに大きく起因する。
第二に、民間で活動する独立自営業者としての建築家が誕生したこと。毛沢東時代の建築設計業は、基本的にすべて政府および国営企業に直属する設計組織によって担われていた。これを「建築設計院」と呼ぶ。建築家はすべてこの組織体制のなかで活動した。つまり、毛沢東時代当時の中国では、建築設計の専門家たる「建築家」とは国営設計院所属の「公務員」であり、みなが「ガバメント・アーキテクト」であったと言えよう。しかし市場経済を導入した改革開放時代になると、私営企業の設立が許可されたことで、建築設計業においても自営の建築設計事務所を構え、自由にプロジェクトを受注する建築家(フリー・アーキテクト)の活動が可能になった。それは1990年代半ばのことである。他方で、国営だった設計院のほうも徐々に民営化するとともに、院内に個性的な建築家を抱えていくことになる。
第三に、デザインの対象が脱領域化したこと。改革開放以後の建築設計業の主流をなすのは、依然として元国営の大型設計組織である設計院であり、中国都市の基調は彼らの手によってつくられていると言ってよい。対して、資本主義世界の建築カルチャーに触れ、小規模ながら自営で事務所を始めた第4世代の建築家たちの活動はより柔軟で、フットワークが い。小規模な文化施設、インテリア、リノベーション、あるいは現代美術的なインスタレーションなどまでを手がける建築家も出てくる。[本書「訳者解題」へつづく…]
注
- 豊川斎赫『丹下健三――戦後日本の構想 』岩波新書、2016年。
- 東南アジアの近代建築を論じる岩元真明は、近代国家(ネーション=ステート)が「国民」と「国家」というふたつの異なる性質をもつことに注目し、国家を代表する建築家を「国民的建築家」(ナショナル・アーキテクト)と「国家的建築家」(ステート・アーキテクト)に分けて考えることを提案している。本稿における「ナショナル」と「ガバメント」の区分は岩元の視点を参照しているが、丹下健三の評価は異なる。参照:村松伸+山名善之+岩元真明+市川紘司「社会の課題から東南アジアの建築を考える」『10+1 website』2016年10月号 https://www.10plus1.jp/monthly/2016/10/issue-01-2.php)。
- 王澍「旧城鎮商業街坊與居住里弄的生活環境」、『建築師』1984年第5期、中国建築工業出版社。同号掲載の入選論文には、劉克成(西安建築科技大学)や徐蘇斌(天津大学)など、のちに建築家や建築史家として大成する顔ぶれが見られる。
- “Wang Shu’s Partner Lu Wenyu: I Never Wanted a Pritzker” (https://www.archdaily.com/463985/wang-shu-s-partner-lu-wenyu-i-never-wanted-apritzker)。この記事によれば、陸文宇は国際的に著名になって生活が脅かされることを懸念し、受賞を拒否した。ちなみに、1991年のプリツカー賞を受賞したロバート・ヴェンチューリも、建築設計やリサーチにおいて妻のデニス・スコット・ブラウンとの協働関係で知られるが、受賞はヴェンチューリ一人であった。ブラウンは、王澍受賞のちょうど翌年に当たる2013年、この件に対する抗議と自身への授賞を求めるコメントを改めて公表している。ヴェンチューリ当人やザハ・ハディドらが賛同したものの、プリツカー賞側は再考しないと回答している。“Denise Scott Brown demands Pritzker recognition” (https://www.dezeen.com/2013/03/27/denise-scott-brown-demands-pritzker-recognition/)参照。
- 楊永生『中国建築四代建築師』中国建築工業出版社、2002年。なお、本書では王澍を「第4世代」として取り上げていないが、その後の活躍により、現在はこの世代の代表と見なすのが一般的である。
copyright © ICHIKAWA Koji 2021
(著作権者のご同意を得てウェブ転載しています)