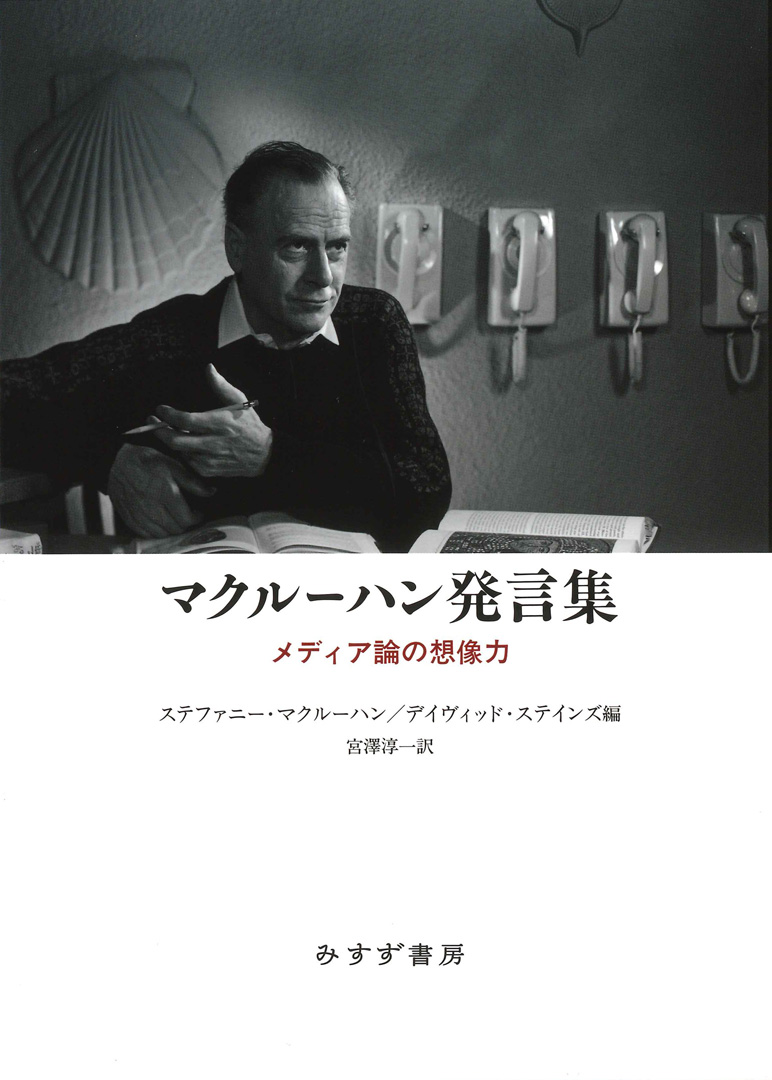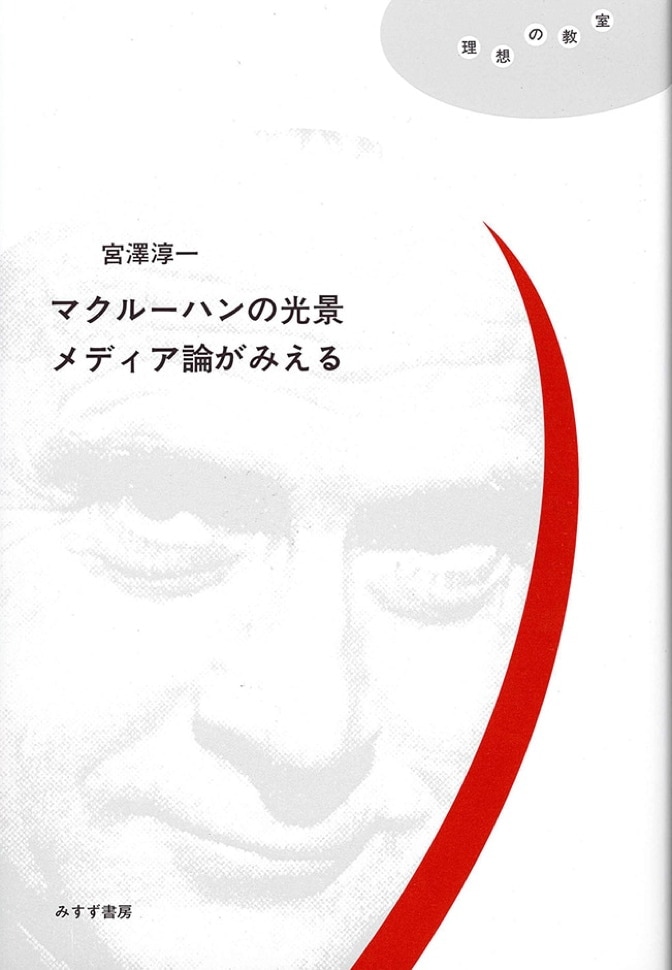この『マクルーハン発言集』に集められたテキストは、47歳のマクルーハンが講じた1959年の「電子革命」に始まり、その20年後の79年に演壇に立ち、「メディアの法則」を提唱した「人間とメディア」に終わる。英文学の大学教師にすぎなかった人物がメディアの専門家として頭角を現わし、世間を騒がせたのはこの約20年間なので、メディア論者マクルーハンの思考や関心の変遷は本書でカバーできることになる。
小見出しからキーワードをいくつか拾うならば――新しい布置、壁のない教室、ユークリッド空間と触覚的世界、アルファベットと絵画の世界、没入とプロセス、ともにある(ウィズ)の状況の出現、テレビは「深層」のメディア、仕事から役割へ、環境の内容は芸術作品、関与の深まりと東洋化、反環境としてのカナダ、バックミラーに映る世界、送られるのは送り手自身、図から地への変化、ほとんどのニュースは偽物、即時再生とパターン認識、自動車とプライヴァシー、今の世界は右脳的、無知の活用法……。
多種多様なトピックが並ぶので、ランダムに開いたページから読んでもかまわない。彼の生きた時代よりも、21世紀の今の方がむしろ通用する発言も見出せるかもしれない。いずれにしても、どこから読んでも、興味深く、刺激的で、彼のメディア論の想像力の源泉に触れられると同時に、その巧みな言説で、いつのまにか、彼の求心的な主張に導かれていくはずだ。
ただし、マクルーハンの思想や言葉に本書で初めて触れる読者が混乱しないように、予備知識を二つ提示したい。
まず、メディア(単数形medium/複数形media)の概念である。今日、メディアと言えば、コミュニケーション(通信・情報伝達)、特にマス・コミュニケーション(報道)の媒体や、データを保存・伝達できる電子記録媒体――のいずれかを指す。しかし、マクルーハンは、それらを含めつつも、メディアをもっと大きな概念として考えていた。つまり、有形無形のあらゆる人工物(artifact)もメディアなのだ。各種の道具に加え、彼が特に重視していたメディアとは、テクノロジーである。よって――
メディア=人工物=テクノロジー
──と考えて差し支えない。
その上で、マクルーハンは、人工物(メディア)を人間の身体や精神の拡張(extension)と考え、また、人間の感覚・思考・行動は必ずそうした人工物の影響を受けると考えた(特に各種の電気メディアを中枢神経の拡張として議論を展開した)。また、新しいメディア(人工物)が生まれるたびに、人間の環境が変化するが、一般の人間はそれに気づかないまま苦しめられることや、新しいメディアによる環境の変化をいち早く察知し、人々に報告できるのは芸術家だけだと説いた。また、差し出される芸術作品は、私たちが変化に耐えるための「免疫」となるのだ。
もうひとつは、有名な標語“The medium is the message.” について。「メディアはメッセージである」と訳されることが多いが、こう考えてみたらどうだろうか――
The medium is the message (rather than the content is the message).
(内容がメッセージであるよりも)メディア(こそ)がメッセージなのだ。
この解釈は有名な『プレイボーイ』誌のインタヴュー(1966年)からヒントを得たものだ。「は」よりは「が」だと考えれば、説明が容易になる(冠詞の用法や情報構造の問題だが、詳しくは拙著『マクルーハンの光景』を参照)。その上で、新しいメディアが出現すると、それがどんなメッセージをもたらすのか(何が起こるのか)を考察したのがマクルーハンのメディア論の中核なのである(この標語自体については、本書でも時期によって少しずつ異なる評釈が付与されているので確かめてみてほしい)。また、彼は「メッセージ」を「マッサージ」と言い換えて人々をさらに挑発したし、電子メディアの出現によって究極的にもたらされたのが「摩擦の多い」地球村(グローバル・ヴィレッジ)であったことを説いている。
メディアをホット(高精細度・低参加度)とクール(低精細度・高参加度)に分類したマクルーハンによれば、セミナーはクールで、レクチャーはホットだという。それをどのように理解するべきかはともかく、本書で初めてわかるのは、マクルーハンはジョークが好きな人で、演壇からジョークを発するたびに、不満の種(grievance)について語っていた事実だ。コメディアンのスティーヴ・アレンの請け売りらしいが、「剽軽な人とは不満の種を貯めている人」であり(本書63頁)、「不満の種があるところにはジョークが山ほど存在する」(本書161頁)という。
ところでマクルーハンは「取り上げる話題はどれも、私が断固として反対していることがら」(本書115頁)だと語っている。結局、活字人間の彼にとっては、テレビなどの新しい電気メディアこそが不満の種だったのだろう。してみれば、彼が構築したメディア論自体が、壮大なジョークだったのではないかと思えてくる。荒唐無稽だと言いたいのではない。「居心地の悪い不愉快な状況」(本書197頁)を乗り越えるための知恵の総体であり、21世紀にも有効なワクチンなのである。
宮澤淳一
copyright © MIYAZAWA Junichi 2021
(筆者のご同意を得て抜粋転載しています)