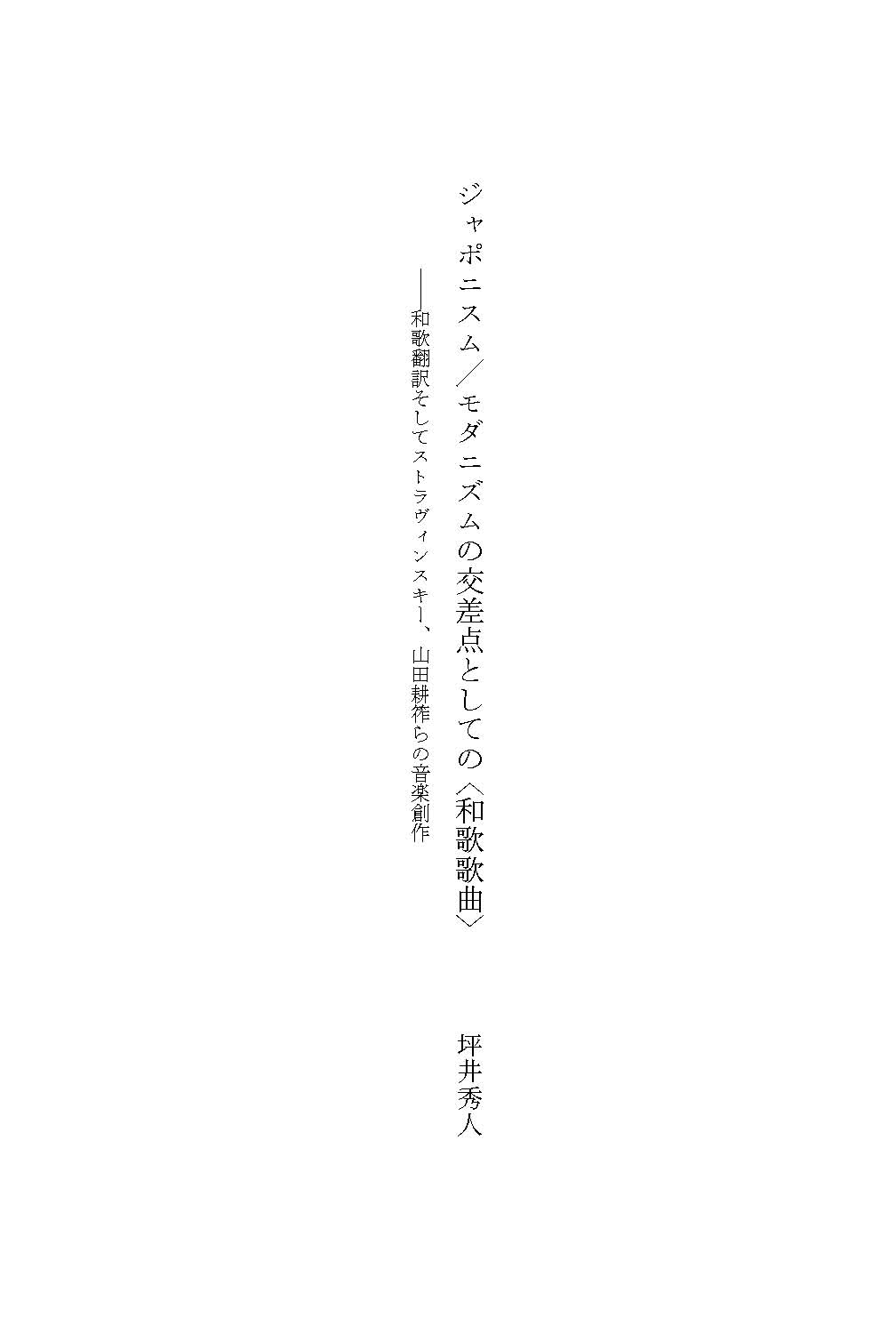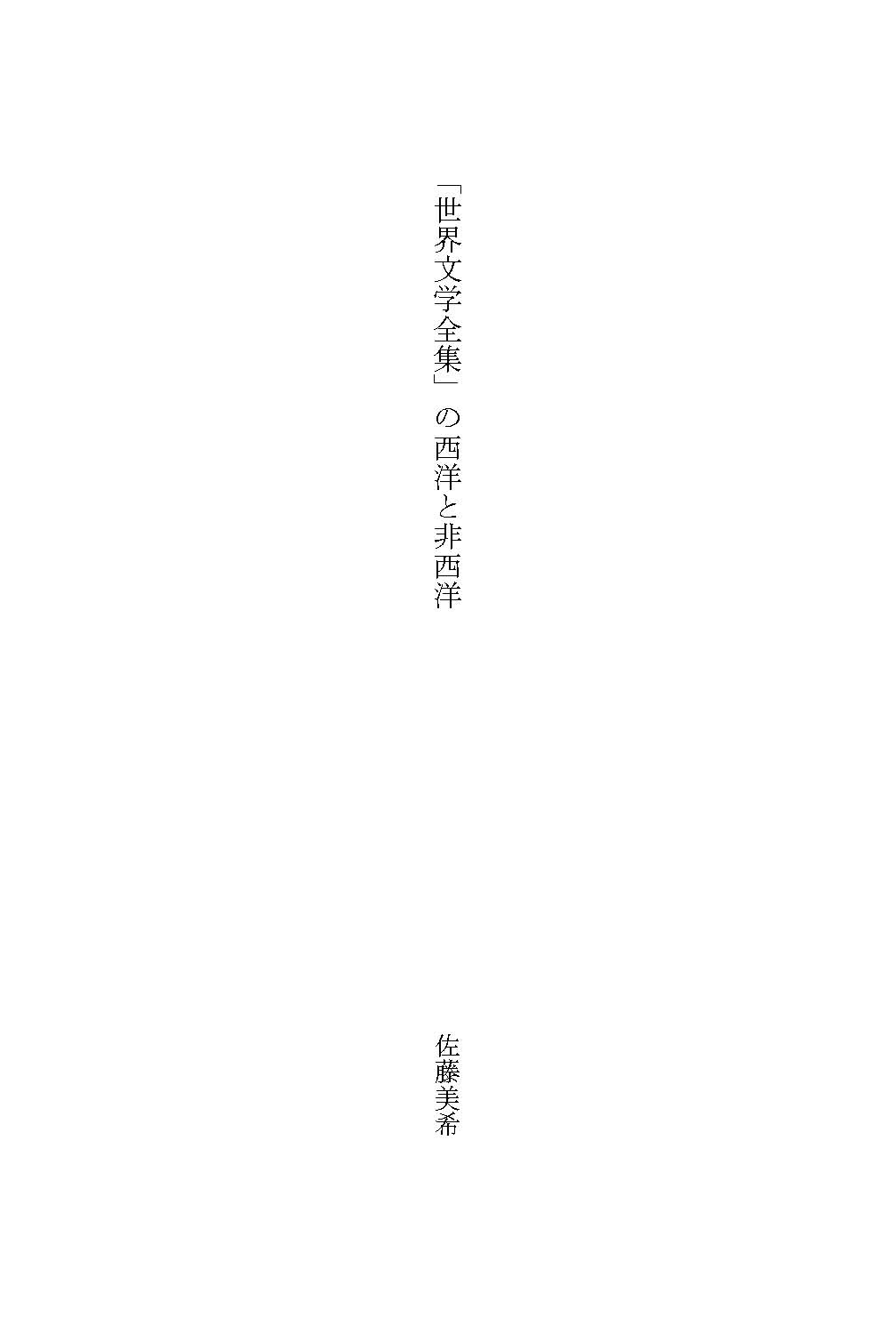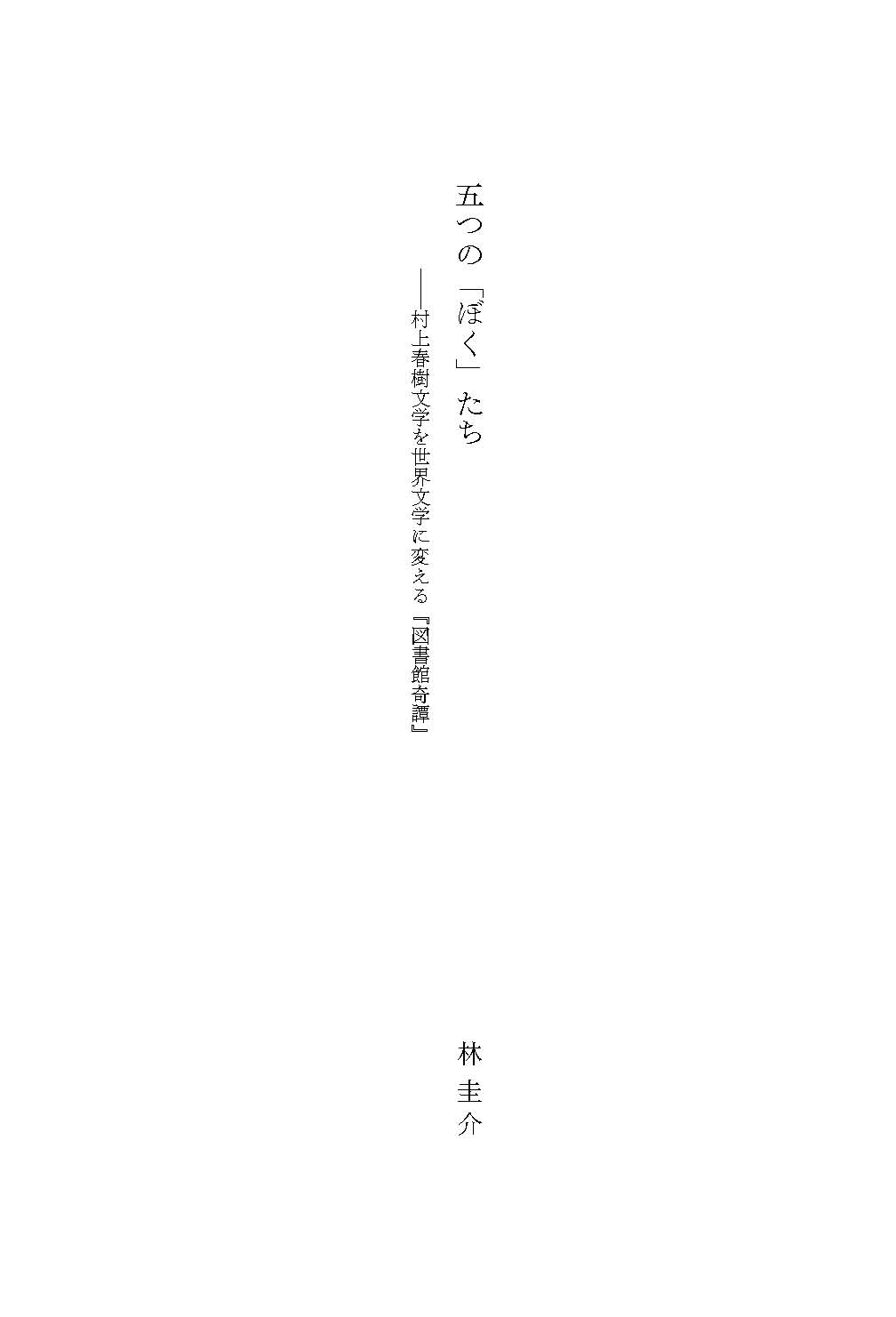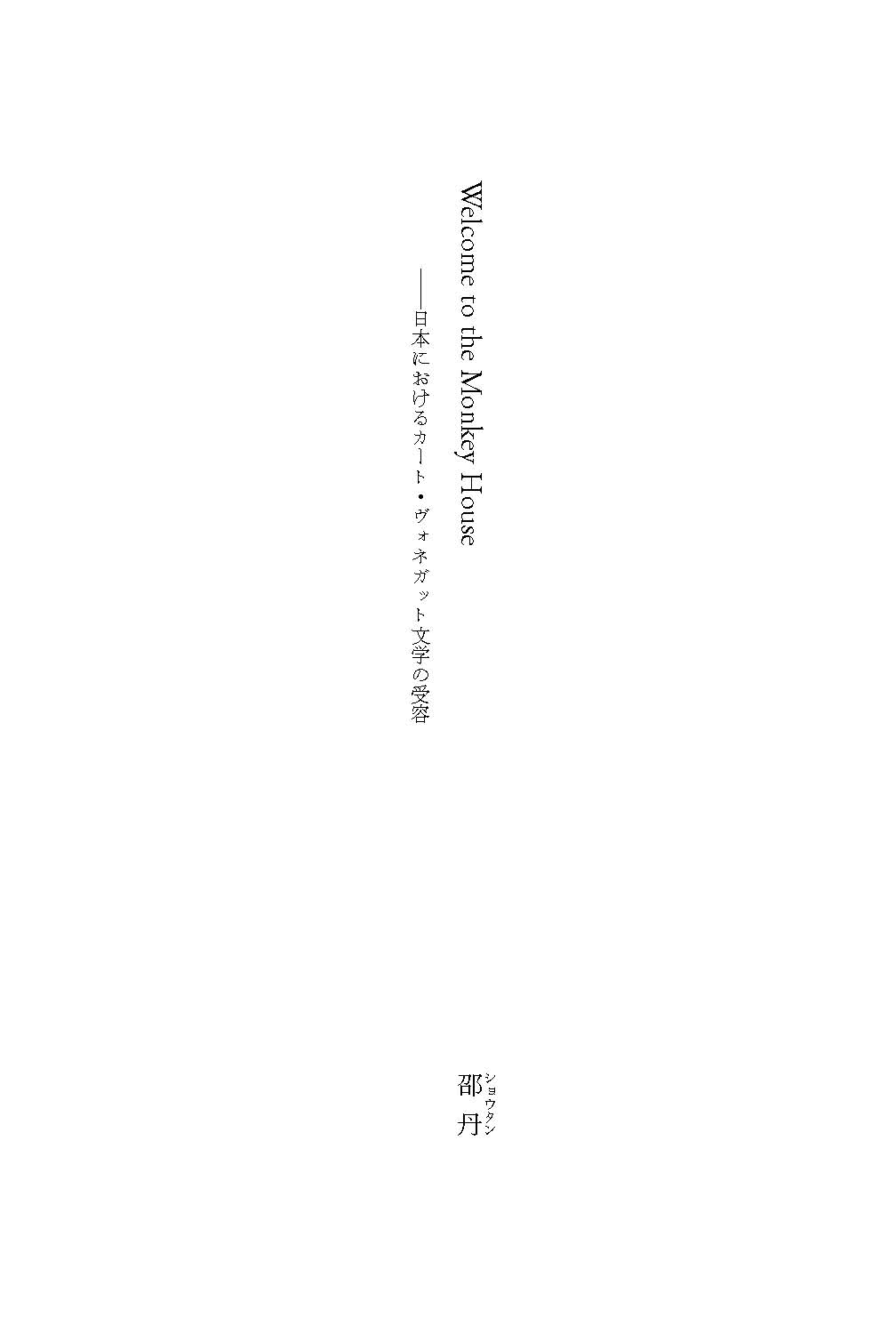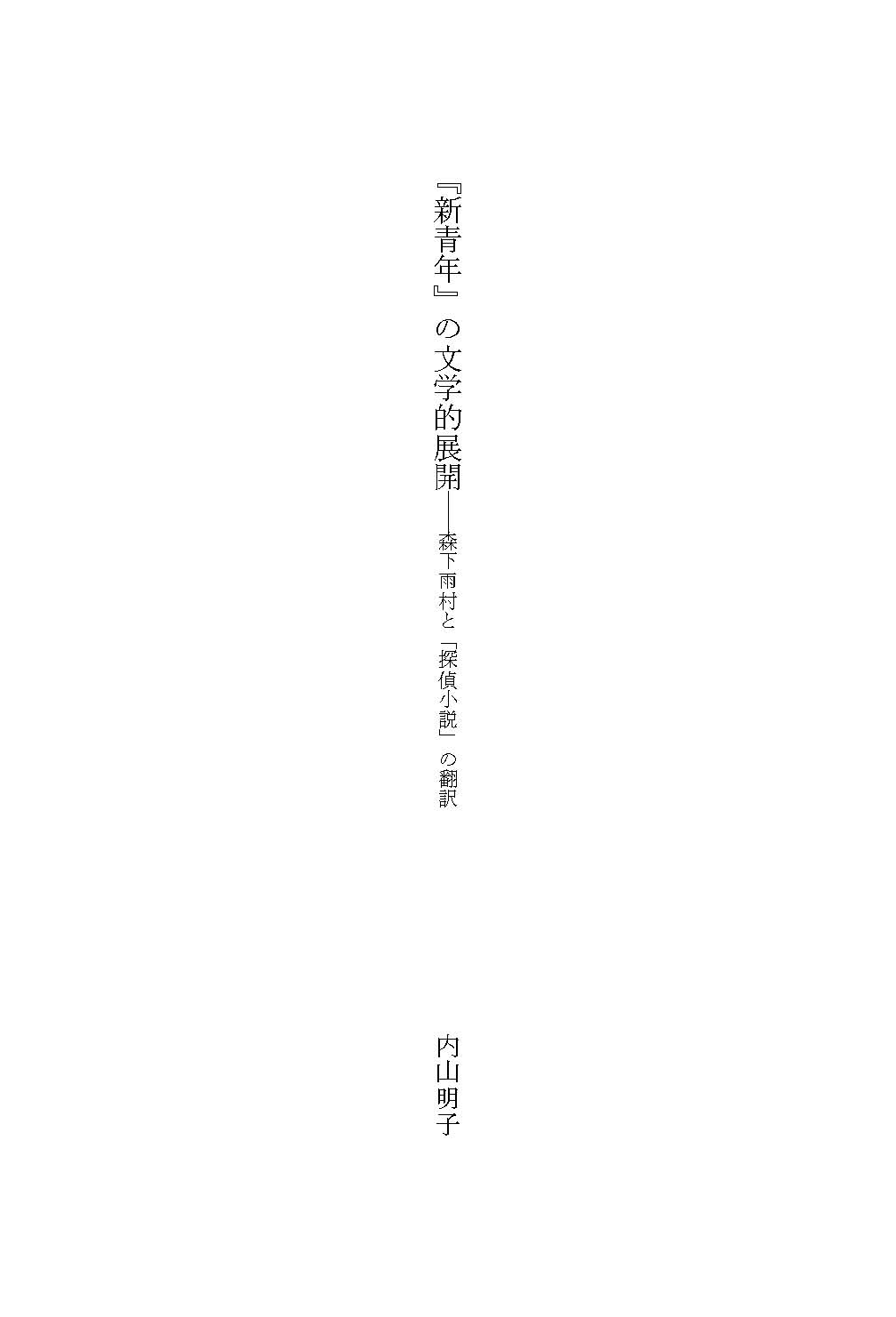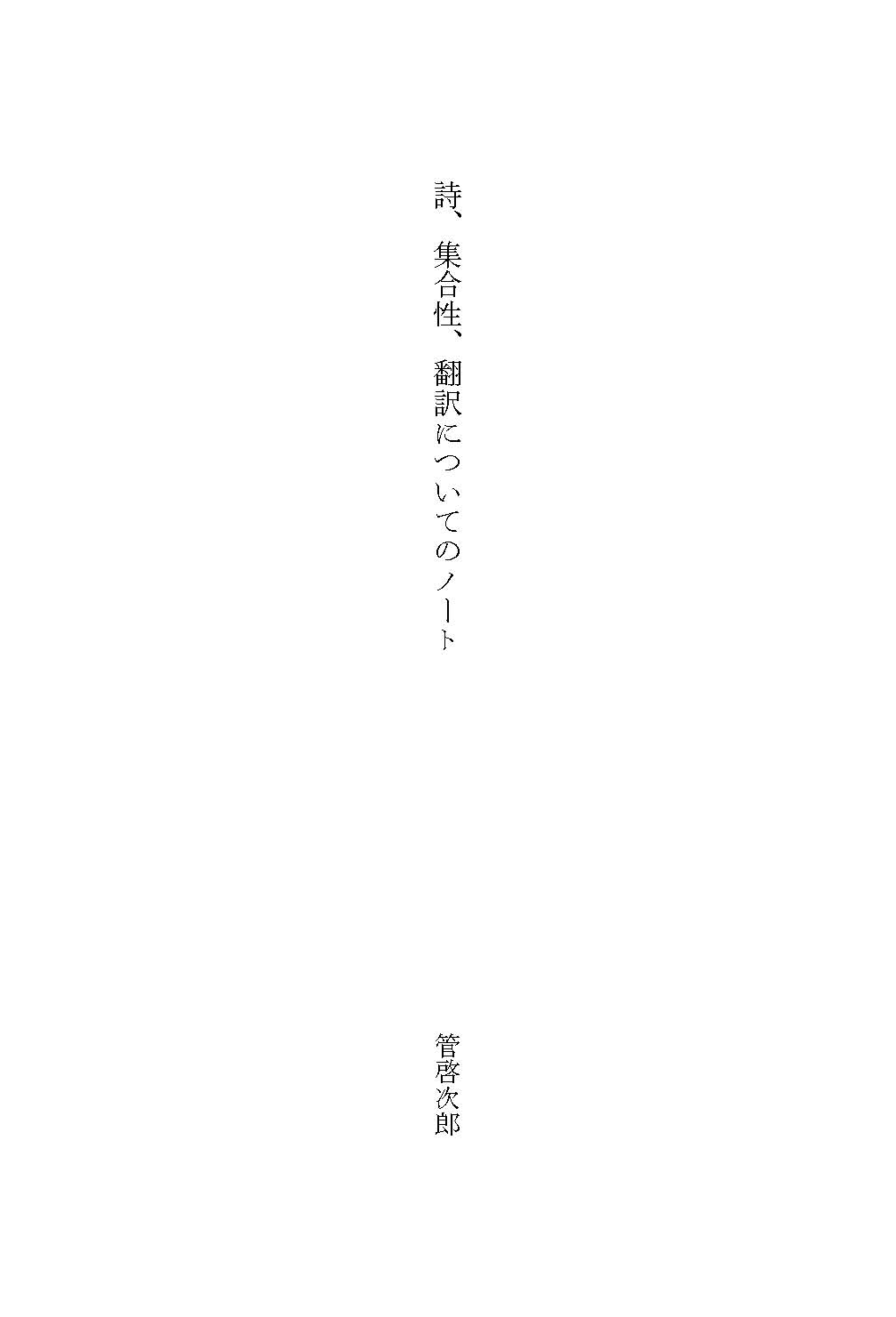執筆は、池澤夏樹、坪井秀人、林圭介、佐藤美希、内山明子、邵丹、管啓次郎、そして編者。
探究の可能性にあふれるこのテーマ〈翻訳と文学〉へ、ようこそ。
一個の作品の内容がすべて作者の意想に由来するかというとそうではあるまい。早い話が、小説というものを一度も読んだことがない者に小説は書けない。和歌を知らぬ者は自分が和歌を詠むということを考えもしないだろう。創作は常に先行するあまたの作品の上に成立するものであり、実はその依存の度は我々がふだん考えているよりずっと大きい。敢えて言えばすべての創作は本歌取りであって、このシステムの全体を伝統と呼ぶのだ。
池澤夏樹「編纂・翻訳・創作」
彼がアルファベット文字の向う側に発見した日本語は、ストラヴィンスキーが試みたような異化作用を更新していく記号ではなく、言葉の自然なアクセントに音が忠実に寄り添うという、〈国語〉としての日本語の真正性を象徴するものとして機能し始めるだろう(……)まさに山田〔耕筰〕は自己オリエンタリズムの過程を歩むことで、日本歌曲を基礎とするナショナルな日本音楽の作者という自己像を発見していく
坪井秀人「ジャポニスム/モダニズムの交差点としての〈和歌歌曲〉」
一人称をめぐる村上春樹的転回は、原典と翻訳の境界を問うているのだ。村上春樹は、日本の読者が世界の読者の眼差しと出会う一人称を作ってきた。「僕」から「ぼく」へ、そして世界文学の「ぼく」へ。
林圭介「五つの「ぼく」たち」
「世界文学全集」は「選集(アンソロジー)」であって、決して世界中の文学作品すべてが収められているわけではない(……)ラインナップのほぼすべてを西洋文学が占める中で、非西洋文学からはどのような作品が選択され、その選択は読者にどのように説明されたのだろうか。
佐藤美希「「世界文学全集」の西洋と非西洋」
雨村編集長時代に紹介された翻訳探偵小説には、「探偵」が登場しない作品も多い。いわゆる探偵小説にとどまらず、怪奇小説、冒険小説、ユーモア小説を含めさまざまな「探偵小説」が掲載された(……)『新青年』の文学的展開に道筋をつけたのが『新青年』誌上に掲載されたさまざまな翻訳探偵小説だ。
内山明子「『新青年』の文学的展開」
ヴォネガット文学の翻訳受容の経緯をたどってみると、半世紀以上にもわたるこの歴史的な過程が既存の日本社会の文化的な秩序に大きな揺さぶりをかけてしまったことが分かる(……)日本でSFが豊かな文芸ジャンルとして成長していくにつれ、ヴォネガットの作品群もまた、次第に日本の文学空間に取り込まれていったのである。
邵丹「Welcome to the Monkey House」
慣れ親しんだはずの、生まれ育った場にいるはずが、いつの間にか「異質」者扱いを受ける。その時、人はどのように現実を受けとめるのだろうか。自己は揺らいでいくのだろうか。よくわからない混沌とした状況を理解しようとする過程の中で、翻訳という行為をせざるを得ないのではないだろうか。
佐藤=ロスベアグ・ナナ「証しの空文」
口承伝統と書字伝統を問わず、制作を全面的にとりかこむ環境としての、選ばれた創作言語の海の中に、小さな島か岩を確保するようにして、われわれは自分の制作のための言語資源を準備する。さらにあらゆる言語資源は、それに対応する実在物の宇宙につなぎとめられる形象であり、実在物と現象の布陣の中には、まだ言語化されないもの(=翻訳・造形を待っているもの)がいくらでもある。この、基本的には無限の可能性の中を進みつつ、われわれの意識は詩として造形しうるものへの翻訳素材を探し求めているわけだ。
管啓次郎「詩、集合性、翻訳についてのノート」