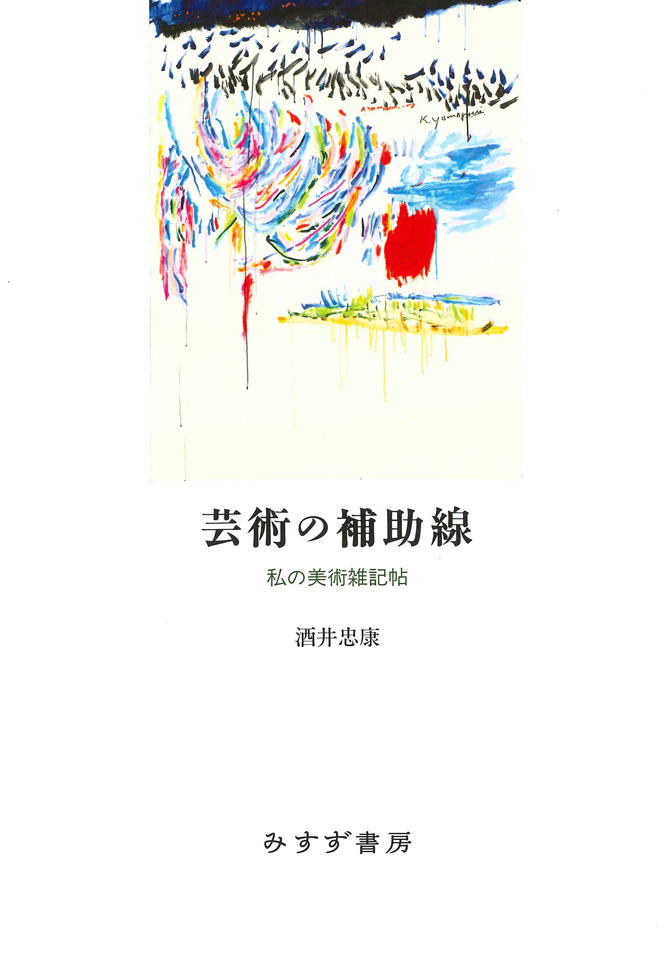酒井忠康「松田正平さんのこと」
安井雄一郎『松田正平 飄逸の画家』[12月10日刊]
2020年12月10日
酒井忠康『芸術の補助線』解説の全文を以下ウェブでお読みになれます。
武田昭彦
酒井さんのことを初めて知ったのは、わたしが美術予備校の事務局に勤めている頃である。東京芸大の院生で、講師をやっていたK君が、「酒井さんの『海の鎖』を読んだか」と訊くので、「いや、読んでいないよ」と答えると、「良い本だから、ぜひ読んだらいい」と彼は薦めた。それで、さっそくその本を買って読んだ。「描かれた維新」という副題は、幕末の黒船来航に関する一枚の絵から始まり、西洋と日本との関わりが美術史というよりも日本史の本のように細かく書かれている。各章に著名な外国作家のモットーの引用があり、それが内容とどう交差するのか、興味をそそられた。そして本文の丹念な記述と、その調査力、問題意識の大きさに圧倒された。その頃わたしは、西洋哲学に興味が向いていたが、『海の鎖』は、その題名とともに、酒井忠康という人格を知るきっかけとなった本であった。
酒井さんと実際にお会いしたのは、わたしが勤めをやめて、鎌倉に住むようになり、哲学専攻の大学院に通っている1980年代である。哲学などをやっていると、就職口がないので、学芸員の資格を取ろうと、実習を近くの鎌倉近代美術館でできないかと、直接に学芸員室を訪ねたのだ。そのとき、対応してくれたのが酒井さんであった。事前の連絡も紹介もなしに来た学生に、ここでは実習できない旨を、あの暗い穴倉のような学芸員室で、やさしく説明してくれたことをいまだに憶えている。そのあと酒井さんは、ハガキで心当たりの実習ができそうな美術館をおしえてくれた。親切な方だとおもった。結局わたしは、師の矢内原伊作の推薦もあって、ブリヂストン美術館(現・アーティゾン美術館)で実習を終えた。だが、美術館へ就職することもなく、学業を続けた。
鎌倉の八幡様のあたりを歩いていると、どこかに向おうとする酒井さんの姿を見かけることがあった。わたしは大塔宮の奥の二階堂に住んでいたので、八幡様の境内は通り道だった。鎌倉近代美術館はその境内にあったので、よく立ち寄った。わたしの実際の美術のとの接触は主にこの美術館によっていた。それを考えると、酒井さんや他の学芸員の方々に間接的に美術を教えてもらっていたことになる。
1989年に師の矢内原伊作が法政大学哲学科を退職し、その年の8月16日に亡くなってしまった。わたしは、師の最後の弟子だったので、もっぱらジャコメッティ関係の遺品の整理を行った。困った問題は、遺されたジャコメッティのデッサンや版画、いまでは本になっている『ジャコメッティ手帖』(みすず書房)の資料の行き先であった。矢内原家の意向もあったが、わたしは酒井さんに相談してみようと思った。酒井さんは館長になっていた。そのときも酒井さんは丁寧にいろいろな方策をわたしにアドヴァイスしてくれた――その後、ジャコメッティのデッサンと版画は、この近代美術館の収蔵品となった。
そんなことがあって以来、美術館の展覧会を見たついでに、ときどき館長室を訪ねた。いまでも憶えているのは、ジャコメッティだけではなく、だれか日本の芸術家も研究すべきだ、という酒井さんの助言だった。そのころわたしは、仙台の友人の美術予備校で学科を教えていた。その関係から、仙台の現代美術のギャラリーで企画を手伝うことになった。わたしは、いくつかの個展を企画し、有名であっても無名であっても、直接に芸術家と係わるようになり、それは美術を知るいい勉強となった。そんな活動が評価されたのか、『宮城県芸術年鑑』の美術の編集委員になり、その記事のために県内の展覧会を見てまわるようになった。また2002年より宮城県の文化創造事業(芸術銀河)の一つとしての若手作家の発掘・育成のためのコンペの企画・開催を任されるようになった。そのとき、この事業の企画を立てるにあたって相談したのが酒井さんであった。
規模、経費、募集、審査員など、いろいろなサジェスチョンを受けた。「ニュー・アート・コンペティション・オブ・ミヤギ」(略してNACOM)という名称も酒井さんと相談して決めたものだ。審査員を一人とするのも酒井さんの案である。むろん最初の審査員は酒井さんになっていただいた。このコンペは、個展形式で、せんだいメディアテークを会場とし、宮城県出身の45歳までの作家が対象であったので、県内外から多数の応募があった。コンペは、10年間続ける予定であったが、途中、芸術に関心のない知事に代わってしまったため、5年で終了となった。しかし、短い期間であったが、全国に知られるようになった作家も輩出できたので、この企画はいまでもよかったとおもっている。
2011年は東日本大震災の年であった。すでにわたしは仙台に居を移していたので、当然、被災した。いままでに経験したことのない揺れで、立っていることが困難だった。それまで、かならず仙台に地震がくるといわれてきたので、家具などを倒れないように細工していたが、天井の蛍光灯は落ち、食器棚のガラスも割れ、棚の本は飛び散った。電気もガスも水も止まった。子どもの頃、北海道で震度5?6の地震は経験していたが、これは強烈だった。生後2ヵ月の小さな黒猫はショックで火鉢の横でボロ雑巾のようなっていた。外に出ると、地盤が沈んだのか、門扉が傾いていた、隣のアパートでは水道管が破裂し、水が噴き出していた。結局、ライフ・ラインが復旧するまで2ヵ月くらいかかったとおもう。或る意味、震災によって、生活も精神もゼロ・ポイントになった。ただひたすら生きていたような気がする。震災から2年経ち、生活は回復したけれど、精神はずっと空っぽだった。それで何気なくおもいついたのが、親しい美術仲間と同人誌を始めることだった。
なぜ同人誌なのか。そのころのことを考えると、こころの交流の場、「友情」を欲していたのかもしれない。誌名は「森ノ道」とした。これはハイデガーの著作にも与っているが、セザンヌやジャコメッティがテーマとしたクレリエール(林間の空き地)が背景にあった。それは、ハイデガー的に言えば、リヒトゥング(明るみ・開け)となる。堅苦しい哲学的解釈は抜きにするが、われわれ現存在の明るみ・開けを希求したのである。ともかく、底辺から出発したかったのだ。だから、印刷所も使わず、プリンターと製本機を買って、自ら編集・印刷・製本を行うことにした。表紙は画用紙だから、工作と同じで、手作りを旨とした。
何かの機会に、美術家が文章を書く同人誌を始めることにしましたが、どうでしょうか、と酒井さんに言うと、酒井さんも参加するという。同人誌好きの酒井さんだから、予想はしていたものの、なんだかうれしかった。同人誌は季刊だったので、年四回、同人八人分の原稿を一人でまとめ、編集、印刷するのはけっこう苦労する。酒井さんの原稿は、毎回A4紙3枚のワープロで打ったものだが、紙面にするためには、もう一度原稿を打ち直す必要があった。もっと効率的なやり方もあるのだが、わたしは敢えてこのやり方に従った。その方が酒井さんの文章を味読できるし、挿絵のアイディアも湧いてくるのである。
いまの酒井さんの文章は、若いころのものと比べれば、かなり「ゆるく」書いている。だからといって、内容がゆるいわけではない。毎回、落語でいう「オチ」に向って、文章で語られているのである。酒井さんの最近のものは、書くのではなく、語りに近い。たとえば、本書第1章の最初のテクスト「一字違いのこと」は、『森ノ道』創刊号に寄稿いただいたものだが、最初の原稿には、「ドイツ文学のO先生」「音楽評論家のY先生」となっていた。本書では、それぞれ本名の「小塩節氏」「吉田秀和氏」になっている。よく読めば、O先生でもY先生でも、その本名は想像がつくように書かれている。ヒントが文脈にちりばめられている。
また、毎回おもうことだが、酒井さんの執筆意識のスタンスである。酒井さんは、本当は偉い人なのに、なぜ自分をこんなに低くするのかとおもう。それは、北海道出身だからだろうか。ちなみに、『森ノ道』の同人の半分、わたしを含め四人は、北海道出身者である。以前、北海道出身の同人に「きみの根源は何か」と訊いたとき、彼は「荒野」と答えた。わたしも同感であった。
きっと酒井さんも同じだとおもう。酒井さんのところは、余市なので、海もあるから、厳しい風土である。酒井さんの著作のなかでわたしが特に好きなのは、『海にかえる魚』(未知谷)である。これは、酒井さんの故郷余市での子どもの頃の記憶を童話にしたものである。「水族館の魚もきっと海にもどりたいにちがいない」と想像した酒井少年は、水族館に行って、「がや(エゾメバル)」の絵をクレヨンで描くのである。すると、それは生きた魚になって海にかえっていく……という話である。
酒井さんは、たいへんな読書家である。教えられた本はいくつもあるが、とくに、ハーバート・リードの『グリーン・チャイルド』(増野正衛訳、みすず書房)は、凄い本で、わたしの愛読書である。かつてわたしは、死んで、塵になりたい、とおもっていた。だがこの本でリードは、肉体が石化し、純化されて、結晶となることが、大地との合一であり、宇宙の調和の一部となることであって、これこそ不滅の美である、というのである。これは衝撃だった。リードは、酒井さんが敬愛する作家である。わたしは、宇佐見英治から、彫刻の研究者になってくださいと、彼自ら訳したリードの『彫刻の芸術』(みすず書房)をいただいて以来、リードの本を愛読してきたが、酒井さんよりも多く深くは読んでいない。
『森ノ道』には、なるべく彫刻家について書いてほしいと酒井さんにお願いしたかどうか忘れてしまったが、それでも比較的多く書いていただいたような気がする。とくに若林奮についての「虫籠」(本書では「ある彫刻家の虫籠」と改題されている)は、若林奮一家のほのぼのとした生活を垣間見ることのできる愛情あふれるエッセイである。酒井さんは、若林奮を愛している。それは、酒井さんからいただいた貴重な本『若林奮 犬になった彫刻家』(みすず書房)を読んで、そうおもったのである。「若林奮に関する『備忘録』」には、「彼となら何時間でもしゃべっていられる……二人の対話の空間は延々と持続する」と書いてある。たしかに、この本での若林との「対談」でも酒井さんは自然に饒舌である。だからといって、一方的にしゃべっているわけではない。よく理解しあえる関係性なんだとおもう。そういう相手には、滅多に出会えない。この本は、その装丁の手触りとともに、友情のかたまりである。
さて、酒井さんから教えてもらったことを、時間順におもいつくままに書いてきたが、一番重要な教えは、酒井さんがエリック・ホッファーについて語っている言葉「平易な表現で自分の心の内を正直に伝えること」である。『海の鎖』との出会い以来40年余りになるが、最近の酒井さんの文章を読みながら学ぶことは、低く素直に語ることで、それによって、あたたかい読書空間がひろがり、われわれも安楽になれるのである。これは、ある種の直接性の境地に近いものではないかとわたしはおもっている。
(美術評論家)
copyright © TAKEDA Akihiko 2021
(著作権者のご同意を得て転載しています)