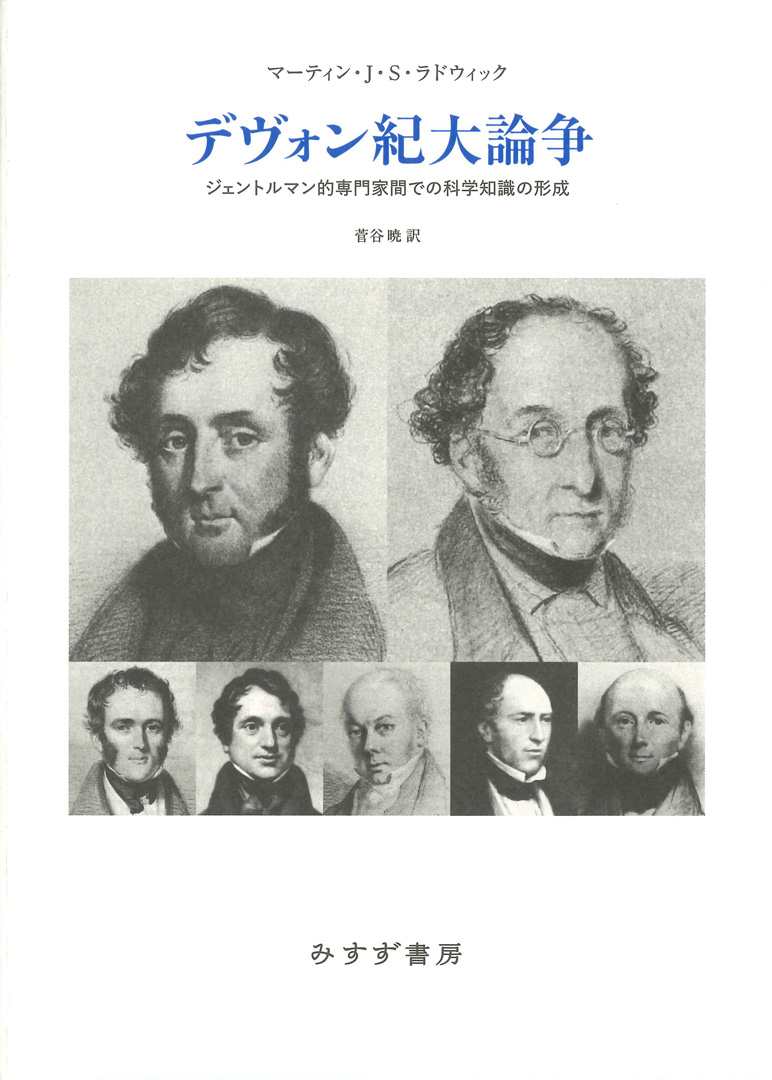デヴォン(またはデボン)紀がおよそ4億2000万年前からおよそ3億6000万年前まで、6000万年続いた地球の歴史の一時期(その期間に堆積した地層がデヴォン系)であり、デヴォンの名称はイギリスの一地方デヴォンシャーにちなむことをご存知の方も、デヴォン紀という用語と概念が確立するまでに「大論争」が存在したことは初めて知るのではないだろうか。それも当然のことではある。その過程に「大論争」のあったことは、本書において初めて明らかにされたのだから。いわば本書によってデヴォン紀論争が「発見」されたのである。たとえばゴオーの『地質学の歴史』(菅谷暁訳、みすず書房、1997、246頁)には次のようにある。「その頃、デヴォン州の岩層に含まれる動物相は、一部分はシルル系の動物相に、一部分は石炭系の動物相に類似しているのに対し、他の一部分はその岩層に固有のものであることが明らかになった。再びマーチソンとセジウィックの研究により、その累層はスコットランド、南イングランドおよびアイルランドの旧赤色砂岩と同時代のものであることが確認された。そしてデヴォン州の海の動物相は旧赤色砂岩の陸の動物相より豊富だったので、シルル系と石炭系の間の系はデヴォン系と呼ぶことが提案された(1839年)」。一般的知識としてはこれで充分である。しかしラドウィックはデヴォン紀確立の過程が豊かな物語的叙述になりうることを確信し、10人ほどの人物の思念と行動をほとんど月ごとの詳しさで追跡して、これほどの大著を書きあげた。しかもその書き方は非常に特異なものであった。
科学史の分野では、「ホイッグ史観」にもとづいた歴史記述は一般に避けなければならないとされる。これは成功したその後の科学の視点からそれ以前の科学を裁断する、「勝利者史観」とも呼ばれる歴史の見方である。デヴォン紀論争に関して見るなら、成功したデヴォン紀という概念の形成に貢献した者たちの事蹟のみが語られ、誤謬の道に迷い込んだ者たちはその誤謬の原因が糾明されることになる。しかしラドウィックは当然ながらこのような「史観」による記述を排除した。しかもその排除の仕方はこれ以上ないほど徹底したものであった。本書から引用すれば「特定の科学的発展の初期の段階を、いまだ提起されていない問題、いまだ実施されていない実験、いまだ考案されていない理論、いまだ書かれていない出版物に対する時期尚早の言及」(本書15頁、本書からの引用は以下では頁数のみ示す)を行ないつつ記述してはならないのである。「ある科学者が9月に言ったり書いたりしたと歴史家として知っていることによって、それ以前の7月に彼らがいったい何をしようと考えていたかの判断が歪められてはならない」(15-16)。「後知恵」の適用は不可ということである。その結果、物語的叙述の内部では、デヴォン系についての現在の知識からの説明はいっさいなされないことになった。読者は当時の地質学者の知識の水準で、ともに「デヴォン系問題」を考えていかねばならない。用語も現在の体系による言い換えや補足は行なわれない。彼らが使っていたしばしばわかりにくい語がそのまま使用される。読者は漸移紀、グレイワッケ、カルムなどのなじみのない用語と格闘することを余儀なくされる。そもそもデヴォン紀(系)という語もその概念が提起されるまでは用いられない。物語的叙述の内部では、デヴォン紀論争(Devonian Controversy)という語が初めて登場するのは第12章第6節(494)でしかない。それまでは一貫してデヴォン論争(Devon Controversy)と呼ばれるのである。
結果として、物語的叙述の部分は気軽に読み進められるものではなくなった。本書のすぐれた書評を書いたスティーヴン・ジェイ・グールドは次のように述べている。「論争の当事者たち自身が、信じられないくらい混乱していたのだから、彼らの視点から語れば、読者も混乱してあたりまえではないか」(「物語の威力」、『嵐のなかのハリネズミ』所収、渡辺政隆訳、早川書房、1991、126頁)。用語を現代的に整理し、本筋とは関連の薄い者たちの記述を省き、その後の知識からの説明を加えれば、もっとわかりやすいものになったかもしれない。そうしていても、本書は間違いなく名著の誉れを獲得できたであろう。しかしラドウィックは「わかりやすさ」を犠牲にしてまで、当事者たちの視点から見ることに固執した。デヴォン紀という科学知識の形成のありのままの姿を記述したいと考えた。もっとも、ラドウィック自身も読者が感じる負担には気づいていたように思われる。「読者はその当時に歴史的役者たちにも入手できたような、方位確認のための陸標だけを目にして、直接性の波にもまれていると感じなければならないだろう。直接性の満ち潮から救われるにふさわしい瞬間は、物語的叙述のあとで、その枠組みの外部にでたときに訪れる」(19-20)と述べているからである。そして少々気が咎めたのであろうか「物語的叙述のなかにはまり込んで身動きがとれなくなったと感じた読者は……第15章における分析にただちに進んでも構わない」(18)とまで記している。だがグールドに言わせれば「しかし、読者はぜったいにそんなことをすべきではない。そんなことは許されるべきではないのだ。出版社は、最後の60ページを袋綴じにしておくべきだった。そして、第2部と第3部のあいだに第2部を読み通した者にしか答えられない多項式選択テストをはさみこみ、合格点を取らない読者は第3部の封を解くことはできないようにしておくべきだった。この本の価値は、詳細な物語にこそあるからである」(前掲訳書124頁)。
しかし訳者としては、その「とっつきにくさ」にもかかわらず、本書をできる限り多くの読者のもとに届けたいと願っている。そこでグールドの禁は破ることになるが、物語的叙述のなかで道に迷ったと感じるようなことがあったら、第15章の「解説篇」を参照していただきたいと考えている。ラドウィックもここでは「詳細な直接的事実の圧倒的とも思われる洪水から、救助される瞬間がついに訪れた。論争の既知の結果に照らした回顧的な熟考が、この時点で許される」(598)と述べている。当初訳者は読者の負担をいくらかでも軽減するために、各章の粗筋をこの「あとがき」に添えようと思っていたのだが、それは思いとどまることにした。ラドウィックが実際には多くの事実を乱雑な洪水のように氾濫させずに、絶妙の語り口でこの複雑な「群像劇」を見事に構成しているのを、つたない粗筋で傷つけたくはなかったからである(グールドは「どんなに入り組んだ推理小説であろうと、デボン紀をめぐる論争にくらべれば単純なものである」(前掲訳書127頁)と少々大げさに評しているが、もし物語的叙述の部分が「推理小説」的に読めるなら、「あとがき」でネタばらしをするのはルール違反であろうと考えたからでもある)。
それでも粗筋に代わるものとして、各当事者の行動の軌跡(これは第15章第3節にある)ならぬ岩石の解釈の軌跡を描くことはできないだろうか。旧赤色砂岩、山稜石灰岩、カルム、あるいはさまざまな石灰岩(黒色カルム石灰岩、ストゥリゴケファルス石灰岩、大石灰岩、南デヴォン石灰岩など)について、どのように解釈が変遷したかを考えることは、物語的叙述の部分の理解に資するのではないか。だがそのすべての岩石について解説することは、いわば補助線を引きすぎてかえって図柄を不鮮明にする恐れがあるし、いずれにせよ「あとがき」の範囲を逸脱する。そこで以下には旧赤色砂岩だけについて解釈の軌跡の素描を試みることとしたい。些少のガイドとして役立ってくれればよいのだが。[後略]
copyright © SUGAYA Satoru 2021
(著作権者のご同意を得て抜粋・転載しています)