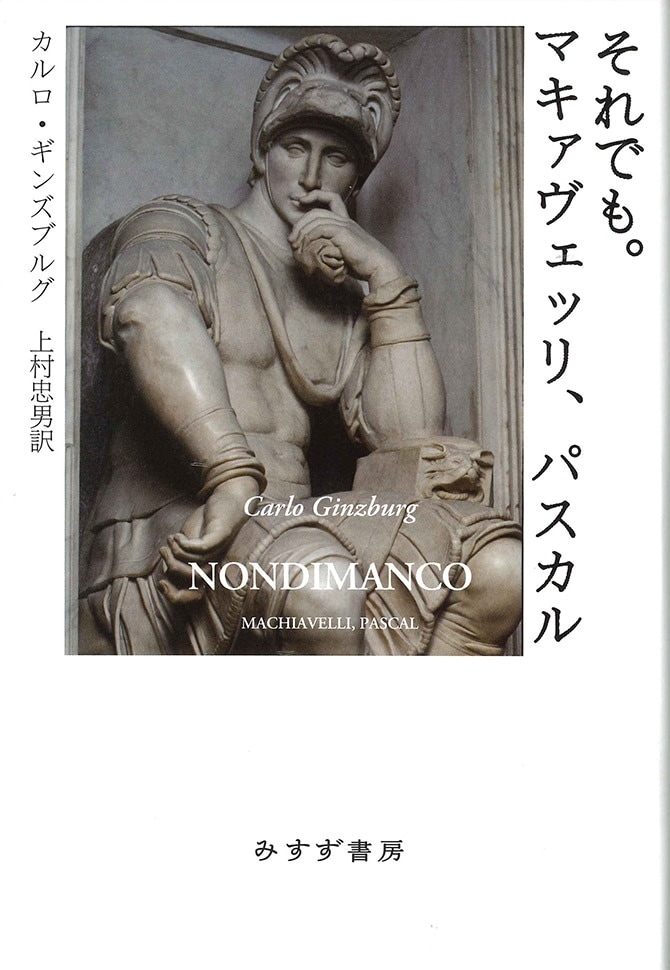マキァヴェッリとパスカル。ふたりは遠く離れた位置にありながらも、緊密につながっていた。本書において歴史家ギンズブルグはテクストの細部を凝視したところから浮かび上がってくる徴候を手がかりにして事柄の核心に迫ろうとする持ち前の手法を駆使して、両者のあいだに存在するとみられる秘かな連関を明るみに出そうとする。
そのさい、ギンズブルグが着目するのは、アリストテレスに由来する中世神学の決疑法(casuistica)、すなわち良心問題にかんして一般的な道徳的規範を個別の事例(casus)に適用するにあたっての実践的な技法への両者の関わり方である。
ルネサンスの時代、従来の宗教的伝統から自由になったところで新しい世俗的な「統治の技術」を編み出し、近代的な政治学への道を切り開いたとされるマキァヴェッリは、じつは中世神学の決疑法から多くを摂取していたとギンズブルグはみる。そしてこのことは、『君主論』や『ローマ史論』において、まずは一般的な原則が提示されたうえで、「それでもnondimanco」という接続詞を置いて、原則の適用が除外される例外的事例を挙げる論法が多用されていることから裏づけられるという。
かたや、パスカルといえば、対抗宗教改革の時代にイエズス会士たちが実践していた決疑法にたいする容赦ない批判者として知られる。ただ、たとえば『パンセ』には、法律を時々の必要に応じて曲げることをしていなかったなら、諸国家は滅んでいただろうが、宗教はそれを許さなかったため、奇蹟が必要とされたという述言がみられる。このパスカルの述言のうちにギンズブルグはマキァヴェッリの「それでも」と通底するものを見てとるのである。
こうした理解を根底に据えつつ、全体で一〇章からなる本論では、文献学者としての本領を遺憾なく発揮して、関連する書物が縦横無尽に渉猟される。そして行間に見えないインクで書かれている事柄があぶり出される。最後に補論として付されている『山猫』にかんする覚え書きも、そうした「行間を読む」試みの具体的成果のひとつである。
Copyright © UEMURA Tadao 2020