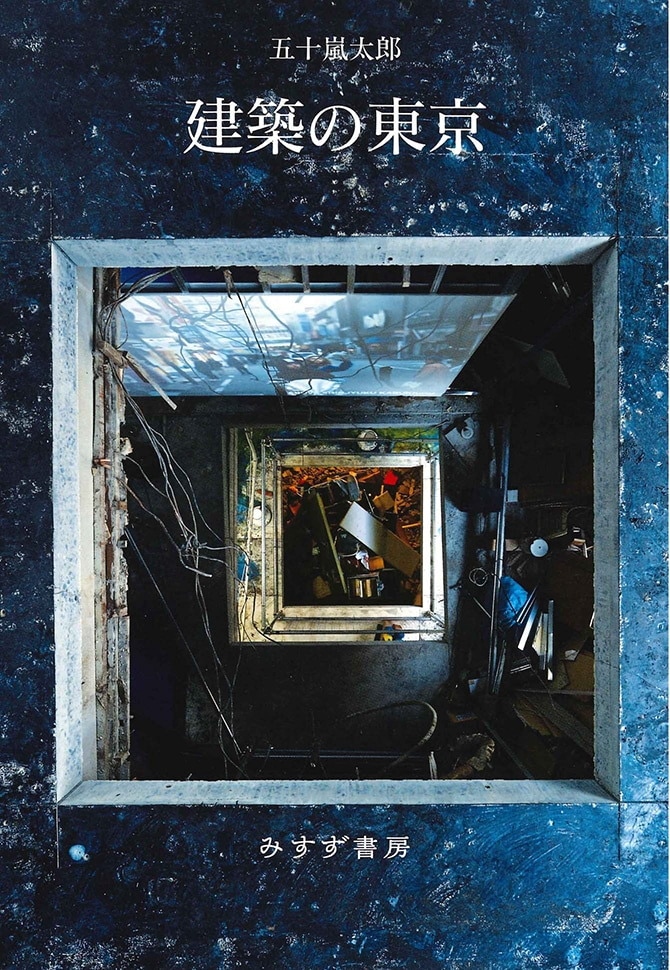この文章は、新型コロナウイルスが世界的なパンデミックを引き起こし、東京オリンピック2020の開催が危惧されている3月中旬、宮崎県にて執筆している(校正時、1年程度の延期が決定)。新しく令和の時代を迎え、最大級の国際的なイベントが東京を祝福しようというタイミングで、再開発が促進され、さまざまな建築が登場した。華やかにみえる21世紀の東京。そこに思わぬかたちで影を落としたのが、見えない伝染病である。が、仮にそれがなかったとしても、新しい東京の姿を手放しで褒めたたえてよかったのか。もしかすると東京の建築は黄昏を迎えているのではないか。
筆者は1985年に上京してから、2002年に名古屋で職を得て2拠点の生活を始めるまで、 駒場、田端、そしてとくに愛着をもった吉祥寺などに暮らし、17年間にわたって東京を中心に活動していた。建築を学んだのも東京である。『建築MAP東京』で表象されたように現代建築の花園だった。ちなみに、1980年代に世界の建築界をリードしていたのはアメリカである。が、もはやそうした地位を失った。実際、アメリカ人の建築家は1991年以降、プリツカー賞をとったのはわずかひとりである。逆に近年は日本人の建築家の受賞が続く。筆者が東京を拠点とした時期は、バブル経済を背景としたポストモダン建築の全盛からユニット派の登場を経てリノベーションが重視されるようになったころである。その後、地方都市で教鞭をとるようになって日本地図の見え方が変容した。外からの視点で東京を見るようになったからだ。痛感したのは建築家の事務所、メディア、文化施設などさまざまなものがやはり東京に一極集中していること。だが、近年は東京に注目すべき建築が減っているのではないかという疑問を抱くようになった。東京は慢心しているのではないか、と。それは上海、ソウル、ロンドン、パリ、ニューヨークなど海外の都市を訪れるなかで確信になった。もちろん長く住んでいた人間として、本来、東京はポテンシャルがあり、もっとすぐれた建築がふえてほしいと思っている。しかし残念ながら、現状はそうではない。東京は冒険しなくなった。
むしろ、本文でもふれているように危機感をもった地方都市にこそ実験的な建築が登場している。 たとえば宮崎県で見学したばかりの場所をあげよう。内藤廣による日向市駅と日向市庁舎、あるいは乾久美子による延岡駅周辺のプロジェクト。前者は多様な主体がまとまる仕掛けとして地元の杉材を選び、それをどう合理的に活用するかを探求しており、木さえ使えば日本的という稚拙な議論ではない。後者は昭和モダニズムの駅舎をリスペクトしつつ、それを現代的に増築したかのような複合施設をそっと横に置く。いずれも東京のまねをしていない。そして経済原理に縛られた東京と違い、空間に余裕がある。現在、こうした建築を紹介すべく筆者はウェブマガジン「WirelessWire News」で「反東京としての地方都市を歩く」という連載を執筆しているが、その内容は本書と対をなすものだ。では、東京はどうすればよいのか。最終章で述べたように、地方がまねする「東京」の焼きなおしを東京がやるのではなく、それでも資金力がある東京にしかできないことを追求すべきだと思う。(…)
ペースメーカーとなる連載の場(「みすず」2018年7・10・12月号、2019年4・6・8・10・12月号、および2020年4月号)をいただき、なんとか最後までこぎついたが、約1年半の連載中、新しい事態が起きることで当初予定していた内容とはだいぶ違う進行となった。ゆえに個人的にはライブ感のある文章ではないかと思う。ちなみに本書の各章は、連載と同じ順番で並んでいる。文中では、これまでに書いた東京に関する論考なども組みこんだ。それぞれに関わった編集者にも御礼を申しあげたい。
経済大国として輝いた時代は過ぎ去った。いまや近代の底が抜け、国家の体をなさない政治の状況が深刻化するにつれ、他国を侮辱し、日本を礼賛する言説が垂れ流されている。建築もこのままではダメになってしまう。本書はあえて東京に苦言を呈しているが、将来、21世紀初頭に現代建築のピークがあったと過去形で語られないように、東京はすぐれた建築家の才能をもっと使いたおすべきである。
copyright © Igarashi Taro 2020
(著者のご同意を得て転載しています)