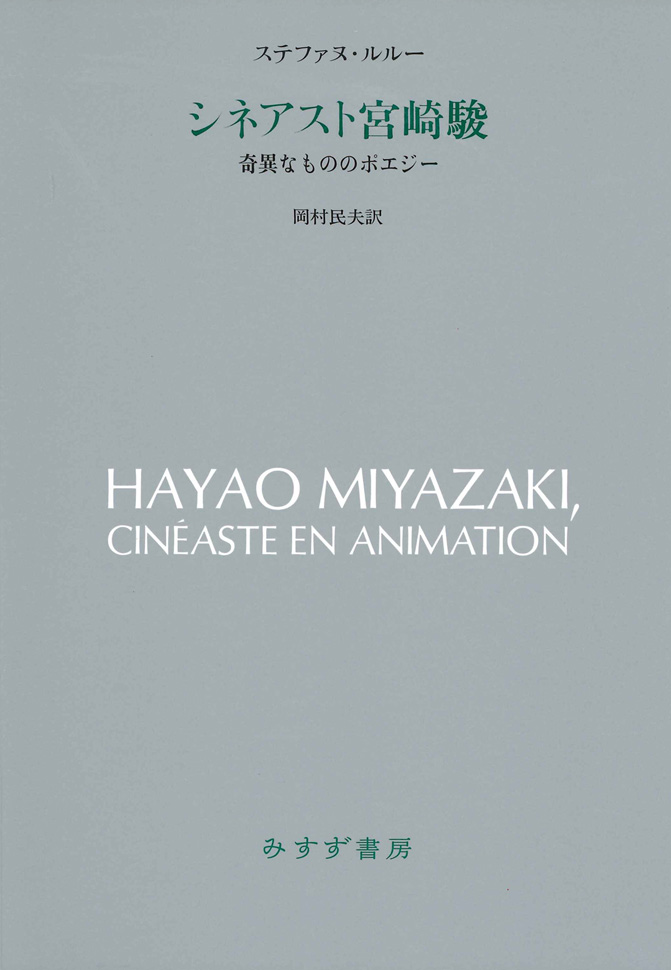これまで映画に関するものを細々と間欠的に書いたり翻訳したりしてきたが、私がはじめて監督やスタッフの存在を強く意識したのは、高校生のとき、NHK初のアニメシリーズとして放映された『未来少年コナン』を観てだった。全体を組織している強烈な人間がいると感じ、アニメ雑誌を買って確かめた。そしてはじめて公にした文章は、大学院生になってほどなく封切られた『天空の城ラピュタ』の映画批評だった。けれどもそれ以降、宮崎駿について書く機会を逸し、何かやるべきことをやっていないような後ろめたさを心の片隅に感じてきた。『シネアスト宮崎駿──奇異なもののポエジー』を翻訳し終え、肩の荷がずいぶん下りたような気がする。
2011年に刊行された本書は海外における単著の宮崎駿モノグラフィの草分けのひとつであり、フランス語圏におけるその嚆矢である。『崖の上のポニョ』(2008年)や『風立ちぬ』(2013年)への言及が欠けているにもかかわらず翻訳したのは、歴史的価値があるばかりでない。現在の日本の読者に対しても非常に刺激的なはずと思ったからでもある。アニメファンは「彼のヴィジュアルな豊かさを讃え、評論家は彼のテーマの密度を誉めるが、彼が同時に、たぶん何にもまして真の映画演出家であるということを強調することがあまりにしばしば忘れられている」。そこで「彼の数多くの才能のなかでも間違いなくもっとも配慮されてこなかったシネアスト宮崎という側面を理解するため」この本を書いたとステファヌ・ルルーは「序」で述べている。これは2011年の時点でのもっぱらフランス語圏における受容に対する批評であるはずだが、現在の日本における受容に対してもまったく妥当する。わずかな例外をのぞき、あまたの宮崎駿論は彼の映画の文体的特徴を無視したままストーリーやセリフや図像の水準で思想・体験・無意識・影響関係・受容などを云々する。ルルーが貫徹しているのは編集・カメラワーク・フレーミング・構図・音声と画面の関係など映画学的水準での分析であり、それをふまえた映画史的・アニメーション史的考察である。(…)
「シネアスト」に劣らず「演出家mettreur en scène」および「演出mise en scène」という語が多用されているのは、演劇的なものを強調してではなく、原語がもつ「シーンに配する」というニュアンスにもとづいてと思われる。宮崎が建築家・造園家的才能によって美術背景のデザインに関与し、登場人物のふるまいや出来事や表現手法が美術背景の委細と密接な相関関係に置かれていることをルルーはくわしく分析している。
「シネアスト宮崎という側面」の強調は、実写とアニメーションの相違の軽視を意味するわけではまったくない。むしろ反対である。ルルーは映画的手法やリアリズムがアニメーションに導入されることによって生まれるダイナミクスに注目し、それが宮崎の世界的にユニークな創造をもたらしたととらえている。本書の原題が『アニメーションにおけるシネアスト宮崎駿──奇異なもののポエジー』とされているゆえんだろう。
2004年の『ハウルの動く城』までのフィルモグラフィ──狭義の監督作品だけでなく宮崎が「場面設計」・部分的演出・絵コンテなどを通じて自分の刻印を深く映像に刻んだ他監督の作も含む──が大きく三期に区分されており、それぞれにほぼ一章が割かれている。
(1)アクションコメディの時期──『長靴をはいた猫』(矢吹公郎、1969年)から初監督テレビシリーズ『未来少年コナン』(1978年)まで。(…)
(2)「驚異的なもの」のうちに「自然なもの」をはらんだ冒険映画の時期──初監督長編映画『ルパン三世カリオストロの城』(1979年)からスタジオジブリ第一作『天空の城ラピュタ』(1986年)まで。(…)
(3)「奇異なもののポエジー」の時期──『となりのトトロ』(1988年)以後。(…)
ルルーのいう「奇異なもの」は、シュルレアリスムの流れを汲みながら、屠殺場を静謐に表現したドキュメンタリー『獣の血』(1949年)や、他人の顔の皮を娘に移植するホラー映画『顔のない眼』(1960年)、主人公が鳥頭の仮装をする犯罪映画『ジュデックス』などを撮ったフランス人監督ジョルジュ・フランジュから拝借した概念であり、シーン全体の幻想性よりも、むしろ文脈上の違和感、日常の「となり」に異常なものが共存するシチュエーションにかかわる。
三期の分節はけっして杓子定規なものではない。先行する時期の技法やモチーフがのちの時期の作品において基礎的役割や付随的役割を果たしたり、未来の萌芽がマージナルな作品や流産した構想に散見したりすることや、作品や場面ごとの度合いの差などにもルルーは配慮を払っている。『ルパン三世 カリオストロの城』は、第一期の特徴を色濃く兼ねそなえた中間的作品として論じられている。「宮崎は、遠心的なエキストラ役をテレビシリーズ『名探偵ホームズ』でシステム化する」という指摘や、『パンダコパンダ』(高畑勲、1972年)のラストでパパンダが動物園からミミちゃんの家へ帰宅するシークエンスを「奇異なもののポエジー」の最初の噴出とする評価は卓見といえよう。
時期区分や各時期の特徴をめぐる論述には数多くの他のアニメや実写映画との比較が伴っており、影響関係・時代性・宮崎作品の特質などを浮き彫りにすることに大きく役立っている。なかでもとくに重要なのは、1930年代末-60年代のディズニーに代表される「古典的アニメーション」との比較とポール・グリモーおよび高畑勲との比較にほかならない。(…)
要するに宮崎駿は、学びとった高畑的リアリズムをそれと矛盾しかねない自己の性向と対話的・批評的関係に置き、オリジナルな第三の領域の創造へ展開したといえる。おそらくその付随現象だろう、まるで宮崎が過去の高畑作品に高畑以上に拘泥し、それを再構築しているような局面が見受けられるのだ。第3章の最後でルルーは『千と千尋の神隠し』の電車のシーンが『火垂るの墓』(1988年)の電車のシーンに対する応答となっていることを説いているが、その種の創造的応答は相当前の作品をめぐってもいろいろ指摘できる。
たとえばオジイが亡くなって孤島にひとり遺されたコナンが遺言にしたがい仲間を求めて船出するという『未来少年コナン』の出だし(第二話「旅立ち」)は、ホルスの出だしとあからさまに類似している。『パンダコパンダ』が『となりのトトロ』の原型となっていることや、『パンダコパンダ雨ふりサーカス』(高畑勲、1973年)の洪水のシークエンスが2008年の『崖の上のポニョ』のそれの先駆けとなっていることはもはや定説である。『太陽の王子ホルスの大冒険』における村とグルンワルドのヒエラルキーを逆転させれば、『もののけ姫』(1997年)のタタラ場ともののけ姫側の対立関係になる。(…)
本書の七割は、個々の映画の場面の詳細な描写に充てられており、それらはときおり論旨から逸脱しているところもある。訳すのはたいへんだったが楽しい作業だった。じつは私は、こうした部分に論述部に劣らぬ価値があると受けとめている。ルルーによる描写はきまじめに詳細なのではなく、映画のツボを押さえた分析となっており、その筆運びにはみずみずしい感受性や喜びが熱く脈打っている。場面のチョイスにもセンスが光る。
とりわけ『長靴をはいた猫』のラストのめまぐるしい追っかけ、『風の谷のナウシカ』で王蟲に襲われたユパを救うためにナウシカがメーヴェで飛び立つところから砂丘に着地してユパに抱きつくまでのシークエンス、『ルパン三世カリオストロの城』でルパンが廃墟の庭園をもの静かに散策するシークエンス、『となりのトトロ』のバス停のシークエンス、『魔女の宅急便』(1989年)でパン屋に住みこむことになったキキが迎える最初の朝のシーンの記述に私は感心した。この種の記述には、その場面をあらためて鑑賞することや、その見解を彼が論じていない場面や作品と突きあわせてみることへ私たちを誘う力がある。(…)
ステファヌ・ルルーが宮崎駿の思想に踏みこまないことを物足りなく思う読者は少なからずいることだろう。スペクタクル芸術コースの博士論文がもとになっている以上当然とはいえ、たしかに各章の結論は美学的範疇をこえない。けれどもルルー自身いくどかふれているとおり、「驚異における自然なもの」や「奇異なもののポエジー」といった美学的概念は、戦争・政治・生活・技術・エコロジー・アミニズムなどについての宮崎の省察と深く接しあっている。つまりこの本は、読者があらためて宮崎の思想を検討すること、それをよりアニメーションの生態に即し、世界に対する根本的態度としてとらえなおすことへも開かれているのである。
岡村民夫
Copyright © OKAMURA Tamio 2020