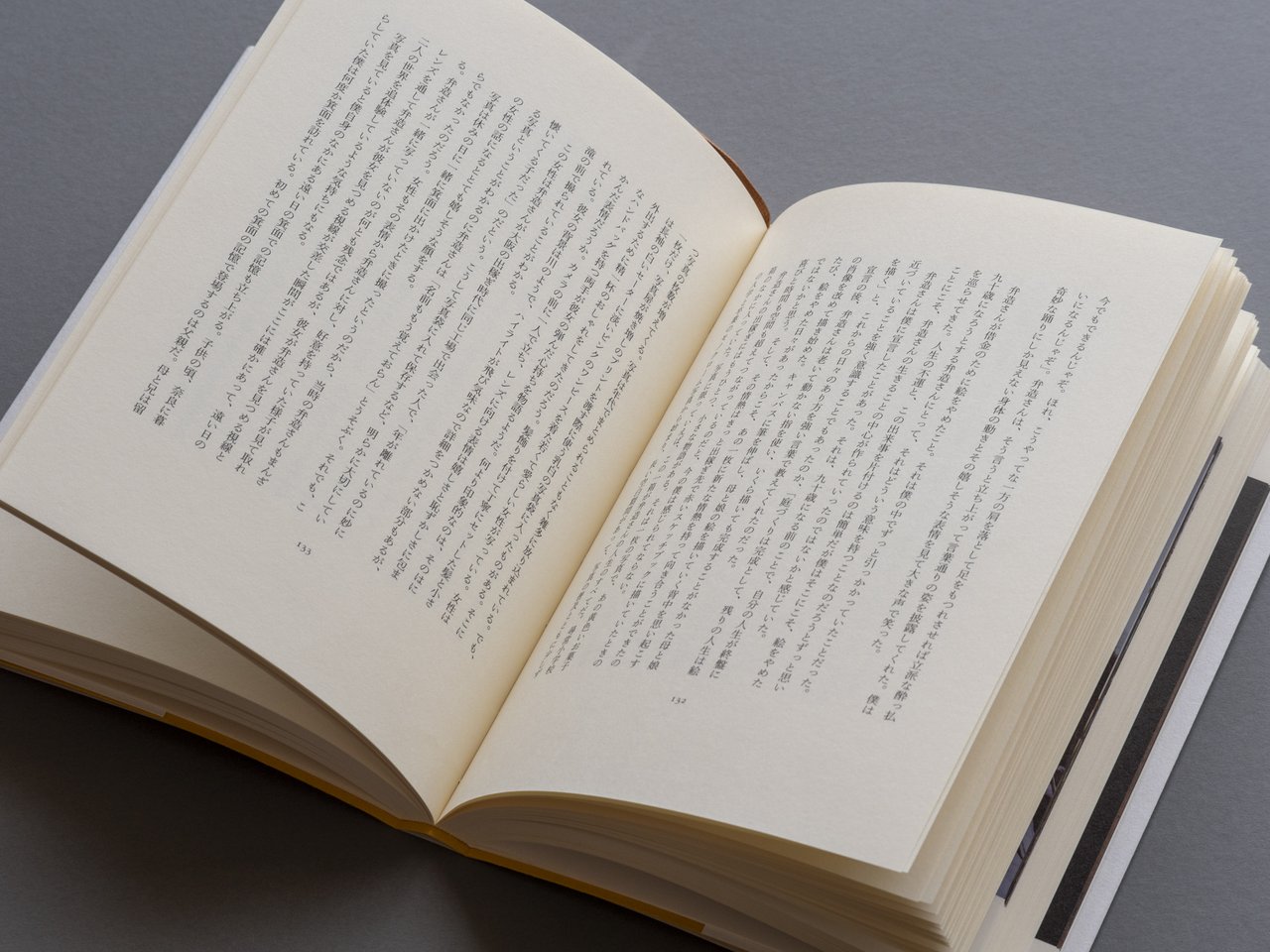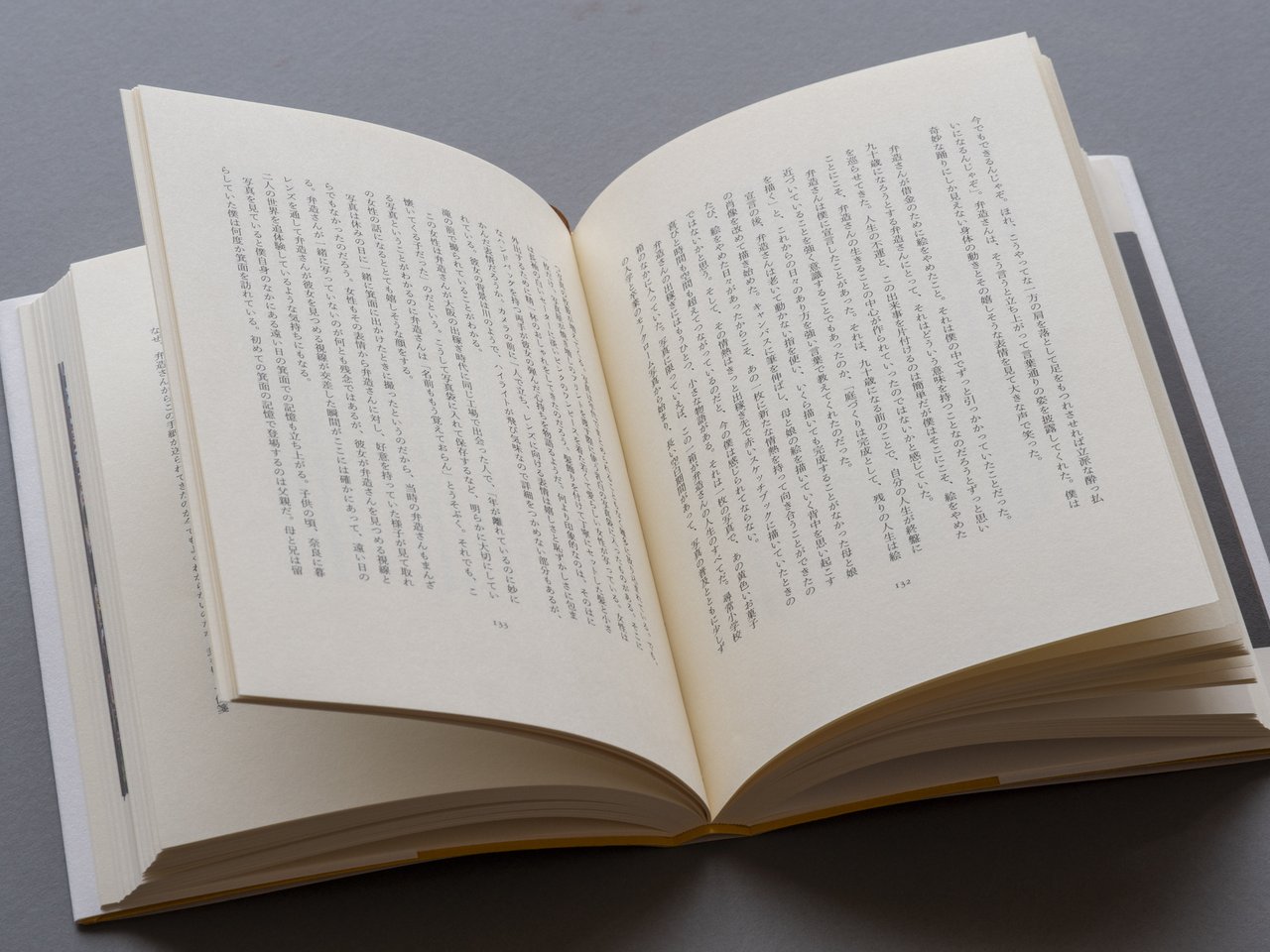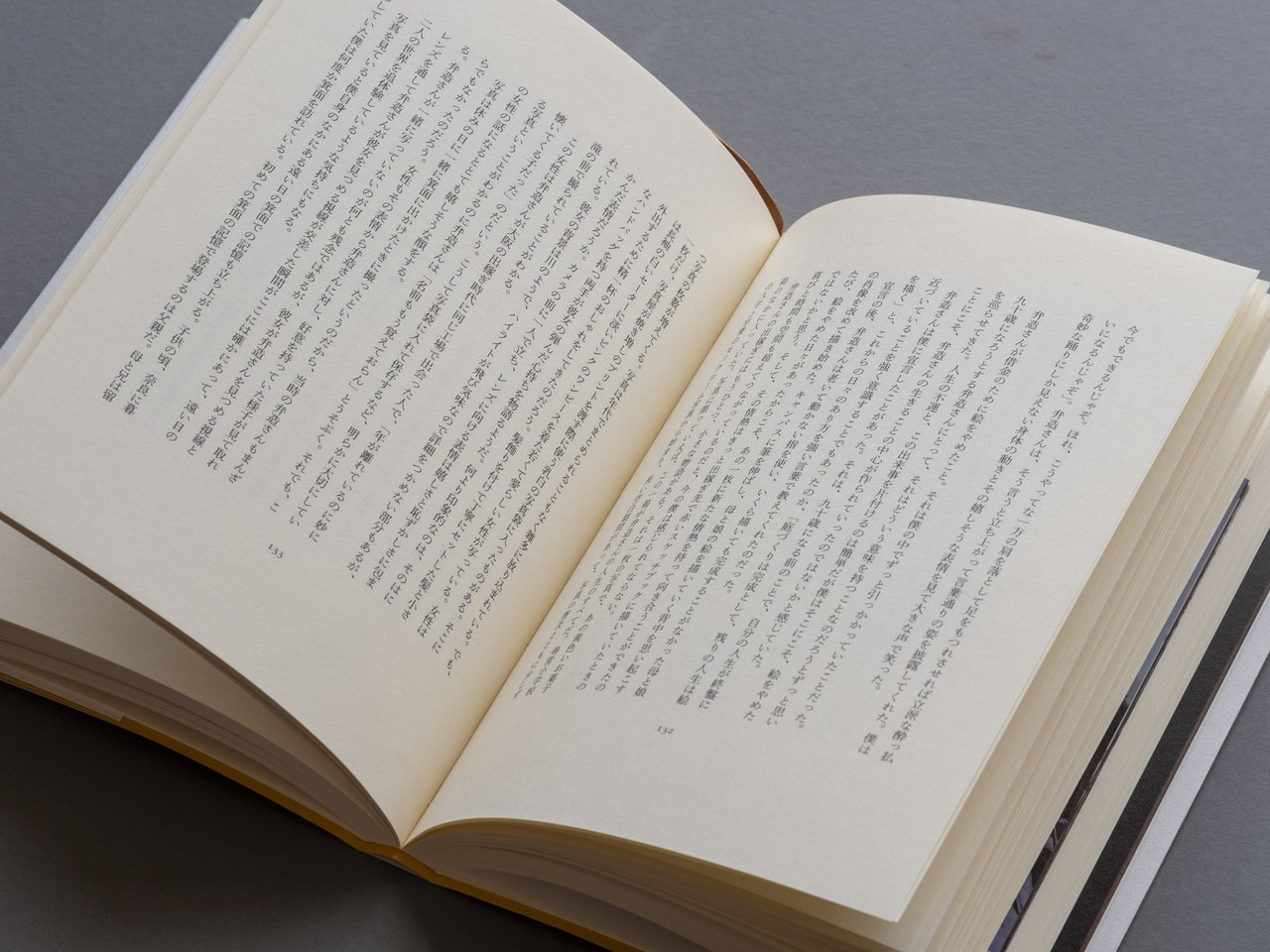(写文集『庭とエスキース』の刊行によせて、著者からエッセイをご寄稿いただきました)
母と娘、小さなエスキースのサイン
奥山淳志
弁造さんがいなくなった丸太小屋にはたくさんのエスキースが遺されていた。衝動的に描いたのだろう。買い物のレシートの裏、封筒、包装紙。部屋のあちこちにぞんざいに放り投げられた紙切れの上には、弁造さんの震える指で描かれた線によって浮かび上がる女性たちがいた。もう、この線を描いた本人がいなくなってしまったからだろうか。女性たちは瞳の先を見つめるばかりで沈黙しているように見えた。
弁造さんの遺品整理はまずこうしたエスキースを集めていくことから始まった。たったひと部屋でひとつの窓しかない小さな丸太小屋には92歳という弁造さんの人生が詰め込まれていた。食器や衣類、掃除機などの生活用具は単なるモノでしかないはずだったが、弁造さんと長い時間を過ごしていたからだろう。体温にも似た熱を帯びているようにさえ感じるのだった。この丸太小屋をそのまま残したい。部屋を見回した僕はそう思った。しかし、それは許されることではなかった。弁造さんは遺言書に自分が死んだら丸太小屋も隣にある納屋もすべて解体してまっさらにするようにと、それにかかる費用も残していた。しかも、この遺書を作るための相談を弁造さんから受けて、それならば公証人役場へ行って遺書を作成するのがいいでしょうと話したのは僕自身だった。
晩年の弁造さんは「死んだら無になる。0(ゼロ)になる」と繰り返し語っていた。そんなとき、殊更「0(ゼロ)」を強調した。弁造さんが言うゼロとは、何を足そうが掛けようが絶対に変わることがない「無」であって、それはいわゆる数学の「0の概念」が生命にも当てはまるということだった。弁造さんはこの信念に従って、自分が死んだときには70年近くも暮らした丸太小屋を無にしようと遺言書に書き込んだのだった。
「あんたにも言っておくぞ。わしが死んだら、この封筒を開けて中に書いてある通りにすりゃあいい。すべてがきれいに片付く」。A4サイズの茶封筒に大きな文字で「遺言書」と記し、そう言っていた弁造さんの顔を僕は思い返した。あのときの弁造さんは実に満足そうだった。公証人役場に何度も通い、一度作成した遺書を書き直したりしながら手間も費用もかけて完成にこぎつけたからなのかもしれなかったが、自分が逝ってしまった後のことを話す弁造さんは大きな仕事をやり終えたかのような満ち足りた表情だった。その日のことを思い起こした僕は、やはりこの丸太小屋を整理しようと再び決心した。弁造さんはもういなくなり、0になってしまったのだ。弁造さんそのものである小屋もまた同じ0になるのがいいのだろう。
でも、絵に関するものだけは無に帰すことはできないと思った。子供の頃から絵描きになる夢を抱き続け、挫折を経験しながらも弁造さんは最晩年まで絵筆を握り続けた。弁造さんにとっての絵は、老いを深めるにつれて重要度を増した。ただ、思うようにすいすいと描けたわけではない。部屋の真ん中には大きなイーゼルがあり、そこに立て置かれているのはいつまでたっても完成しない絵だった。弁造さんは「いつかは個展をしたい。絵描きが個展を開かん理由はない」と語っていたが、絵はいつまでたっても完成することがなかった。弁造さんに残された時間が多くないことは誰の目にも明らかで、僕はいつも完成をせっついたが本人は僕の意見など半ば無視するかたちでエスキースばかりを描いていた。絵を描き上げたいという弁造さんの思いは痛いように理解していたが、僕の目の前にいるのはどうしても描ききれない弁造さんだった。
そして、こうして逝ってしまっても、イーゼルの上にあるのはやはり完成していない絵だった。でも、きっとこれは弁造さんなのだ。生まれ、死んでいくまで生は途上であり続ける。そう思うと、途上のなかにあるエスキースはまさに弁造さんの生を宿したものであるように思えた。これらはすべて残そう。弁造さんが絵に何を込め、絵から何を得ようとしたのか。これらはきっと、弁造さんという存在を考え続けていく大切な材料になるだろう。そこから僕が弁造さんを通じてずっと探していた“生きること”のヒントが見つかるのではないか。それは確信に近い思いだった。
エスキースは部屋のあちこちに遺されていた。キャンバス類は弁造さん自身の身体のサイズに作られたベッドの上部の吊り棚にあり、手がつけられていないものがほとんどだった。また、板に描いた油彩画は、ベッドの正面の壁面に作られた棚に重ねられていた。弁造さんの描き方は思いついたイメージを紙切れに描くことからはじまり、デッサンを画用紙に描いてから油絵の具で色を着けると、次にシナベニヤに再び油彩で描くという流れが取られた。キャンバスが登場するのはこの次で、これを仕上げて完成ということになるのだが、いつもこの流れは板止まりだった。
「わしは徹底的にエスキースを描いてから本番を描く。これがわしの描き方じゃ。エスキースに満足できんとキャンバスには描けん」。板に描かれている絵のどの部分が不満なのか判断がつきかねたが、弁造さんは自分の意思を曲げようとはせず、板絵まで進みそこで中断するとキャンバスに進むことなく、また新しいエスキースを最初から描き始めるのだった。ずっとその様子を見てきた僕はあるとき、弁造さんののらりくらりとした絵の進め具合に我慢ができなくなった。80歳後半となり、体調を崩しがちの弁造さんを前に、少し焦っていたのかもしれない。僕は弁造さんにしつこく絵の完成を迫るようになった。そんな僕に対し、弁造さんは絵が完成できない理由を、震えが止まらない指や自給自足の庭に出た害虫のせいにしようとした。それらは弁造さんにとって切実な問題であるということはわかっていたが僕は、そんなの言い訳だと突き放した。「弁造さんは個展を開くんでしょう。であれば何が何でも描かなくちゃ」と言い張った。そんなやりとりは何度も繰り返され、生意気を言い続ける僕に腹を立てた弁造さんは、「あんた、そんなに完成、完成というがな、わしの絵はもう完成しとる。何もキャンバスに描いたものだけが絵じゃないんじゃ。この板絵だって、実はもう完成しとるんじゃ」と憤慨して大きな声で言い返すこともあった。でも、僕も負けずに「キャンバスに描いて完成だと、何度も言っていたのは弁造さんじゃないですか。板絵はエスキースじゃ、ここからさらに高めんといかんと、ずっと言ってきましたよね」と冷静に応戦した。すると、弁造さんはさらに語気を強め、「いや、わしの絵はもう板絵で完成とする。この一枚もあっちの一枚ももう完成なんじゃ」と半ば叫んだのだった。
がらんと静かな丸太小屋の中で僕は棚に重ねられた板絵を抱えて床に置いた。一枚、一枚、板絵を手にとって眺めていく。ほぼすべてが女性だ。南の島らしき木陰で横たわる裸の女性、暖かな日差しを浴びて楽器を奏でる女性、入浴後に髪の手入れをする女性。そこには弁造さんの暮らしぶりや普段語っている話の内容からは想像もつかない女性たちが描かれていた。結局、弁造さんはこれらのモチーフについて僕に語ってくれることはなかった。何度訊ねても「男を描いてもつまらんだけじゃ」と定番の答えが返ってきた。僕は相変わらずの弁造さんの絵だなと思いながら、ハガキサイズから画用紙サイズまで大小さまざまな大きさの板絵を見ていた。板絵の大きさが異なるのは、弁造さんがいわゆる36(サブロク)版と呼ばれる3尺×6尺寸法で5mm厚のシナベニヤを手ノコで切って作ったものだったからだ。また切り出した板に直接描き始めることはなく、まず白で塗って乾かしてから使うのが常だった。いつか、そんな面倒なことをしてエスキースを描く素材を作る弁造さんに向かって、「なぜ」と問うたことがあった。真っ白なキャンバスが頭の上の棚に何枚も並んでいるのだから、そんなにもったいぶったことをせずにキャンバスに描けばいいのではないか、すでに画用紙に何度もエスキースをしたためたのだからと、弁造さんに進言した。すると弁造さんは「あんたは何もわかっとらんな」とつぶやくと「キャンバスちゅうのはな、わしらにとっては本当に大切なもんなんじゃ。開拓時代の家にないもののひとつが絵が描けるような白い紙じゃった。そりゃあそうじゃ。開拓で生きる者たちに白い紙なんて必要がないじゃろう。学校のノートであってもな、親戚や兄弟からのお下がりで、わしも兄貴が書いた文字の上からでもなぞったもんじゃった。じゃが、子供の頃から絵が描きたかったわしは、ちょっとした隙間でもいいからと紙の白い部分を探しては絵を描いた。いつか真っ白な大きな紙を広げて自由に絵を描くことを夢見ながらな。ましてやキャンバスなんて聞いたこともない代物じゃった。木枠に貼った布に油彩の絵の具で絵を描くだなんて想像もできんさ。じゃから、わしがキャンバスに描くときは徹底的にエスキースを描いて、これで行くぞということが決まってからでないと描くことはできん」と僕を諭すように答えた。そして、振り返って頭の上に並ぶキャンバスを見ると「そうは言ってもな、あんたの言うこともようわかる。わしは時間を描けすぎとる。絵を描かん人生なんて意味がないと思ってきた人間じゃ。もっとも描かんといかんと身に沁みて感じとるのはわし自身じゃ」と少しだけ寂しそうに笑った。
その頃、弁造さんが描けない理由のひとつは指だった。70歳の時に患ったバセドウ病は指の震えという後遺症を残していた。弁造さんが絵を描くうえでもっとも重要なのは「線」で、モチーフの立体感は色の濃淡ではなく、重ねた線でもなく一本の線で描ききるというのが理想だった。この線をいかに描くべきか、筆を走らせるイメージはすでに弁造さんの頭にあったのだろう。だからこそ思い通りに指が動かないことは弁造さんにとって絵を描く上で大きな苦痛となったのだろう。絵を完成させたいという思いが募れば募るほどイーゼルに向かう時間が減っていった。
でも、最終的に弁造さんは一枚の絵を描いた。それは弁造さんが長年にわたって繰り返し繰り返しエスキースを描いた末にキャンバスへと筆を進めた「母と娘」だった。絵のなかにあるのは、5歳ほどの女の子が母親の背中越しに寄りかかって甘えている姿で、子供のいる家庭では日常と呼べる風景を描いたものだった。ただ、青いワンピースを着た母親と淡い桃色のワンピースを着た少女の表情には笑みらしきものは見つからず、どことなくミステリアスな気配も帯びていた。それは、絵を見るこちら側を貫いてさらにその先へと向けられているかのようにも見える、母と娘の四つの瞳の印象から来るものでもあった。
この絵が弁造さんにとって満足のいく絵だったのかどうかはさておき、完成の証にとサインを入れたのは僕が知る限りこの一枚だった。
ところが積み重ねた板絵を見ていくうちに現れた「母と娘」のエスキースには、青の絵の具で「井上弁造」というサインが入れられていた。このエスキースで描かれている「母と娘」は、母親が娘のお下げ髪を結ってくれている姿で、キャンバスの母と娘よりもさらに家庭的な雰囲気をまとっていた。表情についてもわかりやすいもので、穏やかな笑みを浮かべる母親に対し、娘は母親が作ってくれる髪型が気に入らないのか少し不満げな面持ちを浮かべていた。僕はこのエスキースを見たあの日のことを思い起こした。それは、僕と弁造さんとの、早く絵を描け、なぜ完成させないんだというやりとりからの何度目かの一悶着があった日のことで、「板絵は完成しとる。これも、こっちの一枚ももう完成じゃ」と憤慨した弁造さんは「あとはサインを入れるだけじゃ」とやはり叫んだのだった。
A4サイズほどの板絵を手にした僕は改めてサインを眺めた。キャンバスに完成させたたった一枚の「母の娘」には漢字で「弁」と記されていた。しかし、この板絵の「母と娘」には、「井上弁造」と右下の角ギリギリのところに記されていた。しかも、最初の「井」の字を描き入れた場所が悪かったのか「弁造」の部分では半段下に下がり、結果的にいびつなものとなってしまっていた。僕はこのサインを見て、青い絵の具のチューブから手作りのパレットに押し出している弁造さんを想像した。弁造さんは僕との一悶着が悔しくて、「もうこの板絵は完成なんじゃ、こうしてサインさえ入れれば完成じゃ」と筆先に青い絵の具を乗せて「井上弁造」と描いたのだろうか。でも、憤慨した感情に任せて描き始めたからだろう。きっと、しっかり字の文字や大きさを考えなかった。だから、こんなどこか間の抜けたサインとなってしまったのだろう。ここまでを想像した僕が考えたのは、弁造さんという人間への距離だった。弁造さんと出会い14年間にわたって、ずっとカメラを向けてきたが、僕の意識には常に弁造さんに対して“他者”という思いがあった。この感覚は僕にとって重要で、そもそも弁造さんにカメラを向けるきっかけは写真を通じて他者の人生に近寄りたいという思いからだった。しかし、板絵に残された下手なサインが連れてきた、小さなエスキースの片隅に悔し紛れのサインを記す弁造さんという人の想像は、僕に両手で弁造さんを抱きしめたかのような印象を残した。と同時にそれは、弁造さんが絵を描くことにただただ愚直で、だからこそ「絵」に一番近いところにいたのだと確信できた瞬間でもあった。
弁造さんが逝って6年がたった2018年。僕は弁造さんと過ごした日々の記憶を綴ることに1年近くを費やした。そして、「庭とエスキース」という弁造さんが最も大切にしていたことの二つの名をタイトルにした本をこの春に上梓することになった。この本がようやく本屋に並びはじめた今、僕が計画しているのは、弁造さんのエスキースを携えて日本のあちこちを巡ってみようというものだ。弁造さんのエスキースは、僕のなかで弁造さんの“生きること”を問い続けている。この問いを僕ひとりでしまい込むのではなく、もっと多くの人に感じてもらう機会を作ることができればどうなるのだろうか。弁造さんのエスキースを目の前に見た人からは何が生まれるだろうと考えるようになったことがこの計画の発端だ。正直言うと、弁造さんの個展を僕がするなんてこれまで考えたこともなかったけれど、きっとこれもまた、弁造さんの“生きること”に近づきたいと思い続けた日々の延長線上にあることなのだろう。
そして、あともうひとつ。「弁造さん、いつか写真と絵の展示会を札幌でやりましょうよ。だからもっと絵を描いてくださいよ」と僕は生前の弁造さんと約束を交わしたことがあった。弁造さんも確かそのときは、「そうじゃなあ、あんたとならやってみるか」とまんざらでもない顔をして笑ったと記憶している。
遅くなってしまったけれど、この約束を守ってたくさんの人に弁造さんの絵を見てもらいますよと、今の僕は弁造さんのエスキースを世に送り出す準備に勤しんでいる。
Copyright© OKUYAMA Atsushi 2019