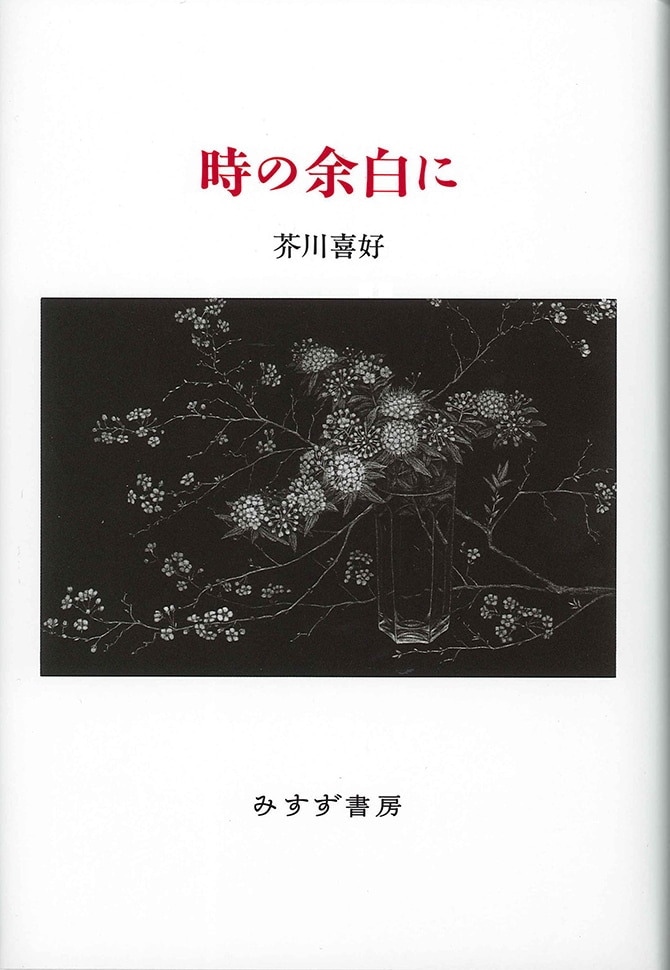泰西名画の展覧会に背を向け、地方の小さな美術館に足を運んで悦に入る。美術に関して私はどこか、天邪鬼を気取りたいからかもしれない。たとえば川崎市にある「中村正義の美術館」で、現代日本画の風雲児と呼ばれた正義の奔放な画群に囲まれていると邪心が洗われるようで清清しい。先だっても名古屋市美術館と練馬区立美術館で大規模な回顧展があったばかりだが、当方にとってはあまり人気画家になられては困る、こっそり秘めておきたい画家の一人だ。
本書の著者である芥川喜好さんもまた、中村正義のように美術史の正史から疎外された作家たちを深く愛した、それこそ大新聞社には似つかわしくない風雲児のような記者と言ってもいいかもしれない。
美術記者として多くの作家と交わり、展評や記事にしてこられた芥川さんが、記者生活の掉尾を飾る仕事として任されたのが連載コラム「時の余白に」である。硬い内容ばかりの新聞解説面で、美との対話を慈しむ味わい深い文章を書き続け、「土曜日の朝、コーヒーを飲みながらゆっくり時間をかけてこの欄を読むのが楽しみ」という多くの読者に愛されてきた。有名無名を問わず美に生きる者たちを訪ね歩き、その輝きをすくい取っては「ほら、素敵でしょう」とそっと差し出す。コラムの名手と言われる所以である。
編集の打ち明け話をするなら、打ち合わせと称してそれぞれが好きな美術を語り合う――そんなやりとりがこよなく楽しかった。芥川さんも、好きな作家のこととなるとうれしそうに筆を走らせる。件の中村正義のほか、画壇と決別して己の画業を究めた小堀四郎、ガダルカナル島で戦死した石巻出身の彫刻家高橋英吉、『生まれいずる悩み』のモデルとなった漁夫画家木田金次郎など、“知る人ぞ知る作家たち”への偏愛は、私のような生半な天邪鬼にはとうてい敵わない。震災後半年を含む5年半を見つめ続けた本書は、激動期のなか敢えて美の側に立ち、現代社会を照射し続けた軌跡である。ぜひ手にとっていただきたい。